夏季休暇を利用して、
久しぶりに “ 西新井大師 ” を参拝致しました。
正式名を「五智山 遍照院 総持寺」。
関東在住時には、折に触れ訪れておりましたが、
東海に転居して以来は、すっかり足が遠のいておりました。
因みに総持寺の「総持(そうじ)」とは、
サンスクリット語 “ ダーラニ(陀羅尼)” の漢訳で、
仏法の「総(すべて)」を「持(たもって)」忘れない、
というような意味とされます。
本年(令和5年)早春の頃、
大和盆地の南に千有余年の法統を伝える巨刹、
長谷寺を参拝しましたことは既に書かせて頂きましたが、
長谷寺は、真言宗豊山派(ぶざんは)の寺院。
今回参詣致しました総持寺も又、
同じく真言宗豊山派の古刹であります。
今を去ること約1200年前の天長3年(826年)の頃、
この一帯は旱魃で枯れ果てていた上、
疫病の蔓延により人々は心身共に疲弊していたのだとか。
そこへ一人の僧侶が現れ、枯れた井戸に向けて、
21日間に亘り加持祈祷を施したところ、
再び清泉豊かに湧き出し、土地も人々も甦ります。
僧侶の名は “ 空海(774~835)” 。
後の世において「弘法大師」と師号された為、
“ 大師が開いた新たな井戸 ” は大切にされて幾星霜、
やがて「西新井大師」なる仏教聖地に・・・。
全国津々浦々に語り継がれる、
いわゆる “ 大師伝説 ” の典型様式ではありますが、
「事実は小説よりも奇なり」で、
一読一聴しただけでは俄に信じがたい伝説の中にも、
一片の真実が宿っているもの。
神社仏閣の開創伝説が生まれた時代背景や、
僧侶聖人による救済伝説が醸成された社会背景には、
それらの伝説に近い事象や出来事が実際にあり、
そうした逸話の元となる人物が実際に居たのだと思います。



総持寺の御本尊は、十一面観世音菩薩と伝わりますが、
本堂の裏手に建つ奥之院には、

弘法大師(空海上人)が祀られていると聞きます。
7年前、関東を去る間際、お礼参りに訪れた時には開扉され、
数々の供物が供えられていたと記憶しますが、
この日は上掲写真の如く “ ヒッソリ ” とした雰囲気。



早川はブログ冒頭に、
「関東在住時には、折に触れ訪れておりました」と、
書かせて頂きました。
その理由のひとつが、こちらの大日如来像であります。

いま少し詳しく申せば “ 金剛界・大日如来 ” 鋳銅坐像。
立て札の解説には、
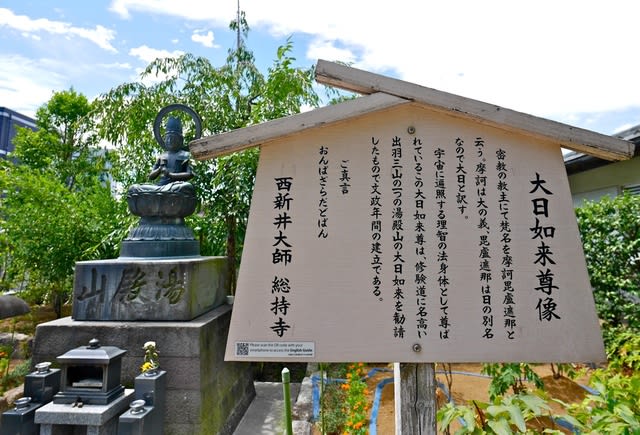
文政年間(1818~1831)の頃、
出羽国(おおよそ現在の山形県)湯殿山から勧請された、
と記されていますが、この説明文は簡略に過ぎ、
一体、どのような経緯や縁起を以て、
“ 大日如来 ” という密教の根本仏が、修験の本拠地・
湯殿山から西新井の地に請来されたものか?
その辺りは残念ながら分かりません。
とは言え「分からない」がゆえにこそ、

そこに自由自在な想像力を羽ばたかせることが出来ます。
そこで早川は、アレコレ想像を巡らせ妄想を膨らませ、
湯殿山を含む出羽三山~修験道~総持寺境内の大日如来~
密教で説かれる曼荼羅の思想~「円」と「縁」~三角関数~
超新星爆発の存在論的意味~電子の反発力~マチュピチュ~
東京目黒の “ 行人坂(ぎょうにんざか)” ~
物理学者エヴェレットの多世界解釈等々をキーワードとして、

一幅の音楽絵巻を作ろう・・・などと夢見たのが、
およそ四半世紀前のこと。
未だ夢叶わず、情けない限りではありますが、
そこはそれ「初心忘るべからず」ということもあり、
今回の参拝に及んだというわけであります。
つまらぬことをクダクダしく書き連ねてしまいましたが、

人間たるもの、いかに他者からの理解は得られずとも、
独自の “ 夢 ” を持っていないと生きてられませんよね。



それにしても、こちらの大日如来像、

もしも文政年間の1823頃に制作建立されたとしたならば、
本年(2023)で、およそ200年。
江戸期の自然災害や大火をしのぎ、
関東大震災や東京大空襲といった大災害をもくぐり抜け、
いま尚このように屹立として智拳印を結ぶ姿に、
いわゆる “ 霊験 ” というものを思うのでありました。
“ 〈Three scale emblem〉and Dragon ” ~ 「三つ鱗」紋と龍

皆様、良き日々でありますように!






久しぶりに “ 西新井大師 ” を参拝致しました。
正式名を「五智山 遍照院 総持寺」。
関東在住時には、折に触れ訪れておりましたが、
東海に転居して以来は、すっかり足が遠のいておりました。
因みに総持寺の「総持(そうじ)」とは、
サンスクリット語 “ ダーラニ(陀羅尼)” の漢訳で、
仏法の「総(すべて)」を「持(たもって)」忘れない、
というような意味とされます。
本年(令和5年)早春の頃、
大和盆地の南に千有余年の法統を伝える巨刹、
長谷寺を参拝しましたことは既に書かせて頂きましたが、
長谷寺は、真言宗豊山派(ぶざんは)の寺院。
今回参詣致しました総持寺も又、
同じく真言宗豊山派の古刹であります。
今を去ること約1200年前の天長3年(826年)の頃、
この一帯は旱魃で枯れ果てていた上、
疫病の蔓延により人々は心身共に疲弊していたのだとか。
そこへ一人の僧侶が現れ、枯れた井戸に向けて、
21日間に亘り加持祈祷を施したところ、
再び清泉豊かに湧き出し、土地も人々も甦ります。
僧侶の名は “ 空海(774~835)” 。
後の世において「弘法大師」と師号された為、
“ 大師が開いた新たな井戸 ” は大切にされて幾星霜、
やがて「西新井大師」なる仏教聖地に・・・。
全国津々浦々に語り継がれる、
いわゆる “ 大師伝説 ” の典型様式ではありますが、
「事実は小説よりも奇なり」で、
一読一聴しただけでは俄に信じがたい伝説の中にも、
一片の真実が宿っているもの。
神社仏閣の開創伝説が生まれた時代背景や、
僧侶聖人による救済伝説が醸成された社会背景には、
それらの伝説に近い事象や出来事が実際にあり、
そうした逸話の元となる人物が実際に居たのだと思います。



総持寺の御本尊は、十一面観世音菩薩と伝わりますが、
本堂の裏手に建つ奥之院には、

弘法大師(空海上人)が祀られていると聞きます。
7年前、関東を去る間際、お礼参りに訪れた時には開扉され、
数々の供物が供えられていたと記憶しますが、
この日は上掲写真の如く “ ヒッソリ ” とした雰囲気。



早川はブログ冒頭に、
「関東在住時には、折に触れ訪れておりました」と、
書かせて頂きました。
その理由のひとつが、こちらの大日如来像であります。

いま少し詳しく申せば “ 金剛界・大日如来 ” 鋳銅坐像。
立て札の解説には、
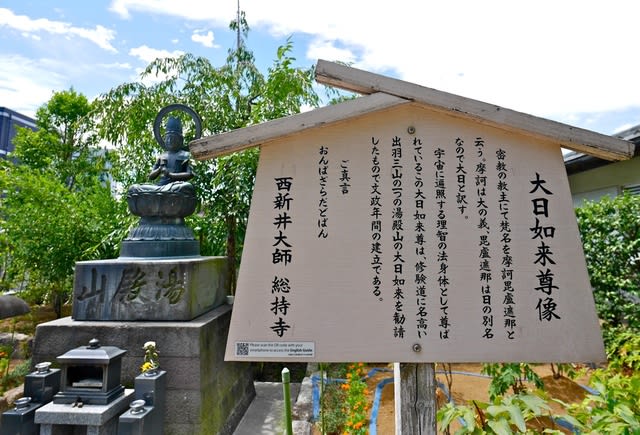
文政年間(1818~1831)の頃、
出羽国(おおよそ現在の山形県)湯殿山から勧請された、
と記されていますが、この説明文は簡略に過ぎ、
一体、どのような経緯や縁起を以て、
“ 大日如来 ” という密教の根本仏が、修験の本拠地・
湯殿山から西新井の地に請来されたものか?
その辺りは残念ながら分かりません。
とは言え「分からない」がゆえにこそ、

そこに自由自在な想像力を羽ばたかせることが出来ます。
そこで早川は、アレコレ想像を巡らせ妄想を膨らませ、
湯殿山を含む出羽三山~修験道~総持寺境内の大日如来~
密教で説かれる曼荼羅の思想~「円」と「縁」~三角関数~
超新星爆発の存在論的意味~電子の反発力~マチュピチュ~
東京目黒の “ 行人坂(ぎょうにんざか)” ~
物理学者エヴェレットの多世界解釈等々をキーワードとして、

一幅の音楽絵巻を作ろう・・・などと夢見たのが、
およそ四半世紀前のこと。
未だ夢叶わず、情けない限りではありますが、
そこはそれ「初心忘るべからず」ということもあり、
今回の参拝に及んだというわけであります。
つまらぬことをクダクダしく書き連ねてしまいましたが、

人間たるもの、いかに他者からの理解は得られずとも、
独自の “ 夢 ” を持っていないと生きてられませんよね。



それにしても、こちらの大日如来像、

もしも文政年間の1823頃に制作建立されたとしたならば、
本年(2023)で、およそ200年。
江戸期の自然災害や大火をしのぎ、
関東大震災や東京大空襲といった大災害をもくぐり抜け、
いま尚このように屹立として智拳印を結ぶ姿に、
いわゆる “ 霊験 ” というものを思うのでありました。
“ 〈Three scale emblem〉and Dragon ” ~ 「三つ鱗」紋と龍

皆様、良き日々でありますように!


















































