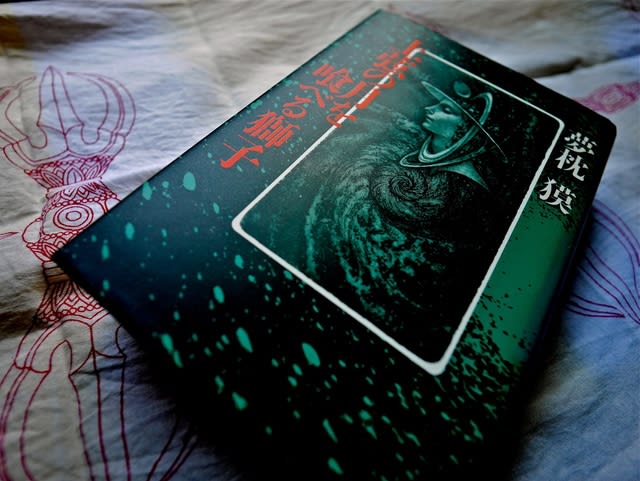記録的な猛暑・酷暑が嘘であったかのように、

朝晩は随分と冷えてまいりました。
いつの間にか金木犀が香り、

柿が、実を結んでいます。




日々に高さと深さを増してゆく秋の空。
城山八幡宮では、

“ 七五三 ” の準備が整えられています。
今春には、

新しい職場への通勤手段として使用する、
自転車の “ お祓い ” をお願いし、
交通安全祈願の昇殿参拝に及ぶなど、

足繁く通う城山八幡宮ですが、
その境内地の片隅にひっそりと、
“ 行者堂 ” が建っています。

どのような経緯で建てられたものかは分かりませんが、
行者堂に向かって右脇には、

「大峰登山二十三度・・・」
向かって左脇には、

「大峰山二十六度登拝・・・」と、
記念の石碑が奉納されています。
御承知置きの通り、
奈良県中部に聳える大峰山(おおみねさん)は、
大峰山回峰行(かいほうぎょう)を始めとする、
山岳仏教の一大聖地。
かつて、この城山の地に、
大峰山系を巡る行者がおられたのだろうか・・・?
八幡宮を訪れる度、
少なからず不思議な想いを抱くのであります。



職場には、歴史好き・旅好きの方がおられ、
色々とお話を伺ううち、“ 龍神 ” の話になり、
“ 青龍会 ” について教えて頂きました。
“ 青龍会 ” は年に3回執り行われる、
京都・清水寺および東山一帯を挙げての仏教大祭。
「青龍会 奉行」と称される師僧に導かれ、
観世音菩薩の化身 “ 青龍 ” が、
「龍衆(りゅうしゅう)」の方々に奉げ持たれつつ、
清水寺の境内から門前町を巡行するというもの。
“ 青龍 ” の鱗が特徴的なんですよね。

皆様、良き日々でありますように!







朝晩は随分と冷えてまいりました。
いつの間にか金木犀が香り、

柿が、実を結んでいます。




日々に高さと深さを増してゆく秋の空。
城山八幡宮では、

“ 七五三 ” の準備が整えられています。
今春には、

新しい職場への通勤手段として使用する、
自転車の “ お祓い ” をお願いし、
交通安全祈願の昇殿参拝に及ぶなど、

足繁く通う城山八幡宮ですが、
その境内地の片隅にひっそりと、
“ 行者堂 ” が建っています。

どのような経緯で建てられたものかは分かりませんが、
行者堂に向かって右脇には、

「大峰登山二十三度・・・」
向かって左脇には、

「大峰山二十六度登拝・・・」と、
記念の石碑が奉納されています。
御承知置きの通り、
奈良県中部に聳える大峰山(おおみねさん)は、
大峰山回峰行(かいほうぎょう)を始めとする、
山岳仏教の一大聖地。
かつて、この城山の地に、
大峰山系を巡る行者がおられたのだろうか・・・?
八幡宮を訪れる度、
少なからず不思議な想いを抱くのであります。



職場には、歴史好き・旅好きの方がおられ、
色々とお話を伺ううち、“ 龍神 ” の話になり、
“ 青龍会 ” について教えて頂きました。
“ 青龍会 ” は年に3回執り行われる、
京都・清水寺および東山一帯を挙げての仏教大祭。
「青龍会 奉行」と称される師僧に導かれ、
観世音菩薩の化身 “ 青龍 ” が、
「龍衆(りゅうしゅう)」の方々に奉げ持たれつつ、
清水寺の境内から門前町を巡行するというもの。
“ 青龍 ” の鱗が特徴的なんですよね。

皆様、良き日々でありますように!