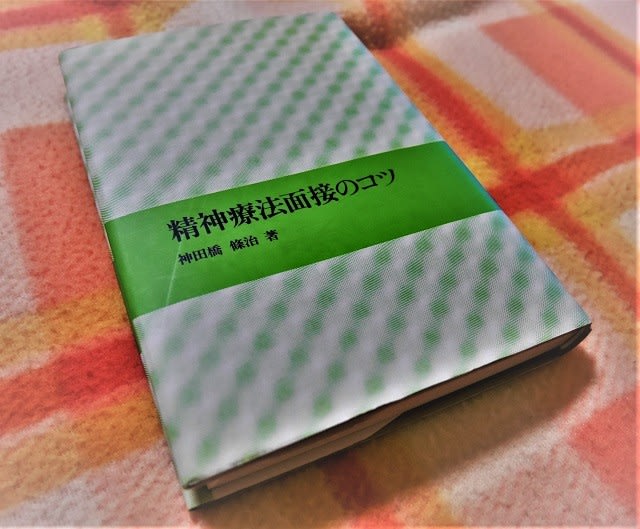よく「若者の活字離れ」などと言われますが、
職場で触れ合う若い方々(18~22歳程度)の中には読書家が多く、
彼ら彼女たちから様々なことを学ぶばかり。
早川は自分自身の活字離れを恥じ入ることはありこそすれ、
「若者の活字離れ」を感じたことはありません。
先日も、新旧の小説を月15~20冊は読むという青年が、
学び舎を巣立つに当たり、別れの挨拶に訪れて下さり、
『いやぁ早川さん、「高瀬舟」いいっすよねぇ・・・』
と感に堪えたように話しかけてくれました。
これを「タイカイ、高瀬舟を読め」との天声人語と受け止めました。



森鷗外(1862~1922)の短編小説「高瀬舟」。
江戸時代、京都町奉行所に勤める同心・羽田庄兵衛は、
“ 弟殺し” の廉で遠島(島流し)となる罪人の喜助を、
高瀬川を上り下りする小舟、通称「高瀬舟」に乗せ、
港まで護送する役目を命じられます。
ベテラン同心の羽田庄兵衛は、
それまで幾度となく高瀬舟での罪人護送を経験していて、
多くの場合、遠島となる罪人と、同船を許された親族との間では、
悲嘆と後悔が交わされ、涙と呻吟に暮れるのが常でした。
ところが喜助は違っていました。
どこかこう落ち着きの中に在るように見受けられるのです。
尤も、それは同船する親族もなく単身島流しに向かう境遇の為、
悲嘆の涙を流し合うことすら出来ないからなのかも知れません。
そのように思ってみたとしても、
庄兵衛の中に芽生えた、喜助に対する好奇心は拭えません。
その好奇心は、自ずと二つの疑問を生じることに。
一つめは、喜助の表情に見え隠れする晴れやかさからくる疑問、
遠島の憂き目に遭っていることをどう感じているのか?
二つめは、喜助の佇まいに滲み出る穏やかさからくる疑問、
これが本当に “ 弟殺し ” を犯した人間なのだろうか?
ついに庄兵衛は尋ねます。
自分は多くの遠島罪人を見てきた。
皆一様に島流しを嫌がり、船上に苦衷の涙をこぼすものだが、
喜助、お前は少しも嫌がっているように見えない。
それどころか、まるで行楽の旅にでも出かけるかのように見える、
なぜだ。
庄兵衛が抱く一つめの疑問に、喜助は概ね次のように答えます。
「そのように見えましたか。お声がけありがとうございます。
遠島となって悲嘆の涙に暮れるのは、それまでの生活が、
それなりに豊かで楽しかった人々なのだと思います。
自分が嘗めてきた辛酸は、他の方々の想像を超えるもので、
それに比べたら遠島の罪で流される先の島の暮らしが、
どうにも楽しみに感じられてくるのです。」
そして彼が幼少期に両親を亡くして以来、
誰にも守られず、世間の中に自分の居場所が無かったこと。
働いても働いても、食べてゆくのが精一杯だったこと。
どのような仕事であっても、骨身を惜しまずに働いたが、
稼いだ金銭は、借財などもあって右から左へと消えたこと。
しかし今、一命だけは助けて貰った上に、
島流しとは言え、自分の居場所を与えられ、
尚「二百文の鳥目(ちょうもく)」までをも授かった。
これ以上に有難いことはない。
といったことが語られるのでした。
「二百文の鳥目」とは、遠島罪人に支給される “ 給付金 ” で、
一概に貨幣換算は出来ませんが、現在の2千円程度でしょうか。
喜助の言葉を聴いた庄兵衛は、自身の身の上に引き比べて、
人間の在り方というものに想いを凝らします。
自分を含め人間というものは、いつも不安の中に在り、
常に “ 渇き ” を覚えながら生きている。
例えば、
今はまだ収入があるけど、仕事が無くなったらどうしよう。
収入のある内に、もっと収入を上げて蓄えが欲しい。
今は健康だけど、明日病気になったらどうしよう。
健康な内に、もっと健康を謳歌したい。
今は愛されているけれど、やがて飽きられたらどうしよう。
愛されている内に、もっと愛を獲得しておきたい。
もっと欲しい、もっと得たい。
人間は、いや少なくとも私や私の妻は、未だかつて、
“ いま・ここ ” に満足したことが無いのではないか・・・。
『人はどこまで往って踏み止まることが出来るものやら分からない。
それを今、目の前で踏み止まって見せてくれるのが此喜助だと、
庄兵衛は氣が附いた。』
(引用元:森鴎外「高瀬舟」新潮社刊、以下同)
喜助の晴れやかさの正体が、辛酸にまみれた半生と、にも拘らず、
辛酸に引きずり込まれることなく堕落しなかった事に由来する、
“ 足るを知る ”
の精神に在ったことに深く感銘を受けた庄兵衛は、
尚のこと、二つめの疑問を抱かざるを得ません。
この男が本当に “ 弟殺し ” の罪を犯したのだろうか・・・。
『色々の事を聞くようだが、お前が今度島へ遣られるのは、
人をあやめたからだと云ふ事だ。己(おれ)に序(ついで)に
そのわけを話して聞かせてくれぬか。』
幼少期に両親を亡くした喜助兄弟は助け合って生きてきました。
西陣織の作業場に職を得た二人は、
粗末な小屋に住みながら職場通いを続けていましたが、
やがて弟が病気にかかり働けなくなります。ある日、
仕事を終え帰宅した喜助は、血だらけで倒れている弟を発見します。
不治の病を得て働けなくなった弟は将来を悲観し、
兄に迷惑をかけたくない一心から、剃刀で喉を切ったのでした。
掠れた声で弟は言います。
『すぐ死ねるだらうと思ったが
息がそこから漏れるだけで死ねない。』
見れば、剃刀は喉笛に深々と刺さったままになっています。
痛がり、苦しむ弟。
医者を呼ぼうとする喜助に弟は懇願します。
『医者がなんになる、ああ苦しい、早く抜いてくれ、頼む』
刺さったままの剃刀を抜けば大きな血管が切れて、
自分は死ぬことが出来る、楽になれる、だから早く抜いてくれ。
弟はそう訴えているのです。
激痛が増し、いよいよ苦しいのでしょう。
『弟の目は「早くしろ、早くしろ」と云って、
さも怨めしそうにわたくしを見てゐます。』
なぜ兄は剃刀を抜き、死なせてくれないのか。
早く楽にしてくれ・・・喜助を見る弟の目は、
『とうとう敵(かたき)の顔をでも睨むような、
憎々しい目になってしまひます。』
喜助も事ここに及んでは、もはやどうすることも出来ません。
『わたくしは「しかたがない、抜いて遣るぞ」と申しました。』
喜助の手により弟の喉から剃刀が抜かれ、噴き出る大量の血液。
弟は、すぐに息を引き取ります。
しかし折悪しく、偶々訪れた隣家の住人がその現場を目撃します。
経緯、事情、事の流れを何も知らない隣人の目に映ったのは、
“ 弟殺し ” の大罪を犯す喜助の姿でしかありません。
すぐさま捕縛され、裁かれ、遠島が申し渡されました。
語り終えて俯く喜助。
聴き終えて俯く庄兵衛。
船が漕ぎ出された頃には耳に届いていた入相の鐘も止み、
夕闇せまる京の町。
高瀬川の水面には、いつしか岸辺の灯火が映り始めています。
庄兵衛には、あらたな疑問が湧いていました。
『これが果たして弟殺しと云ふものだらうか、
人殺しと云ふものだらうかと云ふ疑が、
話を半分聞いた時から起って来て、
聞いてしまっても、其疑を解くことが出来なかった。』



「高瀬舟」を読み直し、
あらためて「安楽死」を巡る問題を想いましたが、
この「安楽死」については、また稿を改めることとして、
むしろ今回考えさせられたのは、喜助の弟が自殺を図った経緯。
不治の病を得て働けなくなり、将来を悲観してのことですが、
自らの喉に剃刀を突き立てて倒れているところを発見し、
驚いて抱き起こす兄の喜助にこう告げているのです。
『済まない。どうぞ堪忍してくれ。
どうせなほりさうにもない病氣だから、
早く死んで少しでも兄きに樂がさせたいと思ったのだ。』
私たちが暮らす社会は、
人間生命というものを経済的価値に換算して成り立っています。
有り体に言うならば、
稼ぐ人間には価値があり、稼がない人間には価値がない、
ということであります。
病気で働けなくなった弟は、自分の存在価値を見失い、
自己肯定感の低下から自殺に及んだのでしょう。
けれども、
『どうせなほりさうにもない病氣』
本人にも、どうせ治りそうにもない病気と分かっているのです。
ならば、
病気の進行に任せて自然死に至るという選択肢もあったはず。
しかし弟は、続けてこう言います。
『早く死んで少しでも兄きに樂がさせたいと思ったのだ。』
自分が早く死ねば、少しでも兄が楽になると考えたわけで、
この発言の背景には、
自分は兄の “ お荷物 ” に違いないという思い込みがあります。
もしかしたら自殺を図った理由に占める割合としては、
病気そのものよりも、病気で稼げなくなったことで生じた、
兄に対する “ 申し訳なさ ” の方が大きかったのかも知れません。



確かに、稼ぐことは良い事ですし、稼げる人は立派です。
しかしながら “ 働くこと ” と “ 稼ぐこと ” とは、
次元を分けて考えるべきではないかと思います。
喜助の弟は、病気で稼げなくなりました。
けれども「働いていた」と、早川は思うのであります。
どういうことかと申しますと、
「生きている」ということは、生命が活動していることであり、
生命が活動しているということは、そこで活動電位が生まれ、
アデノシン3リン酸が生成され、ミトコンドリアが働き、
細胞が働き、細胞の集合体である脳が働き、
心臓を始めとした内臓諸器官が働き、それら働きの上に、
呼吸という働きが働き、摂取・消化・吸収・排泄の働きが働き、
私たち自身は「何もしていない」と感じている時でさえ、
自律神経系・ホメオスタシス系・新陳代謝系等々、
様々な働きが働き詰めに働いている・・・というのが、
私たちの生命の実態なのであります。
「 “ 働くこと ” と “ 稼ぐこと ” とは次元を分けて考えるべき」
と書きましたのは、そういうことからであります。
尤も、これは詭弁・屁理屈の類いに過ぎないのかも知れません。
只、稼ぐ稼がないに拘らず「働いている」のが生命の真実である、
というところに人間存在の根本を据え、そこを死守しないと、
この世界は、
稼ぐ人だけが生きる事を許され、稼ぐ人だけが認められる・・・、
という殺伐荒涼とした世界に堕するように思うのであります。
喜助の弟は、病気で稼げなくなりましたが、
間違いなく「働いていた」のであります。
生きられる限り、堂々と生きていれば良かったのです。
喜助にしても、負担はあったかも知れませんが、
病気の弟を心の支えにこそすれ、迷惑な “ お荷物 ” などとは、
ついぞ思いさえしなかったのではないでしょうか。
長々と駄文を連ねてしまいましたが、
実はこの辺りを足掛かりと致しまして、
コロナ感染した芸能人や著名人は、なぜ謝罪するのか?
「謝罪」という以上、コロナ感染は「罪」なのか?
病気にかかることは「罪」なのか?
「罪」だとしたら「病人」は「罪人」なのか?・・・という、
ずっと以前から抱く疑問について浅慮を巡らせるつもりが、
もはや紙幅も尽きました。
先の「安楽死」問題と同様、機会と稿を改めます。
『次第に更けて行く朧夜に、沈黙の人 二人を載せた高瀬舟は、

黒い水の面をすべって行った。』(森鴎外「高瀬舟」より)





職場で触れ合う若い方々(18~22歳程度)の中には読書家が多く、
彼ら彼女たちから様々なことを学ぶばかり。
早川は自分自身の活字離れを恥じ入ることはありこそすれ、
「若者の活字離れ」を感じたことはありません。
先日も、新旧の小説を月15~20冊は読むという青年が、
学び舎を巣立つに当たり、別れの挨拶に訪れて下さり、
『いやぁ早川さん、「高瀬舟」いいっすよねぇ・・・』
と感に堪えたように話しかけてくれました。
これを「タイカイ、高瀬舟を読め」との天声人語と受け止めました。



森鷗外(1862~1922)の短編小説「高瀬舟」。
江戸時代、京都町奉行所に勤める同心・羽田庄兵衛は、
“ 弟殺し” の廉で遠島(島流し)となる罪人の喜助を、
高瀬川を上り下りする小舟、通称「高瀬舟」に乗せ、
港まで護送する役目を命じられます。
ベテラン同心の羽田庄兵衛は、
それまで幾度となく高瀬舟での罪人護送を経験していて、
多くの場合、遠島となる罪人と、同船を許された親族との間では、
悲嘆と後悔が交わされ、涙と呻吟に暮れるのが常でした。
ところが喜助は違っていました。
どこかこう落ち着きの中に在るように見受けられるのです。
尤も、それは同船する親族もなく単身島流しに向かう境遇の為、
悲嘆の涙を流し合うことすら出来ないからなのかも知れません。
そのように思ってみたとしても、
庄兵衛の中に芽生えた、喜助に対する好奇心は拭えません。
その好奇心は、自ずと二つの疑問を生じることに。
一つめは、喜助の表情に見え隠れする晴れやかさからくる疑問、
遠島の憂き目に遭っていることをどう感じているのか?
二つめは、喜助の佇まいに滲み出る穏やかさからくる疑問、
これが本当に “ 弟殺し ” を犯した人間なのだろうか?
ついに庄兵衛は尋ねます。
自分は多くの遠島罪人を見てきた。
皆一様に島流しを嫌がり、船上に苦衷の涙をこぼすものだが、
喜助、お前は少しも嫌がっているように見えない。
それどころか、まるで行楽の旅にでも出かけるかのように見える、
なぜだ。
庄兵衛が抱く一つめの疑問に、喜助は概ね次のように答えます。
「そのように見えましたか。お声がけありがとうございます。
遠島となって悲嘆の涙に暮れるのは、それまでの生活が、
それなりに豊かで楽しかった人々なのだと思います。
自分が嘗めてきた辛酸は、他の方々の想像を超えるもので、
それに比べたら遠島の罪で流される先の島の暮らしが、
どうにも楽しみに感じられてくるのです。」
そして彼が幼少期に両親を亡くして以来、
誰にも守られず、世間の中に自分の居場所が無かったこと。
働いても働いても、食べてゆくのが精一杯だったこと。
どのような仕事であっても、骨身を惜しまずに働いたが、
稼いだ金銭は、借財などもあって右から左へと消えたこと。
しかし今、一命だけは助けて貰った上に、
島流しとは言え、自分の居場所を与えられ、
尚「二百文の鳥目(ちょうもく)」までをも授かった。
これ以上に有難いことはない。
といったことが語られるのでした。
「二百文の鳥目」とは、遠島罪人に支給される “ 給付金 ” で、
一概に貨幣換算は出来ませんが、現在の2千円程度でしょうか。
喜助の言葉を聴いた庄兵衛は、自身の身の上に引き比べて、
人間の在り方というものに想いを凝らします。
自分を含め人間というものは、いつも不安の中に在り、
常に “ 渇き ” を覚えながら生きている。
例えば、
今はまだ収入があるけど、仕事が無くなったらどうしよう。
収入のある内に、もっと収入を上げて蓄えが欲しい。
今は健康だけど、明日病気になったらどうしよう。
健康な内に、もっと健康を謳歌したい。
今は愛されているけれど、やがて飽きられたらどうしよう。
愛されている内に、もっと愛を獲得しておきたい。
もっと欲しい、もっと得たい。
人間は、いや少なくとも私や私の妻は、未だかつて、
“ いま・ここ ” に満足したことが無いのではないか・・・。
『人はどこまで往って踏み止まることが出来るものやら分からない。
それを今、目の前で踏み止まって見せてくれるのが此喜助だと、
庄兵衛は氣が附いた。』
(引用元:森鴎外「高瀬舟」新潮社刊、以下同)
喜助の晴れやかさの正体が、辛酸にまみれた半生と、にも拘らず、
辛酸に引きずり込まれることなく堕落しなかった事に由来する、
“ 足るを知る ”
の精神に在ったことに深く感銘を受けた庄兵衛は、
尚のこと、二つめの疑問を抱かざるを得ません。
この男が本当に “ 弟殺し ” の罪を犯したのだろうか・・・。
『色々の事を聞くようだが、お前が今度島へ遣られるのは、
人をあやめたからだと云ふ事だ。己(おれ)に序(ついで)に
そのわけを話して聞かせてくれぬか。』
幼少期に両親を亡くした喜助兄弟は助け合って生きてきました。
西陣織の作業場に職を得た二人は、
粗末な小屋に住みながら職場通いを続けていましたが、
やがて弟が病気にかかり働けなくなります。ある日、
仕事を終え帰宅した喜助は、血だらけで倒れている弟を発見します。
不治の病を得て働けなくなった弟は将来を悲観し、
兄に迷惑をかけたくない一心から、剃刀で喉を切ったのでした。
掠れた声で弟は言います。
『すぐ死ねるだらうと思ったが
息がそこから漏れるだけで死ねない。』
見れば、剃刀は喉笛に深々と刺さったままになっています。
痛がり、苦しむ弟。
医者を呼ぼうとする喜助に弟は懇願します。
『医者がなんになる、ああ苦しい、早く抜いてくれ、頼む』
刺さったままの剃刀を抜けば大きな血管が切れて、
自分は死ぬことが出来る、楽になれる、だから早く抜いてくれ。
弟はそう訴えているのです。
激痛が増し、いよいよ苦しいのでしょう。
『弟の目は「早くしろ、早くしろ」と云って、
さも怨めしそうにわたくしを見てゐます。』
なぜ兄は剃刀を抜き、死なせてくれないのか。
早く楽にしてくれ・・・喜助を見る弟の目は、
『とうとう敵(かたき)の顔をでも睨むような、
憎々しい目になってしまひます。』
喜助も事ここに及んでは、もはやどうすることも出来ません。
『わたくしは「しかたがない、抜いて遣るぞ」と申しました。』
喜助の手により弟の喉から剃刀が抜かれ、噴き出る大量の血液。
弟は、すぐに息を引き取ります。
しかし折悪しく、偶々訪れた隣家の住人がその現場を目撃します。
経緯、事情、事の流れを何も知らない隣人の目に映ったのは、
“ 弟殺し ” の大罪を犯す喜助の姿でしかありません。
すぐさま捕縛され、裁かれ、遠島が申し渡されました。
語り終えて俯く喜助。
聴き終えて俯く庄兵衛。
船が漕ぎ出された頃には耳に届いていた入相の鐘も止み、
夕闇せまる京の町。
高瀬川の水面には、いつしか岸辺の灯火が映り始めています。
庄兵衛には、あらたな疑問が湧いていました。
『これが果たして弟殺しと云ふものだらうか、
人殺しと云ふものだらうかと云ふ疑が、
話を半分聞いた時から起って来て、
聞いてしまっても、其疑を解くことが出来なかった。』



「高瀬舟」を読み直し、
あらためて「安楽死」を巡る問題を想いましたが、
この「安楽死」については、また稿を改めることとして、
むしろ今回考えさせられたのは、喜助の弟が自殺を図った経緯。
不治の病を得て働けなくなり、将来を悲観してのことですが、
自らの喉に剃刀を突き立てて倒れているところを発見し、
驚いて抱き起こす兄の喜助にこう告げているのです。
『済まない。どうぞ堪忍してくれ。
どうせなほりさうにもない病氣だから、
早く死んで少しでも兄きに樂がさせたいと思ったのだ。』
私たちが暮らす社会は、
人間生命というものを経済的価値に換算して成り立っています。
有り体に言うならば、
稼ぐ人間には価値があり、稼がない人間には価値がない、
ということであります。
病気で働けなくなった弟は、自分の存在価値を見失い、
自己肯定感の低下から自殺に及んだのでしょう。
けれども、
『どうせなほりさうにもない病氣』
本人にも、どうせ治りそうにもない病気と分かっているのです。
ならば、
病気の進行に任せて自然死に至るという選択肢もあったはず。
しかし弟は、続けてこう言います。
『早く死んで少しでも兄きに樂がさせたいと思ったのだ。』
自分が早く死ねば、少しでも兄が楽になると考えたわけで、
この発言の背景には、
自分は兄の “ お荷物 ” に違いないという思い込みがあります。
もしかしたら自殺を図った理由に占める割合としては、
病気そのものよりも、病気で稼げなくなったことで生じた、
兄に対する “ 申し訳なさ ” の方が大きかったのかも知れません。



確かに、稼ぐことは良い事ですし、稼げる人は立派です。
しかしながら “ 働くこと ” と “ 稼ぐこと ” とは、
次元を分けて考えるべきではないかと思います。
喜助の弟は、病気で稼げなくなりました。
けれども「働いていた」と、早川は思うのであります。
どういうことかと申しますと、
「生きている」ということは、生命が活動していることであり、
生命が活動しているということは、そこで活動電位が生まれ、
アデノシン3リン酸が生成され、ミトコンドリアが働き、
細胞が働き、細胞の集合体である脳が働き、
心臓を始めとした内臓諸器官が働き、それら働きの上に、
呼吸という働きが働き、摂取・消化・吸収・排泄の働きが働き、
私たち自身は「何もしていない」と感じている時でさえ、
自律神経系・ホメオスタシス系・新陳代謝系等々、
様々な働きが働き詰めに働いている・・・というのが、
私たちの生命の実態なのであります。
「 “ 働くこと ” と “ 稼ぐこと ” とは次元を分けて考えるべき」
と書きましたのは、そういうことからであります。
尤も、これは詭弁・屁理屈の類いに過ぎないのかも知れません。
只、稼ぐ稼がないに拘らず「働いている」のが生命の真実である、
というところに人間存在の根本を据え、そこを死守しないと、
この世界は、
稼ぐ人だけが生きる事を許され、稼ぐ人だけが認められる・・・、
という殺伐荒涼とした世界に堕するように思うのであります。
喜助の弟は、病気で稼げなくなりましたが、
間違いなく「働いていた」のであります。
生きられる限り、堂々と生きていれば良かったのです。
喜助にしても、負担はあったかも知れませんが、
病気の弟を心の支えにこそすれ、迷惑な “ お荷物 ” などとは、
ついぞ思いさえしなかったのではないでしょうか。
長々と駄文を連ねてしまいましたが、
実はこの辺りを足掛かりと致しまして、
コロナ感染した芸能人や著名人は、なぜ謝罪するのか?
「謝罪」という以上、コロナ感染は「罪」なのか?
病気にかかることは「罪」なのか?
「罪」だとしたら「病人」は「罪人」なのか?・・・という、
ずっと以前から抱く疑問について浅慮を巡らせるつもりが、
もはや紙幅も尽きました。
先の「安楽死」問題と同様、機会と稿を改めます。
『次第に更けて行く朧夜に、沈黙の人 二人を載せた高瀬舟は、

黒い水の面をすべって行った。』(森鴎外「高瀬舟」より)