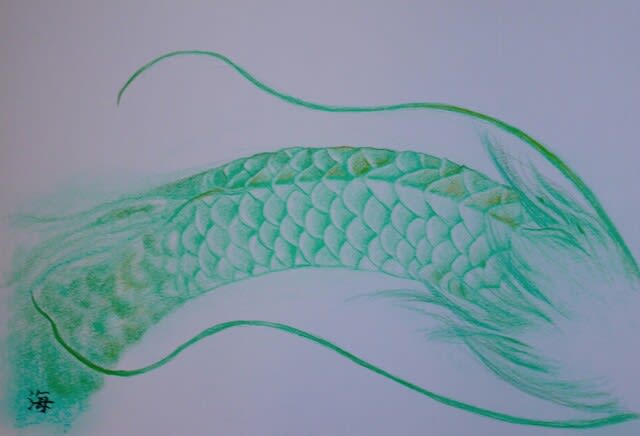明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い申し上げます。
本日は1月8日ですが、早川の体内には未だ屠蘇酒の微酔あり。
上掲写真の絵馬は、
富士山本宮浅間大社から毎年お送り頂いているものですが、
嬉しき哉、そこには “ 屠蘇散(とそさん)” も添えられていて、
早川はこれを本醸造酒に1~2日漬け込み元日に頂戴するのが、
年に一度の楽しみなのであります。
“ 屠蘇散(とそさん)” で思い出しましたが、
現在も「ゴホンと言えば◯◯散」、或いは漢方薬の中にも、
「安中散(アンチュウサン)」「五苓散(ゴレイサン)」、
といった薬が有るように、古来中国を始めとする漢字圏では、
薬のことを「散」と呼び慣らわしてきました。
今を去る1800年程前の中国は三国時代。頽廃した貴族階級の間に、
「五石散(ゴセキサン)」なる薬物が流行したと謂います。
今でいう “ 麻薬 ” に近いものだったようですが、この「五石散」、
服用してから「歩き回る」ことで快感状態が一層高まったらしく、
「五石散」を手に入れた人は、これを服用すると、
矢鱈あちらこちらをグルグルと歩いて回ったのだとか。
五石「散」を飲んで「歩」く。
この様子が「散歩」の語源と、何かの本で読んだ記憶があります。
いや、そんなことはともかく、
社会インフラ業務やサービス業等に携わる方々を始め、
年明けから出社・出勤の方々もおられたことでありましょうし、
また初詣の参拝客を迎える神社仏閣職員の方々であれば、
それこそ正月は 忙しさのピークでもあろうかと思われます。
只、一般的に年明け三ヶ日は「正月休み」。
この「休む」ことを表す「休」なる漢字は、
現行の国語指導要領では、小学校1年生で習う会意文字だそうで、
成り立ちや字義については諸説あるものの、概ね二つ。
一つは「休」の字体を、
「人」が「木」の傍らに留まる様子として捉え、
物事を一旦「停止する」、進めている計画を一時「留保する」、
という意味に解釈する説。
いま一つは「休」の字体を、「人」が「木」の傍らに在って、
立っている、座っている、もたれている、寝ている等と捉え、
憩う、のんびりする、英気を養う、リラックスする等、
文字通り「休む」という意味に解釈する説。
漢字の成り立ちなどというものは、
人それぞれが自由に想像を巡らせ、自身が生きてゆく上での、
精神的な糧を得られるような物語を紡げば良いと思う私は、
上掲2説の内、どうしても後説に共感共鳴し、個人的には、
「休」は「人」が「木」に触れてジッとしている様子であると、
そのようにイメージします。
しかしながら、この「木に触れる」というのは、
山林や森林、或いは公園や庭に立つ “ 実木 ” に触れる・・・、
ということだけを指すものではないようにも思われます。



2011年3月11日に発生した東日本大震災。
ヴァイオリン制作及び修復家の中澤宗幸氏は、
震災による津波被害を受けた陸前高田の流木から、
一挺のヴァイオリンを作られました。
このヴァイオリンは「震災ヴァイオリン」として、
イヴリー・ギトリス氏(1922~2020)により奏でられ、
復興の一端を担ったことは広く知られているところでもあります。
中澤氏の御著書「いのちのヴァイオリン」には、氏が未だ若い頃、

ヨーロッパ中を巡ってヴァイオリンの勉強をしている時期、
あるヴァイオリンに出会った際のエピソードが書かれています。
そのヴァイオリンの横板にはギリシャ語で何か記されていましたが、
氏はギリシャ語を読めないので知人に訳してもらったところ、
『わたしは森にいるときには木陰で人を癒し、
ヴァイオリンになってからは音で人を癒す。』
という、
言わば “ 木からのメッセージ ” とも呼べる詩であったそうです。

ヴァイオリンに記されていた文章の意味を知り、
『木は切り倒されてその寿命を終えるのではなく、
ヴァイオリンになってからも、年々、美しい音を響かせて、
わたしたち人間の心を癒してくれていた』
(引用元:中澤宗幸「いのちのヴァイオリン」ポプラ社)
そのことに深い感動を覚えた中澤氏は、こう綴られています。
『森の木でつくられたヴァイオリンは、
吹きわたる風や雨や幾千の葉の音を、
その音色のなかに潜ませているに違いありません。』(前掲書)



今は木材として楽器に姿かたちを変えてはいても、その木材が、
『かつて森に生きていた時の記憶』(前掲書)
それは、
無数の鳥が、そこで羽根を休め暮らしを営んだ記憶、
無数の昆虫が、そこを住み家とし命を養った記憶、
無数の葉を繁らせ、無数の葉を落とした記憶、
無数の光、無数の闇を樹体に纏いながら光合成を繰り返した記憶。
そうした記憶の断片が、心ある演奏家によって奏でられる時、
ふと甦り、大気の中に響き出し、歌い出される。

それは言わば “ 音の年輪 ” 。
そういうことが起き得るであろうと違和感無く思えるところが、
樹木から作られた楽器の不思議さ奥深さのように感じると共に、
この辺りの神韻縹渺とした世界に、
何か音楽の根源たるものが在るようにも思います。
そう言えば和太鼓も、口径の大きなものになると、
アフリカのジャングルで育った樹齢数千年を超える巨木を伐採し、
日本に運んだ後、幹を刳り抜いて作ると聞いた覚えがあります。
中澤氏の説くところに心を合わせて想うには、もしかしたら、
和太鼓の “ ドーン ” という天地を震わせる一打一音の中には、

和太鼓になる前の巨木が、
アフリカの大地に根を張り立ち続けていた時の記憶が宿っていて、
それゆえに聴く者は心身の奥底を揺さぶられるのかも知れません。
屠蘇酒の微酔に任せて、つい書き連ねてしまいましたが、
「休」という漢字を、
「人」が「木」に触れてジッとしている姿と観想してみた時、
「いのちのヴァイオリン」に綴られているように、音楽には、
耳で「木」に触れる、「森」に触れる、「森の記憶」に触れる、

そういった要素をも内包しているのだなぁと、
年の初めに当たり、あらためて自らの心に刻むものであります。
“ Mt. Fuji and Spiritual Dragon ” ~ 霊峰霊龍 ~

皆様、良き日々でありますように!







本年も宜しくお願い申し上げます。
本日は1月8日ですが、早川の体内には未だ屠蘇酒の微酔あり。
上掲写真の絵馬は、
富士山本宮浅間大社から毎年お送り頂いているものですが、
嬉しき哉、そこには “ 屠蘇散(とそさん)” も添えられていて、
早川はこれを本醸造酒に1~2日漬け込み元日に頂戴するのが、
年に一度の楽しみなのであります。
“ 屠蘇散(とそさん)” で思い出しましたが、
現在も「ゴホンと言えば◯◯散」、或いは漢方薬の中にも、
「安中散(アンチュウサン)」「五苓散(ゴレイサン)」、
といった薬が有るように、古来中国を始めとする漢字圏では、
薬のことを「散」と呼び慣らわしてきました。
今を去る1800年程前の中国は三国時代。頽廃した貴族階級の間に、
「五石散(ゴセキサン)」なる薬物が流行したと謂います。
今でいう “ 麻薬 ” に近いものだったようですが、この「五石散」、
服用してから「歩き回る」ことで快感状態が一層高まったらしく、
「五石散」を手に入れた人は、これを服用すると、
矢鱈あちらこちらをグルグルと歩いて回ったのだとか。
五石「散」を飲んで「歩」く。
この様子が「散歩」の語源と、何かの本で読んだ記憶があります。
いや、そんなことはともかく、
社会インフラ業務やサービス業等に携わる方々を始め、
年明けから出社・出勤の方々もおられたことでありましょうし、
また初詣の参拝客を迎える神社仏閣職員の方々であれば、
それこそ正月は 忙しさのピークでもあろうかと思われます。
只、一般的に年明け三ヶ日は「正月休み」。
この「休む」ことを表す「休」なる漢字は、
現行の国語指導要領では、小学校1年生で習う会意文字だそうで、
成り立ちや字義については諸説あるものの、概ね二つ。
一つは「休」の字体を、
「人」が「木」の傍らに留まる様子として捉え、
物事を一旦「停止する」、進めている計画を一時「留保する」、
という意味に解釈する説。
いま一つは「休」の字体を、「人」が「木」の傍らに在って、
立っている、座っている、もたれている、寝ている等と捉え、
憩う、のんびりする、英気を養う、リラックスする等、
文字通り「休む」という意味に解釈する説。
漢字の成り立ちなどというものは、
人それぞれが自由に想像を巡らせ、自身が生きてゆく上での、
精神的な糧を得られるような物語を紡げば良いと思う私は、
上掲2説の内、どうしても後説に共感共鳴し、個人的には、
「休」は「人」が「木」に触れてジッとしている様子であると、
そのようにイメージします。
しかしながら、この「木に触れる」というのは、
山林や森林、或いは公園や庭に立つ “ 実木 ” に触れる・・・、
ということだけを指すものではないようにも思われます。



2011年3月11日に発生した東日本大震災。
ヴァイオリン制作及び修復家の中澤宗幸氏は、
震災による津波被害を受けた陸前高田の流木から、
一挺のヴァイオリンを作られました。
このヴァイオリンは「震災ヴァイオリン」として、
イヴリー・ギトリス氏(1922~2020)により奏でられ、
復興の一端を担ったことは広く知られているところでもあります。
中澤氏の御著書「いのちのヴァイオリン」には、氏が未だ若い頃、

ヨーロッパ中を巡ってヴァイオリンの勉強をしている時期、
あるヴァイオリンに出会った際のエピソードが書かれています。
そのヴァイオリンの横板にはギリシャ語で何か記されていましたが、
氏はギリシャ語を読めないので知人に訳してもらったところ、
『わたしは森にいるときには木陰で人を癒し、
ヴァイオリンになってからは音で人を癒す。』
という、
言わば “ 木からのメッセージ ” とも呼べる詩であったそうです。

ヴァイオリンに記されていた文章の意味を知り、
『木は切り倒されてその寿命を終えるのではなく、
ヴァイオリンになってからも、年々、美しい音を響かせて、
わたしたち人間の心を癒してくれていた』
(引用元:中澤宗幸「いのちのヴァイオリン」ポプラ社)
そのことに深い感動を覚えた中澤氏は、こう綴られています。
『森の木でつくられたヴァイオリンは、
吹きわたる風や雨や幾千の葉の音を、
その音色のなかに潜ませているに違いありません。』(前掲書)



今は木材として楽器に姿かたちを変えてはいても、その木材が、
『かつて森に生きていた時の記憶』(前掲書)
それは、
無数の鳥が、そこで羽根を休め暮らしを営んだ記憶、
無数の昆虫が、そこを住み家とし命を養った記憶、
無数の葉を繁らせ、無数の葉を落とした記憶、
無数の光、無数の闇を樹体に纏いながら光合成を繰り返した記憶。
そうした記憶の断片が、心ある演奏家によって奏でられる時、
ふと甦り、大気の中に響き出し、歌い出される。

それは言わば “ 音の年輪 ” 。
そういうことが起き得るであろうと違和感無く思えるところが、
樹木から作られた楽器の不思議さ奥深さのように感じると共に、
この辺りの神韻縹渺とした世界に、
何か音楽の根源たるものが在るようにも思います。
そう言えば和太鼓も、口径の大きなものになると、
アフリカのジャングルで育った樹齢数千年を超える巨木を伐採し、
日本に運んだ後、幹を刳り抜いて作ると聞いた覚えがあります。
中澤氏の説くところに心を合わせて想うには、もしかしたら、
和太鼓の “ ドーン ” という天地を震わせる一打一音の中には、

和太鼓になる前の巨木が、
アフリカの大地に根を張り立ち続けていた時の記憶が宿っていて、
それゆえに聴く者は心身の奥底を揺さぶられるのかも知れません。
屠蘇酒の微酔に任せて、つい書き連ねてしまいましたが、
「休」という漢字を、
「人」が「木」に触れてジッとしている姿と観想してみた時、
「いのちのヴァイオリン」に綴られているように、音楽には、
耳で「木」に触れる、「森」に触れる、「森の記憶」に触れる、

そういった要素をも内包しているのだなぁと、
年の初めに当たり、あらためて自らの心に刻むものであります。
“ Mt. Fuji and Spiritual Dragon ” ~ 霊峰霊龍 ~

皆様、良き日々でありますように!