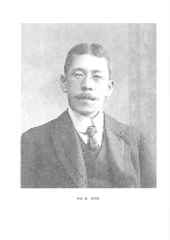<土木のある風景③> 夢の超特急編 『SHINKANSEN』
注釈>>
※8)父子三代:
(2)島 隆(1931- )は、島秀雄※2)の次男であり、島安次郎※8-2)の孫に当たる。東大工学部機械工学科卒。1955年国鉄入社。
若くして新幹線グループに抜擢され、0系の台車設計に当たる。のち東北上越新幹線の車両設計責任者。世界銀行調査委員としても活躍。
「父からは鉄道をやれとは一言も言われていない。まさか父がもう一度同じ職場
に戻ってくるとは思わなかった」秀雄、隆ともに、奇しくも同じ言葉を語ってい
る。
本編および注釈※1~8)については、下記の文献・資料を参考にした。
≪参考文献≫
・高橋団吉著 「新幹線を作った男 島秀雄物語」2000.5 小学館
・碇 義朗著 「超高速に挑む」1993 文藝春秋社
・中島幸三郎著「風雲児・十河信二傳」1955 交通協同出版社
・愛媛県生涯学習センターHPより “愛媛の偉人・賢人の紹介”十河信二:
http://joho.ehime-iinet.or.jp/syogai/jinbutu/html/071.htm
・Wikipedia(フリー百科事典)より 島 秀雄:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E7%A7%80%E9%9B%84
・土木学会HPより 歴代会長紹介・大石重成:
http://www.jsce.or.jp/outline/chair/chairman.html#chair58
以上、完。
注釈>>
※8)父子三代:
(2)島 隆(1931- )は、島秀雄※2)の次男であり、島安次郎※8-2)の孫に当たる。東大工学部機械工学科卒。1955年国鉄入社。
若くして新幹線グループに抜擢され、0系の台車設計に当たる。のち東北上越新幹線の車両設計責任者。世界銀行調査委員としても活躍。
「父からは鉄道をやれとは一言も言われていない。まさか父がもう一度同じ職場
に戻ってくるとは思わなかった」秀雄、隆ともに、奇しくも同じ言葉を語ってい
る。
本編および注釈※1~8)については、下記の文献・資料を参考にした。
≪参考文献≫
・高橋団吉著 「新幹線を作った男 島秀雄物語」2000.5 小学館
・碇 義朗著 「超高速に挑む」1993 文藝春秋社
・中島幸三郎著「風雲児・十河信二傳」1955 交通協同出版社
・愛媛県生涯学習センターHPより “愛媛の偉人・賢人の紹介”十河信二:
http://joho.ehime-iinet.or.jp/syogai/jinbutu/html/071.htm
・Wikipedia(フリー百科事典)より 島 秀雄:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E7%A7%80%E9%9B%84
・土木学会HPより 歴代会長紹介・大石重成:
http://www.jsce.or.jp/outline/chair/chairman.html#chair58
以上、完。