国全体に資するのは 「農村の経済成長」だ 日本総合研究所主席研究員 藻谷浩介
日本農業新聞 2018年3月5日
「スマート・テロワール(美しくきょうじんな農村自給圏)」の提唱者、松尾雅彦氏が亡くなった。松尾氏は、米の低価格と畜産加工品の高価格に着目し、「水田を飼料用トウモロコシなどの畑に転換し、家畜飼料からハム・ソーセージ、チーズなどの加工品までを農村内で一貫生産することで、より多くの付加価値を農の現場に落とす」ことを唱えておられた。
飼料を自家生産すれば、飼料代が出て行かなくなる。加工品を自家生産すれば、原料代と加工品価格との間の大きな差も、生産者のものになる。それだけ農村に落ちる「付加価値が増える」=「経済成長する」わけだ。その場合に農協はどちら側なのか(農村の取り分を増やす側か、農村からお金を取る飼料販売業者なのか)ということも、氏は問うていたと思う。
どちらがプラス
ところで、付加価値が飼料販売業者や食品加工業者のものになるのと、「スマート・テロワール」の実践で農村にとどまるのを比べた場合、国全体の経済にはどちらがプラスだろうか。単純な経済学では「どちらでも同じ」だ。
経済学「風」の俗世間的イメージでは、「小規模農家よりも大企業がもうけた方が、何となく国全体にはプラス、って感じ?」かもしれない。だが現実に立ち帰れば、農村部のもうけが増えた方が、大企業がもうけるよりも、国全体の経済成長への寄与は大きいのである。
というのも日本の大企業は、もうけを現金としてため込むばかりで、投資をするにしても海外向けが多く、国内の経済循環拡大への貢献が乏しい。これは、ここ数年の株高と大企業収益の増加が、全くと言っていいほど個人消費の拡大につながっていない現実からも明らかだ。
他方で現場の農業者は、もうかれば規模拡大に投資し、雇用も増やす可能性が高い。それにより国内の経済循環は拡大する上、出生率の著しく低い首都圏以下の大都市部から一人でも多くの若者が農山村に移住すれば、それだけ日本全体の人口減少にも歯止めがかかる。
チャンス手放す
政治家の多くは、経済学「風」のイメージに思考を染められているだけで、こうした現実を理解しているようには見えない。経済学者の多くも机上の定式を語るだけで、「大企業にお金を集めることが日本の経済成長につながっていない」と言う、明らかな現実には目をつぶっている。
農業者の多くも、経済成長一辺倒の政策や規制緩和万能の安直な風潮には反発するものの、自分の行動としては大企業から飼料や肥料や農薬や燃料や資材を無自覚に買い続け、農村の経済を成長させる機会を逃し続けている。
今般、各紙に載った松尾氏の訃報は「カルビー三代目社長、現相談役」というものばかりで、「スマート・テロワール」には触れていなかった。北海道美瑛町との縁から「日本で最も美しい村連合」の副会長を務めていたという記述もない。
訃報までが大企業側、東京側の視点だけで書かれてしまったことは、松尾氏としても無念だったのではないだろうか。
せめてのはなむけに、遺志を継いで農村の取り分を増やそうと志す農業者が一人でも増えることを、願ってやまない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
まず故人に対し慎んで哀悼を表します。
経済学「風」の俗世間的イメージでは、「小規模農家よりも大企業がもうけた方が、何となく国全体にはプラス、って感じ?」かもしれない。
これこそが重商主義の発想である。
重商主義とは16世紀半ばから18世紀にかけて西ヨーロッパの絶対王政国家で行われた政策であり、「富とは金(や銀、貨幣)であり、国力の増大とはそれらの蓄積である」と考えていることが特徴である。
そして、その実践として植民地からの搾取、他国との植民地争い、保護貿易などを行った。
また、極端に「輸出を増やして、輸入を少なくする」という貿易差額主義を取った。
そのため重商主義は必然的に他国との対立に繋がるものである。
近世から近代では西洋諸国は見苦しい植民地戦争を繰り広げた。
やがて重商主義は近現代の資本主義の基礎となり、戦争や格差社会、富む国と貧しい国、南北問題や無計画な開発による資源の枯渇と環境破壊を招いた。
まさに、重商主義と資本主義が世界の人々を苦しめ、地球を破壊してきたのである。
しかし、資本主義や金融というものは「貨幣から富を作る」もので、その実体は「無から財産を作っている」のに等しい。
この重商主義を批判したのが、18世紀後半フランスのフランソワ・ケネーなどによって提唱された重農主義である。
ケネーは『経済表』を作成してその自然が形成する秩序の姿を明らかにしようとした。彼は社会は神によって創造された自然秩序に基づいて形成されるものとして人為的な社会契約説には批判的であった。自然秩序は物理・道徳の両法則によって形成され、自然法と実定法はこれを制御するために生み出されたものである。人間は自然法則によって自己の欲望を満たしたいとする欲求を実現する権利を持っており、その実現を保障するのが自由権と財産権であり、国家は実定法を用いてこれを保障する義務を持つと唱えた。
つまり近代に入ってから人間中心主義・人間至上主義・科学万能主義に陥り自然を人間の力で制御できるとする思い上がりが始まった時代に、神や自然を尊ぶことを唱えたのだ。
また、彼は農業によって生み出された剰余価値(純生産物)が農業資本の拡大再生産をもたらすとした。一方、商工業は農業がもたらす原材料がなければ何も生産出来ず、生産者としての価値は存在しない。農業生産の拡大再生産による恩恵が原材料などの形で商工業に流れることで初めて商工業が発展するという本質的な主張をした。
「富は土地から生まれる」という当然の主張である。
このような自然を尊重し、農業を重視する発想は東洋の影響を受けていた。
18世紀はイエズス会によって中国を中心とする東洋の思想がヨーロッパに紹介されていた。
東洋では古来、「農は国の本」とする農本思想が受け継がれてきた。
この重農主義と農本主義は国家の基礎を守る理にかなった考え方である。
日本でも明治維新以降、急速に近代化・西洋化が進み、農村社会が崩壊の危機に晒された。
そのため北一輝先生をはじめとする昭和維新の思想家や青年将校たちは資本主義を批判し、国家社会主義と共に農本主義を掲げたのである。
同じように、イタリアのファシストやドイツの国家社会主義者は農業や自然を尊重する真の愛国主義を説いた。
特にドイツのアドルフ・ヒトラーをはじめ国家社会主義労働者党の幹部は菜食主義者が多く、自然保護・自然回帰を主張していた。
国家社会党は「自然は民族の喜び」と説いていた。
自然こそ民族の宝であり、世界の宝なのである。
重農主義・農本主義こそ自然環境を守り、資本主義の矛盾を解決して民衆を救う世界平和の道なのである。
私達ファシストは、祖国を愛するが故に民族の財産たる自然を守り、国家の礎である農村の発展を誓うものである。
そのためには、資本第一主義に陥った経済思想の堕落を正し、土地の尊重と額に汗して勤労する美徳を復活しなくてはならない。
日本農業新聞 2018年3月5日
「スマート・テロワール(美しくきょうじんな農村自給圏)」の提唱者、松尾雅彦氏が亡くなった。松尾氏は、米の低価格と畜産加工品の高価格に着目し、「水田を飼料用トウモロコシなどの畑に転換し、家畜飼料からハム・ソーセージ、チーズなどの加工品までを農村内で一貫生産することで、より多くの付加価値を農の現場に落とす」ことを唱えておられた。
飼料を自家生産すれば、飼料代が出て行かなくなる。加工品を自家生産すれば、原料代と加工品価格との間の大きな差も、生産者のものになる。それだけ農村に落ちる「付加価値が増える」=「経済成長する」わけだ。その場合に農協はどちら側なのか(農村の取り分を増やす側か、農村からお金を取る飼料販売業者なのか)ということも、氏は問うていたと思う。
どちらがプラス
ところで、付加価値が飼料販売業者や食品加工業者のものになるのと、「スマート・テロワール」の実践で農村にとどまるのを比べた場合、国全体の経済にはどちらがプラスだろうか。単純な経済学では「どちらでも同じ」だ。
経済学「風」の俗世間的イメージでは、「小規模農家よりも大企業がもうけた方が、何となく国全体にはプラス、って感じ?」かもしれない。だが現実に立ち帰れば、農村部のもうけが増えた方が、大企業がもうけるよりも、国全体の経済成長への寄与は大きいのである。
というのも日本の大企業は、もうけを現金としてため込むばかりで、投資をするにしても海外向けが多く、国内の経済循環拡大への貢献が乏しい。これは、ここ数年の株高と大企業収益の増加が、全くと言っていいほど個人消費の拡大につながっていない現実からも明らかだ。
他方で現場の農業者は、もうかれば規模拡大に投資し、雇用も増やす可能性が高い。それにより国内の経済循環は拡大する上、出生率の著しく低い首都圏以下の大都市部から一人でも多くの若者が農山村に移住すれば、それだけ日本全体の人口減少にも歯止めがかかる。
チャンス手放す
政治家の多くは、経済学「風」のイメージに思考を染められているだけで、こうした現実を理解しているようには見えない。経済学者の多くも机上の定式を語るだけで、「大企業にお金を集めることが日本の経済成長につながっていない」と言う、明らかな現実には目をつぶっている。
農業者の多くも、経済成長一辺倒の政策や規制緩和万能の安直な風潮には反発するものの、自分の行動としては大企業から飼料や肥料や農薬や燃料や資材を無自覚に買い続け、農村の経済を成長させる機会を逃し続けている。
今般、各紙に載った松尾氏の訃報は「カルビー三代目社長、現相談役」というものばかりで、「スマート・テロワール」には触れていなかった。北海道美瑛町との縁から「日本で最も美しい村連合」の副会長を務めていたという記述もない。
訃報までが大企業側、東京側の視点だけで書かれてしまったことは、松尾氏としても無念だったのではないだろうか。
せめてのはなむけに、遺志を継いで農村の取り分を増やそうと志す農業者が一人でも増えることを、願ってやまない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
まず故人に対し慎んで哀悼を表します。
経済学「風」の俗世間的イメージでは、「小規模農家よりも大企業がもうけた方が、何となく国全体にはプラス、って感じ?」かもしれない。
これこそが重商主義の発想である。
重商主義とは16世紀半ばから18世紀にかけて西ヨーロッパの絶対王政国家で行われた政策であり、「富とは金(や銀、貨幣)であり、国力の増大とはそれらの蓄積である」と考えていることが特徴である。
そして、その実践として植民地からの搾取、他国との植民地争い、保護貿易などを行った。
また、極端に「輸出を増やして、輸入を少なくする」という貿易差額主義を取った。
そのため重商主義は必然的に他国との対立に繋がるものである。
近世から近代では西洋諸国は見苦しい植民地戦争を繰り広げた。
やがて重商主義は近現代の資本主義の基礎となり、戦争や格差社会、富む国と貧しい国、南北問題や無計画な開発による資源の枯渇と環境破壊を招いた。
まさに、重商主義と資本主義が世界の人々を苦しめ、地球を破壊してきたのである。
しかし、資本主義や金融というものは「貨幣から富を作る」もので、その実体は「無から財産を作っている」のに等しい。
この重商主義を批判したのが、18世紀後半フランスのフランソワ・ケネーなどによって提唱された重農主義である。
ケネーは『経済表』を作成してその自然が形成する秩序の姿を明らかにしようとした。彼は社会は神によって創造された自然秩序に基づいて形成されるものとして人為的な社会契約説には批判的であった。自然秩序は物理・道徳の両法則によって形成され、自然法と実定法はこれを制御するために生み出されたものである。人間は自然法則によって自己の欲望を満たしたいとする欲求を実現する権利を持っており、その実現を保障するのが自由権と財産権であり、国家は実定法を用いてこれを保障する義務を持つと唱えた。
つまり近代に入ってから人間中心主義・人間至上主義・科学万能主義に陥り自然を人間の力で制御できるとする思い上がりが始まった時代に、神や自然を尊ぶことを唱えたのだ。
また、彼は農業によって生み出された剰余価値(純生産物)が農業資本の拡大再生産をもたらすとした。一方、商工業は農業がもたらす原材料がなければ何も生産出来ず、生産者としての価値は存在しない。農業生産の拡大再生産による恩恵が原材料などの形で商工業に流れることで初めて商工業が発展するという本質的な主張をした。
「富は土地から生まれる」という当然の主張である。
このような自然を尊重し、農業を重視する発想は東洋の影響を受けていた。
18世紀はイエズス会によって中国を中心とする東洋の思想がヨーロッパに紹介されていた。
東洋では古来、「農は国の本」とする農本思想が受け継がれてきた。
この重農主義と農本主義は国家の基礎を守る理にかなった考え方である。
日本でも明治維新以降、急速に近代化・西洋化が進み、農村社会が崩壊の危機に晒された。
そのため北一輝先生をはじめとする昭和維新の思想家や青年将校たちは資本主義を批判し、国家社会主義と共に農本主義を掲げたのである。
同じように、イタリアのファシストやドイツの国家社会主義者は農業や自然を尊重する真の愛国主義を説いた。
特にドイツのアドルフ・ヒトラーをはじめ国家社会主義労働者党の幹部は菜食主義者が多く、自然保護・自然回帰を主張していた。
国家社会党は「自然は民族の喜び」と説いていた。
自然こそ民族の宝であり、世界の宝なのである。
重農主義・農本主義こそ自然環境を守り、資本主義の矛盾を解決して民衆を救う世界平和の道なのである。
私達ファシストは、祖国を愛するが故に民族の財産たる自然を守り、国家の礎である農村の発展を誓うものである。
そのためには、資本第一主義に陥った経済思想の堕落を正し、土地の尊重と額に汗して勤労する美徳を復活しなくてはならない。















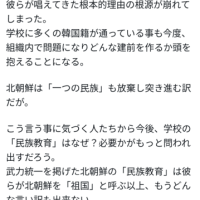
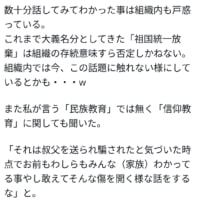



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます