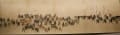次の画は、「火消千組の図絵馬」(天保4年・1833、歌川国芳/画、
成田山霊光館・原資料所蔵、Procession of Edo Firemen)。
江戸町火消しの「千組」(現在の中央区霊巌島辺りを受け持つ)の
行列を描いたもの。梯子を先頭に鳶口などの道具を担いだ火消人足
が続いている。真ん中では組纒が威勢良く舞っている。

次の画も火事にまつわる、「火事図巻」(文政9年・1826、長谷川
雪堤/画、Picture Scroll Depicting Major Fire in Edo)。
明和9年(1772)に起きた目黒行人坂の大火を描いている。火消し
たちが屋根に登り、纒を振るい鳶口や龍吐水を使って火を沈めてい
る光景。

次の画は「五番こ組」(安政6年・1859、歌川芳虎/画、Woodblock
Print Depicting Edo Fireman)。火消しのお兄さんと組纒は江戸の華。

火にも負けない防護服「刺子半纏」(19世紀、Fireman’s Quilted
Jacket)が展示されていた。布に糸で細かく刺繍した“刺子”は、丈夫
な着物で、水を含ませれば火にも強いので消防服としても重宝がら
れた。
江戸東京博物館(墨田区横綱1-4-1)
成田山霊光館・原資料所蔵、Procession of Edo Firemen)。
江戸町火消しの「千組」(現在の中央区霊巌島辺りを受け持つ)の
行列を描いたもの。梯子を先頭に鳶口などの道具を担いだ火消人足
が続いている。真ん中では組纒が威勢良く舞っている。

次の画も火事にまつわる、「火事図巻」(文政9年・1826、長谷川
雪堤/画、Picture Scroll Depicting Major Fire in Edo)。
明和9年(1772)に起きた目黒行人坂の大火を描いている。火消し
たちが屋根に登り、纒を振るい鳶口や龍吐水を使って火を沈めてい
る光景。

次の画は「五番こ組」(安政6年・1859、歌川芳虎/画、Woodblock
Print Depicting Edo Fireman)。火消しのお兄さんと組纒は江戸の華。

火にも負けない防護服「刺子半纏」(19世紀、Fireman’s Quilted
Jacket)が展示されていた。布に糸で細かく刺繍した“刺子”は、丈夫
な着物で、水を含ませれば火にも強いので消防服としても重宝がら
れた。
江戸東京博物館(墨田区横綱1-4-1)