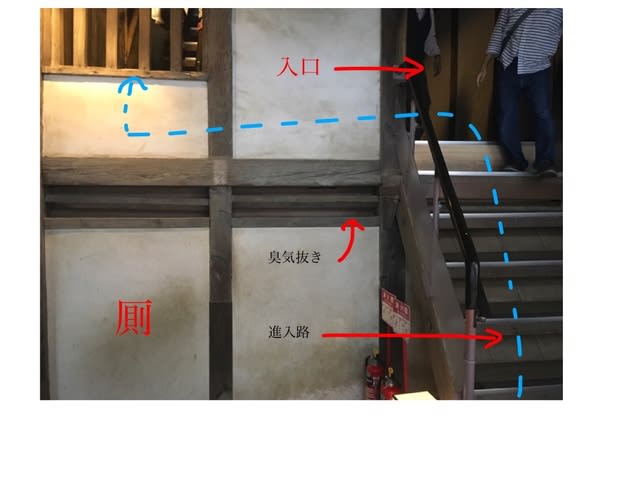以前、と言ってもずいぶん前ですが、「東大柱と西大柱の形が違うのはなぜ?」←タップしてください。
という記事で、三左衛門は大胆な推理をしました。すなわち「東大柱はもともと丸いからそのままで、西大柱は取り替えたことが直ぐ分かるように四角に加工した」
ところが、先日、元姫路城シルバー観光ガイドで、現在関西城郭研究会会長の森喜一さんからこんな資料を頂き、考え直すことにしました。以下引用します。
柱形状が東大柱は〇で、西大柱は▢であるのは!
三階で東西両大柱を見比べると、東大柱は丸柱であるのに西大柱は角柱である。
なぜでしょうか。
・東大柱は一本の通し柱でほぼ素材の形状のまま使われているので丸柱に近い
形状は理解できる。
西大柱は二本継ぎで三階に接手部がある。上下柱が素材のままでは接手部で
下部材と上部材の太さが大きく異なるので、それを同一寸法に調整する必要が
ある。そのために角柱に削り出し接手部を加工したことと想定される。
・旧西大柱も同様に接手部以上を角柱に加工しているので、あるいは単に新西
大柱も旧西大柱の組手部形状に倣ったものなのか。
・姫路城の建築物の柱はすべて角柱である。それ故東大柱の円柱(素材のまま
の形状)が特異と言える。東大柱の最頂部はかなり細く、これを角柱に加工する
と最頂部の平面積が65%(真円ならば)に減少してしまう。これでは荷重に耐え
られないと考えたのでしょうか。
<参考>東大柱の最上部は約50cm×約35cmの楕円形、西大柱の最上部は56cm×44cmの長方形
以上引用終わり
なるほどと思いました。西の大柱の下部は岐阜県の国有林から切り出されたヒノキ、上部は兵庫県神崎郡市川町笠形神社のヒノキで大天守3階でつないであります。だから、「下部材と上部材の太さが大きく異なる」のは明らかであり、下部材と上部材をつなぎやすくするため角柱にして同一寸法に加工したのだと思われます。それに加えて接続のための技術的な種々の問題のために角柱にしたと推理されます。
「姫路城の建築物の柱はすべて角柱である。それ故東大柱の円柱(素材のままの形状)が特異と言える。」
うかつでした。姫路城の建物内では円柱の梁も数多くあるので柱が東大柱を除いてすべて角柱だという事に思い至りませんでした。700回も登城していて恥ずかしい限りです。ということで、前回の記事は訂正します。「菱の門の名前の由来」に引き続き、今回も森喜一さんから助言を頂きました。深く感謝申し上げます。また、他にも三左衛門の推理は無理があると指摘してくださった方もいらっしゃいます。合わせてお礼申し上げます。