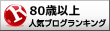祭神は武略に長けた坂東武者、平将門である。
ところが、この武将、平安中期であるが、平氏一族の紛争に乗じ、関東一円を争乱に巻き込み、常陸、下野、下総などの国府(朝廷が国ごとに決めた出先官庁)を奪い、印綬を取り上げてしまった。
そのうえ、京の朝廷にならい、文武百官を任命し、自ら天皇を名乗って関東を独立させようとした空前絶後の破天荒な人であった。
平将門の乱、あるいは天慶の乱といわれる。
結局、天慶3年(940)、藤原秀郷、平貞盛らによって討たれ敗死した。
明治維新ののち、明治天皇の膝元近くに、逆臣将門を祀る社があるのは、不都合とされて、神田明神の祭神から外されてしまう。
ところが、戦後になると、朝廷の横暴に立ち向かった関東武者として、それこそ名誉を回復され、ふたたび祭神に復活したのである。
時代のご都合主義がうかがえるありさまだが、明神さんは、今でも、東京の町民に親しまれ、夏の祭礼は、東京の三大祭りと謳われている。
築地の魚河岸も、皆ここの氏子なのだ。
将門にゆかりのある地、話は、関東一円、ほうぼうにいろいろある。
私のいる佐倉市にも、将門という町名がある。