
新宿ゴールデン街にあった「BAR真紀」(左側手前)。真紀が他界してそれほど時が経っていない頃だろうか、真紀を偲ぶ人が置いた花はそれほど多くない。
新宿ゴールデン街に「BAR真紀」という店があった。女性になった元男性の真紀ちゃんが経営する小さくて古びたスナックである。真紀ちゃんといっても昭和10(1935)年生まれだ。そして平成27(2015)年の暮れ、80年の生涯を閉じた。以下は、真紀ちゃんを真紀と呼び捨てにします。僕が彼女をそう呼んでいたのでそのほうがしっくりくるのです。
ザ・ノンフィクション
亡くなる2年前の平成25(2013)年4月7日、フジテレビの「ザ・ノンフィクション」で真紀のドキュメンタリーが放送された。題名は『せつなくて 故郷~女になって47年目の帰郷~』。引き続き、亡くなった翌年の平成28(2016)年3月27日、後日談を少し加えた『アンコール特別編/せつなくて 故郷女になって47年目の帰郷 その後』が放送された。その時には真紀は故郷である鹿児島県枕崎市の墓に入っていた。
番組の内容はこうだ。真紀が76歳の時に、かつて店で働いていたつぐみちゃんから勧められて、47年ぶりに枕崎に帰り、96歳の母親と涙の対面をする感動のドキュメンタリー。実は僕は、この放送の数年前に枕崎市で真紀の弟さんと会ったことがあるのだが、その時のことはおいおい話していくことにする。
新宿ゴールデン街
僕がBAR真紀に通い始めたのは、真紀が70歳になる前だった。その頃、僕の家は新宿区にあった。訳あってビデオ制作会社を辞め、フリーランス3人でシェアをして九段坂に事務所を借りて、その時のシェア仲間であったデザイナーの紹介で、ゴールデン街に足を踏み入れたのだ。僕が50歳の頃だ。
ゴールデン街は久し振りだった。その昔、僕が20代の頃、最初に入った会社の副社長のお供で何度か行ったことがある。流しのお兄さんが来て、とてもよろしきところだったけど、一人で通うほどの度胸も、また、趣味の方向も少し違っていた。金があればジャズのライブに行きたい年頃だったから。やっとゴールデン街に漂う風が肌に合う年頃になって来たのだろう。
とんぼ
デザイナーに紹介されたのは、BAR真紀じゃなくて「とんぼ」という店だった。とんぼのママは、やがて、津軽三味線の名手である高橋祐次郎のラスト2年を追いかけた『祭爆 SAIBAKU─までぃに三味線奏でるべ』というドキュメンタリー映画を企画することになる。監督は、とんぼの常連中の常連(それ以上は書きません)でゴールデン街では「とみさん」と呼ばれた冨沢満さんだ。冨沢さんは、とんぼのママより5歳ほど年上で元NHKのプロデューサーかディレクター。『井伏鱒二の世界』他、数多くの秀作ドキュメンタリーを作った人である。ちなみに冨沢さんのお父さんは、戦前の芥川賞作家である冨澤有爲男だという。
話を戻す。とんぼのママは在日朝鮮人だ。祭爆のスタッフリストには「企画:蘇秋月」とある。それがとんぼのママだ。ゴールデン街は当初、在日朝鮮人を受け入れてはいなかったらしい。その突破口を開くために尽力したのが真紀なのだ。
僕がとんぼに通い始めた頃、決まって客として来ていたのが真紀だった。その当時、真紀は女の子を雇っておらず、毎日閑古鳥が鳴いていた。それで、話を交わすようになって、「うちにもいらっしゃいよ」と誘われたのだ。
とんぼとBAR真紀
とんぼとBAR真紀は、ゴールデン街の同じ路地にあった。はす向かいというよりは少し距離が離れていたけど、歩けて1分とはかからない。
少し両店を比較しておこう。とんぼがシックなスナックというならBAR真紀は場末のスナックという作り。BAR真紀のカウンターは朱塗りのボードで、ステンドグラスやら、埃をかぶった人形やら、煤けたレースがぶら下がっていたりで、趣味はあまりよろしくない。とんぼには僕の嫌いなカラオケはなかったけど、BAR真紀にはあった。とんぼは明朗会計だったけど、BAR真紀は不明瞭会計だった。とんぼの客層にはいわゆる文化人が多かったが、BAR真紀の客層はなんでもありのカオス状態だった。飛び交う会話も、とんぼのそれには知性の薫りがしたが、BAR真紀は下ネタが多かった。
明らかにとんぼのほうが僕好みの店だった。しかしやがて、真紀の店に行く回数のほうが多くなっていくのである。
つづく
















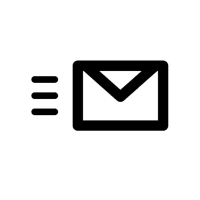

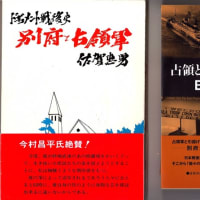
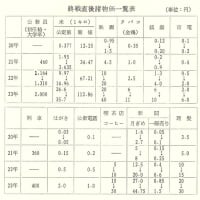
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます