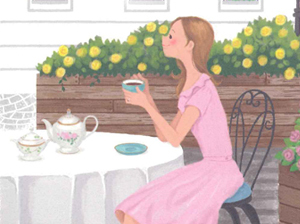2月のラボ便り
2月のラボ便り
皆様、こんにちは。
2月になりましたが、まだまだ寒さが続きます。
風邪など引かれないよう防寒対策をしっかりとしていきましょう。
今回のラボ便りでは、「受精卵(胚)の凍結保存」についてお話しします。
採卵手術で採れた卵は体外受精や顕微授精によって受精させ、2〜6日間インキュベーターで培養します。
無事に受精が確認でき、しっかりと成長している受精卵(胚)を培養2,3日目もしくは5,6日目に凍結して保存します。
受精卵(胚)の細胞のほとんどが水分です。
水は凍らせると体積が大きくなります。
そのため、受精卵(胚)をそのまま冷却すると細胞内の水分が凍って体積が増えるので、細胞が物理的なダメージを受けてしまいます。
これを回避するため、受精卵(胚)凍結時には凍結保護剤で受精卵(胚)の水分を取り除き、液体窒素(−196℃)に入れ急速に冷却し凍結します。
受精卵(胚)を凍結保存するメリットとして、おもに以下のものが挙げられます。
①患者さんの負担の軽減
採卵手術をして複数個の胚を凍結できた場合、1度の採卵手術で複数回の移植が可能になります。
そのため、採卵手術を行う回数を減らし、それに伴う経済的、身体的負担を軽減できます。
また、凍結胚は技術的には半永久的に保存が出来る為、保存年数が経過しても、劣化することはありません。
ですので、将来的にお2人目、3人目のご妊娠を考える際、残っている凍結胚を用いることでより早い結果を期待出来ます。
②ホルモン環境
採卵周期は排卵誘発により、多くの卵胞が育ちます。
そのことから卵胞から出るホルモン値が高くなり、着床に向かない子宮環境になることがあります。
したがって、採卵周期に移植せず一度受精卵(胚)を凍結し、着床に適した内膜状況をつくった移植周期に合わせて融解移植することで子宮と胚の発育を同調させることができ、妊娠率の改善に繋がります。
③多胎妊娠の回避
一度の採卵手術で複数個の胚を得られた場合、それら全てを移植してしまうと双子や三つ子以上の多胎妊娠となる可能性があります。
多胎妊娠は流産・早産の危険が高い、妊娠高血圧症候群の頻度が高いなど、胎児にも母体にもリスクがあります。
そのため、移植しない胚を凍結保存し、一度に移植する胚の数を減らすことで多胎妊娠を予防します。
④卵巣過剰刺激症候群の回避
採卵時の発育卵胞数が多いと、卵巣過剰刺激症候群のリスクが高くなります。
卵巣過剰刺激症候群は妊娠に伴って増悪する可能性が高いため、受精卵(胚)を全て凍結し、次周期以降に移植することで予防します。
何かご不明点がございましたら、スタッフまでお声がけください。