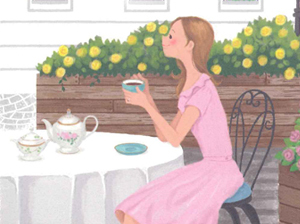10月のラボ便り
10月のラボ便り
皆様、こんにちは!
10月に入り、今年も残すところあと3ヶ月となりました。
このところ朝晩の日中の気温差が激しく、体調を崩しやすい気候が続いております。
新型コロナウィルスに加え、インフルエンザが流行する時期にもなりますので、
しっかりとうがい・手洗い・手指消毒・マスク着用等の対策を徹底して参りましょう。
今回のラボ便りは、「受精障害」についてお話します。
受精障害とは、
体外受精を行い、十分な数の精子があるにも関わらず受精卵が得られない、
もしくは受精率が低い場合をいいます。
つまり、受精障害かどうかというのは、体外受精を行って初めてわかることです。
受精障害の定義は、
受精率25%以下の場合とされています。
さらに、体外受精を3~6周期繰り返しても妊娠に至らない場合を、
受精障害と判断することもあります。
では、受精障害になる原因とはいったい何なのでしょうか。
原因は卵子・精子それぞれに問題が考えられます。
まず、卵子に問題がある場合の原因としては、以下の3つが考えられます。
・採取された卵子が未熟で受精する能力を持たない。
・卵子の殻(透明帯)が固かった、厚かったなどにより精子が入って行けていない。
・受精に必要な卵子の活性化が起こらない。
続いて、精子に問題がある場合の原因は、以下の2つが挙げられます。
・精子の機能的な問題(運動性が低いなど)により、卵子の透明帯を通過できない。
・卵子を活性化させる因子をうまく放出できない、または因子を持っていない。
透明帯を通過できていないことが原因の場合は、
顕微授精により解消することができます。
何らかの原因で卵子が活性化されていない場合には、
活性化を促す処理を実施すれば、解消することができることもあります。
卵子が未熟な場合には、
卵胞の誘発方法を変えることにより、成熟卵を得られるようになることがあります。
ただし、一度の体外受精での結果が悪かった=受精障害とは断定できません。
何かご不明な点等ございましたら、お気軽にスタッフにご質問ください。