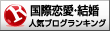billygrahamlibrary.org
William Franklin Grahamは、高名な伝道者で、日本でもビリー・グラハムと言ったらおそらくわかる方もいらっしゃると思うが、99歳で2月21日亡くなった。日本へも四回、1956年、1967年、1980年、1994年と訪問し、ビリー・グラハム国際大会を開催した。現に、のびたさん(のびたとブレイク)は、ご両親と兄上と、日本でのビリー・グラハム氏の大会へ足を運ばれたとおっしゃり、その後ご両親と共に影響を受けた兄上は、神学校へ進み、牧師となられた由。のびたさんご自身、音楽を通じて奉仕活動をなさっていらっしゃる。
グラハムは、第二次世界大戦後、福祉の充実を図るため、福音の価値をアメリカ人に思い起こさせるべく、伝道師として活発に説教するスタイルで名声が上がった。彼の力強い話し方は、1949年にロサンゼルスのダウンタウンのテントに35万人を誘ったのである。最初の主要なビリー・グラハムの集会であり、65の説教をした後、魅力的な説教者として世界中で知られた。 やがてグラハムは、アメリカの伝道師と呼ばれ、トルーマン大統領の1950年代から何十年にもわたって、12人のアメリカ大統領と知り合い、保守的な人で民主党支持者ではあったが、共和党、民主党のどちらの大統領とも親しくし、ビル・クリントンと共に祈ったこともあった。日本では、彼がアメリカの保守派を中心とした政界に強い影響力があった、と報道するが、実際は、本人も晩年述べていたように、政治的ではなく、霊的な精神的な支えとなっていたにすぎない。

https://www2.wheaton.edu/bgc/archives/exhibits/LA49/01intro.html
グラハムは、また英国のエリザス女王とも親交があり、NetflixのThe Crownシリーズをご覧になっていらっしゃる方は、シーズン2、エピソード6で、彼が女王に会見しているのをご存知と思う。伯父の元キングエドワード8世が、離婚者のアメリカ女性(ウオーリス・シンプソン)と結婚したことによって、その重責を弟であったエリザベスの父に押し付け、さらに第二次世界大戦中にナチスと友好的になり、弟王を転覆させようとするドイツの企てに加担、英国爆撃の助けともなった。その事実は戦後になって、次第に明るみに出て、エリザベスは、その伯父を赦すべきか、非常に悩む。その時グラハムは、女王に、赦しがたい人のために祈ることを進言したのである。彼は、「私はただのキリスト者ですから」と常に謙遜であったので、女王にも好かれた。
1970~1980年代のジェリー・ファルウェル的なクリスチャンを票田にするかのような宗教活動や、政治に影響を及ぼそうとする信仰コミュニティを避けるため、次第にグラハムは、政治的行為・活動を控えて、むしろ持てるエネルギーを、人道的な理由に使うようにしてきた。1987年彼は、「私は、それ(政治的活動・行為)を避け、ただキリストの福音を述べ伝えたいのです。何故ならば、ワシントンや政治的な場所からは、世界を助け、男女共に、よりよい存在となるために、(必要なことは)一切出てこないからです。そうお出来になるのは、キリストです。」と述べた。生涯福音主義のキリスト教徒を、公共の広場に引き寄せ、政治的力となることを助けた伝道師は、人生の終わりに近づいて、やはりイエスキリストを礼拝することへ、帰依したのだった。
現在の副大統領マイク・ペンスは、妻以外のどの女性とも一対一の時間を持たないことで有名だが、それは、ビリー・グラハム流と言われる。グラハムが、生涯どんな時でも、昼食や空港への乗り継ぎ時間でも、妻以外の女性と二人きりで時を過ごすことは、一切なかった、とロサンジェルス・タイムズ紙が報告している。そして彼は、自らの財政規制のために、切った(支払いに使った)小切手は、必ず残高記入するシステムを設定していた。小切手(チェック)と残高記入は、balancing your checkbookと言うが、アメリカなら誰もが、個人のチェックブックに残高を記入して、きちんと管理すべきことだが、それが必ずしもできないので、いろいろ問題が起こるわけである。それをきちんとし、女性問題を一切寄せ付けない高潔さを持ち、実践していたのが、グラハムであった。
「グラハムが自分の利益のために何百万人もの人々の注意を簡単に指示できたろうに、彼はプライベートで謙虚な人生を生きることを選んだ」と、テネシアン紙にThe Rainer LifeWay Christian ResourcesnoのCEOであるライナー氏は、述べた。そしてこう付け加えた。「彼の人生で、焦点を当てるべきは、自分自身ではなく、一つのこと、すなわち十字架上のイエス・キリストであることをずっと願ってきたのです。」
その高潔なキリスト者は、晩年病をいくつか得た末、昨日、99歳で神の御顔に触れたのだった。John Gillespie Magee, Jr.の有名な詩、”High Flight"の如くに。
High Flight
by John Gillespie Magee, Jr. (1922-1941)
Oh! I have slipped the surly bonds of Earth
And danced the skies on laughter-silvered wings;
Sunward I've climbed, and joined the tumbling mirth
Of sun-split clouds, — and done a hundred things
You have not dreamed of — wheeled and soared and swung
High in the sunlit silence. Hov'ring there,
I've chased the shouting wind along, and flung
My eager craft through footless halls of air… .
Up, up the long, delirious burning blue
I've topped the wind-swept heights with easy grace
Where never lark, or ever eagle flew —
And, while with silent, lifting mind I've trod
The high untrespassed sanctity of space,
Put out my hand, and touched the face of God.