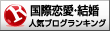結婚して何年経っても、金曜日の夜は、「デートナイト」を長年続けていたので、子供達夫婦も両親を見習っている。たいしたことをするわけではなく、少しの時間に、夫婦で散歩したり、映画と食事、ウィンドウショッピング、コンサート、あるいは親しい友人夫婦とのダブルデートでボードゲーム、などごく気軽に、簡単にできることを楽しむ。ほんの少し時間を取れば済み、初心を忘れずに会話を楽しみ、忙しい週日へのちいさなご褒美と思えれば、それで良い。
もちろん信頼できるベイビーシッターのリストは作ってあったので、ほんの2,3時間でも必ず子供たちは緊急時に必要な対処ができる人々に守られていた。やがて子供達が成長し、学校へ、社会へ、そして自分たちの新しい家族へと飛び立ってからも、両親はデートを続けてきた。
去年、病床に伏し始めた夫でも、病院ベッドを置いた自宅階下の部屋に座り心地のよい椅子を私のために息子たちが持ってきてくれて、私は彼のベッドのとなりに座りながら、二人で昔の名画を鑑賞したり、読書をしたり、昔話をして楽しんだ。旅立ちがまもないことを知っていても、悲壮感に包まれることなく、実に様々なことについて語り、微笑み合い、楽しかった。
先週の金曜の晩は末娘夫婦が、そんなデートをするので私は孫二人のお守りをした。7時には寝かせて、との指示だったので、散々それまで二人と遊び、上の子はパジャマに着替え、歯磨きをし、就寝前の祈りをしてから、ベッドに入り、そのまま眠りについた。
下の子は一旦はクリブで横になっても、モニターを見ると、クリブの柵につかまって立っている。「眠れないのね、それじゃ、ララバイでも聞く?」と私は携帯電話にあるブラームスのララバイを聴かせ始めた。横抱きにして揺り椅子に腰掛けて優しく背中をなでていると、この子の言葉で一生懸命話始めた。「まあ、本当に?それじゃあ赤ちゃんでいるのも大変だわね。」と相槌を打っていると、薄暗さの中で携帯のララバイの静かな光が、この子の大きく開かれた瞳に反射して、まるで清廉な星空のように見えた。
「そのお目目で、おじいちゃん、見えている?おじいちゃんはとてもとても子供達もそのまた子供達も大好きで、今だってきっとあなたや私のそばにいると思うわ。」と私はこの子を抱きしめて言った。答えない代わりにこの子は腕を伸ばして私の頬にそっと触れた。その時、夫がそばにいる気配を感じ、大きな安堵感のような暖かさを覚えた。
この子は夫が発病してから4ヶ月目に生まれ、その2ヶ月後に夫は逝ってしまったが、この子の祝福式(Baby Blessing)には病床にありながらも参加でき喜んでいたのだった。娘とは、「お父さんはまるで、ご自分でハンドピックしたようにこの子を慈しんできたのではないかしらね。たとえ私達の目には見えねども。」などとよく話してきていた。その子の美しい宇宙のような瞳を見ていると、不意に落涙が頬を伝わるのを感じた。
「ああ、やっぱり。貴方は今ここにいらっしゃるでしょう?金曜日の晩ですものね。。。私は大丈夫よ。この子も、そろそろおネムみたいよ。訪問してくれてどうもありがとう。」と心の中で問うた私は、腕の中に目を落とすと、幼な子は、ほぼ寝落ちしていた。
クリブにゆっくりと子供を戻すと、すやすやと静かに息をしながら、眠っている。それを確認して、その部屋を後にした。あの瞳の清廉さと、そこに見えた宇宙の神秘さと、暖かさについて思いを寄せていると、心はとても豊かになっていた。旅立った今でも金曜の晩のお約束ごと、二人のデート、忘れていなかったのね。ありがとう。