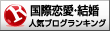Little River Inn
金曜日に休暇を取り、夫と二人で、ウィークエンド・ゲッタアウェイへ。 ここから三時間程の北加のコースト沿いの小さな町二つを訪問した。まずはソノマ郡のサンタロサにあるチャールス・M・シュルツ博物館*(ここ)を訪問した。昨秋の大規模山火事がこの建物の一マイルほど手前で、やっと収まり、危うく難を逃れている。 隣接するスヌーピーのホームアイスこと、レッドウッド・エンパイア・アイス・アリーナは、1969年シュルツ氏が設立し、現在でも営業され、公共的にも個人的にも使用ができる。サンタロサの喧噪を離れたところに位置するこの二つは、大人も子供も十分楽しめる。


Charles M. Schulz Museum and Research Center / ”スヌーピーのホームアイス”



チャールス・シュルツとピーナッツの世界をしばし堪能し、私達はパシフィック・コースト・ハイウェイ(California State Route 1)沿いにあるメンドシーノ郡リトル・リヴァーへ向かうため、うっそうと繁るレッドウッドの森をくねくねと縫うようにある道をしばらく走った。 その森を抜けるたび思うのが、デイズニー映画Darby O'Gill and the Little People(1959年・邦題:四つの願い)の世界である。 この映画をご覧になった方は、納得がゆくことだろう。


森の中を通る時の写真と「四つの願い」のポスター https://en.wikipedia.org/wiki/Darby_O%27Gill_and_the_Little_People#/media/File:Darby_o_gill_and_the_little_people.jpg
ゴールドは発見されなかったが、19世紀にはメンドシーノ郡の豊富なレッドウッドを切り出す林業が盛んになり、多くの人々を国の内外から寄せた。 大きなレッドウッドを切り出し、丸太を船に乗せて各地の製材所へ移送した。その輸送方法は、切り出した丸太をいくつかロープでまとめ、それを原始的なクレーンで持ち上げて海上の船へ降ろす、という恐ろしく不安定で危険な作業だった。 波止場などまだ定着していなかった時代でも、そうしてまでビジネスを成り立たせる意思は、とてつもないものだと感心する。 その後1885年に森林を抜けて内陸へ切り出したレッドウッドを運ぶ鉄道ができ、現在そのラインは、スカンクトレインとして観光客を乗せている。 下はその丸太を運ぶ汽車。 レッドウッドはとにかく大きいので、切り出しもさることながら、その運送もなかなか危険で、なるほど尋ねた小さな墓地には、切り出しや運送工程で亡くなった男性の墓石が多いわけである。

Pinterestから

https://www.winecountry.com/regions/mendocino-county/coastal-mendocino-county/mendocino/
上の写真はメンドシーノの町並みであるが、見覚えのある方もあるかもしれない。これは、”Murder She Wrote"シリーズ(邦題:ジェシカおばさんの事件簿)の最初に出てくる、メイン州のキャボット・コーブの町のつもり、な所である。 母はこのシリーズが大好きだったが、その娘も劣らずに気に入っていたショウである。 母を一度連れてきたかったものだと来るたび思う。 ジェシカ・フレッチャーを演じたアンジェラ・ランズベリーの年を重ねても矍鑠(かくしゃく)とした姿は、私にとって老いることの見本である。

https://mainecrimewriters.com
以前来た時*も寄ったのだが、リトルリヴァーのインの近く、カリフォルニア・コースト・ハイウェイ1に沿って小さな墓地がある。早朝にホテルを抜け出して夜霧に濡れた道や墓地内をぬかるみを避けて歩く。 ハイウェイには車の通りが、ほとんどなく、静寂な厳かな墓地である。 もちろん誰一人いず、一つ一つの墓石を読みながら歩いた。 ホテルからの出がけに「連れてこないでよ。」とベッドの中から夫は言ったが、大丈夫、塩パケットはちゃんと持っているから。 ゆっくりと墓地を回り、ある墓石の前でその墓碑銘を読んでいた時、突然パタパタと子供が駆け回るような音がすぐ後ろでしたので、子供がもう墓地にやってきているのか、と後ろを振り返ると、誰もいない。 「あら?やっぱりどなたか、ついてきたいのかしら?」と思ったが、すぐそれは、墓地中央に建てられている旗ポールに、常時掲揚されている星条旗が、夜露で濡れ、風になびき、ポールをたたきつけるかのようにぶつかっている音だと気がついた。 丁寧に墓石を読んだ後、リンクフェンスの門をきっちりと閉じ、塩を肩越しにふりかけ、墓地のほうを向いてお辞儀をしてホテルへ戻った。
この続きは次の機会に。