今日は、「紅梅」と「ウグイスの誤解」について書いていきたいと思います。
●万葉時代に日本に紅梅はなかった
昨日、『万葉集』にウメを詠った歌は119首あると書きましたが、そのうちの28首はウメのことを「雪」と見立てる歌があります。
多すぎやしませんか?
ということで、紅梅はなかった、という結論らしいです。
平安時代になって清少納言が出てくると、『枕草子』の「木の花は」に
木の花は、濃きも薄きも紅梅。桜は、花びら大きに、葉の色濃きが、枝細くて咲きたる。藤の花は、しなひ長く、色濃く咲きたる、いとめでたし。
と、木の花の筆頭に紅梅が書かれています。その頃にはもう普及していたんだなとうかがえます。
●メジロ
よく、「うめとうぐいす」をセットにして言われますよね。ところが! それは大伴家持の歌による誤解なのです。
ウメの時期にウグイスは来ないし、ウグイスは花の蜜より虫を好んで食べます。
そう、ウメとウグイスは全く関係ないのです。
全てはメジロの誤解でした(;´∀`)
誤解の原因の歌。
原文は見つからなかったのですが、
鶯の鳴きし垣内(かきつ)ににほえりし梅この雪に移ろふらむか
[作者]大伴家持
訳:ウグイスが鳴いている垣根の内に色が映えてて梅(白梅)は今降っている雪に混ざって散っちゃうのかな?
↑このウグイスは、メジロの間違いです。
●万葉時代に日本に紅梅はなかった
昨日、『万葉集』にウメを詠った歌は119首あると書きましたが、そのうちの28首はウメのことを「雪」と見立てる歌があります。
多すぎやしませんか?
ということで、紅梅はなかった、という結論らしいです。
平安時代になって清少納言が出てくると、『枕草子』の「木の花は」に
木の花は、濃きも薄きも紅梅。桜は、花びら大きに、葉の色濃きが、枝細くて咲きたる。藤の花は、しなひ長く、色濃く咲きたる、いとめでたし。
と、木の花の筆頭に紅梅が書かれています。その頃にはもう普及していたんだなとうかがえます。
●メジロ
よく、「うめとうぐいす」をセットにして言われますよね。ところが! それは大伴家持の歌による誤解なのです。
ウメの時期にウグイスは来ないし、ウグイスは花の蜜より虫を好んで食べます。
そう、ウメとウグイスは全く関係ないのです。
全てはメジロの誤解でした(;´∀`)
誤解の原因の歌。
原文は見つからなかったのですが、
鶯の鳴きし垣内(かきつ)ににほえりし梅この雪に移ろふらむか
[作者]大伴家持
訳:ウグイスが鳴いている垣根の内に色が映えてて梅(白梅)は今降っている雪に混ざって散っちゃうのかな?
↑このウグイスは、メジロの間違いです。















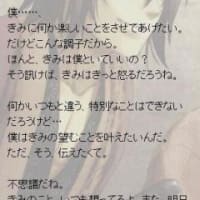

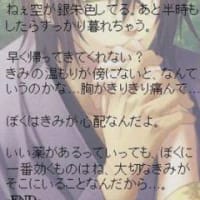

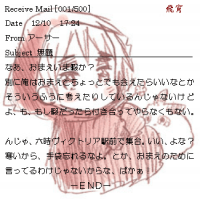
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます