
ということで公演当日。ビンボー人専用の三階天井桟敷席に座っていたのである。

さて幕が上がるとモンテ・ヴェルディならぬ
モン・ブランが舞台にそびえたっているでねーの(それも
ボルタンスキーのインスタレーションもどきのやつ)。これでがくっときたね。

でも、VSPRSおなじみのイントロが始まると、うーん、いいんじゃないの。バンドはサイコー。女性ヴォーカルはオペラ系らしくマイクなしでしっかり三階席まで声が通る。いやあ、盲目のロマ・フィドラー(昔風に言うと屋根の上のバイオリン弾きね)の奏でる哀愁のメロディーもいいねえ。ほんとの角笛があんなに高音を出すのだとはしらなんだ。

ところが、踊りの方がもうひとつしっくりこない。音と融合していない気がする。踊り手たちの習練とその力量はわかるんだけど。片手逆立ち脚踊りとか、後倒ブリッジ踊りとか難易度Cの技を繰り出してるんだけど、あまり美しくない。茅ヶ崎の海岸で「しょっぱいなー」とか呟いている方が似合っていそうな、さーはー頭の東洋人ダンサーのコンフー踊りとか。最期の踊り手全員によるオナニー踊りの群舞はさらにつまんない。みょーに身体性や奇形性を押し出しているんだが、それだけで終わってる感じがする。土方巽は跛だったけど舞台での踊りは美しかったよなあ。これでは下手くそなパッチワークだよなあ(
先月の課題本がそーだった。ようやく読了。地の文でメタフィクションとかいっちゃいけねーや)。

ベルギーの精神分析医のセラピーとの共感とかいうキャッチフレーズも判然としないなあ。

こうなるとモンテヴェルディの聖母マリアの夕べの祈りを選んだ根拠も薄いし、なんの連動性も感じられん。たんなるBGMならほかのものでいいじゃん。これはモンテヴェルディがパトロンである領主の館のプライベートな礼拝堂で演じるために書いた祝祭的な楽曲(一大ページェント)なんだから。

やっぱりぼくはJe suis sangがいいや。「
わたしは血… あいかわらず中世に生きている」

とにかくバンドはむちゃくちゃかっちょよかったんで、帰りにアカ・ムーンという前衛ジャズトリオとオルトゥル・モンターノという古楽アンサンブルそして盲目のチャ率いるロマ・ユニットによる混成部隊のこの演目のCDは買ってしまったのだった。
文責:Y
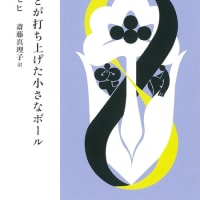 2025年4月の課題本『こびとが打ち上げた小さなボール』
4ヶ月前
2025年4月の課題本『こびとが打ち上げた小さなボール』
4ヶ月前
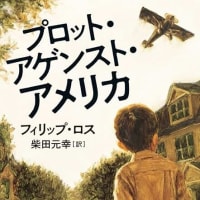 2025年2月の課題本『プロット・アゲンスト・アメリカ』
6ヶ月前
2025年2月の課題本『プロット・アゲンスト・アメリカ』
6ヶ月前
 2024年1月の課題本『江戸の職人譚』
6ヶ月前
2024年1月の課題本『江戸の職人譚』
6ヶ月前
 2024年11月の課題本『ナイン・ストーリーズ』
8ヶ月前
2024年11月の課題本『ナイン・ストーリーズ』
8ヶ月前
 2024年10月の課題本『時穴みみか』
9ヶ月前
2024年10月の課題本『時穴みみか』
9ヶ月前
 2024年9月の課題本『ミシンと金魚』
10ヶ月前
2024年9月の課題本『ミシンと金魚』
10ヶ月前
 2024年6月の課題本『ザリガニの鳴くところ』
1年前
2024年6月の課題本『ザリガニの鳴くところ』
1年前
 2024年1月の課題本『暗い旅』
2年前
2024年1月の課題本『暗い旅』
2年前
 2023年7月の課題本 『嘘と正典』
2年前
2023年7月の課題本 『嘘と正典』
2年前
 2023年5月の課題本『同潤会代官山アパートメント』
2年前
2023年5月の課題本『同潤会代官山アパートメント』
2年前















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます