
課題本は『こびとが打ち上げた小さなボール』チョ・セヒ 著 斎藤真理子 訳 河出文庫 でした。
【河出文庫のサイトより】
【河出文庫のサイトより】
韓国で三〇〇刷を超えるロングセラーにして、現代の作家たちから多大なリスペクトを受ける名作。急速な都市開発をめぐり、極限まで虐げられた者たちの、千年の怒りが渦巻く祈りの物語。
【例会レポート】
出席者…12名
1978年の刊行以来、本国で長年ベストセラーになっている(らしい)今回の課題本。ずずんと重い社会派小説で、韓国小説を初めて読む人、韓流コンテンツに慣れ親しんだ人、韓国に何度も行っている人など、会員のバックグラウンドはさまざまでしたが、意外と読みやすいという声も聞かれ、完読率は高かったです。どちらかというと小説そのものに言及するより、韓国の近現代史や国民性など周辺事情について、それぞれ自分の経験と重ね合わせた思いが語られ、とても興味深い読書会となりました。
たとえば、親世代が口にする「朝鮮人」という言葉が醸し出す負のイメージを否定しつつ、無意識下に刷り込まれてきたと感じる人もいます。また、命を懸けて支配層と闘う韓国の人々の姿は、全共闘世代とその後の世代では共感度が少し違ったりもします。しかし、過去には日本を含めた海外諸国に次々支配され、近年も国内の軍事政権に虐げられ、今も南北分断の問題を抱える韓国では、ずっと市井の人々が権力に立ち向かうエネルギーを保ち続けてきました。それが事なかれ主義で戦後を生きてきた日本人の目には遠くもあり、まぶしくもあるという感想を自省の念を込めて語る人が多かったように思います。
韓国のコンテンツには「恨(ハン):Wikiによれば痛恨、悲哀、無常観をさす朝鮮語の概念」という、積もり積もった不満を解き放とうという下層社会の人々の思いが根底にあるといわれます。『こびとが打ち上げた小さなボール』はまさに70年代の軍事政権下で虐げられた貧困層の苦悩と不条理を、チョ・セヒ氏が検閲の目を逃れながら細切れに書き続けた短編小説に描いたもので、作者自身も資本家と貧民層の間を行き来する「チソプ」役で登場しますが、いかなる努力も無に帰します。そのリアルな絶望感を忘れてはならないという思いが、今の世にも継がれているのでしょうか。最近でも何十万人ものデモ隊が国会を取り巻く動画を見ますが、例会では我々も頑張らないとねーという声も上がりました。
なお、文庫本にある作者、四方田犬彦氏、訳者の斎藤真理子氏の解説はどれも素晴らしく、大いに理解の助けとなりました。
講師のお話
・タイトルがすごい。短編から成る構成も非常にしっかりしている。
・韓国小説は基本的に「叙述」スタイルをとることが多く、出来事や事実をそのまま集めて順に書き出し、その中に作者の思いが描かれている。
・一方で文章表現においては「リリシズム(叙情主義)」が重視され、短い言葉が詩的につづられる。
そして、併せて読みたい小説として次の2冊が紹介されました。
①『されどわれらが日々』柴田 翔著
例会でも、多くの人が全共闘世代の青春を描いたこの小説を挙げていました。過去の課題本にもなりましたが、「もはや古すぎて昭和が遠い」みたいな感想が多かったような…。それ自体、平和ボケしてしまったってことかもしれませんが。
②『苦海浄土』石牟礼 道子著
工場廃水の水銀が引き起こした文明の病・水俣病。この地に育った著者は、患者とその家族の苦しみを自らのものとして、壮絶かつ清冽(せいれつ)な記録を綴った(Amazonより一部抜粋)
1978年の刊行以来、本国で長年ベストセラーになっている(らしい)今回の課題本。ずずんと重い社会派小説で、韓国小説を初めて読む人、韓流コンテンツに慣れ親しんだ人、韓国に何度も行っている人など、会員のバックグラウンドはさまざまでしたが、意外と読みやすいという声も聞かれ、完読率は高かったです。どちらかというと小説そのものに言及するより、韓国の近現代史や国民性など周辺事情について、それぞれ自分の経験と重ね合わせた思いが語られ、とても興味深い読書会となりました。
たとえば、親世代が口にする「朝鮮人」という言葉が醸し出す負のイメージを否定しつつ、無意識下に刷り込まれてきたと感じる人もいます。また、命を懸けて支配層と闘う韓国の人々の姿は、全共闘世代とその後の世代では共感度が少し違ったりもします。しかし、過去には日本を含めた海外諸国に次々支配され、近年も国内の軍事政権に虐げられ、今も南北分断の問題を抱える韓国では、ずっと市井の人々が権力に立ち向かうエネルギーを保ち続けてきました。それが事なかれ主義で戦後を生きてきた日本人の目には遠くもあり、まぶしくもあるという感想を自省の念を込めて語る人が多かったように思います。
韓国のコンテンツには「恨(ハン):Wikiによれば痛恨、悲哀、無常観をさす朝鮮語の概念」という、積もり積もった不満を解き放とうという下層社会の人々の思いが根底にあるといわれます。『こびとが打ち上げた小さなボール』はまさに70年代の軍事政権下で虐げられた貧困層の苦悩と不条理を、チョ・セヒ氏が検閲の目を逃れながら細切れに書き続けた短編小説に描いたもので、作者自身も資本家と貧民層の間を行き来する「チソプ」役で登場しますが、いかなる努力も無に帰します。そのリアルな絶望感を忘れてはならないという思いが、今の世にも継がれているのでしょうか。最近でも何十万人ものデモ隊が国会を取り巻く動画を見ますが、例会では我々も頑張らないとねーという声も上がりました。
なお、文庫本にある作者、四方田犬彦氏、訳者の斎藤真理子氏の解説はどれも素晴らしく、大いに理解の助けとなりました。
講師のお話
・タイトルがすごい。短編から成る構成も非常にしっかりしている。
・韓国小説は基本的に「叙述」スタイルをとることが多く、出来事や事実をそのまま集めて順に書き出し、その中に作者の思いが描かれている。
・一方で文章表現においては「リリシズム(叙情主義)」が重視され、短い言葉が詩的につづられる。
そして、併せて読みたい小説として次の2冊が紹介されました。
①『されどわれらが日々』柴田 翔著
例会でも、多くの人が全共闘世代の青春を描いたこの小説を挙げていました。過去の課題本にもなりましたが、「もはや古すぎて昭和が遠い」みたいな感想が多かったような…。それ自体、平和ボケしてしまったってことかもしれませんが。
②『苦海浄土』石牟礼 道子著
工場廃水の水銀が引き起こした文明の病・水俣病。この地に育った著者は、患者とその家族の苦しみを自らのものとして、壮絶かつ清冽(せいれつ)な記録を綴った(Amazonより一部抜粋)










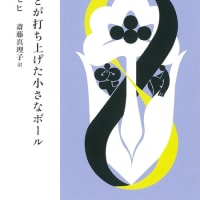
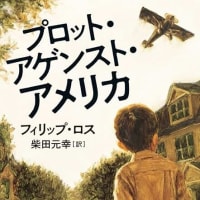













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます