【放出(はなてん)】
普通なら難読中の難読「はなてん」。
だが、大阪人なら誰もが知っているCMがある。
昭和50年(1975)深夜に流れた大阪のローカルCMが、
セクシーで意味不明だが耳に残るフレーズ&メロディーだった
ので、子供にまで口ずさまれるようになった。
今でもバージョンが変って流れているみたい。
[CM]ハナテン中古車センター 昭和50年バージョン
youtube → https://www.youtube.com/watch?v=F1c5n13wwKo
現在は大阪市鶴見区と城東区にまたがる放出。
古代の低湿地で、その付近でいくつもの河川が合流し、
大きな湖沼ができていた。この湖沼の水量調節のために、
樋(とい)などを使って旧淀川へと水を放出した場所であった
ことから、「放出」の地名が生じたらしい。
≪別説≫
①暗渠(あんきょ)説・・・排水などのための地下水路を暗渠というが、
一部の方言では暗渠を「放出(はなで)」ということから。
②剣を放り出す説・・・「天知天皇七(668)年、新羅の道行という僧が
熱海神宮から草薙剣(くさなぎのつるぎ)を盗んで
新羅に逃れようとしたが、この地で大嵐に遭い、
これを神罰だと恐れて、剣を河中に放り出して
逃げ去ったことから「放出」の地名が出来た。
JR学研都市線「放出駅」の北東駅前ににある阿
遅速雄(あじはやお)神社に、伝承の石碑がある。
③放し飼い説・・・古くにこの地で牛馬の放し飼いにされており、
その飼育地を放出と呼んだことから。
④「はなちで」説・・・平安時代に『寝殿などに続けて外へ建て出した
建物』や『母屋を南北に区分した南の半分』の
ことを「はなちで」と呼んだことから、この地に
なんらかの建築物があったのでは?
いずれにしても、「はなちぃで」「はなちで」が「はなてん」に変化した
ものと考えられている。
 『大阪地名の由来を歩く』 若一光司:著
『大阪地名の由来を歩く』 若一光司:著 
≪実在の名称と学問上の名称≫
☆「瓶(みか)」と「甕(かめ)」
「甕(かめ)」・・・日常の食物や飲み水を入れるもの
「瓶(みか)」・・・神に捧げるお酒や水を入れる神聖な容器
瓶は甕とも書き、(みか)とも(かめ)とも読めるとありましたが、
今の時代に生きる私たちにとっては、瓶=ビンの方が読み慣れて
いるのではないでしょうか。
なのでなんとなく小さいものとして感じとれるので形からして
大きいものを甕(かめ)と思い込んでしまっています。
考古学者が「甕(かめ)棺」と呼んできたものがある。
古代には権力者や高い階級の人を甕棺に入れて葬る風習が
あり、そのさい、日常生活の容器である甕(かめ)に入れたか、
神聖な神に捧げる「みか」に入れたかという謎が出てきた。
『倭人伝を徹底して読む』の著者である古田氏は神聖な方
「みか」ではないかと思うようになってきたという。
しかし、考古学者は形態からみて「甕(かめ)棺」と名付けてしまった。
基本的には共通しているから即物的に「仮に呼んだ名前」を
つけたわけだが、「歴史上の名前は別個ですよ」「考古学者の
任務外ですよ」と考古学者は言うべきだし、また一般の読者も
そのことを頭に置いて、読むべきだといっている。
そういう分類上の「仮説・名称」という概念を忘れ、「実態」だと
錯覚していることに問題があるという。
結果、ヒミコではなくて「ヒミカ」である、
「太陽のミカ」ではないかという問題にもいきついたという。
「名称批判」があり気づかれたようです。
☆「剣」と「刀」
埼玉県の稲荷山鉄剣は、普通鉄剣と呼ばれているが、
実際の銘文では「刀」と書かれている。
有名な七支刀も剣なので、本来なら七支剣と呼ばれるべき
なのに「七支刀」と書かれている。
剣・・・両刃
刀・・・片刃
しかし、実用上決して間違って使っていたわけではなく、実際に
六世紀の関東の人々は“稲荷山の両刃の利器”を刀と呼んでいた。
七支刀は、それを作った百済でも刀と呼んでいたのである。
四世紀の百済と六世紀の日本列島の関東とが共通して刀と
呼んでいるところからみると、歴史的に実在した名称であった
と考えるのが、筋だと著者は言っています。
『あの国宝・七支刀は「鋳造」 復元した刀匠、鍛造説覆す分析』
(1/2ページ) 産経ニュース
 『倭人伝を徹底して読む』 古田武彦:著
『倭人伝を徹底して読む』 古田武彦:著 
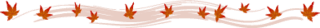
確かに、私たちは習ったことが正しいと思っていたら、
歴史が変わっていたとか、誰でも知ってる有名な写真が違う人
だったなんて話、最近よく聞きます。
つい先日も銅像が弟と間違えられていたなんて話も新聞にあったような・・
子供のころ、私たちは間違ったことを教えられていたのか~、
なあんてショックにも思いますが、その当時では最新のもの
だったのでしょう。新しい発掘や文献によって、歴史は変わる
ものとは、今じゃあ、皆が承知のことでしょう。
TVでも面白おかしく、かなり教えてくれてますからね。
学校に行っていない大人たちもお勉強できて有難く、便利な
世の中になったものです。
古文書があったら事実と思うことも最近では疑ってみたりもする
ことがあります。人に見られるものには嘘とは言わないまでも、
善い風に見られるように書かれている場合があるでしょうね。
また、書く人だけの思い込みってのもあるかも。
ま、そんなものは一般人が見る前に整理されているとは思います。
日記など、本当に大事なことを赤裸々に書いてあるのはやはり、
家に残ってるものが多いのでしょう。
家族や親類、誰もいなくなって初めて手放され、人目に触れ、
真実がわかるものなのでしょう。
他人に知られたくないものは、隠す。
ことも・・・
今、古文書が密かにブームになりつつあるそうです。
特に江戸時代は文字が多使用されていたので、
気をつけなければならない「仮説・名称」だらけです。
・・・ていうか~、単純な書き間違いもありま~す。
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
↓↓↓

いつもありがとうございます!
【瓶原(みかのはら)】
京都府の南端に位置する木津川市に、瓶原村があった。
現在は俗称になっている。
瓶原公民館がある正式名称は、加茂岡崎。
現在では「みか」とはいわず、
「瓶」=「甕」=「かめ」と読むことが多い。
古代人は、美しく流れる川を「御河(みか)」と呼んだ。
その川沿いにひらけた原野に、「御河之原(みかのはら)」と地名をつけた。
川の流れ込む形が甕(カメ)に似ていたからという説もある。
瓶原は、東西に流れる木津川沿いにひらけた土地で、
古代には、草花が咲き誇る風景が開けていたであろう。
そのあたりで伊賀街道と信楽街道が分岐していた。
聖武天皇がそこに恭仁京(くにきょう)をおいて生活していた
時期がある。(740~744年)
「三日原(みかのはら)、布当(ふと)の野辺を清(すが)みこそ、
大宮処(おおみやどころ)定めけらしも」―― 『万葉集』
恭仁京の穏やかな風景は天皇の心をなごませていたらしい。
布当とは瓶原の近くを流れる布当(ふたぎ)川にちなむ。
しかし、恭仁京は交通に不便だったこともあり、
国政の地に相応しい平城京に戻って行った。
≪実在の名称と学問上の名称≫
「みか」と「かめ」についての私のブログ参照→ こちら
 『意外な歴史が秘められた 関西の地名100』 竹光誠:著
『意外な歴史が秘められた 関西の地名100』 竹光誠:著 
【纒向(まきむく)】
「邪馬台国」の候補地として有名。
『万葉集』に「巻目(まきもく)の由槻(ゆつき)が嶽(たけ)」とあり、
マイボクに訛る。
「巻向の山辺…」(巻七-1269)と詠まれた巻向川流域の傾斜地。
中世の「野辺の庄」。
また、車谷といわれるように水車の多い所。
山辺の傾斜平地で、牛馬飼育の最適地となる。
「邑外これ郊という、郊外これを牧という」・・・『爾雅(じが)』
(=中国の辞書)
「牧」は「枚」と同意で、大阪府に「枚方(ひらかた)」「枚岡(ひらおか)」の地名がある。
大和国中ではもっとも豊かに夕日に向う斜面で、「雄略記」に
「纒向の日代(ひしろ)の宮は、朝日の日照る宮、夕日の日がける宮」といわれた。
纒向の「向」は「向原」「向田」「向島」「向山」の地名があるように、
ムク・ムカイ・ムコウ「その方向に向う」「向かい合う」こと。
「互いに向かい合う」→巻向川の南北に向かい合う牧(地域)かも。
関連ページはこちら→ 「(伊)古代珍姓珍釈篇」へ行く。
 『奈良の地名由来辞典』 池田末則:編
『奈良の地名由来辞典』 池田末則:編 
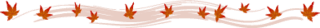
纒向地域には初期古墳が連なっている。
2009年5月、その中にある箸墓古墳の建造年代が、卑弥呼の
死んだと言われる西暦247年と、ほぼ一致したという研究結果が
発表された。
「奈良・纒向遺跡:3世紀の大型建物跡 卑弥呼の宮殿の可能性」
というTV番組もあったようで検索したらいろいろでてきた。
これまで300年にわたって論争を呼んできた邪馬台国の場所が、
この奈良に間違いないだろうといわれているらしい。
あることないこと、様々な憶測が論議されてきたようだが、
書の無かった時代の日本のことは、当時戸籍まで作られていた
中国の書にしか載っていない。
なので、後に携わった人の考えによるものが殆どだろうと思う。
嘘か真実かなんて、今の時代の私たちにわかるはずもない。
だからこそ、研究者でないものが、遥か古の生活を想像しながら
あれこれと談義するのは、コミュニケーションの一つとしては
結構盛り上がって面白いものなのかもね。
関連検索記事「ちょっといい話」は→ こちら
杏(からもも)
奈良の春日山の北を回って流れる佐保川と南を流れる
岩井川とが合流する地点にある町名。
「からもも」とは「唐桃」と書き、中国産桃の一種。
「あんず」と読まれる。
バラ科の落葉高木で、中国北部が原産地。
南北朝から見られる町名。
古くは「唐桃」とも書かれていた。
花を結ぶ植物名にちなむ地名は、「梅」「萩」「桜」などに
象徴されるように花そのものを指していることが多い。
なので、「杏」植えられていたと思われる。
この地は添上郡(そえかみぐん)の辰市郷のうちで、
辰市杏郷ともいった。現在の杏町のほぼ真ん中に
辰市(たついち)神社がある。
<「辰市(たついち)」の由来>
奈良・平安時代の折、辰の日に開かれていた市場が、
「辰の市」と呼ばれ賑わっていた。 『奈良の地名の由来を歩く』谷川彰英:著
『奈良の地名の由来を歩く』谷川彰英:著 

辰市(たついち)は、私の父の故郷です。
小さい頃、線路を伝って駅から歩いてお墓へ行っていたこと、
そのときには必ず寄る家があったことでよく覚えていました。
父が亡くなったとき、手続きでこの地を調べるのに
なんとなく覚えているこの「辰市」で調べたのでした。
しかし、住所が全く違っていたんですね。
どおりで解らなかったわけです。
結局は、ここにはすでに書類は無く実家のあった所に
移していたようで、滞りなく手続きが済んだんですけどね。
マーちゃんと知り合ってからは、お墓へ車で行くようになった
ので、今はもう行き方を忘れてしまいました。
近道の線路伝い歩きって、田舎を良く知っているもので
なければ危なくてできないですよね。
今は随分変わってしまいましたねぇ。
「辰市神社」と「からもも」 懐かしい響きです。
蛇穴(さらぎ)
奈良県御所(ごせ)市の葛城川東岸にある農村。
この村のワキス(水源地)から流れる水は東北に延び、
玉手(たまで)・茅原(ちはら)・本馬(ほんま)・根成柿
(ねなりがき)を過ぎ、曽我川に注いでいた。
この流路に沿って葛上道が斜行する。
俗に筋違(すじかい)道、あるいは行者道とも言った。
同村の野口神社には神八井耳命(移住してきた茨田連の
祖神と伝えられる)が祀られている。
木彫竜を神体とするのは水源地(竜神信仰)を対象とする
俗信から起こったに違いない。毎年五月五日には
「汁かけ祭り」(蛇引き)という民族行事が行われている。
蛇穴をサラギと読むのは蛇がトグロを巻き、穴を作る状態を
サラキ(サラケ)というからで、土器のことをホトキ、または
サラキという。
土器は蛇が円くなるような過程をへて製作されるからだろう。
仏をサラギと読む理由もここにある。
『延喜式』にもサラケ(瓼)、ホトキ(瓮)の用字がみえ、
サラキに蛇穴の文字を使用することも容易に考えられる。
千葉県香取郡では浅甕(底の浅いかめ)と書き、サラケと訓(よ)
む地名がある。
蛇穴は「ジャアナ」「ジャケツ」と読む地名があるかと思えば
「蛇化市」「蛇化地」などに改字する例もみられる。
サラキというのは新来(いまき)のことで、今来(いまき)・
新漢(いまき)・今城(いまんじょう)・新来(にひき)などと同
語で、新しく移り来た所であるから、新来はサラキであった。
つまり、蛇穴も一種の義訓(語の意義によって漢字をあてるもの)
であるといってよいだろう。
室町時代の文書にはサラケとあるので、新家の意にも
解したのであろう。
ちなみに奈良県春日大社内にある佐良気神社はすなわち
蛇穴社で、この蛇穴は蛭児(えびす)の草書体からの誤読
であるともいわれる。
しかし、蛭児神も福徳の神で外来神とも考えられるので新來
(さらき)の神とする説もある。
関連ページはこちら→ 「(伊)古代珍姓珍釈篇」へ行く。
こちらの関連ページへもどうぞ→ 「(仁)獣類珍姓」
 『古代地名紀行 大和の風土と文化』池田末則:著
『古代地名紀行 大和の風土と文化』池田末則:著 
 『奈良の地名由来辞典』池田末則:編
『奈良の地名由来辞典』池田末則:編 

≪リンク集≫
野口神社・汁かけ祭 (奈良県御所市蛇穴)←YouTub動画
同ブログ「明日を追いかけて」様
兵庫県上崎郡の蛇穴神社(じゃけつじんじゃ)
蛇穴神社と指定文化財の絵馬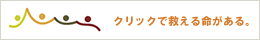
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
いつもありがとうございます!
『日本書記』祟神紀に「依網(よさみ)池」、「皇極紀」には
「依網の屯倉」、『続日本紀』には「依網造」の名がみえる。
また依網屯倉阿弭古が「異鳥を捕まえて天皇に献じた」との
記事(仁徳紀)もあることなどから、古代には鳥類を捕獲する
ことを職業とする依網部の集団があったとみられる。
大網は磯城郡田原本町の大字でオオアミと読む。
『和名抄』では、摂津国住吉郡の郷名「大羅」に対し
「於保与佐美(おほよさみ) 」の訓注を付している。大網は
大羅と同義語で大依網(おおよさみ)の二字化地名であろう。
『播磨国風土記』でも「大羅野」の地名については、老夫婦が
山中に網を張り、鳥を捕まえた野であるという説話がみえる。
この大網は、曽我、飛鳥の両川が最も近接する低湿地で、
『古事記』応神段の長歌に「みづたまる余佐美の池」とある
ように、水鳥の生息地であった。
ところで、曽我、飛鳥川が大和川に注ぐ地域も湿地帯で、
額田部の地名がある。これは沼(ぬ)ヵ田のことで、
泥湿地を意味する形状地名である。
関連ページ「依羅(よさみ)≪古代珍姓珍釈篇≫」へ行く。
 『古代地名紀行 大和の風土と文化』池田末則:著
『古代地名紀行 大和の風土と文化』池田末則:著 
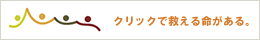
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
いつもありがとうございます!
定使(じょうつかい)
奈良県橿原市豊田町に「定使」、同市観音寺町に「定遣」、
奈良市池田町に「上遣田」の小字がある。
ジョウツカイと発音する。
定使は、中世荘園の下級壮官で、領家(本所・荘園の所有者)と
現地壮官との間を往復し、命令伝達、年貢の徴収などを担当した。
定使田は定使給として与えられた給田のことであろうか。
中世文書にもしばしば見られる名称である。
別に触使とも言った。いわゆる近世・近代の村の用使いをする
人で、所によっては農民が廻り番でつとめることもあった。
『和名抄』によると、安房・美濃・下野・越中の国などに丈部
(はせべ)の郷名をみる。ハセツカヒのことで、もっぱら
馳せ使いに従事した部民(後世の飛脚のようなもの)で、丈部
はもともと杖使部で、馳せるとき杖を持っていたといわれる。
額田部を客 阝と書くように、杖部が丈部となった。
万葉歌人にも丈部直大麻呂(あたひおほまろ)・
丈部川相(かはあひ)・丈部足人(たりひと)らの名がみえる。
多賀城市内の発掘操作で、8世紀頃とみられる木簡に
「丈部大麻呂」(「宮城日報」昭和58年12月27日付)
茂原市西之前遺跡の発掘操作で「丈」と書かれた奈良・
平安朝の土器が検出された(「千葉日報」同日付)。
関東・東北地方に多く住んだらしく、ジョウツカイとし、
中・近世に伝承した語であろうか? 『古代地名紀行 大和の風土と文化』池田末則著
『古代地名紀行 大和の風土と文化』池田末則著 
【丈部 (はせべ・はせつかべ)】
杖部とも書く。古代の職掌名からくる。
その名の由来は、使者の標識として「杖」を帯していたため、
「杖」が「丈」と略され丈部と称するようになった。
丈部は「馳使部」の意で、令制の駈使丁に類し、
貴人に仕えて、その身を守ったり、その命によって用をたしたりする。
「走り使い」すなわち馳使丁(はせつかひ)のことが語源。
「丈部。天足彦国押人命(あまたらしくにおしひとのみこと)の孫、
比古意祁豆命(ひこおげつのみこと)之後也。」とある。
諸国に丈部が存在していたことから、これらの豪族は
大きな勢力を持っていたらしく、軍事的な部民(べのたみ)で
あったことが推測される。
①移住説:「北武蔵に早くから移住し、土着した在地土豪に成長」
②編成説:「阿倍氏の東国進出後まもなく同氏の部民として
編成された東国土着の部族」
***************************
≪豆知識≫
現代の杖術(じょうじゅつ)は4尺(120cm)だそうだが、江戸以前は
7.5尺~10尺。古代、杖といえば拷問などにも使われていたものも
あるという。技術としては棒術の一種で、犯罪者を捕縛する者の捕手
術としてまた、農民や商人等の護身術として、そして今では、日本の
警察で警杖術として採用され武道の杖道となっている。
(2015.12.20 豆知識としてカテゴリ表記のみ記載を本文に追記)
***************************
関連ページ→ 定使(じょうつかい)≪地名由来≫へ
 「研究ノート竹芝伝説」:参照
「研究ノート竹芝伝説」:参照
4 丈部直=武蔵宿禰家の勃興と没落
(不和麻呂以前の丈部直)
 『日本家系・系図大辞典』 奥富敬之:著
『日本家系・系図大辞典』 奥富敬之:著 
 『姓氏・家系・家紋の調べ方』 丹羽基二:著
『姓氏・家系・家紋の調べ方』 丹羽基二:著 
【久々智 (くくち)】
麹智とも書く。
大彦命(おおひこのみこと)の後裔。阿倍氏族。
発祥は摂津国河辺(かわべ)郡久久知で、今の兵庫県
尼崎市久々知にあたる。クク・チとは、水がクク・ル(潜る)
ことに由来する、砂地のようなところ。
『倭名類聚抄』の菊池の項に
「久々知」とあってククチと読んでいたことが知られ、
「久々智。同上(阿倍朝臣同祖。大彦命之後也)」とある。
後世、肥後国よりおこった菊池氏は、この久々智氏のこと
との説がある。
ククチと読んでいたことから、『魏志倭人伝』で邪馬台国
と対立抗争していた狗奴国国王の狗古智卑狗 (くこちひく)
は菊池彦(きくちひこ)ではないかとみるムキもある。
 『日本家系・系図大辞典』 奥富敬之:著
『日本家系・系図大辞典』 奥富敬之:著 
 『姓氏・家系・家紋の調べ方』 『難姓・難地名字典』 丹羽基二:著
『姓氏・家系・家紋の調べ方』 『難姓・難地名字典』 丹羽基二:著 






















