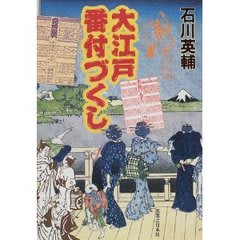≪実在の名称と学問上の名称≫
☆「瓶(みか)」と「甕(かめ)」
「甕(かめ)」・・・日常の食物や飲み水を入れるもの
「瓶(みか)」・・・神に捧げるお酒や水を入れる神聖な容器
瓶は甕とも書き、(みか)とも(かめ)とも読めるとありましたが、
今の時代に生きる私たちにとっては、瓶=ビンの方が読み慣れて
いるのではないでしょうか。
なのでなんとなく小さいものとして感じとれるので形からして
大きいものを甕(かめ)と思い込んでしまっています。
考古学者が「甕(かめ)棺」と呼んできたものがある。
古代には権力者や高い階級の人を甕棺に入れて葬る風習が
あり、そのさい、日常生活の容器である甕(かめ)に入れたか、
神聖な神に捧げる「みか」に入れたかという謎が出てきた。
『倭人伝を徹底して読む』の著者である古田氏は神聖な方
「みか」ではないかと思うようになってきたという。
しかし、考古学者は形態からみて「甕(かめ)棺」と名付けてしまった。
基本的には共通しているから即物的に「仮に呼んだ名前」を
つけたわけだが、「歴史上の名前は別個ですよ」「考古学者の
任務外ですよ」と考古学者は言うべきだし、また一般の読者も
そのことを頭に置いて、読むべきだといっている。
そういう分類上の「仮説・名称」という概念を忘れ、「実態」だと
錯覚していることに問題があるという。
結果、ヒミコではなくて「ヒミカ」である、
「太陽のミカ」ではないかという問題にもいきついたという。
「名称批判」があり気づかれたようです。
☆「剣」と「刀」
埼玉県の稲荷山鉄剣は、普通鉄剣と呼ばれているが、
実際の銘文では「刀」と書かれている。
有名な七支刀も剣なので、本来なら七支剣と呼ばれるべき
なのに「七支刀」と書かれている。
剣・・・両刃
刀・・・片刃
しかし、実用上決して間違って使っていたわけではなく、実際に
六世紀の関東の人々は“稲荷山の両刃の利器”を刀と呼んでいた。
七支刀は、それを作った百済でも刀と呼んでいたのである。
四世紀の百済と六世紀の日本列島の関東とが共通して刀と
呼んでいるところからみると、歴史的に実在した名称であった
と考えるのが、筋だと著者は言っています。
『あの国宝・七支刀は「鋳造」 復元した刀匠、鍛造説覆す分析』
(1/2ページ) 産経ニュース
 『倭人伝を徹底して読む』 古田武彦:著
『倭人伝を徹底して読む』 古田武彦:著 
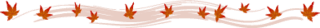
確かに、私たちは習ったことが正しいと思っていたら、
歴史が変わっていたとか、誰でも知ってる有名な写真が違う人
だったなんて話、最近よく聞きます。
つい先日も銅像が弟と間違えられていたなんて話も新聞にあったような・・
子供のころ、私たちは間違ったことを教えられていたのか~、
なあんてショックにも思いますが、その当時では最新のもの
だったのでしょう。新しい発掘や文献によって、歴史は変わる
ものとは、今じゃあ、皆が承知のことでしょう。
TVでも面白おかしく、かなり教えてくれてますからね。
学校に行っていない大人たちもお勉強できて有難く、便利な
世の中になったものです。
古文書があったら事実と思うことも最近では疑ってみたりもする
ことがあります。人に見られるものには嘘とは言わないまでも、
善い風に見られるように書かれている場合があるでしょうね。
また、書く人だけの思い込みってのもあるかも。
ま、そんなものは一般人が見る前に整理されているとは思います。
日記など、本当に大事なことを赤裸々に書いてあるのはやはり、
家に残ってるものが多いのでしょう。
家族や親類、誰もいなくなって初めて手放され、人目に触れ、
真実がわかるものなのでしょう。
他人に知られたくないものは、隠す。
ことも・・・
今、古文書が密かにブームになりつつあるそうです。
特に江戸時代は文字が多使用されていたので、
気をつけなければならない「仮説・名称」だらけです。
・・・ていうか~、単純な書き間違いもありま~す。
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
↓↓↓

いつもありがとうございます!
【瓶原(みかのはら)】
京都府の南端に位置する木津川市に、瓶原村があった。
現在は俗称になっている。
瓶原公民館がある正式名称は、加茂岡崎。
現在では「みか」とはいわず、
「瓶」=「甕」=「かめ」と読むことが多い。
古代人は、美しく流れる川を「御河(みか)」と呼んだ。
その川沿いにひらけた原野に、「御河之原(みかのはら)」と地名をつけた。
川の流れ込む形が甕(カメ)に似ていたからという説もある。
瓶原は、東西に流れる木津川沿いにひらけた土地で、
古代には、草花が咲き誇る風景が開けていたであろう。
そのあたりで伊賀街道と信楽街道が分岐していた。
聖武天皇がそこに恭仁京(くにきょう)をおいて生活していた
時期がある。(740~744年)
「三日原(みかのはら)、布当(ふと)の野辺を清(すが)みこそ、
大宮処(おおみやどころ)定めけらしも」―― 『万葉集』
恭仁京の穏やかな風景は天皇の心をなごませていたらしい。
布当とは瓶原の近くを流れる布当(ふたぎ)川にちなむ。
しかし、恭仁京は交通に不便だったこともあり、
国政の地に相応しい平城京に戻って行った。
≪実在の名称と学問上の名称≫
「みか」と「かめ」についての私のブログ参照→ こちら
 『意外な歴史が秘められた 関西の地名100』 竹光誠:著
『意外な歴史が秘められた 関西の地名100』 竹光誠:著 
大江戸番付けづくし (著者:石川英輔)
参考に→ 江戸時代の相撲見立番付(山陰中央新報 2009.12.28)
江戸時代の人々は特に相撲好きだったという。
その番付表をまねた様々なランク表が古文書として残っている。
江戸時代にはたてまえは厳しいが、実際は自主規制、というより
見立て番付ぐらいは放任主義だったようだ。
大部分が勝手に印刷して売っていたようだ。
明治になっても番付見立ては発行され続けたらしく、文字・体裁・
内容とも幕末期の番付のままで、刊行年の表示がなければ区別
することができないものもあるようで、変体仮名による木版摺りは
明治20年ごろまでは発行されていたという。
明治時代になると、次第に近代的官僚制度ができて許認可などが
厳重になり、チラシのような印刷物まで「御届」が必要になったようで、
ガチガチの規制時代が始まっていたのである。
もしかすると江戸番付けと書かれているものの中には、明治初期
のものも多く含まれているかもしれないと思った。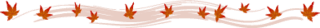
【その一つの例】
番付けタイトル―― 『おしへ草 娘かヾみ』
左欄外――「御届 明治十七年十一月廿四日
編輯出版人 神田通新石町九番地 木村定五郎」
上欄外――「悪 酉の春新撰 善」
発行時(明治18年は酉年)
右(東方)に〇の中に善、左(西方)〇の中に悪の字
※教(おしへ)草・・・教材
※鑑(かヾみ)・・・・・模範や手本の意味
タイトル下の行司欄(右)――「こうのひとつ 親の為に身を賣る娘」
タイトル下の行司欄(中)――「よかれあしかれ 親の身代を立て直す娘」
タイトル下の行司欄(左)――「ふこうのずい 色情で命を捨てる娘」
タイトル下の2段目(右)――「心だて素直な娘」
タイトル下の2段目(中)――「遊藝(ゆげい)を好む娘」
タイトル下の2段目(左)――「我ままな娘」
タイトル下の3段目(右)――「善 箱入り娘」
タイトル下の3段目(中)――「悪 他人のおへになる娘」
タイトル下の3段目(左)――「其 おてんば娘」
右側(善)・・・「おなごのたしなみ 針仕事の好きな娘」
「一しやうの得 読書のできる娘」
「かないぶじ 継母を大切にする娘」
「みやうにかなふ ミへかざりをせぬ娘」
「たのもしい 兄弟おもひの娘」
「やさしいこころざし 年寄りをいたわる娘」
・
・
うちきな、口慎しみよい、しんぼう強い、等々
左側(悪)・・・「とんでもない 親へ悪口する娘」
「おやへくらうをかける 尻っぱやな娘」
「おなごのミちがたたぬ 針仕事を忌ふ娘」
「ろくなことはしでかさず 夜あるきを為(す)る娘」
「つつしまねばならぬ けんどんな娘」
「おんぎをしらず 親兄弟を見捨てる娘」
・
・
いじの悪い、いけ好かない、大食をする、等々
今じゃあ身売り自体憲法違反だから考えられないだろうけど、
昔は孝行の一つで、身代を立て直すほどの気の強い娘は、
善い娘さんだけど息子の嫁にはちょっと~、って感じかな?
未婚娘の品定め番付らしいが、内容は特に女性に要求すべき
ことに限らず、人間一般が心がけるべき言葉ばかりである。
わりと恋愛が大らかだった江戸時代の道徳よりも封建的で、
男でも当てはまることも多いのに・・・と、今なら女性差別
となる番付ばかりだぁ~って、女性側からの文句が出そう。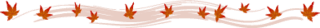
≪江戸時代、大流行の心中≫
江戸の心中は近松門左衛門が書いた道頓堀の竹本座の立て直し
のための苦肉の策だったのかもしれない『曽根崎心中』で大流行。
その後の近松の心中物全てが大流行、心中そのもさえ流行った。
その為、享保7年(1722)に、当時編纂中だった幕府の
処罰規定が、「公事方御定書」に盛り込まれ、翌年お触書を出した。
≪心中後の厳しい処罰≫
二人とも死んだ場合・・・裸にして晒され、そのまま取り捨て。
(寛政五年(1793)、晒されている女性のちょっと
えっちな話題で見物人が殺到するという見世物
騒ぎがあり、裸はやめたらしい)
二人とも生き残った場合・・・三日間晒したうえ、身分に。
片方が生き残った場合・・・死罪。
生き残ったのが主人の場合・・・主人はへ。
生き残ったのが奉公人の場合・・・死罪。 『大江戸番付づくし』 石川英輔著:参照
『大江戸番付づくし』 石川英輔著:参照
 『週刊江戸38 心中事件の流行』(株)デアゴスティ-ニ・ジャパン:参照
『週刊江戸38 心中事件の流行』(株)デアゴスティ-ニ・ジャパン:参照
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
↓↓↓

いつもありがとうございます!
昨日は入院中の義母の誕生日でした。
とりあえず「おめでとう」って言うべきだったかな?
検査結果次第では、嫌がる手術もしなくちゃあならないかも
知れないから、今回「おめでとう!」って言えなかったんですよね。
義姉が用事があって行けないとの事だったので、
お祝いがてら(入院中だからお祝いってのも変かな?)
食べやすいケーキをということで、
ラ・パティスリークルールのプリン&レイティエ、
そして義母のお気に入りの穴子寿司を持っていきました。
(今回は穴子寿司の画像は撮るのん忘れたぁ)
チーズケーキのレイティエは、この店がオープンした時に買って、
義母にも味見で持っていったことがあります。
「洋酒にあうんだわぁ♪」
とあの時はかなり気に入ってくれたようです。
プリンは初めて持っていったので、
「変ってるけど、美味しそう~!」と喜んでくれました。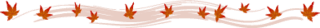
la patisserie Couleur (ラ・パティスリークルール)
 ←クリックで大画像に(名前までわかりますョ)
←クリックで大画像に(名前までわかりますョ)
お店の前に車が止まってて、
「たった今シュークリームが来た所なので、まだ、1時間ぐらいは
食べれませんがよろしいですか?」といわれて、
「あ、シュークリームって冷凍なんだ!」と答えてしまいました。
家用にはシュークリームを買いました。

ここのは、シュー皮が独特です。
しっかりしてて、ややかためです。
そういや思い出しました。
前は、アイスクリームみたいと思って食べたのでした。
あれは解凍されてなかったのね、納得!
美味しいですよ~♪
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
↓↓↓

いつもありがとうございます!
【纒向(まきむく)】
「邪馬台国」の候補地として有名。
『万葉集』に「巻目(まきもく)の由槻(ゆつき)が嶽(たけ)」とあり、
マイボクに訛る。
「巻向の山辺…」(巻七-1269)と詠まれた巻向川流域の傾斜地。
中世の「野辺の庄」。
また、車谷といわれるように水車の多い所。
山辺の傾斜平地で、牛馬飼育の最適地となる。
「邑外これ郊という、郊外これを牧という」・・・『爾雅(じが)』
(=中国の辞書)
「牧」は「枚」と同意で、大阪府に「枚方(ひらかた)」「枚岡(ひらおか)」の地名がある。
大和国中ではもっとも豊かに夕日に向う斜面で、「雄略記」に
「纒向の日代(ひしろ)の宮は、朝日の日照る宮、夕日の日がける宮」といわれた。
纒向の「向」は「向原」「向田」「向島」「向山」の地名があるように、
ムク・ムカイ・ムコウ「その方向に向う」「向かい合う」こと。
「互いに向かい合う」→巻向川の南北に向かい合う牧(地域)かも。
関連ページはこちら→ 「(伊)古代珍姓珍釈篇」へ行く。
 『奈良の地名由来辞典』 池田末則:編
『奈良の地名由来辞典』 池田末則:編 
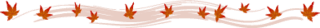
纒向地域には初期古墳が連なっている。
2009年5月、その中にある箸墓古墳の建造年代が、卑弥呼の
死んだと言われる西暦247年と、ほぼ一致したという研究結果が
発表された。
「奈良・纒向遺跡:3世紀の大型建物跡 卑弥呼の宮殿の可能性」
というTV番組もあったようで検索したらいろいろでてきた。
これまで300年にわたって論争を呼んできた邪馬台国の場所が、
この奈良に間違いないだろうといわれているらしい。
あることないこと、様々な憶測が論議されてきたようだが、
書の無かった時代の日本のことは、当時戸籍まで作られていた
中国の書にしか載っていない。
なので、後に携わった人の考えによるものが殆どだろうと思う。
嘘か真実かなんて、今の時代の私たちにわかるはずもない。
だからこそ、研究者でないものが、遥か古の生活を想像しながら
あれこれと談義するのは、コミュニケーションの一つとしては
結構盛り上がって面白いものなのかもね。
関連検索記事「ちょっといい話」は→ こちら
今日はお墓参りへ行ってきました。
命日(一日ずれましたが)には毎月、お墓参りへ行くようです。
今回は、入院中の義母の代理を頼まれました。
自分の所だけでよいということでしたが、
お線香だけは皆供えておきました。
これからはマメにお墓参りへ行くことになりそうです。
今日は、嫁ぎ先の方だけなのでちょうど昼ごろ
帰りに≪かごの屋≫で昼食をとりました。
ここの面白いところは、
下駄箱が銭湯の下駄箱になってるとこです。
けっこう、懐かしいものです!
(写真は取り忘れちゃったぁ)
↓この端にチラっと見えてるのが鍵である木の番号札です。
かごの屋弁当&焼肉弁当
最近時々、
義母は我家へと外泊許可を取って帰ってきているようです。
今日は帰ってきてないようですが。。。
今のところは、脊髄注射で痛みを止めて様子を見ているようです。
が、なんせ、背骨がへしゃがっているので、
注射が難しく、うまくいかないときもあるようです。
注射の液が違う所へ流れると痛らしく、暫らくあけては
何度かチャレンジしているようです。
原因がわからぬ血圧も高いようで要注意とのこと。
「アルコール切れてるからちゃうか~!」
なあんて冗談を言いながらのドライブでした。
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
↓↓↓

いつもありがとうございます!
「人に逢いに行く!」って事の方が優先になってるかな。
そのうちの一人、Tさん(としておこう)とは
ずーっと昔からの知り合いのようでもあり、親友のようでもあり、
悩みや身体の欠点でさえも、本当に何でも話せる人なのだ。
不思議なことに、話せるだけで心がスーとするっていうのは
Tさんだ けかもしれないなあ・・・
遠くに離れてるから返って何でも話せるのかもしれない。
人を裏切らない人、というより裏切れない人なのだと思う。
まるで、恋人?親?のような感じがする人でもある。
特に、家族のことを話しているときは羨ましいぐらいだ。
Tさんといると、いつも家族を大事にしてるなあ。。。と、心が和む。
一生涯を通じての“心の友”とこっちが勝手に思ってるだけかも
知れないけれど、そういう人がいるっていうことは幸せなことかもね。
「苦労を知ってるから今があるんだと思う。。。」
Tさんの言葉にはしっとりとした優しい重みがある。
一番大好きな、大事にしたい、私の尽生優人の一人です。
↓れんこんサブレー

ピーナッツ味噌 ピーナッツ煮豆
ピーナッツの煮豆って噂では聞いていたが、今回偶然見つけた。
お店に入ると「生はまだ置いてないんですよ」
と店主さんが言われたが、大阪では生ピーナッツなど売ってない。
ここら辺のお客さんにみな聞かれるぐらい普通なんだろうね。

ピーナッツ煮豆 ピーナッツ味噌
それにしても、柔らかくて美味しかった~!
柔らかいピーナッツは初めて食べたけど、やみつきになりそう~♪

蓮根粉末を使ったものだそうです。
れんこんの味がもっときついかなと思ったけど、
そうでもなかった。というより、サブレーの味だあ~♪
美味しかったで~す。
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
↓↓↓

いつもありがとうございます!
(ただし医療費の助成のある特定疾患治療研究事業対象の疾患ではない)
(ウィキペディア:参照)
へぇ~、治療費はタダにするほどの病気ではないけど難病なのね。
***************************************************
―――昨日の話。 (ダーリンであるマーちゃんの話)
「突発性難聴みたいやねん。」
私が帰るなりマーちゃんが言った。
叔父さんの仕事の手伝い中、本当に突然だったらしい。
行きつけの小さな病院では、無理があるので紹介状をもらったとのことだった。
意気消沈して、明日行ってくるわ、って言ってたのに今日朝起きると、
「治ったみたい!やっぱりやめとくわ。治ったのに行ってもしゃーないし。」
なあんて子供みたいなことをいう。
こういう症状事体が、最初の自身のからだからの警告だというのに・・・
「知らんで~!次に聞こえへんようになったら手遅れになってた、
なんてよくある話やで~。。。ま、私の身体違うからいいけど。」
といつもの私流の脅し文句をすぐに言っておいたせいか、
昼頃、今日金曜だし日・月と連休だから、今日中に行った方が
いいんじゃあないの、と念押ししたら「火曜日に行く!」だって。
今日は用事で義姉に会うことがあったので相談したら、
叔父に聞いて知ったらしく、入院中の母に心配させまいと内緒
にしておいて、と言ってたことを聞いた。
「ほんならうちから電話かメールしとくわ。お母ちゃんに言うでー!
って脅しといたるわ~。なあんてうちら、子供みたいやん!」
なあんて笑ってた姉の忠告が聞いたかな・・・?
男ってそういうところあるなあ、結局、母には弱しか。。。
なあんて思いながら、自分も母であることを感じるのでした。
今日は、相談できる家族がいることを有難く思う日でした。
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
↓↓↓

いつもありがとうございます!
「脊髄損傷すると一生歩くことは難しい!」
日本ではそれが常識とされてきたこと。
そんな言葉を覆えそうとしている人がいる。
脊髄損傷のトレーナー 渡辺淳さん 29歳
「無理と思っていることは絶対無理だから、できないと思って諦めてははいけない」
「1人歩いたら奇跡って言われても、自分がもし100人歩かせたらそれは絶対奇跡とは言わせない」
≪11年前アメリカで確立されたトレーニング方法≫
カリフォルニア州・サンディエゴ
世界初の脊髄損傷者専門トレーニングジムである
「プロジェクトウォーク社」
設立から11年約200人を歩けるようにしてきたと言う。
そのノウハウを日本に初めて持ち込んだのが渡辺さん。
脊髄損傷者専門のトレーニング施設を3年前(2007年)に設立。
ジェイ・ワークアウト株式会社 http://j-workout.com/
脊髄損傷・・・背骨の中を通っている中枢神経が事故などで傷つき
腕や足が麻痺してしまうこと。
現在日本に10万人以上もいるといわれている。
一度傷ついた損傷は再生することは無いので、歩くことは難しいと考えられていた。
しかし、渡辺さんのジムで回復した人がいる。
9歳で脊髄の腫瘍を患い、以来車椅子生活を続けてきた2008年北京
パラリンピックのテニスで金メダルを取った国枝慎吾さんは、17年間
歩くことを諦めていたといいます。
ところが、渡辺さんのジムに通い始めると、杖で歩けるまでに回復したという。
また、3年前ラグビーの試合中に脊髄損傷して、首から下が麻痺して
歩くことは難しいと言われた人もトレーニングから2年後の現在走るまでに回復した。
≪どのようなトレーニングか?≫
中吊りにするマシーンで身体を立った状態にし、トレーナーが足を
動かせながら歩く動作を反復させる。歩くたびに足をどう動くか意識
させるため、何百回、何千回も繰り返しながらトレーナーは声を掛け続ける。
脳からの指令は背骨の中の脊髄を通り、足を動かす。
この脊髄が損傷すると、脳の指令を伝えるルートが途絶え、
そこから先が麻痺状態になる。
一度切れた神経は二度と繋がらない。
ところが、少しでも神経線維が残っていると、残った神経に
歩行状態を教え込むことで歩ける可能性がある。
残っている所に歩行機能をもう一度再教育するというやり方。
しかし、そのやり方は何千回何万回と同じ動作を繰り返すこと。
かなり根気のいることだと思います。
「神様だ!」とある患者さんが感動して言ってました。
その練習中に自分が動かせたという感覚があったのでしょう。
車椅子生活が続くと筋肉は使われなくなりやせ衰えていきます。
しかし、使わなくなった筋肉をトレーニングすることで筋肉を鍛えておくのです。
いざ動かす時に耐えられるようにするといいます。
現状では常識を覆すものだと医師は言っていました。
本人の意志でなくても人に動かされていても、それにつられて筋肉
は動いているので、無理なことが出てきたら、それがなぜ動かせ
ないかを考えるそうです。そして、その人への運動メニューを増やす。
ある人は300ものメニューとかいってましたね。
もの凄い運動量だそうです。
「うちらにできるのは25%ぐらいしかない。ほとんどは自分たちがやることなんです。」

子供の頃スポーツ万能といわれた渡辺さんは、10代でかかった病(脊柱管狭窄症)のため自分が身をもって歩けなかった経験(2年)があったそうです。
病を克服した後、新しいことに挑戦するため2000年アメリカへ留学。
そこで運命的な出会いの世界初の脊髄損傷者専門トレーニングジムを知るのです。
そして、2005年、そのプロジェクトウォーク社へ入社。
そこでの様子に衝撃を受けて、歩けない人を歩けるようにしたいと
難関のトレーナー資格を取るために勉強して、2006年最高クラスの
トレーナー「スペシャリスト」の資格を取得。
米国人以外では初めてだそうです。
「多分日本だったら見捨てられていたような重度の人たちが
凄い結果を出してるので、やりたいなと思ったんですよね。」

そして、リハビリとその後の回復度に合った仕事の紹介、
支援など、彼らが生きがいを見つける手助けもしたいと、
就労支援センターを今年立ち上げたようです。
ジムとの連携をしたい。きめ細やかに仕事を探す。
またしたい仕事にあわせて回復させる機能をリハビリする。
など、これからの自分の人生を諦めていた人に、
希望を持たせたいと考えているそうです。
「奇跡はちゃんとした法則の中でしか起こらない」
という言葉が好きという渡辺さんのマイゴール。
≪2015年までに100人の脊髄損傷者の人を歩かせたい≫
来年春に、この大阪に新しいジムができるそうです。

私たち素人からすれば、吃驚ですね。
お医者さんに歩くことが無理と言われたら、奇跡でも起きない限り
無理だと思うのが普通ですよね。
リハビリも自分で出来た人は奇跡の復活と言われるけど、
何万回も他人の手で動かしても回復可能になるとは。。。
最初、それをしようとした人って凄い!
日本でもやってみようとする渡辺さんも凄い!!
歩けないと言われた人たちにとって救いの神ですね。
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
↓↓↓

いつもありがとうございます!