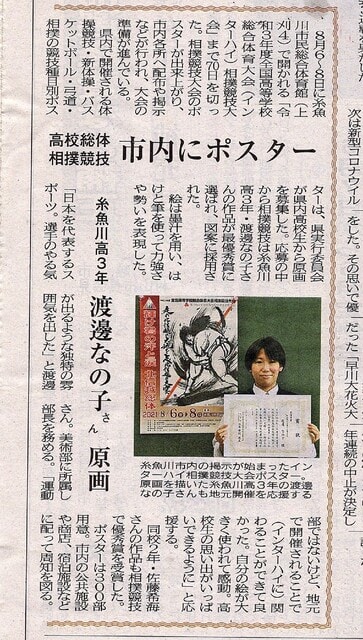「はい、あ~んして」・・・「あ”~ん!」

作者の子育てを物語っているかのような筒型土偶。

八戸市の縄文仲間、佐京さんがSNSに投稿した土偶の写真に笑ってしまい、詳細が知りたいと連絡したら複製を送ってきてくれた。

以下の写真は、佐京窯さん製作の複製。側面。
底近くにチンポコ風の突起があり、内部まで貫通しているので、注口器土偶の類型であるらしい。

側面その2.
顔が「合掌土偶」に似ているし、文様からも後期から晩期くらいの土偶ではないか?

背部。
中期だと口から底に貫通した孔を持つ「笛形土偶」もあるので、このあ”~んと大口をあけた土偶をモチーフで、オカリナを作ってみることにした。

正面
「筒型土偶」としか名前がなく、それほど有名な土偶ではないので、ニックネーム募集中!
長野の考古学者さんなら親しみやすいネーミングをして、博物館のマスコットにしそうですぞ。

ボトムアップ式にかわいい土偶として人気者になり、出土地の階上町のマスコットキャラクターになったら面白い。
日本列島に住む人々は、大昔からお家芸といえるくらいに漫画的表現が好きであったらしい。
目と口を点だけで簡素に表現しただけの、北斎漫画、松浦武四郎の描くところのアイヌ民族風物画などなど。
かわいい!が好きなのね。