









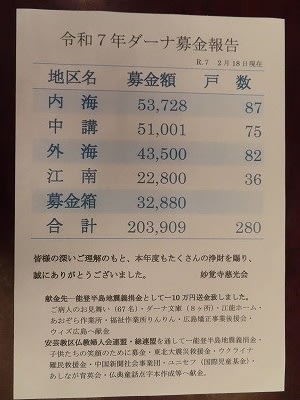


















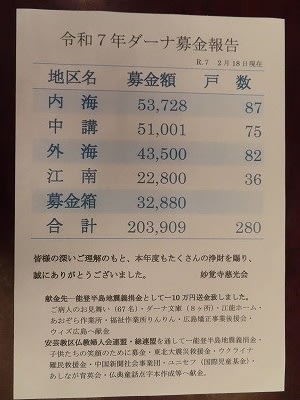























1月16日(木)7時より、親鸞聖人ご命日 御正忌の法要が始まりました!

参拝者全員、お焼香いたしました。



ご印書が拝読されました。

第三代覚如上人は、永仁2年(1294)の冬、親鸞聖人の三十三回忌を迎えるにあたって、報恩謝徳のためにと『報恩講式』を作られ、これ以来、親鸞聖人のご命日におつとめする法要を報恩講と呼ぶようになりました。

御正忌報恩講のお聴聞をいたしました。

ぜんざい接待がありました!

ようこそお参りいただきました!










デイサービスは今日もお勤めをして始まりました。

今日も宜しくお願いします!

今日は「箱入りかざり」を作りました!

皆さん、かわいいもの大好きです

可愛い飾りがたくさん出来ています

葉ボタン制作中


こんな感じにできました

昼休みには、連続ドラマを見ました

これから、健康チェックをして、午後のレクレーションに入ります

今日もいろんなお話をして、盛り上がりましたね

かわいい箱飾りが出来上がりました!

冬の唱歌を歌いました
リンゴの唄・雪・たきび・・・
そして、高校三年生、星影のワルツを歌いました!

今日も無事終了!

また月曜日にお会いしましょう!

1月15日(水)13:30より、御正忌法要昼席が始まりました。

「正信偈」をお勤めしました。

「御伝鈔」上巻が拝読されました。
「本願寺聖人親鸞伝絵」とも称され、親鸞聖人の曾孫にあたる第三代覚如上人が、聖人の遺徳を讃仰するために、その生涯の行蹟を数段にまとめて記述された詞書と、数段の詞書に相応する図絵からなる絵巻物として成立しました。それが、写伝される過程でその図絵と詞書とが別々にわかれて流布するようになりました。そして、この図絵の方を「御絵伝」、詞書のみを抄出したものを「御伝鈔」と呼ぶようになりました。
「御伝鈔」上巻

本日の講師は、当山住職です。

「御絵伝」をもとに、親鸞聖人のご生涯をお偲びしました。

御絵伝(ごえでん) 右から第1幅 第2幅 第3幅 第4幅
御絵伝は場面の配列が下から上の順序で配列されています。見るときには第1幅の下から始まり第4幅の上で終わるように順を追って見ます。
御伝鈔(上下巻)は御絵伝と同じ順序で読み上げられますから、声を聞きながら絵を見て聖人の御一生を偲ぶことができるようになっています。御伝鈔で「第2段」と読み上げられたら、御絵伝「第2段」の場面を見ます。

「御絵伝」のプリントを見ながら、お説教をお聴聞しました!










19:30より、大逮夜のお勤めが始まりました。

「御伝鈔」下巻が拝読されました。

御伝鈔(上下巻)は御絵伝と同じ順序で読み上げられますから、声を聞きながら絵を見て聖人の御一生を偲ぶことができるようになっています。このような方法によって多くの人が同時に物語を耳で聞きながら、巧みに描かれた絵を目で見ることが可能になり、当時の画期的な伝道手段となりました。文字を読むことができない人でも読み上げられる声を聞くことなら可能です。

絵巻は貴族が物語を鑑賞するためにつくったのが始まりのようですが、絵と詞書を分けることにより、庶民にも門戸が開かれてきたのではないでしょうか。

慈光会による、ぜんざい接待がありました。
美味しかったです

住職のご法話をお聴聞しました。

大逮夜のお説教です!親鸞聖人をお偲びいたしました!

皆様ようこそお参りいただきました!

「ゆきうさぎ」です!
昨日から広島市内は雪が積もっているそうです!
江田島市は、雪は積もっていません!

デイサービスは今日もお勤めをして始まりました!

今日も宜しくお願いします!

今日は、ゆっくりしましょう!

おしゃべりしながらの塗り絵タイムです

女子会はつづきます!

話して、笑って、和やかに過ごされました!

昼休みには、連続ドラマを見ました!

これから健康チェックをして、午後の時間となります!

午後はお茶をいただいたり、おしゃべりをして過ごしました!

今日の作品です!

冬の歌をうたいました!

りんごの唄・ゆき・たきび・高校三年生・星影のワルツを歌いました

今日も無事終了!

来週お会いしましょう!