区の広報に掲載された「芝浦工業大学SITテクノロジーカフェ」に申し込んで参加した。
今回のテーマは「S3Dで蘇る百年前の東京、そして日本」。
講師からS3Dの解説。両方の目で見ているのと同じように、左右2つの映像を使って奥行や立体感を再現する映像をS3D(Stereoscopic 3D)と呼んでいるそうだ。
スクリーンの映像を特殊なメガネをかけて見ると奥行があって、その場にいるような感じがした。
このような原理をもとにした写真が120年前にイギリスなどで富裕層向けに売られていたというから驚いた。
2つのレンズを持つカメラで写した2枚の写真を横にならべたものを、ビューワーという手に持って使う鑑賞装置で見ると立体感があるように見える。
日本の各地の風景や人々の生活の写真も残っていて、それを特別に加工した映像を今回見せてもらった。
浅草、横浜、鎌倉、松島、京都、岩国など、100~120年くらい前の映像に奥行があってとてもおもしろかった。祖父母、曾祖父母の生きていた時代に興味があるので、明治~大正時代の映像に親しみを感じた。
取り壊される建造物、変わっていく風景や風俗をこうしたS3D映像で残していくことはたいせつだと認識を新たにした。3D映像の技術を社会に生かしていく研究が進むと良いと思う。
今回のテーマは「S3Dで蘇る百年前の東京、そして日本」。
講師からS3Dの解説。両方の目で見ているのと同じように、左右2つの映像を使って奥行や立体感を再現する映像をS3D(Stereoscopic 3D)と呼んでいるそうだ。
スクリーンの映像を特殊なメガネをかけて見ると奥行があって、その場にいるような感じがした。
このような原理をもとにした写真が120年前にイギリスなどで富裕層向けに売られていたというから驚いた。
2つのレンズを持つカメラで写した2枚の写真を横にならべたものを、ビューワーという手に持って使う鑑賞装置で見ると立体感があるように見える。
日本の各地の風景や人々の生活の写真も残っていて、それを特別に加工した映像を今回見せてもらった。
浅草、横浜、鎌倉、松島、京都、岩国など、100~120年くらい前の映像に奥行があってとてもおもしろかった。祖父母、曾祖父母の生きていた時代に興味があるので、明治~大正時代の映像に親しみを感じた。
取り壊される建造物、変わっていく風景や風俗をこうしたS3D映像で残していくことはたいせつだと認識を新たにした。3D映像の技術を社会に生かしていく研究が進むと良いと思う。


















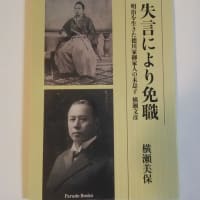

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます