~~引用ここから~~

他店でスーパーバイザーが幅を利かせていた時代から、ワークマンはネットで済ませていた
(略)
コロナでも絶好調だったワークマン
コロナでほとんどの企業が売り上げ大幅減になる中で、ニトリ、ワークマンはむしろ売り上げを増やした
コロナ禍でも4月は売上5.7%増加にとどまったが、5月は19・4%増などずっと2桁増を維持している。
ワークマンも他の小売りチェーンのように営業を自粛したり、営業時間を短縮していた。
(略)
努力より効率重視
これだけならケチケチ商人だが、ワークマンは日本での有数のIT活用企業で、テレワークも以前から導入していた。
社風は「残業しない」「努力しない」「先に褒美を出す」だそうで、店舗には主婦がパートでできる程度の事しか要求しない。
ワークマンは直営店が少なくフランチャイズが多いが、個人オーナーにとって発注が大きな負担になる。
ワークマンは発注作業をなくしてしまい、売れている商品や売れそうな商品を自動的に補充している。
残業は一切なく閉店後の事務処理もなし、オーナーや従業員は閉店後にすぐ帰宅し開店前の準備もしない。
だから朝7時からなど常識外の時間から開店できるが、ユニクロのように準備に数時間かけたら開店が10時ごろになってしまう。
ワークマンでは会議やハンコを押すために全員集合する事は無く、以前からネットや電話で済ませていた。
某コンビニでは本社社員が店舗を回ってオーナーに罵声を浴びせたり蹴とばしたりしていたが、店舗にもほとんど行かずテレワークで済ませていた。
店舗に行かずともデータはネットでやり取りできるし話は電話でできるので、行く必要がないという考え方だそうです。
ワークマンはFCオーナーがほとんど固定で親子で世襲する場合も多く、閉店が極端に少ないという。
納入メーカーも数十年固定で変化がなく、社員もほとんど辞めず数十年顔ぶれが変わらない。
これは「競争」を至上とするバブルからデフレ期の日本企業にとっては負け組の法則に近い。
だが現実には競争をすればするほど日本は弱くなり、非効率になり30年間ゼロ成長を続けている。
競争で弱くなった日本企業の特徴
バブルからデフレ期に成長した企業は労働者に無限の頑張りを要求し、はっきり言えば違法な労働をやらせていた。
社長が「しぬまで働け」「泳げない人間は沈める」と平気で言うような会社ほど日本では優良企業とされていた。
コンビニのブラックオーナー問題のように、誰かに極限の苦労をさせて、それを企業側は利益にしていた。
たとえば8時間の給料しか払わず16時間働かせれば人件費が半額に抑制でき、その分会社が儲かる。
日本の優良企業の正体はこれで、優良企業であるほど正体は最悪企業というパターンが多い。
こうした企業の在り方は労働効率で見ると非常に効率が悪いので、日本の生産性が世界最悪な原因になっている。
例えばドイツ人が8時間で済ませる労働を日本企業が16時間でやらせたら生産効率が半分に低下します。
人件費は違法にカット出来ても他のコストは時間に応じて増えるので、そんな企業はどこかで成長が止まる。
ブラック労働を前提にしているような企業は外国で通用しないだろうし、賃金カットを社長が自慢する会社で働くべきではない。
~~引用ここまで~~
ユニクロの柳井正が京都大学に100億円寄付すると宣言して称賛されたが、京都大学に100億円寄付するより前にやることがあるだろう。ユニクロに搾取されている従業員の待遇を改善することだ。搾取して浮いたお金で100億円寄付するのだから全く称賛できなかった。
~~引用ここから~~

ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は、ノーベル医学・生理学賞を受賞している京都大学の本庶佑特別教授と山中伸弥教授の研究に個人の資産から総額100億円を寄付すると発表しました。がんや新型コロナウイルスと闘うためだとしています。
24日、京都市左京区の京都大学で開かれた会見には、柳井社長と本庶特別教授、それに山中教授がそろって出席しました。
このなかで柳井社長は「医学の世界で最大の問題はがんとウイルスだ」と述べ、個人の資産から総額100億円を寄付することを明らかにしました。
具体的には本庶特別教授がトップを務めるがん免疫総合研究センターの研究費や人件費として、今後10年間、毎年5億円を寄付します。
また、山中教授に対しては、新型コロナウイルスの感染対策や治療薬の研究に対して5億円、iPS細胞を低コストで製造するための施設の建設などに来年度から9年間、毎年5億円を寄付するということです。
本庶特別教授は、「新しく自由な構想でお金を使えることが民間基金の有利な点で本当にありがたい」と話していました。
また、山中教授は「寄付に対して非常に重い責任を感じる。100%成功する研究はありえないが、最大限有効に使うよう心がけたい」と意気込みを語りました。
~~引用ここまで~~
ワークマンのテレワークやネットを利用した経営は実に合理的だ。それでいて従業員に決して無理をさせない。サービス残業や過当競争を強いる日本企業も見習うべきだろう。
ブラック企業の代名詞はユニクロだ。柳井正が日本と日本人を憎んでいるのか従業員を人扱いしない。サービス残業など当たり前で、従業員にはユニクロの商品の買い取りも強いる。
それでいてブラック企業と報道すれば提訴を仄めかすからマスコミは文春以外ユニクロのブラック企業ぶりを報道しない。広告費という飴もあるのだろう。
企業経営の感覚で国家を運営してはならない - 面白く、そして下らない
柳井正の妄言は日本と日本人への憎悪からか - 面白く、そして下らない
ユニクロは利用しないようにしていたが、これからはワークマンを利用するようにしよう。
もうひとつのブラック企業の代名詞はコンビニオーナーだ。「一国一城の主」になれると甘い言葉で騙しておきながら、実際は「奴隷頭」に過ぎない。家族にも過重労働を強いるし、家族の協力がなければ店は回らない。
しかし過重労働をいつまでも続けられないから、どこかで破綻してしまう。コンビニ本部は知らん顔で新しい「奴隷」を探すのである。
コンビニオーナーになるメリットはないことは知られてきた。新しくコンビニオーナーになろうという人は少ない。新型コロナウイルスとレジ袋有料化でコンビニは売り上げが落ちていると聞く。ブラック企業は退場させたい。今コンビニオーナーをしている人には悪いが。

コロナで好調だったワークマン、実はテレワーク先進企業だった : 世界のニュース トトメス5世
他店でスーパーバイザーが幅を利かせていた時代から、ワークマンはネットで済ませていた画像引用:【新川】ワークマンプラス北海道初出店!新店舗にい...
世界のニュース トトメス5世
他店でスーパーバイザーが幅を利かせていた時代から、ワークマンはネットで済ませていた
(略)
コロナでも絶好調だったワークマン
コロナでほとんどの企業が売り上げ大幅減になる中で、ニトリ、ワークマンはむしろ売り上げを増やした
コロナ禍でも4月は売上5.7%増加にとどまったが、5月は19・4%増などずっと2桁増を維持している。
ワークマンも他の小売りチェーンのように営業を自粛したり、営業時間を短縮していた。
(略)
努力より効率重視
これだけならケチケチ商人だが、ワークマンは日本での有数のIT活用企業で、テレワークも以前から導入していた。
社風は「残業しない」「努力しない」「先に褒美を出す」だそうで、店舗には主婦がパートでできる程度の事しか要求しない。
ワークマンは直営店が少なくフランチャイズが多いが、個人オーナーにとって発注が大きな負担になる。
ワークマンは発注作業をなくしてしまい、売れている商品や売れそうな商品を自動的に補充している。
残業は一切なく閉店後の事務処理もなし、オーナーや従業員は閉店後にすぐ帰宅し開店前の準備もしない。
だから朝7時からなど常識外の時間から開店できるが、ユニクロのように準備に数時間かけたら開店が10時ごろになってしまう。
ワークマンでは会議やハンコを押すために全員集合する事は無く、以前からネットや電話で済ませていた。
某コンビニでは本社社員が店舗を回ってオーナーに罵声を浴びせたり蹴とばしたりしていたが、店舗にもほとんど行かずテレワークで済ませていた。
店舗に行かずともデータはネットでやり取りできるし話は電話でできるので、行く必要がないという考え方だそうです。
ワークマンはFCオーナーがほとんど固定で親子で世襲する場合も多く、閉店が極端に少ないという。
納入メーカーも数十年固定で変化がなく、社員もほとんど辞めず数十年顔ぶれが変わらない。
これは「競争」を至上とするバブルからデフレ期の日本企業にとっては負け組の法則に近い。
だが現実には競争をすればするほど日本は弱くなり、非効率になり30年間ゼロ成長を続けている。
競争で弱くなった日本企業の特徴
バブルからデフレ期に成長した企業は労働者に無限の頑張りを要求し、はっきり言えば違法な労働をやらせていた。
社長が「しぬまで働け」「泳げない人間は沈める」と平気で言うような会社ほど日本では優良企業とされていた。
コンビニのブラックオーナー問題のように、誰かに極限の苦労をさせて、それを企業側は利益にしていた。
たとえば8時間の給料しか払わず16時間働かせれば人件費が半額に抑制でき、その分会社が儲かる。
日本の優良企業の正体はこれで、優良企業であるほど正体は最悪企業というパターンが多い。
こうした企業の在り方は労働効率で見ると非常に効率が悪いので、日本の生産性が世界最悪な原因になっている。
例えばドイツ人が8時間で済ませる労働を日本企業が16時間でやらせたら生産効率が半分に低下します。
人件費は違法にカット出来ても他のコストは時間に応じて増えるので、そんな企業はどこかで成長が止まる。
ブラック労働を前提にしているような企業は外国で通用しないだろうし、賃金カットを社長が自慢する会社で働くべきではない。
~~引用ここまで~~
ユニクロの柳井正が京都大学に100億円寄付すると宣言して称賛されたが、京都大学に100億円寄付するより前にやることがあるだろう。ユニクロに搾取されている従業員の待遇を改善することだ。搾取して浮いたお金で100億円寄付するのだから全く称賛できなかった。
~~引用ここから~~

「ユニクロ」柳井氏が100億円寄付 “がんやコロナと闘うため” | NHKニュース
【NHK】ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は、ノーベル医学・生理学賞を受賞している京都大学の本庶佑特別教…
NHKニュース
ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は、ノーベル医学・生理学賞を受賞している京都大学の本庶佑特別教授と山中伸弥教授の研究に個人の資産から総額100億円を寄付すると発表しました。がんや新型コロナウイルスと闘うためだとしています。
24日、京都市左京区の京都大学で開かれた会見には、柳井社長と本庶特別教授、それに山中教授がそろって出席しました。
このなかで柳井社長は「医学の世界で最大の問題はがんとウイルスだ」と述べ、個人の資産から総額100億円を寄付することを明らかにしました。
具体的には本庶特別教授がトップを務めるがん免疫総合研究センターの研究費や人件費として、今後10年間、毎年5億円を寄付します。
また、山中教授に対しては、新型コロナウイルスの感染対策や治療薬の研究に対して5億円、iPS細胞を低コストで製造するための施設の建設などに来年度から9年間、毎年5億円を寄付するということです。
本庶特別教授は、「新しく自由な構想でお金を使えることが民間基金の有利な点で本当にありがたい」と話していました。
また、山中教授は「寄付に対して非常に重い責任を感じる。100%成功する研究はありえないが、最大限有効に使うよう心がけたい」と意気込みを語りました。
~~引用ここまで~~
ワークマンのテレワークやネットを利用した経営は実に合理的だ。それでいて従業員に決して無理をさせない。サービス残業や過当競争を強いる日本企業も見習うべきだろう。
ブラック企業の代名詞はユニクロだ。柳井正が日本と日本人を憎んでいるのか従業員を人扱いしない。サービス残業など当たり前で、従業員にはユニクロの商品の買い取りも強いる。
それでいてブラック企業と報道すれば提訴を仄めかすからマスコミは文春以外ユニクロのブラック企業ぶりを報道しない。広告費という飴もあるのだろう。
企業経営の感覚で国家を運営してはならない - 面白く、そして下らない
柳井正の妄言は日本と日本人への憎悪からか - 面白く、そして下らない
ユニクロは利用しないようにしていたが、これからはワークマンを利用するようにしよう。
もうひとつのブラック企業の代名詞はコンビニオーナーだ。「一国一城の主」になれると甘い言葉で騙しておきながら、実際は「奴隷頭」に過ぎない。家族にも過重労働を強いるし、家族の協力がなければ店は回らない。
しかし過重労働をいつまでも続けられないから、どこかで破綻してしまう。コンビニ本部は知らん顔で新しい「奴隷」を探すのである。
コンビニオーナーになるメリットはないことは知られてきた。新しくコンビニオーナーになろうという人は少ない。新型コロナウイルスとレジ袋有料化でコンビニは売り上げが落ちていると聞く。ブラック企業は退場させたい。今コンビニオーナーをしている人には悪いが。












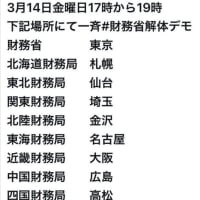

















ゼロ成長時代の日本にワークマンのビジネス・モデルを普及させて欲しいものだ。https://eukolos.fc2.net
>少ない労力で大きな成果を生む企業こそ望ましい
まさにですね。ユニクロのように賃下げばかりする企業に退場して欲しいです。