~~引用ここから~~

2021年の農林水産物・食品の輸出は好調な滑り出しとなった。農水省がまとめた1月の輸出額は前年同月より40%増の758億円で、1月としては過去10年で最高だった。新型コロナウイルス下、牛肉やリンゴ、緑茶などの引き合いが家庭向けで強まった。飲食店の規制が続く地域もあり、輸出拡大には家庭用需要の開拓が重要になっている。
前年からの伸びが特に大きいのは、リンゴで185%増の40億円。最大の輸出先の台湾では、春節向けの需要がピークを迎えた。コロナ下で家庭用需要が高まったことや、昨年は春節が早く1月には輸出のピークを過ぎていたことで増加幅が大きくなった。青森県は、「台湾や香港で小売りの伸びが大きい。リンゴは日持ちも良く、巣ごもり需要で選ばれた」(国際経済課)と指摘する。
牛肉、豚肉、鶏卵など畜産物も軒並み、家庭での需要の高まりを受けて好調だった。牛肉は、69%増の23億円。カンボジア、香港、台湾などアジア向けが伸びた。「香港向けは、家庭用に日本産の牛肉需要がある」(日本畜産物輸出促進協議会)という。
緑茶も25%増の14億円と勢いがある。日本茶輸出促進協議会によると、家庭でも手軽に飲める粉末茶が支持されている。担当者は「緑茶のおいしさや効能が認知されて、繰り返し購入する人が増えている」と話す。
その他の青果物も巣ごもり需要で好調だった他、米は31%増の5億円。日本酒も64%増の23億円と大きく伸びた。
政府は30年に農林水産物・食品の輸出額を5兆円にする目標を掲げる。海外のニーズや規制に対応し、輸出向けに生産する輸出産地を選定して、支援している。
~~引用ここまで~~
日本農業新聞が喜んでいるところ水を差すことになるが、農林水産物・食品の「輸出」を増やすべきなのだろうか。それよりは食料自給率を上げるべきなのではないか。
近年の貿易収支はトントンくらいで黒字でも赤字でもない。しかし所得収支が年間20兆円ほども黒字なので経常収支は大幅な黒字なのだ。これ以上外貨を稼ぐ必要はない。円高が進行するだけだ。
所得収支の大幅な黒字を喜ぶ向きもあるかもしれないが、それは国内に投資先がないことと同義なのだ。国内に投資先がないから海外に投資して利益を回収しているわけだ。それよりは国内に投資して雇用を増やしGDPを成長させた方が国益になる。
農林水産物・食品はたくさん売ってもあまり儲けにならない。政府は2030年に5兆円も輸出する目標を掲げているそうだが、どれくらい売るつもりなのか。
輸出輸出で儲ける時代はもう終わっている。それよりは輸入を増やしてGDPを増やすべきなのだ。
食料は輸入に頼りすぎると食料危機が世界的な規模で起きた際に輸入できなくなるかもしれない。だから食料自給率を上げておかねばならないのだが、カロリーベースの食料自給率はずっと40%程度でしかない。
平時は輸出を増やしておき、食料危機が起きた際に輸出分を国内に回すというのも一つの手段だが、国際社会から非難されないか。食料危機が起きた際には形振り構っていられないか。
日本産の農林水産物・食品を売ることで日本の認知度を上げて、良質な農林水産物・食品であれば好感度が増そう。それは「ソフトパワー」に繋がるから輸出を増やすことは悪くはない。
しかし同じ労力を使うなら食料自給率を上げることの方が国益に叶うと考えるのである。
日本人が食べるものは安い輸入品で、海外の富裕層向けに国産品を輸出することになるのは狂っている構図ではないか。食品は安全な国産を食べたいものだ。もっとも国産が必ずしも安全とは言えないのだが。
グローバリズム路線を見直すべきではないだろうか。

日本農業新聞 - 1月農産物輸出40%増 家庭向け好調 過去10年で最高
日本農業新聞は、国内唯一の日刊農業専門紙です。農政や農家の営農に役立つ技術情報、流通・市況情報に加え、消費者の関心も高い食の安全・安心、農産...
日本農業新聞
2021年の農林水産物・食品の輸出は好調な滑り出しとなった。農水省がまとめた1月の輸出額は前年同月より40%増の758億円で、1月としては過去10年で最高だった。新型コロナウイルス下、牛肉やリンゴ、緑茶などの引き合いが家庭向けで強まった。飲食店の規制が続く地域もあり、輸出拡大には家庭用需要の開拓が重要になっている。
前年からの伸びが特に大きいのは、リンゴで185%増の40億円。最大の輸出先の台湾では、春節向けの需要がピークを迎えた。コロナ下で家庭用需要が高まったことや、昨年は春節が早く1月には輸出のピークを過ぎていたことで増加幅が大きくなった。青森県は、「台湾や香港で小売りの伸びが大きい。リンゴは日持ちも良く、巣ごもり需要で選ばれた」(国際経済課)と指摘する。
牛肉、豚肉、鶏卵など畜産物も軒並み、家庭での需要の高まりを受けて好調だった。牛肉は、69%増の23億円。カンボジア、香港、台湾などアジア向けが伸びた。「香港向けは、家庭用に日本産の牛肉需要がある」(日本畜産物輸出促進協議会)という。
緑茶も25%増の14億円と勢いがある。日本茶輸出促進協議会によると、家庭でも手軽に飲める粉末茶が支持されている。担当者は「緑茶のおいしさや効能が認知されて、繰り返し購入する人が増えている」と話す。
その他の青果物も巣ごもり需要で好調だった他、米は31%増の5億円。日本酒も64%増の23億円と大きく伸びた。
政府は30年に農林水産物・食品の輸出額を5兆円にする目標を掲げる。海外のニーズや規制に対応し、輸出向けに生産する輸出産地を選定して、支援している。
~~引用ここまで~~
日本農業新聞が喜んでいるところ水を差すことになるが、農林水産物・食品の「輸出」を増やすべきなのだろうか。それよりは食料自給率を上げるべきなのではないか。
近年の貿易収支はトントンくらいで黒字でも赤字でもない。しかし所得収支が年間20兆円ほども黒字なので経常収支は大幅な黒字なのだ。これ以上外貨を稼ぐ必要はない。円高が進行するだけだ。
所得収支の大幅な黒字を喜ぶ向きもあるかもしれないが、それは国内に投資先がないことと同義なのだ。国内に投資先がないから海外に投資して利益を回収しているわけだ。それよりは国内に投資して雇用を増やしGDPを成長させた方が国益になる。
農林水産物・食品はたくさん売ってもあまり儲けにならない。政府は2030年に5兆円も輸出する目標を掲げているそうだが、どれくらい売るつもりなのか。
輸出輸出で儲ける時代はもう終わっている。それよりは輸入を増やしてGDPを増やすべきなのだ。
食料は輸入に頼りすぎると食料危機が世界的な規模で起きた際に輸入できなくなるかもしれない。だから食料自給率を上げておかねばならないのだが、カロリーベースの食料自給率はずっと40%程度でしかない。
平時は輸出を増やしておき、食料危機が起きた際に輸出分を国内に回すというのも一つの手段だが、国際社会から非難されないか。食料危機が起きた際には形振り構っていられないか。
日本産の農林水産物・食品を売ることで日本の認知度を上げて、良質な農林水産物・食品であれば好感度が増そう。それは「ソフトパワー」に繋がるから輸出を増やすことは悪くはない。
しかし同じ労力を使うなら食料自給率を上げることの方が国益に叶うと考えるのである。
日本人が食べるものは安い輸入品で、海外の富裕層向けに国産品を輸出することになるのは狂っている構図ではないか。食品は安全な国産を食べたいものだ。もっとも国産が必ずしも安全とは言えないのだが。
グローバリズム路線を見直すべきではないだろうか。










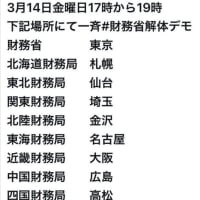









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます