
↑方丈は、広島の安国寺にあったもので、1599年に安国寺恵瓊(あんこくじえけい)によって移築されました。屋根は銅板葺になっています。

↑方丈から茶室に行く方向(裏庭)に安国寺恵瓊の首塚がありました。“関ケ原(司馬遼太郎著)”を読み終えた私にはグッドタイミングな感じで、少し気分が高揚してしまいました。
禅僧であり大名である恵瓊は、関ケ原の戦い(1600年)で西軍側の最高首脳として暗躍します。敗者となった恵瓊は、毛利家西軍荷担の罪で六条河原で斬首されますが、建仁寺の僧侶が首を持ち帰り、埋葬したそうです。

↑茶室“東陽坊”です。1587年に豊臣秀吉が催した北野大茶会(京都北野天満宮の境内にて)で、千利休の高弟・真如堂東陽坊長盛が担当した副席と伝えられています。明治34年に安永萬次郎氏により建仁寺に寄贈されることになりました。

↑山門(望闕楼)です。江戸時代の建築物で、1923年に静岡の安寧寺から移築されました。「御所を望む楼閣」と意味で“望闕楼(ぼうけつろう)”と名づけられました。

↑浴室です。江戸時代初期の蒸し風呂が復元されています。ちなみに日本における入浴の起源は、6世紀に仏教とともに中国から伝来した“沐浴”にあるといわれています。仏に仕える者が身を清める重要な行為であり「七病を除去し、七福が得られる」との事から、日本の寺院にはたくさんの浴室が作られたそうです。
その他、建仁寺にはたくさんの見所があり、色々とお勉強になりました。
■建仁寺■
京都市東山区大和大路四条下ル小松町
拝観時間 10:00~16:00 (行事により拝観できない場合あり)

↑方丈から茶室に行く方向(裏庭)に安国寺恵瓊の首塚がありました。“関ケ原(司馬遼太郎著)”を読み終えた私にはグッドタイミングな感じで、少し気分が高揚してしまいました。
禅僧であり大名である恵瓊は、関ケ原の戦い(1600年)で西軍側の最高首脳として暗躍します。敗者となった恵瓊は、毛利家西軍荷担の罪で六条河原で斬首されますが、建仁寺の僧侶が首を持ち帰り、埋葬したそうです。

↑茶室“東陽坊”です。1587年に豊臣秀吉が催した北野大茶会(京都北野天満宮の境内にて)で、千利休の高弟・真如堂東陽坊長盛が担当した副席と伝えられています。明治34年に安永萬次郎氏により建仁寺に寄贈されることになりました。

↑山門(望闕楼)です。江戸時代の建築物で、1923年に静岡の安寧寺から移築されました。「御所を望む楼閣」と意味で“望闕楼(ぼうけつろう)”と名づけられました。

↑浴室です。江戸時代初期の蒸し風呂が復元されています。ちなみに日本における入浴の起源は、6世紀に仏教とともに中国から伝来した“沐浴”にあるといわれています。仏に仕える者が身を清める重要な行為であり「七病を除去し、七福が得られる」との事から、日本の寺院にはたくさんの浴室が作られたそうです。
その他、建仁寺にはたくさんの見所があり、色々とお勉強になりました。
■建仁寺■
京都市東山区大和大路四条下ル小松町
拝観時間 10:00~16:00 (行事により拝観できない場合あり)










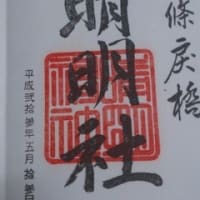









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます