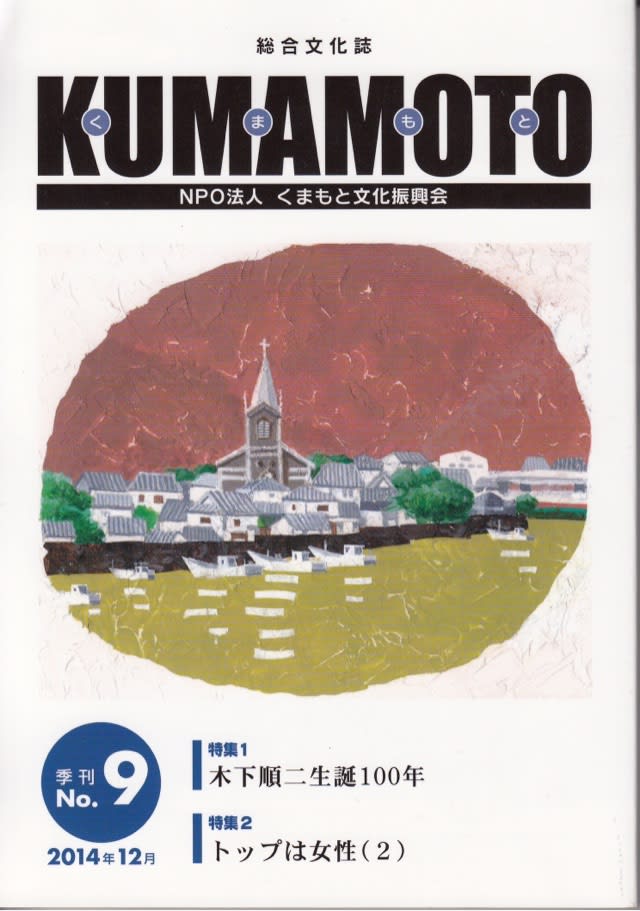NPO法人 くまもと文化振興会
2015年9月15日発行
はじめての夏目漱石・俳句
~熊本時代は俳人だった~
永田 満徳
一 熊本時代の漱石
1 学制確立期の教育者
授業は厳格で、テキスト一冊全部やり終えるので進度が速く、今日重視されている実用英語にも理解があり、入試問題に導入する見識を持っていた。よんどころない理由がない限り、欠勤はせず、週24時間の授業を受け持つほかに、明治29年9月からは生徒の要望に応えて午前7時より課外講義を行っている。漕艇部の二代目部長にも就任している。福岡・佐賀の中学校の視察を命ぜられ、佐賀県尋常中学校では急遽校長に講演を請われ、高等学校の教授の立場で中学生に語りかけている。この学校視察などは「視学官」的な役割を担っていたと思われる。第七回目の開校紀念式では職員総代として祝詞を読んでいることや、校務においては管理職の職務に属する人事異動に深く関わり、不適格教師の追放に関与するなど、教師陣の強化に心を砕いている。明治33年4月には教頭心得になっていることからも窺えるように、五高職員のなかで中枢の立場に立っていたといえる。
2 新派俳句の俳句創作者
明治28年8月 新派俳句の唱道者・正岡子規が従軍で得た病の療養のため松山に帰郷して漱石の仮宿舎「愚陀仏庵」に転がり込んだことから、漱石は俳句を作り始め、病が癒えた子規が東京に戻ったあとは子規に句稿を送って添削依頼する。熊本時代の俳句はこの子規に送った句稿がほとんどである。明治32年1月、〔子規へ送りたる句稿 その31〕の最後に、「冀くは大兄病中煙霞万分の一を慰するに足らんか」と書いている。つまり、病魔に襲われている子規の苦痛を添削によって軽減しようというものである。この月が75句、2月が105句を子規に送っている。その積み重ねが熊本時代の千句あまりの句数である。
明治31年春、五高学生の蒲生紫川 (栄)と厨川千江 (肇)が俳句に興味を持ち、井川淵の漱石家を訪ねたことが事の発端である。特に千江の俳句熱は旺盛で、同じ五高生の白仁白楊(後の坂元雪鳥)、寺田寅日子(寅彦)ら11人を誘い、10月2日、井川淵から越した内坪井の漱石宅で、念願の運座を開くに至る。この座は「紫溟吟社」と命名される。翌三十二年秋、「紫溟吟社」は五高外からも池松迂巷、渋川玄耳らが加入してきて、会はますます活況を呈することになる。迂巷の尽力で、九州日日新聞社の紙上に翌年1月から「紫溟吟社詠」が発表されるようになり、漱石の周辺を越えて、新派俳句が広く知れ渡ることとなった。熊本時代の夏目漱石は俳句全体の四割を作り、正岡子規が唱えた新派俳句を熊本にもたらした。
このように、夏目漱石は教育行政側の期待に応えるべく、第五高等学校の発展に尽力し、ひいては明治期の学制の確立に貢献した教育者、教育官僚であった。その一方、多忙極まりない中、子規を慰労する一心でせっせと句を作っていたのである。
三 漱石俳句の特色
1 俳句のレトリック
子規が「明治二十九年の俳句界」で、漱石俳句の特色として「活動」という二字評を下した言葉は的確であった。対象や方法を限定することなく、どのようにも「活動」できる幅があったと言わなければならない。その元になったのは漱石が「俳句はレトリックの煎じ詰めたもの」(「夏目漱石先生の追憶」昭和7年12月)であるという認識である。漱石がどれだけ「俳句のレトリック」に習熟していたかは、漱石俳句に対して、門下生と呼ばれる寺田寅彦・松根豊次郎・小宮豊隆が標語している『漱石俳句研究』が参考になる。そこには、「写生」「季語」「取り合せ」「省略」「デフォルメ」「連想」「擬人化」「同化」などの、あらゆる俳句のレトリックが使われている。例えば、俳句のレトリックではあまり使われないレトリックを取り上げる。
連想=季語の内包する美的イメージを表す
寒山か拾得か蜂に螫されしは 漱石
空想=現実にありそうにもないことを想像する
無人島の天子とならば涼しかろ 漱石
デフォルメ=対象を強調する
夕立や犇く市の十萬家 漱石
2 熊本時代の俳句の素材
熊本の地名や雰囲気を詠んだものには紛れない漱石の足跡が刻み込まれている。
【地名を詠みこんだもの】
大慈寺の山門長き青田かな
明治29年作。熊本市南部にある曹洞宗の古刹大慈禅寺。あたり一面の青田のなかに参道の長い「門」に焦点をあてることによって、「大慈寺」のたたずまいが見えてくる。「青田」の青と「山門」の色との対比も、「大慈寺」の風格のあるさまをよく表現している。季語「青田」=春
天草の後ろに寒き入日かな
明治31年、小天旅行の折の作。天草の島に日が沈むのを詠 んだもの。「天草」という言葉は、キリシタン禁制、天草・島原の乱などのかなしい歴史を背負っている。そうしたイメージを「天草の後ろ」に込めて、冬の「寒き入日」と取り合わせることによって、冬の一情景をみごとに表現している。季語「寒し」=冬
【地名の雰囲気を詠みこんだもの】
湧くからに流るるからに春の水
明治31年作。「水前寺」という前書のある句。水前寺成趣園の池は阿蘇の伏流水である清水が湧き出ている。つぎつぎに湧いて流れる水のさまを「湧くからに流るるからに」と的確に表現している。特に「からに」のくり返しが湧水のリズムを捉えている。「春の水」=春
行けど萩行けど薄の原広し
明治32年作。「阿蘇の山中にて道を失ひ終日あらぬ方にさまよふ」という前書がある句。このときの体験が「地にあるものは青い薄と、女郎花と、所々にわびしく交る桔梗のみ」という『二百十日』の作品に生かされている。萩と薄だけが生い茂っている草原のひろがりと次々にわき起こる不安とが「行けど」のくり返しで表現されている。季語「萩・薄」=秋
【五高を詠みこんだもの】
第五高等学校に勤務していなければ表現できない内容の句で、当時の高等学校の様子が記録されている点で貴重である。
いかめしき門を這入れば蕎麦の花
明治32年作。「学校」の前書がある句。旧制五高の表門は赤レンガの堂々とした立派な造りである。当時はその表門から校舎のある中門のあいだには畑があった。当時九州の最高学府である赤い門と蕎麦の白い花との対比がすばらしい。季語「蕎麦の花」=秋
かしこまる膝のあたりやそぞろ寒
明治32年作。「倫理講話」の前書がある。倫理科の授業は各学年各学級と合わせて週一回行われていた。「かしこまる膝」という表現によって、その授業が五高生にとっては厳しいものであったことがわかる。「かしこまる」と「そぞろ寒む」とが呼応して、倫理講話の緊張感が伝わってくる。季語「そぞろ寒む」=秋
【家庭を詠みこんだもの】
実に微笑ましい家庭の事情がよく分かる句で、漱石の生活の一断面が切り取られている。
名月や十三円の家に住む
明治29年、二度目に移り住んだ合羽町(現坪井)での作。「十三円」とは家賃のことであるが、新築でありながら粗雑な普請であったことに対しての不満が込められている。しかし、「名月」という季語によって、その不満をよそに置き、自然に親しもうとする風流な心が表されている。季語「名月」=秋
安々と海鼠の如き子を生めり
明治32年、長女筆子が生まれたときの印象の句である。「海鼠の如き」には赤ん坊の得体の知れない姿がよくとらえられている。「安々と」という言葉はむろんのこと、父親として初産の安心感を詠んだものと思われる。季語「海鼠」=冬
【内面を詠みこんだもの】
内省力の強かった文豪夏目漱石を彷彿させる句で、人生に対する一貫した態度が窺える。
木瓜咲くや漱石拙を守るべく
明治30年作。『草枕』の主人公に「世間には拙を守るという人がいる。この人が来世に生まれ変わるときっと木瓜になる。余も木瓜になりたい」と言わせている。頑固者の意である「漱石」という号にしても、「拙を守る」という言葉にしても、決して上手な生き方を望まない人生態度を表明したものである。季語「木瓜の花」=春
菫程な小さき人に生まれたし
明治30年作。転生への願いを美しくかれんな「菫」に託した句。のちに文豪と称される人の言葉としては意外に思われるが、漱石は決して華やかで世慣れた人物は好きではなかった。「菫ほどの」より「菫ほどな」と小休止したほうが「菫」のやさしい感じがよく出てくる。季語「菫」=春
【多彩な内容を詠みこんだもの】
自由奔放な詠みぶりで、子規派の中でも異彩を放っている。
人に死し鶴に生れて冴返る
明治30年作。「冴返る」とはゆるんだ寒さがぶりかえすという意味。寒気の中にすくっと立っている鶴に、生まれ変わった人間の姿を見ている。漱石にとって「鶴」は孤高の象徴であるという。「冴返る」という季語と鶴への転生という言葉とがよく響き合い、純粋な美へのあこがれが読み取れる。季語「冴え返る」=春
ふるひ寄せて白魚崩れん許りなり
明治30年作。半透明の「白魚」のかよわさと美しさを詠んだものである。四ッ手網などで掬い取られた「白魚」に焦点をあてて、一瞬の景を「崩れん許り」という比喩によって的確に表現している。季語「白魚」=春
四 小説『草枕』に於ける俳句
ところで、阿蘇の旅の経験を元にした『二百十日』にしても、小天に訪れた経験を活かした『草枕』にしても、その折に詠んだ俳句が背景にあることは言うまでもない。小森陽一氏が「昔」(『永日小品』)を取り上げて、俳句が記憶装置として働いて、文章を書いたのではないかと述べていることは「二百十日」「草枕」にも当てはまる。
記憶装置としての俳句が「草枕」を生み出したのであれば、これまで明確にされなかった場面も熊本時代の俳句と照らし合わせることによって、舞台が浮き彫りになってくる。
『草枕』13章の川下りの場面は明らかに漱石の俳句が記憶装置として機能していると言わなければならない。
菜種咲く小鳥を抱いて浅き川
掉さして舟押し出すや春の川
柳ありて白き家鴨に枝垂りたり
という漱石の江津湖の俳句が文章化されて、『草枕』第13章の、
川幅はあまり広くない。底は浅い。流れはゆるやかである。(中略)舟は面白いほどやすらかに流れる。左右の岸には土筆でも生えておりそうな。土堤の上には柳が多く見える。まばらに、低い家がその間から藁屋根を出し、煤けた窓を出し、時によると白い家鴨を出す。家鴨はがあがあと鳴いて川の中まで出て来る。
というふうに、俳句と小説とが相関関係になっている。川下りの場面が江図湖を舞台にしているとの説は、中村青史氏がすでに『熊本文化』(平26・12号)で指摘しているところである。
ちなみに、『草枕』11章の「観海寺」の舞台として挙げられているのは本渡の「明徳寺」である。もちろん、漱石は五高生の修学旅行の引率で本渡に宿泊している。『草枕』11章と明徳寺との符号を明徳寺の側からみてみる。長い階段と上り口の「不許葷酒入山門」という石橙。漱石が訪れた当時は「石橙を登りつくしたる時、朧にひかる」「海が帯のごとくに」見えたであろう。「不許葷酒入山門」という石橙は禅宗の寺には珍しくほとんど見ないものだそうである。何よりも『草枕』の季語を調べた折に「覇王樹」が出てきたことである。春の季語が絢爛に散りばめられた『草枕』の世界にあって、夏の季語「覇王樹」は異質であった。聞くところによると、明徳寺には「覇王樹」が生えていたという。「観海寺」の場面の「覇王樹」は明徳寺の記憶から記述されたものである。「覇王樹」については、南国の植物の象徴であるとともに、明徳寺が観海寺の舞台であることを証拠立てるもので、必ずしも俳句(季語)に囚われる必要がないとは、「明徳寺」説を夙に唱えられている中村青史氏の見解である。
英国留学中に寄せた書簡で「小天など旅行したい」と書いた漱石である。『草枕』の主な舞台である前田別邸のある小天(現天水町小天)に対する強い憧れが『草枕』を執筆の要因であることは間違いない。『草枕』の舞台を熊本時代に帰しているのは、漱石自身が「俳句的小説」(「余が草枕」)と公言してことからも、熊本時代の俳句が深く関与していると思っているからである。要するに、『草枕』は漱石にとって、熊本時代を再体験して、熊本時代を封じ込めた、熊本のよき思い出の記念碑的な作品であったということである。
そういう意味で、熊本時代は俳人だったのである。
(ながた みつのり/熊本近代文学研究会会員)
NPO法人 くまもと文化振興会
2015年9月15日発行
はじめての中村汀女
~肥後の猛婦の反骨精神~
永田満徳
初めに
中村汀女は昭和十九(一九四四)年二月に『汀女句集』を出版している。この句集は第一句『春雪』(昭15・3)の全ての俳句を取り込んでいるため、実質的には第一句集ともいうべきものである。次の昭和二十三年三有社出版の句集『花影』と併せた初期の二つの句集には汀女俳句として愛唱されている句がほとんど含まれている、この時期の俳句によって、世に汀女の名声を確立されたと言っても過言ではない。
汀女は明治三十三(一九〇〇)年四月、飽託郡江津村(現熊本市中央区画図町上江津)生まれ。画図小学校、大正五年には熊本県立高等女学校(現第一高等学校)卒業後母の厳しい躾(しつけ)のもとで裁縫、家事を習った。生花を指導した山崎貞嗣に贈られた斎号「瞭雲斎花汀女」の「汀女」を俳号とする。
一 熊本俳句史に於ける汀女
正岡子規が唱えた新派俳句を熊本にもたらしたのは漱石であった。明治三十一年春、五高学生らが内坪井の漱石宅で、念願の運座を開くに至る。この座は「紫溟吟社」と命名される。翌三十二年秋、「紫溟吟社」は五高外からも一般人が加入してきて、会はますます活況を呈することになる。池松迂巷の尽力で、九州日日新聞社(現熊本日日新聞)の紙上に翌年一月から「紫溟吟社詠」が発表されるようになり、漱石の周辺を越えて、新派俳句が広く知れ渡ることとなった。漱石離熊の翌三四年、紫溟吟社は機関誌「銀杏」を創刊し、活動は軌道に乗るが、会員の卒業や転任、戦争への出征等で、翌三五年五月に「銀杏」は休刊する。しかし、紫溟吟社の精神は、後に九州四天王の一人に数えられた井上微笑が精力的に発行した「白扇会報」に引き継がれることになる。「白扇会報」終刊後、微笑の才能を惜しんだ友人の斡旋で、九州日日新聞の「熊本会俳壇」の選者になったが、大正二年には熊本俳壇の重鎮となる広瀬楚雨に譲ることになる。広瀬楚雨は「紫溟吟社」に加わった一般人の一人である。大正七年はその広瀬楚雨も熊本を離れることになり、新選者になったのが三浦十八(じゅうはち)公(こう)であり、二十九歳の若さであった。大正十八年になると、常連の投句者が出揃い、その中に中村汀女がいた。この俳壇の特色は有季定型俳句を重んじて、新傾向俳句いわゆる自由律俳句を排斥していることである。汀女は初心者ゆえにその影響を受けて、有季定型を逸脱することのない俳句を作っている。夏目漱石が種を蒔(ま)いた新派俳句有季定型の世界で開花した俳人ということになる。
中村汀女は熊本の俳句史のなかで育てられ、育った俳人であったと言わなければならない。
二 二人の師との巡り合い
汀女一八歳である大正七年のある日、前庭の垣根に生えている寒菊を見て、「我に返り見直す隅に寒菊赤し」という句が浮かび、俳句とはこんなものかと俳句に目覚めて、父の愛読していた「九州日日新聞」の俳句欄に投句してみると、選者三浦十八公の目に留まることとなる。その十八公から大変お誉めの手紙を貰い、それを契機に俳句を作る気になるのである。ここで注目したいのは汀女に対する十八公の慧眼(けいがん)である。十八公無くして汀女無しという感が強く、汀女は名伯楽に出会ったということである。大正八・九年が「九州日日新聞」の俳句欄が最盛期であったことも幸いしている。翌大正八年には十八公の勧誘によって『ホトトギス』に投句してみたところ、一句でも入選すると大喜びした時代で、いきなり初投句で四句入選するという早熟の才を示すこととなる。
税務監督局の夫の転勤に伴って俳句から遠ざかっていた三十二歳の汀女が昭和七年に杉田久女が発行した個人俳誌『花衣』に投句を再開することになり、約十年ぶりに作句への意欲が沸き起こる。昭和七年には『ホトトギス』発行所にいた高浜虚子を訪れ、ついでに虚子の次女である星野立子を知ることとなる。この二人はのちに「ホトトギス」派女流の双璧と呼ばれることとなる。汀女は高浜虚子によって、当時珍しかった「女流の俳句」(虚子)の作り手として育てられ、「男性を凌ぐ」(虚子)位置を与えられることになる。
中村汀女は俳人としての出発点を熊本の俳壇の隆盛期に出会い、熊本を離れては中央俳壇の大御所高浜虚子の恩恵に浴するという幸運に恵まれたことになる。
三 汀女俳句の特色
ここでは、初期の『汀女句集』と『花影』を主に取り上げて、句風の特色に触れてみたい。『汀女句集』は第一句集『春雪』を含み、最終稿を除くと第一章が最も句数が多い。その章の題名が〈湖畔抄江津〉となっていて、「江津湖畔に私の句想はいつも馳せてゆく」(『汀女句集』序文)に端的に表される江津湖及び湖畔の村での生活を詠んでいる。
政争の激しかった「江図」の村長斉藤平四郎の一人娘であって、その雰囲気を肌で感じる環境であったにも拘(かかわ)らず、政治或いは世事を離れて、日常を見たまま感じたままを表現する素直な表現はともすれば陳腐で月並みな俳句に堕することになる。例えば、
身かはせば色変る鯉や秋の水
という句以外は俳句として今一歩という点が少なくない。
初期において既に現れていて、のちに「「私の句法」(昭43)を語った「心にあふれ、そのまま消し去るにしのびないもの( 注)を十七字にする」ことを信条とする態度は俳句を再開し始めた昭和七年以降に一気に才能を発揮させることになる。『汀女句集』では、汀女の代表句として名高い、
とどまればあたりにふゆる蜻蛉かな(昭7)
を始めてとして、
たんぽぽや日はいつまでも大空に(昭9)
稲妻のゆたかなる夜も寝べきころ(昭9)
中空にとまらんとする落花かな(昭十)
秋雨の瓦斯が飛びつく燐寸かな(昭十)
ゆで玉子むけばかがやく花曇(昭11)
などがある。吾子俳句として有名な句では、
あはれ子の夜寒の床の引けば寄る(昭11)
咳の子のなぞなぞあそびきりもなや(昭12)
などもこの時期である。『花影』では次の句も汀女の代表句の一つである。、
外(と)にも出よ触るるばかりに春の月(昭21)
汀女の名句は偶発的に突発的にできた訳ではない。家庭に入れば、良妻賢母としての立場を弁(わきま)え、主婦という「ひとりの女の明け暮れ」(「汀女自画像」)を技巧に走ることなく、心に動かされた(注)ものを平易に描いたところに生まれた事実を忘れてはならない。
終わりに
汀女が家庭内の事柄を読むことに対して「台所俳句」と男性俳人から揶揄(やゆ)されたことは承知のことである。汀女はその「台所俳句」という呼称を逆手にとって、「女性の職場ともいえるのは、家庭であるし、仕事の中心は台所である。そこからの取材がどうしていけないか」(「汀女自画像」)と一蹴していて、肥後の猛婦の一面を覗(のぞ)かせている。この汀女の反骨精神ともいうべき宣言が男性上位の俳句界に一石を投じることになり、俳句の素材の範囲を拡大させることになった。
身近に作句の材料があることを示してくれた功績は計り知れないものがある。
注 「俳句をたのしく|作句と鑑賞」(昭和43年)には作句の心構えと要領として「作り事は避ける」「技巧に走らぬこと」「誇張はしないこと」を説いている。
(ながた みつのり/熊本近代文学研究会会員)
総合文化誌「KUMAMOTO」第11号
NPO法人 くまもと文化振興会
2015年6月15日発行
《はじめての小泉八雲》
日本人の心になりきった小泉八雲
永田満徳
初めに
木下順二の小泉八雲研究は、旧制熊本中学五年(順二18歳)の時、『江原』(1932年12月)に発表された「研究 ラフカディオ・ハーン 其の研究の一班」と題する長文の論文に見ることができる。順二の八雲観は「外国人のバタ臭味から完全に脱却して日本人の心になりきつた強い意味を示す「染(ぢ)み」だ」と言い切ったところに最大の功績がある。しかし、八雲に対する評価において、八雲の文学が「日本人の心になりきつた」という言葉は何も順二に限らず、多くの論者が指摘するものである。ただ、『夕鶴』で国民的劇作家になった順二にとっては、この研究が順二の民話劇に影響を与えた点では大きい意味を持っている。
一 東洋への愛
八雲が西洋人でありながら、順二をして「日本人の心になりきつた」と言わしめるほどの、日本理解を示しえた理由の説明として最も的確なのは、教え子である田部隆次の「母親のおぼろげな記憶はいつもやさしく、思慕の愛情にあふれており、後年、ハーンが東洋の一切の事物を愛す原因となった。ハーンによるとたまたま『生まれた場所が東洋で血も半分は東洋であった』からである」という文章であろう。八雲の東洋への「愛」に影響を及ぼしたのは「母親」であるという田部の恩師に対する理解は、ロジャー・スティール・ウィルソンが「ハーンの西洋文明に対する疑問と不信」(注1)において、「シンシナティで見捨てられた青年だった頃、彼の父は、酉洋のすべて悪いもの、彼の母の東洋の遺産は、良くて正しいことすべてを体現していた。彼は若い記者になった時、これらの二つの世界にひっかかっていた。非同情的な現代文明の犠牲者へのハーンの感情はこれらの状況から起っているのだろう」と述べ、「母の東洋の遺産」に触れていることと大差がないことからも納得できる。ただ、八雲の日本の文化に違和感なく入り込めた根本的な要因では、この母の存在以上に重要なのは「コノート出身の乳母」である。
二 ケルト文化と俳句
ポール・マレーが「ハーンのイェーツとの文通を通してダブリンで小さい少年だった時ハーンはアイルランドの妖精の話や幽霊の話をしてくれるコノート出身の乳母を持っていたことを私達は知る。このようにして一生続く民俗的なことへの関心が始まったのである。実際、アイルランドを含めた前工業的世界の多くでは普通のことである妖精の話は、ハーンが後に日本分析の中心にした日本の古代宗教の神道とある点で似て、生きているものに、平行して存在し、時々作用を及ぼしているあの世からなっている」と「講演」(注2)で話しているのは注目に値する。八雲の経歴を閲(けみ)するまでもなく、父の生地であるアイルランドのタブリンに二歳から四歳に掛けて住んでいたことは周知の事実である。わずか二年間であったけれども、「三つ子の魂百まで」という言葉がそっくり当て嵌まるように、「コノート出身の乳母」による「アイルランドの妖精の話や幽霊の話」は深く刻み込まれることになる。
ポール・マレーが同じ講演で話していている「ケルトの妖精の信仰は『ロマンティックで詩的で、またものすごい』想像力に起因している。彼のアイルランドの農民生活の見解はまた明治前の日本の神道に基本を置いた精神にかなり似ている」という部分を参考にして、ケルト文化と俳句との繋がりを考えるとすれば、日野雅之が『大谷繞石』(注3)のなかで触れている「アイルランドの樹木や岩や川に魂があるというアニミズム(精霊信仰)を大切にしたケルト文化の妖精の話を乳母から聞いて育ったハーンにとって自然を詠む日本の俳句はケルト文化と共通するものがあったと思われる」という文章は大いに共感できる。
三 日本の韻文(俳句)
そこで、八雲と日本の韻文、特に俳句の関係を考察してみたい。
そのためにはまず、俳句の基礎知識として挙げなければならないのは季節・季語・季感の問題である。「俳句への一歩」(注4)を基にして説明するとする。日本人は知らず知らずのうちに季節に敏感になっている。例えば、「風鈴」の音色に涼しさを感じる消夏法などは、日本の季節・風土がつくりあげた感性によるものである。日本文学と季節・季語では、日本文学が古来季節と深い関わりを保ちながら形成されてきた。季節を「季語」という美学に置きかえて文学に作り上げたのが俳句と考えてよい。就中(なかんずく)、重要なのは季語の働きである。一句の中には、季語が必ず一つある。季語が作品の中で作用しているはたらき・色あい・雰囲気などと季語の背景(成立までの過程)や、季語の周辺(風土の中での存在性)をも含めて詠み、味わう。その季語を総合的に網羅したのが「歳時記」である。膨大な量の季語群に丹念に眼を通してゆくと、日本人の生活美学が作り上げた美しい季語に出会うに違いない。時候・天文・人事・宗教・動物・植物というものが採り上げられていて、百科全書の観がある。
四 俳句鑑賞
俳句鑑賞において、日本人と八雲を比較してみると、八雲の日本の韻文、特に俳句への理解の特色が見えてくる。
① 日本人の場合、ここでは、「俳句への一歩」の鑑賞文より抜き出し、A~Cの記号を付けて、分析しやくする。
金亀子擲つ闇の深さかな 高浜虚子
A いろいろ種類もあって、紫金色・赤鋼色・黒褐色などある。夏の夜など、うなりながら灯に飛んで来て、ポタリと落ちたりする。拾って窓外へほうり出すと又やって来たりするし、なかには、つかまると死んだ真似をするものもあるという。
B この句の「金亀子」もまさに、こうした「こがねむし」で、灯を求めて戸外の闇からやってきた「金亀子」を作者は闇へほうり投げて帰してやったというのである。畳の上に落ちた金亀子を掌にとると、金亀子はジッとして動かない。そこで縁側までたっていって、漆黒の夏の闇に向かって、大きくほうり投げてやる。はじめはただの小石か物のように、投げられたごとく宙を進んだ金亀子は、途中から、翅をひろげて、いかにも重さのなくなった物のごとく、闇の奥へ飛びはじめ、座敷の灯の及ばぬ闇へと消えていったというのである。
C 何でもない、只のことがらを叙しているようではあるが、投げたものが地上にぶつからずに消えてゆくという、手応えのなさから闇の無限の深さを感じとったことにも留意したい。実際に金亀子を投げた経験が土台になければ作り得ない句といえよう。したがってこうした句は鑑賞する側も、その経験の有無によって、その感じ方に違いがあるかも知れない。【金亀子=夏】
日本人による俳句鑑賞にはある型(パターン)がある。まず、書き出しのAで、「金亀子」の昆虫学(学問)的な習性と内容などを説明し、Bでは、句の状況を具体的に述べて、Cにおいて初めて、虚子の句の鑑賞に及び、名句たる所以を説き明かす。A・Bは客観的な記述に徹し、Cは鑑賞者の力量が試されるところで、どちらかというと、主観的な記述となることが多く、どれだけ納得させきれるかが問われる。
② 八雲の俳句鑑賞
八雲は俳句については、長澤純夫編訳「小泉八雲 蝶の幻想」(注5)のなかで、「俳句に関するほとんど唯一のものと思われる約束事は――別にそれはきびしいものではないが――俳句はことばで描いた一幅の小さな絵でなければならない、――見たり感じたりしたものの記憶を再生させるものでなければならない、――感覚上のある経験に訴えるものでなければならないということである。これから、わたくしが引用する俳句の大多数のものは、まさにこの要求を満たしており、読者は実際にそれらが絵であることを――浮世絵派の手法による小さな彩色版画であることを発見するであろう」と言い、「俳句のほとんどいずれも、日本画の巨匠の手によれば、ほんのわずかな筆致で、ことごとくこれを見事な絵にしてしまいうる作品である」とまで述べているのは、今日の俳句の認識とほぼ同じで、異なるところがない。この文章からは八雲が俳句の本質を知り、並々ならぬ理解を示していることを物語っている。
それでは、八雲の俳句鑑賞の一例として、「小泉八雲 蝶の幻想」のなかの「蟬」を取り上げる。ハーンの愛弟子の一人で執筆資料の提供者、協力者として長年ハーンのために尽くした大谷正信の手により、編纂、訳註が付せられて、大正十 (一九二一)年、『小泉八雲・蟲の文学』と題した、瀟洒(しょうしゃ)な小型の美本として北星堂から刊行された十篇の英文と、新たに加えた「蝶の幻想」は、『シンシナティ・コマーシャル』紙(一八七六年五月九日付)所載の原文を、そして「蚕」は『霊の日本』(一八九四年初版)を底本になされた。「蝶」をはじめ、後の「蟬」「蜻蛉」「螢」などは『怪談』(明治三七(一九〇四)年)に収録されている「虫の研究」の一章である。なお、A~Fの文章は本稿の分析に必要な部分のみを抜粋している。
「蟬」
A 日本の文学では、陸運という名で知られている中国の著名な学者が、蟬の五徳という(中略)面白いことばを書き残している。
B これを、今から二千四百年前の昔に書かれた、アナクレオンのあの美しい蟬の讃歌と比較するとき、ギリシアの詩人と中国の賢人との間に、思想上の数々の一致点を発見して驚く。
C 一方、日本の詩人たちは、これとは反対に蟬の声よりも、夜鳴く虫の声をより賞美する傾向がある。もちろん、蟬を詠んだ詩歌は日本にも無数にある。しかしその鳴く声をほめたたえたものはきわめて少ない。もともと日本の蟬は、ギリシア人の知っているそれとは、非常に違っている。日本の蟬のなかにも、たしかに音楽的に鳴くものもいるにはいるが、大多数のものは驚くほど騒々しい。彼らの鳴き騒ぐ声は、あまりにうるさいため、夏の季節の大きな苦痛の一つに思われているくらいである。
D 蟬に関する日本の詩歌は、おおむね非常に短いものが多く、わたくしの集めたものも、十七音節の俳句でほとんど占められている。そしてその俳句も大部分は蟬の声を――というよりも、蟬の声が作者の心にもたらした感興を詠んだものが多い。
E 蟬を詠んだ日本の詩歌には、哲学的な作品はそう多くない。
F 八雲の一句鑑賞
やがて死ぬけしきは見えず蟬の声 芭蕉
この小さな句の中に秘められている思想は、虫の声の哀れさとともに、自然の寂寞のなかから訴えてくる夏の憂愁を、多少なりとも説明しているのではないかと、わたくしは思う。こうした幾百万という小さな生きものたちは、無意識のうちに東洋の古代の叡(えい)知(ち)を――諸行無常を説く永遠の経典を説き教えているのである。
そもそも、八雲に対して俳句の指南役を務めたのが島根時代の教え子で、俳人の大谷正信(繞石)であり、英語圏の読者に向けての紹介文であることを差し引いてみても、八雲らしい俳句観が披瀝されている。AとBに見られる中国文学、ギリシア文学、CとDにおいては和歌にも言及して、比較文学的な考察を試みていて、八雲の博識ぶりが充分に窺えるものである。特徴的なことは、俳句の世界に「哲学」や「思想」、あるいは「諸行無常」といった宗教を持ち出して説明しているところである。Fでは、「寂寞」「憂愁」などの言葉を用いて、日本人の情緒を明らかにしている点は日本人の鑑賞文にあまり見られないものである。情を排し、「こと」ではなく、「もの」を詠むのが俳句であるからである。
終わりに
八雲の韻文、特に俳句に関する文章から浮かび上がってくるのは、いみじくも、アラン・ローゼン氏が「ラフカディオ・ハーンの科学的論説 Ⅰ」(注6)のなかで、ハーンは「英語圏の読者に向けて外国の文学作品を発見し、翻訳し、紹介する役割を果たす者となる夢を常に持ち続けていた。また、ハーバート・スペンサーなどによる社会哲学や、神道や仏教などの宗教にも、ハーンは深い関心を抱いていた。しかし、人文学の分野に対して純粋に文学的な取り組みをしているときにおいてさえ、科学は脇に押しやられることはなかった。また逆に、科学的な分野における論説においては文学的な色合いを指摘することができる」と述べているように、科学的分析力と文学的感性との適度のバランスの上に立って、俳句を理解し、鑑賞していると言わなければならない。
注1 『現代に生きるラフカディオ・ハーン』2007・3、熊本出版文化会館
注2 島根大学、1995・11・5
注3 2009・9、今井出版
注4 平九年七月、俳人協会
注5 1988・9、築地書館
注6 (『ハーン曼荼羅』、2008・11、北星堂)
(ながた みつのり/熊本近代文学研究会会員)
NPO法人 くまもと文化振興会
2015年3月15日発行
《はじめての与謝野鉄幹》
「大阿蘇」考
1 『五足の靴』と与謝野鉄幹の短歌
『五足の靴』は明治40年7月28日から8月27日まで、九州西部中心に約1ヶ月旅した、5人(与謝野寛(鉄幹)、北原白秋、木下杢太郎、吉井勇、平野万里=五足の靴)による紀行文である。与謝野鉄幹はその旅で阿蘇を訪れた折に作った短歌を詠んでいるが、再度阿蘇を訪れた際に、次のように語っている。
阿蘇の湯がよかつたね。何といつても阿蘇は世界一の火山とゐばれるよ。だが歌から云へば阿蘇の歌は無かたつたんですよ。清少納言の父の清原元輔も阿蘇に来たらしいんだが一つも山をうたつてゐない、僕が始めてだ。それからよくこゝにゐる舊友の松村辰喜君等が「大阿蘇」なんて大の字をつけるが之も僕が最初に言い出したのだ。何でも明治四十年頃ですよ。僕の門に集まった大學時代の北原白秋、木下杢太郎、吉井勇、平野万里四君を僕が引率者といふ格で栃木から阿蘇へ登山した時「大阿蘇の古きくだきの一角を天に捧げて香の炉とする」との一首を作つたのがはじめらしい、今では當時學生の四君が大家となり各方面に活躍してゐるのを思つて阿蘇は又いい感慨だ
『九州日々新聞』「内牧にて―阿蘇の話をする」昭和7年8月日(土)
つまり、「阿蘇」に“大”の字を使ったのは与謝野鉄幹が最初だというのである。確かに、与謝野鉄幹の「相聞」(明治年)の中に「五足の靴」来蘇中の短歌首が掲載れている。しかも、『五足の靴』の旅中の作品はこの阿蘇を詠んだものだけである。この「相聞」は『明星』全盛時代の作品を集めたものである。鉄幹には詩歌集が多く、唯一歌集のみのものはこの「相聞」だけで、与謝野晶子が編集したことでも知られている。
大阿蘇の古きくだけの一角を天に捧げて香の炉とする
深潟の鼎沸りて地鳴しぬわれ証し賜べ大阿蘇の山
黒けぶりに真直に揚りそのもとにとどろと鳴りぬ大阿蘇の山
「大阿蘇」という言葉を含む3首は「古き」「地鳴」する阿蘇の雄々しさを詠んだ短歌で、短歌革新のさきがけとして登場し、御歌所派の歌を軟弱なものと批判して、の歌を唱えた与謝野鉄幹らしいものである。
与謝野鉄幹が最初に「阿蘇」に“大”の字を使ったかどうかの当否はともかくとして、「大阿蘇」という言葉が明治年以後にどのように使われているかを辿ってみた。そして、そこから浮かび上がってきたものについても言及したい。
教育者
注目すべき第一は、多くの校歌に「大阿蘇」という言葉が使われているということである。例えば、必由館高校の校歌第二章に「大阿蘇」の歌詞がある。
大阿蘇に 映ゆる朝雲
金峰に 匂う夕霧
環境の 恵みにわれら
美しき 虹を仰ぎて
逞しく 錬磨に励む
作詞者は山口白陽である、山口白陽は大正年、熊本県立師範学校を卒業後、阿蘇郡内の小学校にて教鞭を執るかたわら白陽と号して、文筆活動を活発に行っている。特に作詞を手がけ、今日にいたるまで多くの学校で愛唱されている。彼が作詞した300を超える小学校・中学校・高校・大学の校歌、果ては会社の社歌には多数「大阿蘇」という言葉が使われている。「大阿蘇」(「阿蘇」も含む)の使われ方をみると、阿蘇の山と全く関係のない天草、球磨人吉などの校歌にはさすがに見えないが、熊本市内などの、阿蘇に近いところの校歌は必ずと言っていいほど「大阿蘇」(「阿蘇」も含む)の詞が見える。これは白陽が阿蘇一の宮出身であることも無関係ではない。教育の場において、白陽の歌詞を通して、「大阿蘇」が広く知れ渡り、定着したことは事実である。小説、俳句、短歌等さまざまな分野の創作を行っているので、与謝野鉄幹の「大阿蘇」の短歌を目にして、「大阿蘇」を使った可能性が高い。
② 文学者
第二に、文学者で、例えば国民的詩人である三好達治の存在である。三好達治は阿蘇登山の経験をもとにした詩『大阿蘇』と『草千里浜』の二篇を発表している。この「阿蘇詩二篇」の中にも2箇所に「大阿蘇」という言葉が使われている。
『大阿蘇』(『雑記帳』昭和)は題名そののものが「大阿蘇」であり、。また、『草千里濱』(『むらさき』昭和・9)では、
杖により四方をし眺む
肥の国の大阿蘇の山
駒あそぶの牧
名もかなし艸千里濱
として、最後の連に出てくる。特に、三好達治の『大阿蘇』は中学校の教科書に載っている関係もあり、「大阿蘇」という言葉は三好達治によって全国的にも知れ渡ったということがいえる。
さらに、蔵原伸二郎の詩にも「大阿蘇」の語句がある。蔵原伸二郎は阿蘇町黒川村(現阿蘇市)生まれ。詩人。本名惟賢。慶応大学在学中に萩原朔太郎の影響を受けて詩作を始める。昭和年の処女詩集『東洋の満月』で「おれは谷と火山の町で生まれた」「あの日暮の火山地の高原へ走ってゆかう」と歌い、大都市の近代文明を否定、原始的な阿蘇の自然への回帰を願う。昭和年1月発表の『故郷の山』(『文芸汎論』)の最終連は「大阿蘇山は/神さびにけり」とあり、まさしく神々しい「大阿蘇」に対する賛歌である。また、『大阿蘇』(詩集『旗』昭和・3)と題そのものが「大阿蘇」となっている詩もまた、『故郷の山』と同工異曲で、「煙吐き立ち高知れる/大阿蘇山は勇しきかな」と、「大阿蘇」の雄々しさを強調することによって阿蘇を賛美している。その点では与謝野鉄幹の短歌と同じ趣向で、鉄幹の影響がなきにしもあらずといった感がある。『天来臣民』(『文芸汎論』昭和16年)では、「わたしは/あのおそるべき/大阿蘇の山奥から出て来た/火山は私の少年に火を燃やし/祖先は純粋日本人の血を遺伝した」と述べ、阿蘇氏の直系の誇りが前面に打ち出され、阿蘇の火の山そのものと化した詩人の意識が描かれている。
③ 観光振興者
第三に、観光振興者の間にも使われるようになったということである。大正10年8月に、阿蘇を国立公園化しようとして、阿蘇谷・南郷谷の町村の役場と温泉主を中心とした期成会結成の協議が行われたが、その名称が「大阿蘇国立公園期成会」である。関東大震災により、国立公園の問題は一時下火となるものの、大阿蘇国立公園期成会の運動を一層発展させるため、新たに県レベルの大阿蘇国立公園協会が設立されることになった。そういう運動の中でさかんに「大阿蘇」という言葉が飛び交ったものと思われる。昭和2年8月に国立公園候補地基礎調査のために、田村剛博士が熊本県の嘱託により2、3週間阿蘇を中心に調査をしている。その時の「大阿蘇風景調査書」(頁、奥付なし)には「陥落カルデラノナス外輪山ヲ有スル大阿蘇ハソノ風景ノ量ニ於テ世界ニソノ大ヲ誇リ得ル本邦唯一ノ風景地デアル」と大阿蘇(高岳などの五岳、外輪山、波野高原などを含んだ大風景地)の天然公園としての価値を絶賛している。その一方で、阿蘇国立公園指定を目前にして道路整備・観光バスや旅館ホテルの経営などを視野にいれた「大阿蘇観光道株式会社」が熊本の財界人によって設立されることになった。「大阿蘇観光道株式会社」は「大阿蘇登山バス会社」を買収し、翌年1月1日から坊中駅―山上広場間のバス運行を引き継いだ。昭和年には、九州産業交通の子会社として、貸切バス専業の「大阿蘇観光バス株式会社」が設立され、会社名にも使われるようになった。現在、「大阿蘇」の名称はごく一般的に企業名として使われている。
これらの「大阿蘇」の名称の一般化には、国立公園化の運動とともに、『阿蘇市史』に掲載されている「阿蘇登山の説明」、いわゆる観光バスガイドブックの存在を見逃すことができない。この昭和7年頃の作成である観光バスのアナウンス原稿には「大阿蘇」という言葉が7箇所出てくる。このガイドの説明は阿蘇登山バスに乗る人は地元の人でも聞いていたという。従って、「大阿蘇」という言葉が否応なく、阿蘇登山バスに乗った人の耳の中に入ってきただろう。観光振興者が阿蘇に「大」を付けるのは、阿蘇が観光地としてすばらしいものであることを宣伝する意味があったようである。
このようにして、「大阿蘇」という言葉は、3つの事柄から広く使われるようになったといえるだろう。一つの言葉にも歴史があり、1つの言葉にも注目すべきことを実感させる例である。
3 与謝野鉄幹と松村辰喜
さて、与謝野鉄幹「『大阿蘇』考」で浮上してきた人物がいる。松村辰喜という人物である。松村辰喜は五十も過ぎてから阿蘇の国立公園化に邁進する。そのとき、“阿蘇の泥亀の大風呂敷”と陰口を叩かれ、誰も相手にしなかったという。この松村辰喜は与謝野鉄幹とかなり親密な関係にあったことが与謝野鉄幹の来熊の様子でわかる。まず、『五足の靴』の(二十) 画津湖(8月29日)の章には
楼上では松村氏の韓国王妃当夜の懐舊談が初まる。大院君が深夜異邦の志士に護せられ王妃を刺さむとするに、悠悠冷水を引いて身を拭ひ、かに髪を結び、衣裳を此か彼かと撰び改め、更に天地四方の神を拝し、祖宗を祀り、して漸くに乗る、此間費すこと三時間。志士等もどかしがりて促せば、大事を挙ぐるにか軽々なるべけむやと云ふ。之が為に予定の時間より五時間も遅れて、王城の正門に達した頃は既に白々と夜が明けた……。
先ほどの『九州日々新聞』(昭和7年8月)の記事には「阿蘇は又いい感慨だ」に続いて、
と「大阿蘇」論を一くさり、丁度その座へ阿蘇国立公園理事の松村さんが現れたので「なつかしや肥後の辰喜は」の舊歌その儘に、事件の朝鮮時代の懐舊談に青春が甦る。
というくだりがある。
この二つの記事から分かることは、与謝野鉄幹と松村辰喜とは会えば必ず閔妃暗殺事件への「懐旧談」にふけっていることである。これらのことから、与謝野鉄幹の度々の来熊は、後藤是山の熱心な招聘・仲介があったとしても、松村辰喜に再会することを期待する気持があったことはまちがいない。閔妃暗殺事件とは、明治28(1895)年10月8日、親露に傾いていく朝鮮の皇后・閔妃が大院君や開化派勢力、日本などの諸外国に警戒され、日本軍を中心に大院君を担ぎ出そうとした勢力によって、景福宮で殺害され、遺体も焼却された事件である。松村辰喜は与謝野鉄幹とともに義塾教師であり、閔妃暗殺に関与したとされるが、証拠不十分として釈放された。閔妃暗殺事件への関与云々はともかく、与謝野鉄幹と松村辰喜の関係の深さは「閔妃事件の朝鮮時代」に求められるだろう。「舊友の松村辰喜君等が『大阿蘇』なんて大の字をつける」(前掲)のはこの関係の深さと関連はあったのか。昭和初年、市街地の拡大に併せて、「大都市法」が制定された。その結果、大東京・大大阪・大京都など名称が使われ始め、熊本も大熊本というようになった。松村辰喜は熊本市会議員としてその名称を推進する立場であったので、「阿蘇」に大の字をつけたのは与謝野鉄幹の影響ではないと言い切ることもできる。しかし、与謝野鉄幹の側にしてみれば自分の影響・関連はあったとみているといっていい。ここにもまた、与謝野鉄幹の、松村辰喜に対する親密感・信頼感の表れを感じる。
(ながた みつのり/熊本近代文学研究会会員)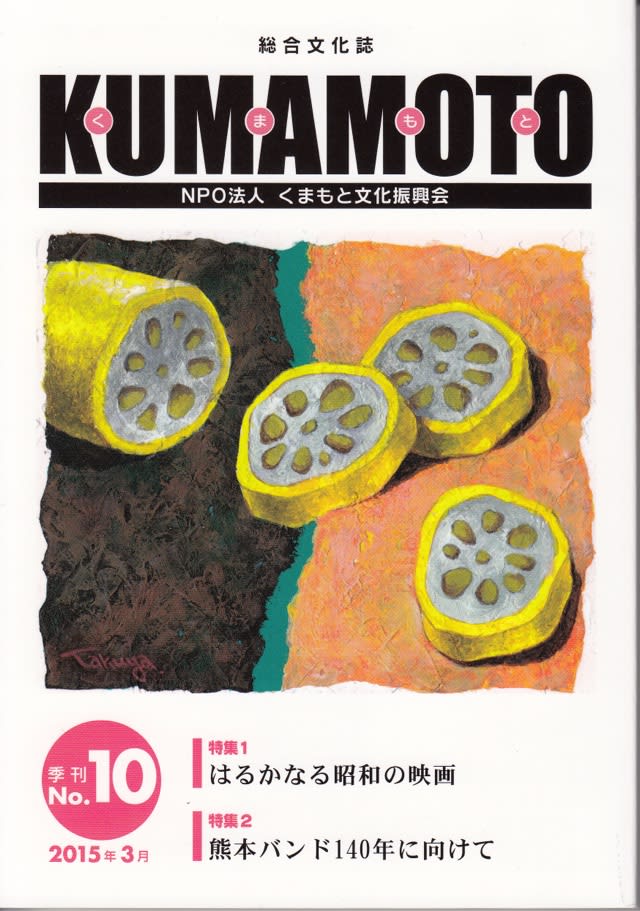
NPO法人 くまもと文化振興会
2014年12月15日発行
《はじめての夏目漱石「草枕」》
〈俳句の方法〉を駆使した俳句的小説
永田満徳
始めに 俳句=漱石文学の底流
夏目漱石は熊本時代、多くの俳句を作り、全体の四割、つまり千句あまりを作っている。漱石文学における、その俳句の影響については一過性のものとは考えられない。漱石文学の底流に流れていて、漱石文学に滋養を与えていると考える。小森陽一氏が「昔」(『永日小品』)を取り上げて、俳句が記憶装置として働いて、文章を書いたのではないかと述べている。阿蘇の旅の経験を元にした「二百十日」にしても、小天に訪れた経験を活かした「草枕」にしても、その折りに詠んだ俳句が背景にあることは周知の事実である。
一 子規派の潮流の一派としての俳句的小説
「草枕」は雑誌『新小説』(春陽堂・明治三十九年九月一日発行)に発表された。この時期の俳句界の状況は正岡子規亡き後、子規の後継者争いの様相を呈してくる。河東碧梧桐が『日本』俳句欄を、高浜虚子が『ホトトギス』を受け持つわけだが、四十年頃から碧梧桐が従来の五七五調の形にとらわれない新傾向の句を発表するようになり、虚子が碧梧桐派の行きすぎを尻目に、大正元年頃から〈守旧派〉の立場を明らかにして俳壇に復帰し活動を開始する。こうした子規派の分裂、抗争の中で、漱石は漱石なりの俳句観を示す必要があった。夏目漱石自身が「草枕」を「余が『草枕』」で「俳句的小説」と宣言することによって、後継者の高浜虚子や河東碧梧桐らとは違った子規派の潮流を歩み始めたことを意味する。
寺田寅彦が「夏目漱石先生の追憶」の中で漱石の言として述べているように、まさしく「俳句はレトリックの煎じ詰めたもの」である。漱石がどれだけ「俳句の方法」(レトリック・以下省略)に習熟していたかは、漱石俳句に対して、門下生と呼ばれる寺田寅彦・松根豊次郎・小宮豊隆が標語している『漱石俳句研究』が参考になる。そこには、「写生」「季語」「取り合せ」「省略」「デフォルメ」「連想」「擬人化」「同化」などの、あらゆる「俳句の方法」が使われている。
いみじくも、画工は小説の読み方として、「初から読んだつて、仕舞から読んだつて、いゝ加減な所をいゝ加減に読んだつて、いゝ訳ぢやありませんか」[九章]と那美に教える。これを俳句的観点からみると、この小説の読みが決して人を食っていないことがわかる。一章、一場面が俳句の一句に近い世界と考えたらどうだろうか。「草枕」でよく話題になる峠の茶屋の場面、風呂場の場面、髪結床の場面、鏡が池の場面、観海寺の場面、最後の場面など、その代表的な場面が鮮やかに脳裏に浮かぶのはそれら場面が俳句の一句のような世界を持っているからである。ということは、「草枕」の一章、一場面は、それぞれが独立した世界であるということである。もしそうであれば、「草枕」そのものがどこから、どこを読んでもいいことを証明した小説ということになる。この常識を覆す読み方ができる小説を書くことはかなり実験的なものであったに違いない。それを可能にしたのが「俳句の方法」を縦横に駆使したことにあったのである。
二 「草枕」における「俳句の方法」の主な使用例
写生=そもそも、「俳句の方法」の根本的なものは「写生」である。「写生」とは西洋画家中村不折に教わった正岡子規が俳句に応用したものである。「写生」が意味を持つのは、子規が、長編時評「明治二十九年の俳句界」で説いているように、「非情の草木」や「無心の山河」には「美を感ぜしむる」ものがあるからである。「草枕」の第一章の中で、すでに「わかる丈の余裕のある第三者の地位に立たねばならぬ。三者の地位に立てばこそ芝居は観て面白い。小説も見て面白い。芝居を見て面白い人も、小説を読んで面白い人も、自己の利害は棚へ上げて居る。見たり読んだりする間丈は詩人である。」と出てきて、画工が「第三者の地位」で物を見るという基本姿勢を示している。この画工の「余裕のある第三者の地位」を言い換えるならば「第三者」の立場に置くことである。「草枕」で決まって問題視される「非人情」は「第三者」の立場になることで、「不人情」とは似ても非なるものである。それは、「草枕」の中で、「非人情」と「不人情」とを使い分けられていることからもわかる。
季語=俳句では「季語」は「俳句の生命」(寺田寅彦)で、俳句は「季題を主題として詠ずる詩」(高浜虚子)と定義づけられるほど、必須の条件となっている。「草枕」では、現代の『歳時記』には〈春〉の項に載っていない季語もあるが、「季語」がこれでもか、これでもかと出てくる。画工自身が詠んだ俳句の「季語」を入れたとしても、これほど多くの「季語」を使っている小説は多くない。画工が「余が心は只春と共に動いて居る」〔六章〕と言い、〈春〉という季節をことさら強調している。特に俳句的小説「草枕」にとって、「季語」は作品の善し悪しを決めるうえで重要な要素である。「季語」の面からいえば、那古井の旅は四季の内ではどうしても〈春〉でなければならなかった。多くの〈春〉の季語を散りばめた「草枕」は〈春〉という季節の普遍的な情緒、美意識のエッセンスを堪能させてくれる。その点で、〈春〉という「季語」の選択は間違っていなかったというべきである。
取り合せ=俳句の実作経験のない方には理解し難いものの一つに「取り合せ」がある。俳句という韻文が散文と区別される方法である。特に、芭蕉が強く唱えている〈雅〉と〈俗〉との対比が「取り合せ」の基本中の基本である。「草枕」ではその代表が「今わが親方は限りなき春の景色を背景として、一種の滑稽を演じて居る。」〔五章〕とあるように、「春」の景色と髪結床の親方の「滑稽」との関係も一種の「取り合せ」である。章単位でも、観海寺の場面を〈雅〉とすれば、その髪結床の場面は〈俗〉ということになる。〈雅〉の世界だけでは古色蒼然でありすぎるが、そこに〈俗〉なる物を取り合せることで、なんと生き生きとしてくるではないか。
省略=俳句は五・七・五という、わずか十七文字(十七音)の言葉が一篇の詩として独立するには言いたいことを抑えて、核心部分だけを表現する。冗漫さを取り除くことによって余韻を生み、読み手の想像力を引き出し、表現したいものを鮮明に浮かび上がらせるのが「省略」の効果である。「草枕」では第七章の「白い姿は階段を飛び上がる。ホヽヽヽと鋭どく笑ふ女の声が、廊下に響いて、静かなる風呂場を次第に向へ遠退く」、あるいは第九章の「女はすらりと立ち上る。三歩にして尽くる部屋の入口を出るとき、顧みてにこりと笑つた」といった終末部分は、いずれも「飛び上が」り、「立ち上が」った後、「風呂場を次第に向へ遠退」き、「部屋の入口を出る」といった感じで、気懸かりな立ち去り方をする。あたかも舞台劇のような、鮮やかな幕切れである。画工ならずとも、「茫然」となるのは致し方がない。この各章の終わり方はまさしく「省略」の方法が用いられているといえる。「草枕」はこれ以外の章でも例として挙げることができるので、この効果を十二分に考慮して書かれていると思われる。
同化=俳句の方法で最も難しいのは「同化」である。徹底した「写生」を通して、どれだけ対象と〈一体化〉することができるかどうかで、句境の深化が見て取れる。「草枕」において、「同化」の問題を考える場合、漱石の「余が『草枕』」で述べている次の文章は重要である。「中心となるべき人物が少しも動かぬのだから、其処に事件の発展しようがない」というものの、「草枕」にストーリー展開をもたらしているのは、画工という「観察する者の方が動いてゐる」主体が那美という「少しも動かない」対象に対して、「非人情」、あるいは「第三者」の立場でどれほど「同化」できたかである。「余が胸中の画面は咄嗟の際に成就した」〔十三章〕という有名ながあるとはいえ、あくまでも「画面」の「成就」であって、「十三章に亘って描かれるすべてが画工の心理のフィルタ越しでしか、那美という対象を見ることができなかった。
終わりに
従って、「草枕」は那古井の温泉場で、「非人情」という「第三者」の立場を通して、「御那美さん」という他者を理解しようとして、理解することができなかった他者了解不能の物語であると言ってよい。そこにこそ、人情世界の普遍性があって、この「草枕」の最大の魅力となっている。たとえ「草枕」が他者了解不能の物語で終ったにしても、多様な「俳句の方法」を小説に応用するといった「天地開闢以来類のない」(小宮豊隆宛書簡)小説にあえて挑戦し、子規の提唱した「美なる処のみ」(「俳諧反故籠」)を詠む俳句説に従って、「美を生命とする俳句的小説」(「余が『草枕』」)を仕立て上げた漱石の手腕はお見事である。漱石自身が「草枕」を「俳句的小説」と述べているのは嘘偽りのないことであると言っても差し支えがない。
(ながた みつのり/熊本近代文学研究会会員)