#103 京都・宇治
~なぜ 宇治は“天下一の茶どころ”になった?~
放送日:2018年5月5日(土)
明恵 鎌倉時代に京都で栽培ご始まる
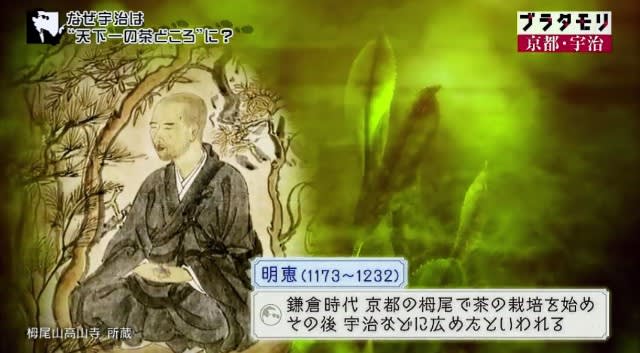
宇治川岸茶屋通圓
創業800年
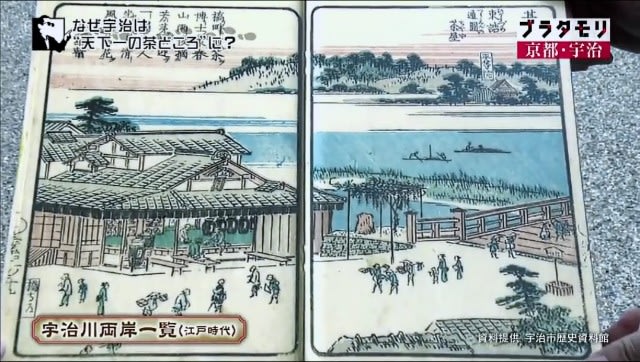

豊臣秀吉から宇治川から水をとる許可と釣瓶
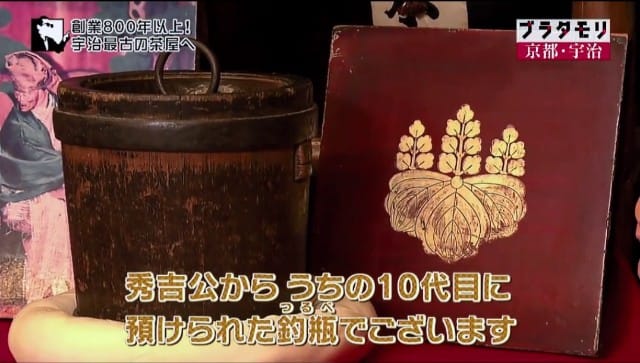
一休禅師が「通圓」より彫る

宇治川とこんな位置関係だったんだ・・・。

扇状地で水がわく

旨味成分テアニンができる

川ご見えない林田アナ(笑)

折居川などの河岸段丘

室町時代からの奥ノ山茶園
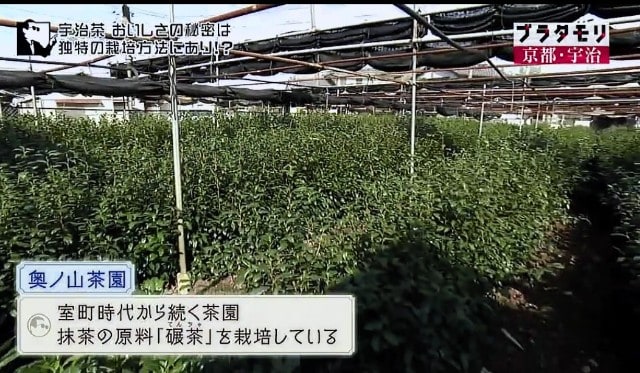
カテキンの生成をおさえるために覆下栽培
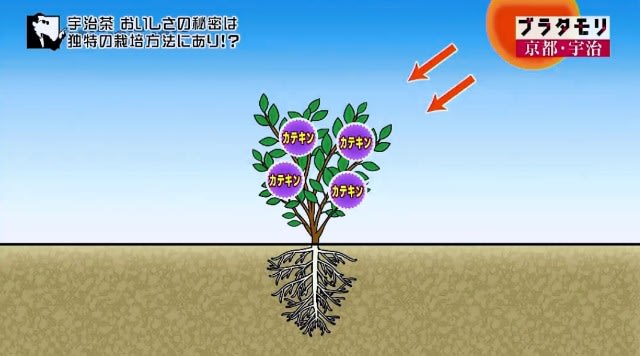

扇状地のお茶は旨味が多く、段丘上のお茶は香りが高い
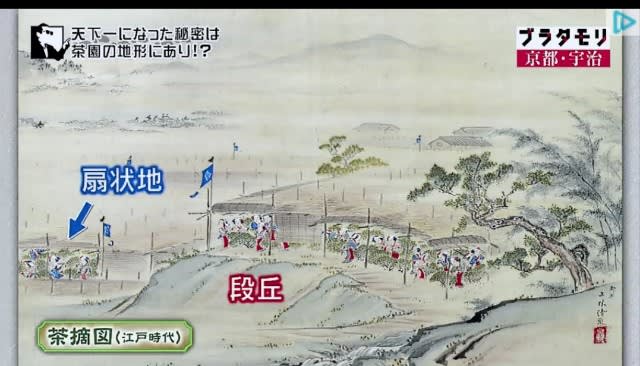
茶師がブレンド

★★★★★
NHK公式ホームページより
ブラタモリ、京都の宇治へ!
宇治といえば、なんといってもお茶。高級抹茶の産地として鎌倉時代からの伝統を守り続ける「お茶どころ」です。しかも国宝・平等院鳳凰堂や『源氏物語』の舞台としても知られる、風光明媚な観光地でもあります。京の都からほど近い宇治が、お茶で天下に名を知られるようになった理由を、タモリさんがブラブラ歩きながら解き明かします。
旅の始まりは、町の中心を流れる宇治川のほとり。800年の歴史を誇るお宝いっぱいの茶屋で、まずは抹茶を一服!そのお味は?
続いては、宇治のシンボル・平等院鳳凰堂へ。10円硬貨でもおなじみの国宝の美しい建物ではなく、その前に広がる池に、宇治がお茶の産地になった秘密が隠されていた・・・ってどういうことでしょう?
町なかを歩くタモリさんが発見した「見えない川」とお茶の関係とは?
室町時代の将軍がお墨付きを与えた茶畑に潜入!宇治のお茶の味をよくしたのは、タモリさんが大好きな「河岸段丘」だった?
お茶を扱う商人・茶師のあいだで脈々と受けつがれた「秘伝」に、タモリさんも脱帽?
オープニング
01:“なぜ宇治は「天下一の茶どころ」になった!?”
全国に数ある茶の産地のなかで、なぜ宇治が有名になったのか探ります。
02:創業800年の茶屋
宇治茶の栽培が始まったのは鎌倉時代。そのころから続く茶屋です。
平等院
01:平等院の参道
通りには茶屋がずらりと並んでいます。
02:平等院の境内
ここは元々、藤原道長の別荘があった場所。平安時代、宇治は貴族のリゾートでした。
03:鳳凰堂
10円玉のデザインでも有名です。
04:水が湧いていた場所
この辺りは扇状地。扇の端にあたるこの場所で水が湧いていました。
扇状地と茶
01:見えない川を感じる
道路の左右は崖。今は暗渠(あんきょ)になっている折居川が削ってできました。
02:扇状地の始まりを感じる交差点
川が山から平野に流れ出るポイントです。
03:扇状地と茶の栽培を知る
扇状地のやわらかく、水はけの良い地質が茶の栽培に適しています。
繁栄の痕跡
01:長屋門(ながやもん)だった建物
実はもともとはひとつの建物。江戸時代、茶を扱う商人「茶師」が住む、格式の高い「長屋門」という建物でした。
“天下一”の茶
01:室町時代からの茶園
<見学には事前の予約が必要です>
02:宇治独特の茶の栽培方法を知る
日光を調節する「覆下(おおいした)栽培」は、江戸時代、宇治だけに認められていました。
<見学には事前の予約が必要です>
03:茶園の地形を知る
扇状地の南側は段丘。異なる地形で性質の違う茶葉が生まれます。
04:茶葉の加工工場
高級抹茶は、機械を使っても1つの臼で1時間に40gしかひくことができません。
<一般には公開していません>
05:「合組(ごうぐみ)」を知る
宇治では、江戸時代から、異なる性質の茶葉を客の好みにあわせてブレンドする「合組」という作業が行われていました。
<一般には公開していません>
~なぜ 宇治は“天下一の茶どころ”になった?~
放送日:2018年5月5日(土)
明恵 鎌倉時代に京都で栽培ご始まる
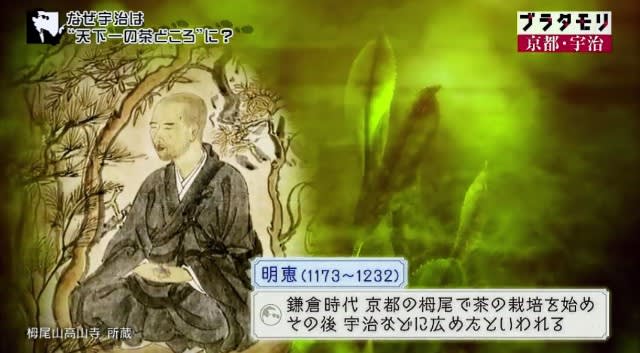
宇治川岸茶屋通圓
創業800年
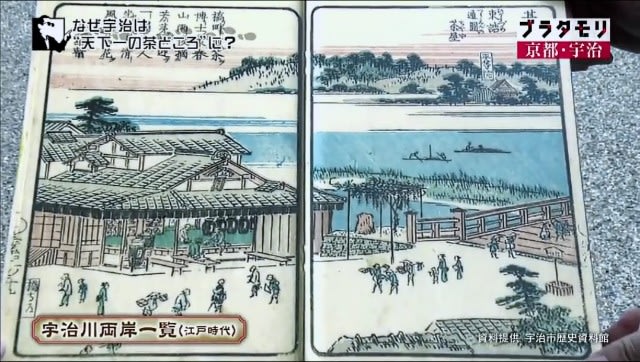

豊臣秀吉から宇治川から水をとる許可と釣瓶
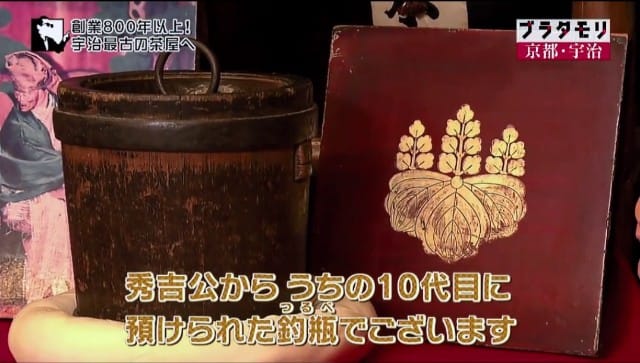
一休禅師が「通圓」より彫る

宇治川とこんな位置関係だったんだ・・・。

扇状地で水がわく

旨味成分テアニンができる

川ご見えない林田アナ(笑)

折居川などの河岸段丘

室町時代からの奥ノ山茶園
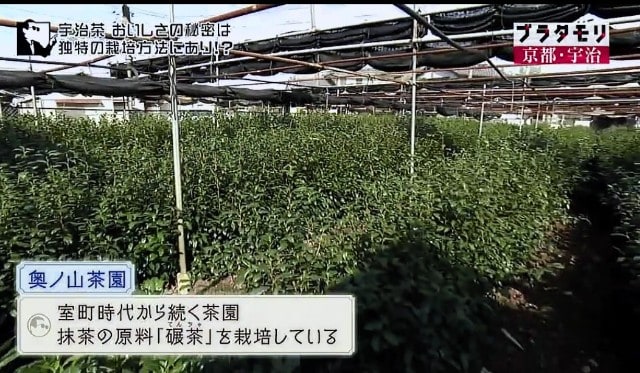
カテキンの生成をおさえるために覆下栽培
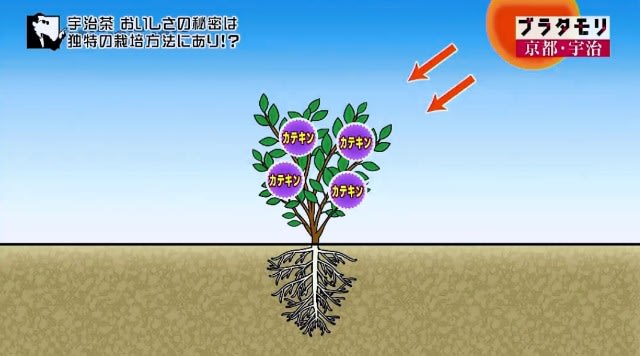

扇状地のお茶は旨味が多く、段丘上のお茶は香りが高い
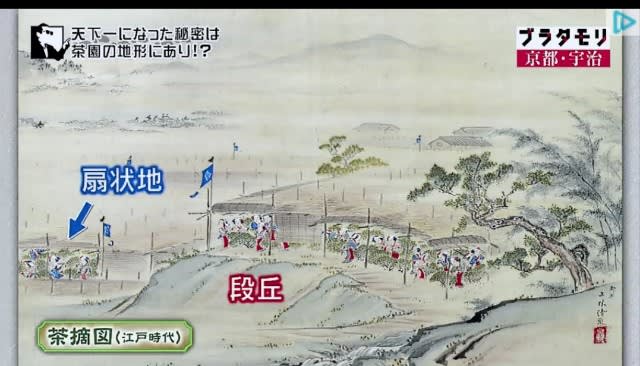
茶師がブレンド

★★★★★
NHK公式ホームページより
ブラタモリ、京都の宇治へ!
宇治といえば、なんといってもお茶。高級抹茶の産地として鎌倉時代からの伝統を守り続ける「お茶どころ」です。しかも国宝・平等院鳳凰堂や『源氏物語』の舞台としても知られる、風光明媚な観光地でもあります。京の都からほど近い宇治が、お茶で天下に名を知られるようになった理由を、タモリさんがブラブラ歩きながら解き明かします。
旅の始まりは、町の中心を流れる宇治川のほとり。800年の歴史を誇るお宝いっぱいの茶屋で、まずは抹茶を一服!そのお味は?
続いては、宇治のシンボル・平等院鳳凰堂へ。10円硬貨でもおなじみの国宝の美しい建物ではなく、その前に広がる池に、宇治がお茶の産地になった秘密が隠されていた・・・ってどういうことでしょう?
町なかを歩くタモリさんが発見した「見えない川」とお茶の関係とは?
室町時代の将軍がお墨付きを与えた茶畑に潜入!宇治のお茶の味をよくしたのは、タモリさんが大好きな「河岸段丘」だった?
お茶を扱う商人・茶師のあいだで脈々と受けつがれた「秘伝」に、タモリさんも脱帽?
オープニング
01:“なぜ宇治は「天下一の茶どころ」になった!?”
全国に数ある茶の産地のなかで、なぜ宇治が有名になったのか探ります。
02:創業800年の茶屋
宇治茶の栽培が始まったのは鎌倉時代。そのころから続く茶屋です。
平等院
01:平等院の参道
通りには茶屋がずらりと並んでいます。
02:平等院の境内
ここは元々、藤原道長の別荘があった場所。平安時代、宇治は貴族のリゾートでした。
03:鳳凰堂
10円玉のデザインでも有名です。
04:水が湧いていた場所
この辺りは扇状地。扇の端にあたるこの場所で水が湧いていました。
扇状地と茶
01:見えない川を感じる
道路の左右は崖。今は暗渠(あんきょ)になっている折居川が削ってできました。
02:扇状地の始まりを感じる交差点
川が山から平野に流れ出るポイントです。
03:扇状地と茶の栽培を知る
扇状地のやわらかく、水はけの良い地質が茶の栽培に適しています。
繁栄の痕跡
01:長屋門(ながやもん)だった建物
実はもともとはひとつの建物。江戸時代、茶を扱う商人「茶師」が住む、格式の高い「長屋門」という建物でした。
“天下一”の茶
01:室町時代からの茶園
<見学には事前の予約が必要です>
02:宇治独特の茶の栽培方法を知る
日光を調節する「覆下(おおいした)栽培」は、江戸時代、宇治だけに認められていました。
<見学には事前の予約が必要です>
03:茶園の地形を知る
扇状地の南側は段丘。異なる地形で性質の違う茶葉が生まれます。
04:茶葉の加工工場
高級抹茶は、機械を使っても1つの臼で1時間に40gしかひくことができません。
<一般には公開していません>
05:「合組(ごうぐみ)」を知る
宇治では、江戸時代から、異なる性質の茶葉を客の好みにあわせてブレンドする「合組」という作業が行われていました。
<一般には公開していません>
















