強いインパクトを受けた直後に自分の中で起こっていたことを整理して言語化するのは、とてもむずかしい。アタマだけで理解されることを拒み、感情や身体をとおして私たちの奥深いところを揺さぶる経験も、少し時間をおいて振り返ってみると、さまざまなことに気づかされることがある。それでも、ことばにすると何か肝心なことがするりと逃げていく。いくら追いかけて、ことばの網ですくい取ろうとしても獲物は逃げてしまい、網に残るのは一緒にすくい上げた藻だったりする。そんなものを見せられて、獲物はこんなに大きかったと興奮しながら語られても、その場に居合わせなかった者は戸惑うばかりだ。そんな直接経験と言語表現との乖離を承知していながらも、この前の日曜日(10月21日)に聞いた古山さんの講演については、ほんの断片でも語らずにはいられない。(獲物のしっぽでも捕まえることができればいいのだが・・・)
その日、私たちは整然と並んでいた机を動かして、いびつなひし形のように並べて準備していた。会場に入ってこられた古山さんは、(おそらく、だれもが暗黙のうちに「講師席」と思い込んでいたであろう)壁と白板を背にした席ではなく、広い窓を背にした角の席に座られた。「ホリスティックな知は定義できません。皆さん、あの青空をご覧なさい。」開口一番、古山さんはそう言って、窓の外を指さされた。それで、私たちは、背景に(壁と白板ではなく)外の世界を眺めながら話を聞くことになった。ことばの海に溺れそうになったら(実際はそうならなかった)、いつでも爽やかに晴れわたった秋の空に視線を移すことができる。(仕事など、何かに忙殺されたり、行き詰まったりしたときに、目を向ける対象を変えて気分転換をはかるのもいいが、対象に向き合いながら、その背後に広がる世界に視線を向けておくのもいいものだ)
こうして古山さんは、クリシュナムルティとシュタイナーの学校のつくり方の違いを、ご自身の塾での子どもたちの様子なども引き合いに出しながら、自分の感覚に引きよせて話してくださった。丁寧にことばを選び、ゆっくりとした物静かな語り口だった。ふと声が途絶えて視線を戻すと、身振り手振りで身体の動きを表現しておられる。後の質問にも、その人の気持ちを受けとめて丁寧に応えておられたのが印象的だった。(そういえば、ふだんの私は話のナカミばかりに注目して、相手と自分の全体に向き合うことがおろそかになっているなあ)
人間の全体性を深く見つめて独自の教育を創りあげたシュタイナーとクリシュナムルティは、共に時代に対する危機意識をいだいて自由で愛に満ちた人を育てることが真の社会変革をもたらすとして、それぞれの学校をつくったが、そのつくり方は大きく異なっていた。シュタイナー学校では、カリキュラムから経営までの方式をシュタイナー自身が創って教師教育を徹底したのに対して、クリシュナムルティ・スクールは、方式に依存せず、学校ごとに大きな違いがある。クリシュナムルティは、教育や学校のあるべき姿を語ったが、具体的な実践は現場の教師たちに任せたのである。その学校づくりの理念は、以下の文章に集約されている。
「校内の自治は後々の人生における自治のための準備である。もし児童が学校にいる間に、日々の問題に関する議論において思いやり深くし、私情を交えず、英知を働かすことを学べば、後年、人生のよりおおきなより複雑な試練に効果的かつ冷静に対処できる」(10月21日のレジュメによる)
これからの時代を生き抜く子どもを育てる場としての学校と学校図書館の姿を考えている人なら、だれもが納得できるだろう。この理念を教師集団が共有し、実践をとおして学ぶ姿勢をもちつづけることができれば、ふつうの学校でも実りある教育ができるのではないか。そんな期待さえ抱くことができる。問題は具体化への道筋だが、古山さんは、メールでの私の問いに応えて、こうおっしゃっている。
「シュタイナーの言っていることは比較的理解しやすいのですが、それを自分の血や肉にして、実践の場で生かすには、そうとうな苦労がいります。いっぽう、クリシュナムルティは、いったい何を言いたいのか理解するのに一苦労なのですが、もし理解できれば、それはそのまま実践的な知でして、即座に効果があります」
クリシュナムルティの理念を現実化するカギは「見る」という行為にあるのではないか。かねてから私はそう思っている。だから、前回のセミナーで菊地栄治さんが「生徒を見る」という表現を多く使われていたことについても、10月3日のブログで次のようにコメントしていた。
「次回の講演のテーマにもなっているクリシュナムルティも、既知のものを注意深く「見る」こと、あるがままのものを「見る」ことが対象の全体を把握するために大切だと言っています」
レジュメには「観察者なしに観察すること」とあった。見る者と見られるものを分離しない。見る者の価値判断を停止して見る。それは、傍観することでも分析することでもない。対象(他者)と向き合う関係の中で自己知に至るプロセスといえばいいだろうか。その場に自らを投入し、対象(他者)との関係を変えることによって世界(社会)を変えていく契機になりうるだろう。
古山さんには『変えよう!日本の学校システム 教育に競争はいらない』(平凡社)という著書がある。「古山さんの本を事前に三分の二ぐらいまで読んでいたのですが、認識があれば、ホリスティックな観点から書かれていることが伝わるように描かれているのだと、話を聞いていて思いました」。講演の後に寄せられたコメントの中に、この一文を見つけて古山さんは「これを読み取っていただけるとは・・・」と感激しておられた。
 |
変えよう! 日本の学校システム 教育に競争はいらない |
| クリエーター情報なし | |
| 平凡社 |
(じつは、この本が出版されて間もなく、ささやかなコメントをブログに書かせていただいている。いま読み返してみるとお恥ずかしいかぎりだが・・古山明男著『変えよう!日本の学校システム 教育に競争はいらない』(平凡社))
ちなみに、古山さんは「ベーシックインカム」に関する論客でもあるが、そこにもホリスティックな観点から社会のありようを具体的な形で考えておられることを読み取ることができる。
古山明男さん講演録(2009年7月12日 於:青山学院大学)
「ベーシック・インカムのある社会―労働と教育の根本的転換―」第1部










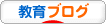





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます