以下の文章は、学校図書館問題研究会の機関紙「学図研ニュース」編集部の依頼に応じて寄稿した文章に若干の加筆と修正をほどこしたものである。依頼されたテーマは「学校図書館で育む『力』」。(9月1日号に掲載されるとのことだった。)しかし、学校現場を離れて久しく、図書館や情報学の専門家でもなく、司書・司書教諭としての実務経験もない部外者の私がどれほどの現実性をもって学校図書館のことを語れるのか、はなはだ不安ではあったが、せっかくの機会なので、学校と社会をつなぐ学校図書館の存在意義について私なりの想いを綴ってみた。
学校図書館で育まれる力は、図書館を使いこなす力である。トートロジーともいえるこの事実は、あまりにも自明であるために、いまさら語られるべきことではないのかもしれません。もちろん、学校図書館は、読書をしたり、調べものをしたり、レポートや論文を書いたり、そのほか、さまざまな力を育む場として活用できます。でも、そういった力は必ずしも図書館を使わなければ育てることができないというわけではありません。それにたいして、図書館を使いこなす力は、実際に図書館を使うことによって身につけるほかありません。学校に学校図書館があって、ふだんから、さまざまな目的のために役立てる経験を重ねているうちに、いつのまにか図書館を使いこなす力がつき、それにともなって図書館にたいする理解が深まり、図書館を見る目も養われてきます。的確な評価眼をもった利用者が世の中に増えれば、図書館は鍛えられて進化するでしょうし、その時々の社会に生きる市民の生活を支え、豊かにする活動をとおして、民主主義社会における情報基盤としての機能も高まるでしょう。そのことの社会的な意義を、図書館にかかわる人たちばかりでなく教師や一般市民が、もっと認識すべきだと思います。
「図書館を使いこなす力」といっても、単に図書の分類に関する知識や資料の探し方といったテクニカルな図書館利用術のことを言っているのではありません。子どもたちは、日常の生活で起きるさまざまな問題に向き合うときや、自分の殻を破って新しい世界に飛び出そうとするときなど、さまざまな場面で、周りの大人や友人たちなど自分以外の人たちとのかかわりの中で自分の世界を組みかえていきます。これまで自分が生きてきた世界とは異なる価値や基準によって生きている人たちの経験に触れることができれば、さらなる成長のチャンスになるでしょう。そうした子どもたちの学びと成長のために、家庭や学校における限られた人間関係では触れることのできない世界や他者と出会う場として図書館があるのだと思います。子どもたちは、図書館を使って自らの問題に取り組む過程で自分のもっている読書力や情報活用力やコミュニケーション力をせいいっぱい発揮し、洗練させ、高めていきます。つまり、図書館を使いこなす力は、異質なものを受け入れて成長する営みの中で総合的に育まれるものだと思うのです。この理路(目的と手段)を切り離したり、逆転させてしまうと学校図書館の存在意義が極端に薄れてしまうのではないでしょうか。
残念ながら、いまの学校教育に、そのような学校図書館の働きを十全に開花させる素地ができているとは言えません。日本の多くの学校では、知識と技能を効率的に身につけて上級学校に送り出すことに追われて、子どもの社会的成熟を助け、民主主義社会の担い手を育てることが手薄になっているか、あるいは、そうした視点がすっぽりと抜け落ちているのではないかとさえ思います。大学や高校は入試のための偏差値によって序列化され、小中学校の教育もその影響を受けています。多くの学校は、建前はともかく実態として、そんな一元的な学力階層の上位を占めることを目指しているように見えます。そういうシステムの中に学校図書館も組み入れられています。しかし、学ぶことの意味が個人的利益の追求という側面だけをとらえて過剰に強調されるようになると、子どもたちは、ますますテスト結果への依存を強め、学校は卒業と進学、そして競争に勝ち抜いて成功するための単なる通過点になっていくでしょう。
そんな状況のなかで、教師や子どもたちは、学力向上に効果の上がる学習手段を求めています。だから、大学入試がマークシートの試験だけでなく、小論文などの記述式の問題が出されるようになり、AO入試が採用され、PISA型学力が導入されるようになれば、そういった入試に対応できることを学校図書館の付加価値としてアピールすれば喜ばれるでしょう。読書の意義についても「よく本を読む子どもは学校の成績も良い」とか「将来の成功のために役に立つ」「集中力がついて、落ち着いて勉強できるようになる」などと語られます。こうして学校図書館が使われる機会が増えれば、それはそれで喜ばしいことかもしれませんが、大学入試の動向によって教育内容が左右されるという構造は変わることなく、学びや読書の本来の意義が見失われたまま、これまでのように子どもたちは次々とふるいにかけられていきます。
私たちは、学校図書館が可能性としてもっている、さまざまな学びの回路を閉ざしてはいないだろうか、と問うてみる必要があるのではないでしょうか。たとえば、何らかの理由で学校が提供する学びの回路に乗っていけない子どものことを考えてみましょう。障害があるとか、文化的背景が異なるというだけでなく、子どもは、さまざまな要因によって学校の勉強につまづくことがあります。子どもは感受性も知識の獲得のしかたも一人ひとりちがっているので、ひとつのやり方についていけない子どもがでるのは当然のことです。そんなとき、子どもの個人差をできるだけ尊重する学びの場を提供してあげることも、学校図書館の大切な役割ではないでしょうか。一人ひとりの子どもが抱える問題や欲求に柔軟に対応しながら、その子たちが自分なりのやり方で学べる機会を提供できることは、学校図書館の大切な特性です。そんな環境では、さまざまな条件や要因が絡み合って、教師も子どももまったく意図していなかった思いがけない学びが起きる可能性が高まります。そんな一人ひとりの内面から自動的に発動される「意図されない学び」が、場合によっては人生を左右するきっかけになったりすることもあります。
そういったことから、私は、図書館を使いこなす力を育むにあたって何よりも「自発性」を大切にしたいと考えています。自発性は、あらゆる学びの原動力ですが、昨今の学校教育では疎んじられているのではないでしょうか。たしかに学習指導要領でも教師の研修会でも「主体的な学び」や「自主的な学び」が盛んに謳われています。しかし、主体性や自主性ということばは、単なる「積極性」といった意味で使われている場合も多く、かならずしも自発性と同義ではありません。「自発」とは「自己の内部の原因によって自然発生的に行われること」で、他者からの強制や同調によるものでないだけでなく、「べき」「べからず」といった自らの意志によるものでもありません。ですから、教師の指示や意図を的確に察知して自ら積極的に動き出す、いわゆる「優等生」や「いい子」の行動は自発的とは言いません。「レポートはこういう手順で書きましょう」と教えられて、さっさと課題を決めて、要領よく調べて発表するまでのプロセスをこなしてしまう子どもも、ただ先生の言いつけを守って、それを実行しているだけであれば自発的に動いているわけではありません。図書館を使う授業をたくさん経験しても、自らの必要や欲求に応じて学ぶことなく、ただ積極的に受け身の姿勢をとりつづけているだけでは、その場でどれだけ楽しくやっていても、生涯にわたって生活のさまざまな局面で図書館を使いつづけるようにはならないでしょう。かといって、子どもに「自発的に学べ」というのは矛盾していて、そう言われて自発性が育つものではありません。自発的な学びを促すには、むしろ「指導」という網をかぶせないほうがいいのかもしれません。だからといって放っておくのではなく、子どもの自発性の芽をつみとらないで、しっかり育てることを心がけるべきでしょう。図書館では、多様な情報源が身近にある環境に身を置くことで触発される一人ひとりの子どもの心の動きを大切にしたいものです。図書館の利用法を限定するようなルールや注意はできるだけ少なくして、さまざまな子どもたちの自由な発想を触発し、お互いに交感できる仕掛けが必要だと思います。だから、学校図書館の実務に携わっておられる皆さんは、図書館を子どもの興味や好奇心を引き出す場にしようと日頃から取り組んでおられるのでしょう。「分からない」「困った」「どうしよう」と思ったとき、「そうだ!図書館に行ってみよう」と思う子どもが増えればいい。そう思って、子どもたちのさまざまな問題を察知して親身になって向き合っておられるのでしょう。そんな志をもった皆さんの実践が先生方を動かし、一元的な学力観で動いている学校のシステムを見なおして多様な学びの場を生み出すきっかけになればいいのですが、私の知るかぎり、そういう学校は、けっして多いとは言えません。
学校図書館の実践が学校教育全体に浸透するのを難しくしていると思われる一つの事例を取り上げて考えたいと思います。
昨年(2011年)の10月に文部科学省が小中高校生向けに放射線に関する副読本を作成したとき、ある新聞に「文部科学省が作成したものなので、安心して授業で使える」という校長先生のことばが出ていました。まとまった談話の一部を切り取ったものなので校長先生の真意を反映しているかどうかは分かりませんが、自ら内容を検討たうえで、それを妥当とする根拠を示すことなく、ただ「文部科学省が作成したものなので安心」というのは、子どもの現実と向き合う教育者の論理ではありません。このような校長先生のもとで「子どもたちの思考力と判断力を育てる」という学習指導要領の理念は実現できるのだろうか?というのが、この記事を読んだときに私が抱いた率直な疑問です。さらに、この校長先生が放射線副読本のことを「中立的」と評価しておられることにも違和感を覚えました。教育という場で「中立的」であるということは、偏った考えを押し付けないということです。この副読本は「放射線のメカニズム」を解説してくれていますが、子どもたちが3.11以後に自分たちの身の回りで現実に起こっていることを考えるのに直接的に役立つ知識は示してくれていません。ものごとをひとつの観点からしかとらえていなければ「中立」とは言えません。客観的な「事実」とされていることも、その選択と配列(=編集)のしかたしだいで、特定の立場に誘導することだって可能だからです。私たちがやるべきことは、まず、子どもたちに問題を直視するために必要な基本的事実を教えて、解釈や見解が分かれる場合には、さまざまな立場の考え方を「公平に」検討したうえで、自分なりの考えや意見をもたせることだと思います。学習指導要領は「多様な情報を活用し、異なる視点から考え協同的に学ぶ」(学習指導要領解説)ことを求めています。放射線のように専門家の間でも議論の分かれる複雑な問題については、結論を教えることよりも、子どもの発達段階に応じて、問題の構造をできるだけ広く深く把握できるように導いてあげることが大切でしょう。学校は、子どもたちが、自分の存在にかかわる事態に真っ向から取り組む真の学び(authentic learning)の実現を遠ざけるべきではありません。
もちろん、私は、この校長先生ひとりを責めているのではありません。教職に身を置いていた自分自身を振り返ってみて、このような考え方はよくありがちではないか、つまり日本の学校システムに特徴的な思考パタンではないかと思うのです。こうした上意下達型の思考と行動が教職員の間に定着し、日々の教育活動の中で子どもたちのあいだに浸透していけば、やがて学校は、柔軟性と広がりを欠く硬直した組織となり、学校内でのいじめや突発的な災害といった危機的状況に直面したときに、教師も子どもたちも、生命を守ることを最優先にして状況に応じた的確な判断と行動ができなくなるのではないかと危惧しているのです。
放射線の人体への影響といった、情報の評価に専門的知識が求められる問題に関しては、まず教師自身が学ばなくてはならなりません。そして、子どもの問題意識をどのように掘り起し、どこに焦点をあてて、どのように教えるかを検討し、授業研究を積み重ねていくことが必要です。そんな教師の学びの場に学校図書館職員も参加して多様な資料や情報にもとづく調査結果を提供し、一緒に学び合うことができれば、教師にとっても有難いことです。といっても、問題の多い争点について、唐突にそんな提案をされても教師は戸惑うばかりなので、日常的にさまざまなレベルでお互いのコミュニケーションや学び合いの場を確保しながら、学校図書館の理念が受け入れられる土壌をつくっておくことが大切なのでしょう。私は、かならずしも学校図書館の理念や方法論を学校全体で共有・実践しなくてはならないと言うつもりはありません。学校図書館は、独自の立場から学校教育の弱点を補うことで全体として調和のとれた教育を可能にする、いわば従来の学校教育に対する批評的空間として存在することにも意味があると思うからです。
「図書館を使う力」をめぐっていくつかの観点から考えてきましたが、公教育の場としての学校の目的を実現するためには、さまざまな局面で学校図書館を使いこなしていく力が、子どもばかりでなく教師にも、そして学校図書館職員自身にも求められるといえるでしょう。そのために大切なことは、学校の中に多様性を包み込んで協働できる土壌をつくりだすことではないでしょうか。










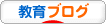

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます