今朝は5時前に目を覚まして、ラジオをつけたらNHKの「ラジオ深夜便」が終わろうとしていた。誕生日の花と花ことばのコーナーである。
 今日の誕生日の花は、パンジー
今日の誕生日の花は、パンジー
語源はパンセ、「考える」こと
花ことばは「物思い」「私のことを忘れないで」
(つぼみが垂れる形が、物思う姿を連想させるのか?)
形が蝶に似ているところから「遊蝶花」と呼ばれることもある
そこで、今日の一句
「遊蝶花 春は素朴に 始まれり」水原秋櫻子
とても祝福された気分で、そのまま、うとうとと一時間ほど至福の二度寝をしてしまった。
昨年、70歳で迎えた3月11日。それからは、これまでの生き方を深いところで問い直す一年だった。17年前に阪神淡路大震災に見舞われたときは、破壊を転換の機ととらえることで元気が出た。しかし、この一年は、自分が直接的な被害を受けたわけでもなく、地理的にも少し距離をおいたところで起こったことなのに、なぜか重苦しい。年齢のせいもあるだろう。自分が当事者でないからよけいに、そんな気分になるのかもしれない。自らが被害を受けた当事者だったり、東北の地まで足を運んで支援活動に参加したりしていたら、そんなことを感じる余裕もなく、がむしゃらに復興に向けて汗をかいていたにちがいない。
この一年、私には、3.11で浮き彫りになった社会や文明の危機という現実と、そろそろ自分の死を準備する年齢にさしかかっているという現実をどのように折り合いをつけて生きていくのかという課題がのしかかっていた。つい先だっても、毎年、楽しみにしている京都シティフィル合唱団の第37回定期演奏会で、久しぶりに聞いた大曲、バッハの「ロ短調ミサ曲」を見事に演奏しておられて、深い感動につつまれたのだが、演奏会を前にして私と同年代の団員である元英語の先生がなくなられ、ご葬儀ではステージ衣装を着せてお送りしたという話を聞いたばかりだ。他人事とは思えない。
そんな心境にあった私は、昨年、日隅一雄さんの存在を知って、とても勇気づけられた。フリーのジャーナリストであり弁護士でもある日隅さんは、一年近く前に末期の胆のう癌宣告を受けてからも「闘病」に専念することなく、むしろ癌を受け入れながら、これまでどおりNews for the People in Japan(NPJ)編集長として、「マスゴミ」から排除されがちな情報の流通を人々の立場に立って促進する活動を幅広くつづけておられる。とりわけ、この1月に刊行された『検証 福島原発事故・記者会見 東電・政府は何を隠したのか』(木野龍逸さんとの共著、岩波書店、2012/1)は、福島原発事故以後の東電と政府の記者会見で「語られたこと」と「語られなかったこと」、それをメディアは「どう伝えたか」を整理した貴重な記録である。そこから見えてくるのは、主権者である国民不在の姿勢だ。その意味でも近く発行される予定の日隅さんの『「主権者」は誰か』(岩波ブックレット)にも期待している。
 |
検証 福島原発事故・記者会見――東電・政府は何を隠したのか |
| クリエーター情報なし | |
| 岩波書店 |
日隅さんの個人ブログは「情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄」
世代を超えて受け継がれていく人間の営みを、成長と発展ばかりでなく老いと病、そして死という衰退をも視野に入れて見つめるという点で、平川克美さんの最近の著作にも惜しみない喝采を送りたい。
平川さんは、ジャンルの異なる二冊の本を異なる出版社から同日に出版された。
『小商いのすすめ 「経済成長」から「縮小均衡」の時代へ』(ミシマ社、2012/1/20)
 |
小商いのすすめ 「経済成長」から「縮小均衡」の時代へ |
| クリエーター情報なし | |
| ミシマ社 |
『俺に似たひと』(医学書院、2012/1/20)
 |
俺に似たひと |
| クリエーター情報なし | |
| 医学書院 |
多面的で矛盾に満ちた、複雑な人間の営みを語ることは一筋縄ではいかない。それを平川さんは評論と小説という二筋の縄で編もうとされたのである。それぞれの著作にも幾筋もの語りが絡み合っていて、『俺に似たひと』は、父親の介護と福島原発事故というテーマがtwitterの記録によって繋がれている。
ラジオデイズを主宰しておられる平川克美さんが、これまでにも経済やビジネスの本を出しておられることは知っていたが、自分には無縁だと思って遠ざけていた。今回はじめて、この二冊を合わせて読んで、平川さんにとっては介護と商いという「身の回りの人間的なちいさな問題を、自らの責任において引き受けること」を通して現状を乗り越えていく姿勢が、私自身の展望としてリアリティをもって見えてくるのだった。4月に出版される予定という『移行期的乱世の思考 「誰も経験したことがない時代」をどう生きるか』(PHP出版)も楽しみだ。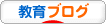



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます