
六十年代後半から七十年代。黎明とたそがれ。政治的にも状況的にも、(すべてが)騒擾のころ。あのころのオキナワの青春は夜が楽しかった。夜は闇の時空を提供し、なにか解放されたような気分になり、文学書とアルコールと対話が身近にあった。仲間と議論して帰るとき少し冷たくなった夜風がアルコールで火照った頬にあたると、とても気持ちがよかった。レインコートを羽織って、夜の道を、革靴やときには下駄を履いて、首里の町を歩いた。首里キャンパスが時折、霧がかかる時があって、街灯がぼんやりと灯っていた。そのとき、ああ、生きているな、と最高に昂揚した気分になったものだ。
学生運動くずれで文学に染まったころ、文学仲間と毎日のごとく、飲んでいた。琉大文学の原稿を頼みにいったのがきっかけで清田政信という詩人と知り合いになり、その後、ときどき、会って飲んだりしていた。もちろんほかの仲間と一緒だった。東京から帰省した役者くずれのNさんがやっていた浮島通りの「石」とか安里の「芭蕉」とか栄町の「うりずん」「東大」とか桜坂の「とんぼ」………といった飲み屋で飲んだ。ある夜、清田さんと飲んでいて、なんの拍子か、東風平恵典さんの家に行こうということになって、安謝に近い浦添のお宅を訪ねると、そこに数人の男どもがいた。
そこではじめて宮城正勝さんと会った。たぶん比嘉加津夫さんや上原生男さんもいたと思う。宮城さんは清田政信や琉大文学に、思想が入りすぎ難解でよくないとかの批判的言動していた(と思う)。私はその宮城さんに「じゃあ、だれの詩がいいのか」と訊ねると、当時流行った、入沢康夫の「わが出雲・わが鎮魂」をあげていた。ああ、このひとは現代詩を読んでいるな、と思った。
それから時々どこかで偶然会ったりしたが、関係が密になりはじめたのは、やはり東風平さんを介してである。東風平さんは、七十年代のある時期から、出自の宮古島に戻って学習塾などしながら、個人誌らら』という雑誌を出していた。あるとき、東風平さんから電話があって、『らら』への詩稿を頼まれるようになったり、一緒に同人誌をやらないかとか、ときどき連絡がきた。たまに那覇に行くから会わないかとの電話があり、そのとき宮城正勝さんも一緒だというのが通例だった。
私が懇意につきあっていたのを思い出すと、ほとんどが六十年代の人である。その沖縄の六十年代を代表する詩集、清田政信の処女詩集『遠い朝・眼の歩み』。東京の詩学社から出すというので、頼まれてそこに原稿を持って行ったのは、宮城正勝さんだったというのは、知る人ぞ知る逸話である。宮城正勝さんも確かに六十年代の洗礼を受けた世代だと思う。
のちに『らら』や比嘉加津夫さんの『脈』同人になって、そこで俳句を発表していたのを知って、俳句か、なるほど、俳句とは、決まっているな。おそらく感覚的に俳句があっているんだろうと思った。詩なんていうのは、饒舌すぎるし、甘すぎるんだろう。
私自身も拙い句作をするが、大道寺将司の『棺一基』を読んで、「ああ、日本の俳句はこれで決まった、もうこれを超える俳句はないだろう」と、自分一人で勝手に決している。十七文字への句境の凝縮という視点での、きまじめの俳句観であることは承知している。境涯ありて句境あり、なのだ。
宮城正勝さんの俳句の風景には、境涯につらなる人や町角や路地やビルの廊下や空の色や畑や庭や干潟や時間やらを通して生や生活の〈間〉を視ている感性が吹き抜けている。そう、〈間〉なのである。だがそれは撫でながらちくりと刺していく機知がある。形而上にいくことはしないし、形而下にあるのでもない。句集タイトルの『真昼の座礁』とは、どこか屈折している、律儀な感性を宿す生の表現である。難破ではない。静かに座礁するのである。
形而上と形而下の相対の緊張が生み出す五七五の句語がまさに詠う主体の句境をぴたりとあらわす。「「形而上」に移行する機運を、「まて」と止めて「形而下的」にするが、その風景にさえ句境は距離をもってみている。外部と心理が相互に応じている。外部の風景を句にするときも心理的なものが入り込んでいる。句流は小林一茶的とみた。宮城正勝も往路はたしかにあったし、いま還路にいるかは句境が語るものである。
潮干狩りどこまでゆけば黄泉の国
西日から死へすみやか移行せり
死ぬまでは日常がある蝉時雨
死と遊ぶひとりの砦日向ぼこ
ところどころ頻出する「死」の影。時に映じる光景にみえるものは、老いの日常と生と死の形、そして叙景も意味的にする孤独の姿である。だが叙情に甘えない。寄るべきものを持たぬ、ある意味、断念がある。そして「醒めている」。俳句とは瞬間のレトリックとその表出、句境に俳句精神が宿るからして、〈詠う〉ことは韻律の美学となる。











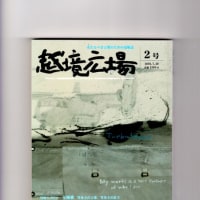
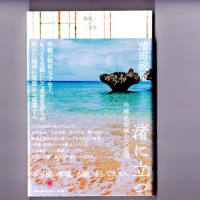
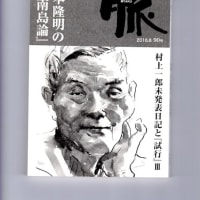
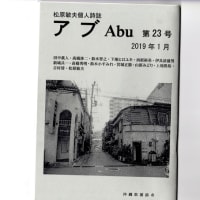
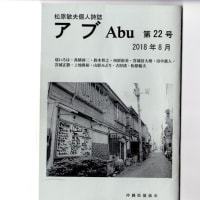
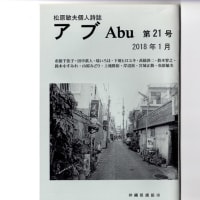
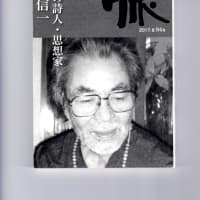
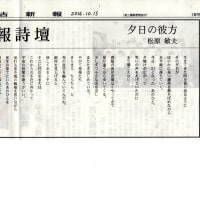
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます