
詩は手套のような女―川満信一の詩と思想
(ショート・ユンタク)松原敏夫 × 東中十三郎
つもりつもった 古くて重たい物語を
麻袋に詰め 古里をでたが
はて どこへ旅するつもりだったか
わたしは忘れてしまった
(「わたしはどこへ……」(川満信一詩集))
【松原】 『川満信一詩集』を久しぶりに開くと、この詩篇に印をつけてあったんだな。「古い重たい物語」と「古里をでる」「旅する」という動詞が「行き先不明になる」にひかれた。
【東中】 雰囲気がわかる感じだな。『川満信一詩集』は、水納あきらの所から出したんだよね。
【松原】 1977年12月で、この年の10月にぼくも初めての詩集『那覇午前零時』を出したんだよ。
【東中】 『川満信一詩集』も川満さんの処女詩集だったんだな。
【松原】 初めての詩集というのは意外だった。年齢からすると45歳になっているからね。ぼくの詩集は、画家のトヨヒラヨシオさんに装丁を頼んで、シンプルな形にだしたんだ。比べて、『川満信一詩集』は表紙に宮古島のウヤガン祭りの老いた神女の写ったモノクロ写真を使っていたね。リアルでインパクトがあった。あれをみて、ああ、川満さんらしいな、と思ったね。
【東中】 あのころは復帰後の沖縄が色んな分野で売りだされたような時代だった。特に民俗学的にみたり語ったりすることがブームだった。
【松原】 祭式や古謡をテーマにいろいろな書物がでていたよね。「おもろさうし」とか「南島歌謡集」とか「イザイホウ」とか、ね。詩を書く人たちも関心をもっていた。
【東中】 おめえのものは、飯島耕一の『ゴヤのファーストネームは』のマネをしたと、おめえから聞いたことがあるぜ。
【松原】 サンプルにトヨヒラさんにみせたら、詩集というのは、言葉が全てだから、装丁は目立たない方がいい、という意見だった。結果的に、サン印刷の宮城明さんに頼んで箱入りの飯島耕一のものに似てしまった。
【東中】 『川満信一詩集』は、詩集にしては、よく売れて、書店のベストセラーに顔を出したと話題になったんだよね。
【松原】 川満信一さんは有名な知識人であったし、交遊範囲が広い人だったから、ま、売れて当然という感じだったな。
【東中】 おめえのものは売れたの?
【松原】 無名が売れるわけないじゃないか。300部だして、今でもまだ五部くらいは家に在庫しているよ。
【東中】 ま、売れればいいってもんじゃないしな。………あ、これって、慰めでいっているからな。さっきおめえがあげた詩篇だけど、旅の喪失が主題になっているということ?
【松原】 川満信一さんは、ぼくと同郷の人というのを知っていたが、ぼくは「島を出る」を「旅」とみることにまだ感覚がなかった。島を脱出したという異郷存在感だけが強くて、「行き先」は考えなかった。いま考えれば、出た意味を実際は問わないといけなかった。
【東中】 つまりそれはどういうこと?
【松原】島の若者は島を離れて都会をめざしていくものが多かった。島では古い慣習やしきたりがあって個人の生き方を苦しくさせる、意識を持っては狭い観念の島社会には住めない。進学して島を離れて学問をすれば、知識が増えて思考の位置が島から離反する。しかし異郷や都会に行ってもそういう「島の物語を宿している自分」は消せない。そこで離れた先はなにか、ということに苦悩する。これは近代を求めた誰にも宿命的なものといえる。
【東中】 島を離れるということの意味と個人の意識の選択の先にあるものが問われるということか。
【松原】 なにか風土の桎梏から解放されたかのような気分にはなった。島を出るということはそういうことではなかったかな。島を離れて島を見つめ直して、生き直しというのか。もちろん進学とは別に島で暮らせなくて生活のため仕事をさがして沖縄本島に移住したひとも多かった。
【東中】 生き直しか、なるほど。那覇とかコザなんかには宮古のひと多いね。
【松原】 つまり流民なんだよ。島を離れて、色んな仕事について、家はないからほとんど借家住まい。当時のスラム街の下層民は離島のひとが多かった。下層労働者や水商売とかね。
【東中】 あの戦争の地上戦で破壊されたあとの沖縄の復興は、まずは生活や経済の立て直しにみんなが大変だった。アメリカの軍事支配の下での経済でどうにか食っていかなくちゃならなかったし、いびつな体制下のつくる特殊な社会の雰囲気があったし、しかし政治でどうこういっても、やはり経済生活が問題だからね。貧しくてもどんなふうにも生きていかなくちゃならない。
【松原】 全てにおいて飢えがあったと思う。経済も生活も文化も遊びも、満たされることを夢見てがむしゃらになっていたと思うんだな。焼け跡派的な。川満信一さんも焼け跡派といえるよね。
【東中】 川満さんは終戦を思春期で迎えているね。で、島を離れて首里にあった琉大に進学して、まず文学活動に目覚めて、「琉大文学」を出して次に政治に目覚めるんだな。
【松原】 あのころの文学青年はだいたいそうだったようだね。かならず社会状況や政治状況に関心をもって目覚めるんだね。ぼくは逆だったけど。
【東中】 琉大文学の歴史を語る資料がたくさんでているから、それをみれば明らかになっていくね。琉大文学のメンバーが当時の学生運動をリードしていくような感じがあるけど、ほんとにそうだったのかな。はじめからの政治青年もいたんじゃないの?
【松原】 いたでしょう、それは。沖縄人民党の瀬長亀次郎が民衆運動をリードしていたし。民衆運動は学生運動のなかに入り込んで学生を刺激していたし。
【東中】 文学よりは政治運動に魅力を感じたんだろうね。世の中がこんなにおかしいのに、文学なんかやってられるか、というね。文学意識よりも現実感が強かったんだろうな。
【松原】 文学では世界は変わらないとね。政治や現実に関心のない文学はダメだとしたわけでしょう。当時流行していた新日本文学運動やプロレタリア文学、社会主義リアリズム文学の方向へカジをきったわけでしょう。文学作品を創造するエネルギーのほうではなく、政治運動的な方向へ傾きすぎたんだね。
【東中】 土地闘争の島ぐるみ運動はいちばん影響が大きかったようだね。密室のようなところで書かれる個人的な文
学の意味と大衆が燃えている島ぐるみ運動をみると、そういう社会性から文学をみていく方向性がそこで決まったんじゃないか。
【松原】 大衆の動きと連動した文学を求めたわけだよ。そのほうが文学する理由がすとんときたわけだし。しかし、どうだろうね。そこを大城立裕は批判しているわけよ。運動に入れ込みすぎて文学作品を創造することへ力を注がなかったことへの、ね。文学が貧困になったという批判ね。次の世代である清田政信からの詩的現実を拠点にした川満世代の批判とかね。ま、そこは、話が変になっていくから、やめるけど、川満信一さんをどうとらえるかと考えるとき、ぼくはやはり文学的な側面からみていきたい、と思っている。
【東中】 川満信一さんは知識が多彩で豊富な人だね。だから文学と思想の連関をとらえないと語れないひとだな。
【松原】 川満信一さんは詩人として活動していたわりには文学作品をあまり書いてこなかったんじゃないかなと思う。文学に目覚め、活動はじめた20代から今日までをひととおりみてみると年齢のわりに他の詩人に比べて、文学表現が少ない。文学主義者のぼくからすると川満さんは文学者(詩人)なのか思想家なのか判然としない。沖縄の戦後文学、戦後思想に必然的に顔だす存在であり、その発言は時代を撃つ言葉がたしかに多い。ぼくも、彼の言語を読むとき、ある角度からは敬意を持つし、人知れずに注目をしてきたつもりだが、しかし、彼の思考の持続は複層的で、その複層を詩の言葉で表現するのに困難な回路にあったんじゃないかな。
【東中】 文学表現するには重たい思想意識が強すぎたということか。
【松原】 いま目の前に川満さんの本がある。『川満信一詩集』と『世紀末のラブレター』だ。その傍に思想論集である『沖縄・根からの問い』とか『沖縄・自立と共生の思想』とか「沖縄発――復帰運動から40年」もおいてあるが。この三冊には、なぜか、文学に触れたところがほとんどないわけ。繰り返しになるけど、ぼくにとって川満信一は詩人と言うより思想家というイメージが強かった。川満さんは戦後の沖縄思想を語る大御所であったし、その存在を横目でみながら、ぼくは真剣には読まないできた。文学に熱心に発言する人ではなかったし、思想を優先して語るような印象があった。川満さんは弁舌がうまいし、滑舌なひとだなという印象があった。知識も豊富にあるし、ジャーナリスト(新聞記者)でもあるし、仕事柄、知識を持つのは必然だったろう。とは思うけど、反面、文学を書くとなると、その知識は障害になってしまっていたんじゃないか。
【東中】 物足りないのは、詩や文学への言及があまりないということか。詩や文学が好きであれば、その文学意識に沿って、文学的発言、文学的言説が多く出てきそうであるが、それがあまりないな、たしかに。
【松原】 思想というか評論というか、「宮古論」、「民衆論」、「共同体論」は、当時、川満さんが復帰の時期をはさんで、さかんに、たぶん、求められたからだと思うけど、自分の思想の核となるような評論を生み出した時期の文章だよ。そういう、ま、散文というか批評というか、言語表現を、思想言語に集中過ぎて、詩作がおろそかになったんじゃないか。しかし、川満さんの仕事は、沖縄が抱える状況から表層ではなく沖縄が宿命的に持つものの根源を可能性として構築したいとの思念がある。そこは川満思想として学ぶところはある。
【東中】 詩に思想を入れ込むと、背負いすぎて重たくなるからな。思想と詩的表現がバランスとるのがむつかしくなる。
【松原】 そういうときに、川満さんは、どういうふうに自分の内部のなかで詩意識と思想意識を結合させて、詩的形式に言語表出するのか。もしかしたら、このころの川満さんは、あまり詩は、いや文学は、好きではなかったのではないか、と誤解させるところがある。その結果が、これまで出してきた詩集が二冊だけとなるのか。もちろん雑誌などに発表して詩集に入らない詩作品も多いのも現実だけど。
【東中】 出した詩集はその二冊だったかな。たしかに物足りないな。作品が散逸しているのはもったいない。川満詩の全体をとらえるのが困難になる。全詩集が出ないと、な。
【松原】 1994年にエポック社から出た『世紀末のラブレター』は、うらやましいほど、作りがいい。装丁がいい。さすが詩人の泉見享さんが手がけただけはある。この詩集を読んで、川満信一さんは垢抜けしたといったら語弊があるが、詩人の位置を取り戻したと思った。つまり、言葉に思想や複層の意味を持たせるのではなく、現実を通過したあとの詩的内面の声というのがある。日常生活や仏教的な世界を歌った作品がある。
『川満信一詩集』は、〈飢餓意識〉が隠されたテーマとして低通しているよね。島の飢餓を背景に、詩と思想に社会性をたたき込んだような重たいテーマで書かれている。犬を食った、鷹を飛ばして鷹を食ったとか、羽をむしられた鳥とか、なにか飢餓というか欠如感が強いイメージ、それとアメリカ支配の基地や沖縄社会の貧困生活や島の古代や神話というものの根源的なイメージを構築しようとした言葉がある。
【東中】 まさに複層沖縄の詩集という感じだな。
【松原】 印をつけてあったもうひとつ詩篇をあげよう。「詩人と詩」という作品だが。
詩は手套のような女
二月の吹きさらしで
凍てついた指がちぎれそうに痛むとき
ぼくはそのふところへ深々ともぐりこむ
この詩は、さらに「詩はさびしい薬のような女」とか「詩は発情期の雌馬」とか連が続くんだが、この詩意識は、詩に抱擁される弱さや遊びが屈折して出ている。詩に対する詩想を書くのは珍しいけど、率直さがでている。川満さんが、別のところで詩人というものについて語っているところがある。ちょっと読んでみるぜ。
「世間では、詩人とは常識をはみだした頭の左巻きの奴だ、という暗黙の了解があります。犯罪でない限り、世間の常識を逸脱しても、大目に見てもらえるのです。ですから詩人は、一度味をせしめたら乞食と同様になかなか止められません。」(異場の思想とは何か―『沖縄発――復帰運動から40年』所収)
おやおや、へえ!そうですかね?とぼくなんか思うんだけど、詩を書く自身の世間に対する自己存在を装飾として語りたかったのか。ぼくなんかは詩人なんていわれるのは恥ずかしくってしょうがない。詩人のセンスがないし。ぼくは魂の自由人、それだけでいいと思っている。
【東中】 今は詩集を出せば、「詩人」と呼ばれるような軽い時代になっているが、詩人であれば詩を自覚的に思索して書いてほしいし、詩に貪欲になってほしいね。そうすれば詩論とか詩人論とかが生まれてくるはずだが最近それがないし、低調だよね、沖縄の現代詩は………ところで「川満信一」という存在は、詩人としてよりも沖縄の思想を語るうえで、必然的な思想家として考えられている人だよね。反復帰論者として六〇年代から七〇年代にかける、72年復帰を周縁する状況を川満信一は誰よりも数多語ってきた。
【松原】 そんな「反復帰論者」としての見方は一面的だとおもうね。さっきもいったように求められたからだとおもうけどね。マルクス主義や社会主義思想に傾注していった当時の若い世代にあって、いわば社会変革、革命の夢を内在化して、状況に対峙していた。50年代の土地闘争や島ぐるみ運動に参加しつつ、政治意識を追って大衆とともに戦うことの運動の意義があった。六〇年の復帰協設立とともに、祖国復帰運動が全県的な運動として、広まった。だが、それは単に祖国に帰るという、民族主義運動でしかなかった。川満さんは、この運動の、この先、未来をどうしていくのかと、その運動の本質から問うことをしたわけね。その辺は『沖縄・根からの問い』、『沖縄・自立と共生の思想』という著作に出ている。
【東中】 川満思想の発生と変遷か。最初の著作『沖縄・根からの問い』は「共生への渇望」という副タイトルがついているね。
【松原】 川満さんの共生思想には「全体への合一化の危険性」と「個人の疎外克服の先の可能性」があることをいっているんだよ。
「ところで、私の今日までの闘争体験と、状況への対峙から導き出した思想は、やはり「共生の思想」という以外に表現のしようがありません。あえて定義らしく言いますと「ミクロ的には生物心理学的な深層まで視野をおろし、マクロ的には地球または宇宙まで視野を広げ、相互扶助に行為の価値基準を設定すること、それによって歴史的に歪みを拡大してきた自己の人間性の根源的な変革を進める」ということになります。(沖縄・自立と共生の思想)」
これはマルクスやヘーゲル的思考をしていた初期のころからの思想の超克を告白しているとおもわれる。「共生の思想」はたどり着いた思想で、これを敷衍して思考を進めたわけよ。国家論や天皇制論の展開も共生の思想が基盤になっている。またこうもいっている。
「ところで、民衆の現存の基層には、共生、共死の志向があり、それは村落共同体内では、絶えず求心的に働いている。その求心的に働く共生の志向が、他人に対する必要以上の関心として現象し、その他人との関係の持ち方が、相互の個的行為の逸脱を規制する。」(共同体論)
村で生まれたものには、自然と備わる共同体意識や感性があって、それにふりまわされることがある。他人に対する必要以上の関心とは、共同体意識のそれであり、個の視線は共同体の視線になっている。
【東中】 「民衆の現存の基層」は信じたいけど、都市化されてシマが個に解体されている現状ではどうかな。復帰後の21世紀の沖縄は都市化、本土化が相当に進んで、内地からの移住者が多くなっているし、村落共同体も変容しているし、沖縄社会そのものが相当変質しているわけだよね。
【松原】 その変容、変質は不可避的にたしかにあるよ。すさまじいくらいにね。それとグローバル化の流れで、外国人も多くなっているでしょう。場所が世界化され、その影響は沖縄社会をさまざまに変えてきているよね。共同体とか民衆とか、言葉の響きがもう古く感じる。社会の変質はタイムリーな課題だね。
【東中】 「アイデンティティ」で包め込めるのかなあ、これからの沖縄は。もっと沖縄的思考を多様に柔軟にする必要があるね。
【松原】 アイデンティティというとぼくは言いたいことがいっぱいあるから、ここではやめておこう。川満信一という〈沖縄の思想家〉は沖縄における戦後思想の方向性に警鐘を鳴らした人でしょう。その思考法は、日本主義でもなく西洋主義でもなく、アジア的共生意識とつながる方向性を持っていた。「民衆論」や「共同体論」はその結実であるとみていい。
「………自己の存在を問う思想への出発から、すでに孤絶の位相をとらざるをえないヨーロッパなどキリスト教文化圏の知識人の自我は、いわば純粋の孤個へ昇華せざるを得ないが、自然の万物に、よろず神をみるシャーマン的な共同体の感性や、よろずのものに仏性偏在をみる仏教思想、そして正教の一致を説く儒教の処世訓の思想を、その出自とする沖縄および日本の知識人の自我は、その出発点からして、全能の唯一神との格闘という孤個の位相ではなく、まずその出自であるところの共同体ないし民衆に対する意識の距離測定としての位相をとるしかない。(共同体論)
【東中】 沖縄の思想の在り方と方位を語っているような感じだな。
【松原】 共同体や民衆をどう対象化するか、という思想的問いは沖縄では必然的な課題ということだね。西洋の個人主義の思想が、共同体の回路を通らなくて、個人の思想を作り上げてきたのに、共同体意識が強い沖縄ではまわりくどい道をくぐらないといけない。詩を書こうとすると、共同体と対立する宿命がある。その対立を清田政信も敏感に感じ取って、自らの言葉を対峙させながら書いていたわけよね。悲劇的にあったけど。
【東中】 川満さんは個人の絶対性よりも個人の共同性に可能性をかけたようにみえるね。
【松原】 川満さんは谷川雁の不可視のコンミューン論にほとんど触れていないけど、私見では、その共生思想は谷川雁がいう「民衆に内在する前意識の共同体イメージ」と類似しているという気がするんだよな。
【東中】 たしかに谷川雁のことはほとんど触れていないね。民衆の持つ前意識のコンミューンと共生思想はクロスしそうなものだけど。それと思想のなかに仏教的観念があるね。
【松原】 川満さんの思想の型を考えると、「共生の思想」と「仏教的思考」が両義的に混在している。共生の思想は人間が集団で生きていくときの思想、仏教的思考は、存在論としての思想になると思う。その両方の混淆が、川満思想になったと、みていいんじゃないか。それから後に「異場の思想」を提起している。
「簡単にいいますと、日常から非日常へ、それが「異場」への転移です。」(異場の思想とは何か)
「時間と場所を包括している歴史や、日常とは異なった地点に、思考や感性のスタンスを定め、そこから現実へ打って返す思想、それが「異場の思想」であり、人間のほんとうの進歩に加わろうという思想だと考えています。」(同)
そしてこの先に親鸞の非僧非俗、阿弥陀仏、悟りや涅槃という境地があって、そこへつくには四つの段階があると熱心に説明している。
「私は最初、仏教は神秘主義であり、唯心的な思想だと思い込んでいました。………略………龍樹菩薩の中観論に出会って、意外なことに仏教が、唯物論的思索に基づいていることに気付きました。阿弥陀がサンスクリットのアミターバ(無量光)と、アミターユス(無量寿)を意味することを知ってから、仏教全体の思索の輪郭が少しづつ見えてきたのです。」(同)
そうすると「共生思想」「仏教的思考」「異場の思想」という三本柱が、川満思想の根幹になっているとみなしていいだろうな。かつての政治的思想から普遍性を帯びた思想に近づこうといろいろ追求して現在にあるといえばいいか。島尾敏雄が書いていることが絶妙だね。
「彼の姿はつかまえようがない。…(略)…そうだ、川満信一は詩人だったのだ。」(島尾敏雄「川満信一詩集略注」)
【東中】 ごめん、おれは仏教についての知識がないから………。
【松原】 ぼくも仏教は少し囓ったりしたことはあるけど、奥が深いし、語れない。川満さんが、思想の形成に仏教との出会いが大きかったということはわかった。個人誌「カオスの貌」で川満信一の現在を読む必要があるということで、いちおう終わろうか………。















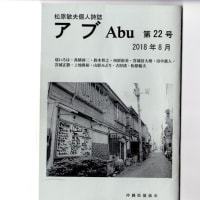
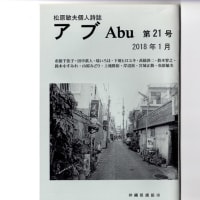



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます