沖縄市は、かつては、こんな粋なこともやっていたんだね。

ぼくは柄にもなく、沖縄フィルハーモニック協会の上地隆裕氏に誘われて、1999年11月29日に行われたリトアニア国立交響楽団演奏会プログラムにこんなことを書いていたので、ここに再掲載する。
チュルリョーニスとの出会い
しじまにもカオスの香り納め有り
未だ聴かぬ淵の奧にはリトアニア
チュルリョーニス流る祖国に風を聴く
〈チュルリョーニス〉という作曲家の存在をはじめて知ったのは、演奏プログラムをみたときだった。
チュルリョーニス!? 沖縄市民コンサートで、リトアニアの交響楽団を呼ぶと聞いていたが、演奏される曲目のなかに、聞き慣れない名前が入っていることから、生来の好奇心が湧いてきた。
その時から、私は、折りあるごとに、音楽教養のあるひとに、チュルリョーニスという作曲家を知っているか?と尋ねた。でも、「誰れ、それ?」と応えるのが殆どであった。私の脳裏に、知らないのはこちらだけではないな、という安堵感と優越感があったのはいうまでもない。日本では、現在は、それほど知られていないマイナーな作曲家なのだ。マスメデイアに登場するとか、教科書に載るかして全人教育しなければ「人口に膾炙されない」、この世の習わしの蔭に隠れて、埋もれた芸術家が非常に多い。チュルリョーニスもそのひとりである。
リトアニアともなると、かつてソ連の一員であったために、クレムリンの検閲を通してしか入ってこなかった文化情報が、一九九一年の独立を経て、ようやくにして、国として、自由に日本でも紹介されるようになった。この交響詩「森の中で」が日本で初演されたのが、一九九五年というから、リトアニアの音楽紹介が、いかに遅れていたかがわかる。
チュルリョーニスは、教会のオルガン奏者を父に持つ、リトアニアを代表する作曲家であり、三六歳の短い生涯(一八七五ー一九一一)で、最後は精神に異常をきたして亡くなった、画家としての才能もあった、楽曲二〇〇点以上、絵画三〇〇点以上を残したが、しかし、その評価は死後三〇年経ってからであったということ等がわかった。一九九二年に西武美術館で、彼の絵画を集めた「チュルリョーニス展」が開かれたという。絵の一部は、インターネットで外国のサイトを通して画像を見ることができる。これもなかなか面白い絵ばかりである。「Creation of the World」で、Vytautas Landsbergis(元リトアニア首相)はオリジナルな作風であることを強調しているが、たしかにそうだ。私は、新鮮な驚きを受けたといっておこう。ストラビンスキーは、チュルリョーニスの絵のコレクションを持っている、とロマン・ロランに自慢していたらしい。どちらかというと、チュルリョーニスは画家として名をはせている趣がある。
チュルリョーニスは、リトアニアでは、英雄扱いされるほど有名な芸術家であるようで、彼の名前の入った芸術学校があるというし、リトアニア第二の都市カウナス市には、美術館があって、チュルリョーニスの特別ギャラリーもあるという。その国で、よく知られている芸術家が、外国で無名であることは、文化情報の流通にもよると思われる。アメリカの微細の情報が、ふんだんに入ってくる時代なのに、まだまだ未知の状態にある外国が多い。しかし、いまやインターネットの時代である。専門家が独占的に紹介するのを待っていてはじれったい。通信手段があれば、自ら情報を探れることが可能なので、自力で外国の情報を得たほうがいい。
交響詩「森の中で」は、リトアニアを離れてポーランドのワルシャワ音楽院に留学しているときに着想され、チュルリョーニス、二五歳頃の作品である、といわれている。これは、幼年のころに、父がよく話して聞かしたリトアニアの民話や伝説の記憶が題材になっているのであろうか。祖国の歴史と風土を楽想にもつ交響詩で、チュルリョーニスは何をイメージしたのであろうか。
この曲は、はじめリトアニアの緑の草原を吹く風のように静かに響いてくる。弦と管の和音が、風になって周囲を呼び込むような、情景をなでるような、優しいメロデイを奏でる。感情と自然の調和から出てくる情念の表現であろうか。樹木のざわめき、民話の飛び交うノスタルジー、叙情詩的韻律、ときに嵐の音..........。祖国リトアニアに思いを寄せながら、リトアニアの自然の情景やそこに流れる時間と空間が交わって生まれる音。そして、最後に、楽器が一斉に蜂起するように高らかに鳴り響き、余韻を引きながら終わる。高らかに終わるのは、おそらく、「おお、我らがリトアニアよ!」という感情が高まったときの賛歌であろう。一六分ほどの曲だが、聴いていながら、イメージ的な、印象派風な、情感が満ちあふれた作風だと思った。
私たちは、「四季」「田園」「ロマンチカ」....といった自然をモチーフにした交響曲を知っているが、交響詩「森の中で」には、チュルリョーニスの血の中に流れる受難の歴史を持つリトアニア人魂が、脈打っている。ほかに交響詩「海」やピアノ曲がCDで出ているらしいのだが、私は、残念ながらまだ聴く機会を持ってない。
私は、この演奏会でなければ出会わなかったであろう作曲家の音が聴ける幸運を享受しようと思う。











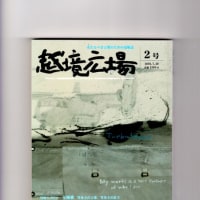
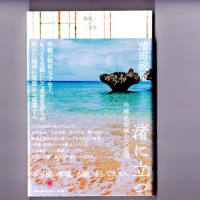
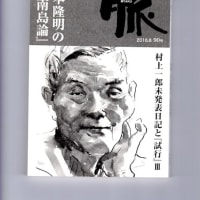
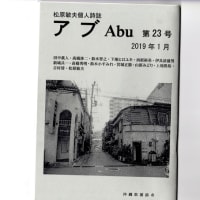
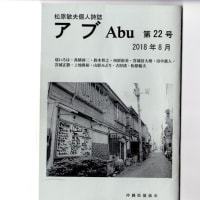
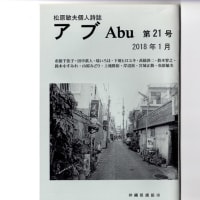
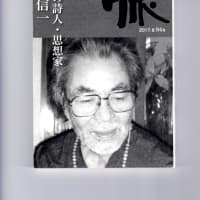
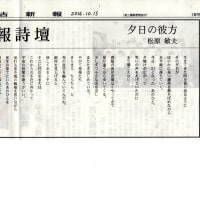
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます