6年ぶりに『沖縄詩人アンソロジー 潮境』第2号が発行された。風聞だが、沖縄の詩は注目されて、まま売れていると聞く。事実ならうれしいことだ。今号は作品だけでなく、沖縄詩壇への感想、意見、アンケートといった趣向が入っている。詩に対して何を思っているか、自覚的に詩に関わっているかの一端を読むことができる。掲載順が若い世代から年長者順になっているから、詩想の差異、詩的感覚、詩的言語の綾が読めるのもいい。沖縄詩の現在や傾向について、未知の親愛なる読者はどう読んでくれるだろうか。
『現代詩手帖』11月号「特集 琉球弧の詩人たち」は最大のトピックだ。沖縄の詩人が全国的に紹介され読まれる、という画期的な企画に随喜した。現代詩手帖側によると『潮境2号』を参考にして人選したらしい。川満信一、八重洋一郎、伊良波盛男、新城兵一、松原敏夫、高良勉、仲本瑩、市原千佳子、おおしろ健、宮城隆尋、トーマ・ヒロコ、西原裕美の作品と短文エッセイが載っている。展望として、高良勉が「二十一世紀の彼方へ」で復帰後50年間の沖縄詩壇を俯瞰、言及し、論考に藤井貞和、野沢啓、今福龍太が書いている。高良は70年代から現在まで清田政信を筆頭とした「詩と思想」「詩と批評」の時代から現在の詩まで詩史的に語ることで沖縄詩の現状を浮き上がらせた。
短文エッセイで批評言語の重厚な視点をもつ新城兵一が、『潮境2号』を現代詩手帖の月評で須永紀子がとりあげ、「歴史に関わる複雑な感情を描いたものが多い」と評し、そういう傾向にない作品に「希望をみた」と書いていることに「詩的審級による思考停止がもたらす『選別』」と批判して、消費文化の先端をいく大都市に住む東京圏詩人の充足した都市感覚の言語基準で作品を選択する現代詩の傾向を喝破した。言語詩を純粋に追及する東京圏の詩人と言語詩を求めつつも沖縄の現実に呪縛される沖縄の詩人は位相が違うということだ。個人の言語感性で書くのは前提であるが、沖縄の詩人は、状況、歴史、風土を内部に取り込み咀嚼しながら、いかに自立した詩的言語に生成するかを自問しながらやっている。だがそれは個人の詩的行為に依拠するものだ。感性や苦悩は個人に宿るからだ。歴史や状況に対峙する個の姿勢を構築し、〈個に宿る何か〉をこそ根拠に詩を表出するのが正当である。歴史性、社会性、思想性を先行する詩想は滑稽である。そういう志向は個人の感受性で裁断していいことだ。状況や歴史の苦難や叫びの共同性への収斂よりも、それぞれの、ことばを拓く詩的創造の自由な精神を表現することがいいのだ。
野沢啓の「詩集でも出してなにか賞のひとつでもゲットしようとするようなさもしい根性は沖縄の詩人たちには無縁である。」と評価する言い方には同調できない。野沢の〈沖縄の詩人に寄り添う心〉はありがたいが、引き上げて型をはめる働きにもなっているからだ。詩集を出して、何かの賞やらに応募するのが沖縄の詩人でも多いのである。沖縄で山之口貘賞ができたとき、詩人たちが色めきだったし、貘賞狙いで詩集をだしているひともいる(いた)のである。どこでも「さもしい根性」を持っている人はいる。おれは一冠だ、あいつは二冠、三冠じゃないかと嘆く人をみてきた。清貧さに呪縛される必要はない。「さもしい」行為は個人の自由な欲求にかかわることである。
詩集。下地ヒロユキ『アンドロギュヌスの塔』、波平幸有『むる愛さ』、八重洋一郎『転変・全方位クライシス』、かわかみまさと『仏桑華の涙』、伊良波盛男『人類』、上原紀善『連音』、東木武市『蘇った遠い昔の僕』『ジャコの唄』、安里英子『月と太陽』、ローゼル川田『肝ぬ愛さ』、高柴三聞『ガジュマルの木から降ってきた』。……今年も年季の入った書き手の活発さが目立った。
詩誌。『あすら』『アブ』『霓』『全面詩歌句』『だるまおこぜ』『縄』『南溟』『滸』『万河』はそれぞれ号を重ねた。もうそろそろ詩集にまとめてもいい書き手がいっぱいいる。出してほしいものだ。
山之口貘賞に林慈の『浜紫苑』が決まった。











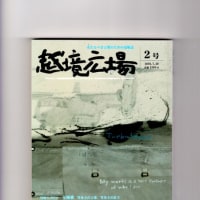
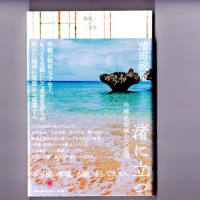
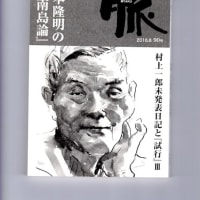
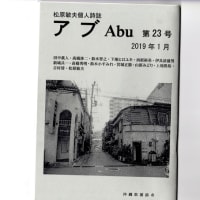
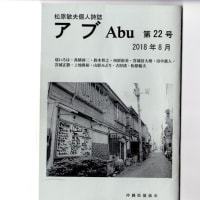
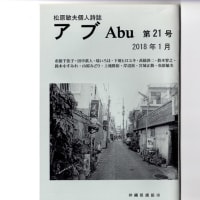
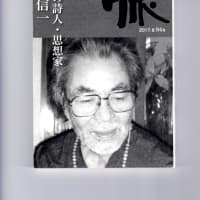
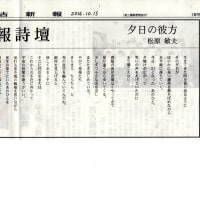
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます