この作品は1978年10月に出した4冊目の詩集『疼きの橋』に入っているが、あとがきの「ノート」で清田政信は詩集の発生の動機について書いている。
「詩を書くということは、自らの遠い出自を現在に現出するという行為と深くかかわっているかもしれない。地方の都市にいてなにか自らの生が希薄になり、生の根拠がくずされるという感情にみたされる時、いつでも遠い出自を喚起した。そして東京を小さくしたような那覇で、生活の内質がうすれるような時、村にかつて在った日の、あるいは今でも私の感受性の原質をかたちづくる村の体験は、言葉のちからによって蘇り、現在の生に遠近を展いてくれたようだ。」
詩の生成への情念と論理が、わかりやすく書かれている。詩集は1976年8月から1978年9月の2年間にかけて発表あるいは未発表の作品を収録している。単純に考えて、その2年間の清田の詩想の境地を表出したものといっておこう。ここには自己形成の再体験から生の蘇生と存在の把握へ歩む詩的言語を注いでいく方法をも語っている。こういう自己史のディテールの喚起を辿ると何かがみえてくると企図しているといえるが、清田は「近代というもの」を自己体験と交叉させた断層にたちあらわれたものに対峙する方法からことばを編み出した詩人だと思う。近代の甘いサウダージではない。ぼくらは誰も近代をまといながら生きているわけだから先天する島的身体性の断層と近代の明暗を生きる磁場から逃れることはできない。現在の生の精神にうずくアポリアがあり、近代をどう超えるかという古い命題を迷路のごとく自意識のなかに落としながら、現代という時代に佇んでいるということを自覚すべきである。清田がモダニズムや荒地派を批判するのは、かれが出自と対峙し相反する日本近代の牙城、東京=都市への精神的生理の異和と隔意があるからだ。
私が『那覇午前零時』を1977年に出したとき、清田政信に解説を書いてもらったことがある。時期からすると、『疼きの橋』に収録した作品を書いている頃だろうと推測する。解説の題は「試練としての近代」である。そこにこう書いていた。
「沖縄で〈近代〉をかんがえるのは憂鬱である」(試練としての近代)
「詩を書くということは、近代の風俗としての現象に対峙する出自の自覚という面と、村という共同の感情から身をそぐように意識を分離していく二つの面を持っていると思う」(同)
「南島はいま〈近代〉の圧倒的な浸蝕を前にして思想する者の根拠が問われている。云うなれば近代は不可抗力として機能しつつあるけれども、またそれに対する精神の位相が確定されていないということかもしれない。」(同)
「「荒地」派から六十年代まで続いた現実からの孤立の中で思想を試す困難にきているのがこの青年たちだ。」(同)
こういう文章を交差させると、いかに清田政信が近代の南島への浸透を敏感に感じ取り、出自と自己形成の磁場を近代と遭遇させ宿命的な隔意をもっていたかがわかる。沖縄において近代は「憂鬱」であり「試練」という。シュルレアリスムだけでなくモダニズム言語やモダニズム表現を好んでいた当時の私への批判と警告があったわけだが、清田の思考法、詩想からするとモダニズムへ安易に入って行く私の書き方を批判するのは当然であったわけだ。いまならポストモダン的思考と相対して語る魅惑を感じるが、消費資本主義社会が未達の当時の沖縄の島や村をポストモダンで語るにはあまりにギャップがありすぎる。だから、そんなポストモダン的な語法で土着、風土、島、村、人間を語るのは似合わない。
日本現代詩の現在は北の首都を中心に、ことばの錬金術と知識に長けた秀才たちが知的ジャーゴン語を競っているようだ。先ゆく現代詩への遅々感と内なる狭小感と隔意を持たざるを得ない。この隔意は〈絢爛たる空虚〉で踊っている現代詩にあきあきした辺境からの本音だ。詩はここまできたか、現代詩はもう読まなくてもいいかな、知的ジャーゴン界の者たちがジャーゴン語の祝祭を楽しめばいい、辺境では〈現代詩〉よりも、〈いわゆる詩〉のもつ差異的創造の詩魔で行方を照らすのがいい、と暗澹たる岸辺で佇んでいる。………と思わぬ反語的感想を示したが、ここでは、「潮の発作」をとりあげて清田政信という詩人の内界を〈古典的な〉見方で自己流読解することを試行したい。
「ノート」に書いていることを秘密、動機とみれば、「潮の発作」もそういうモチーフのなかで書かれたと解釈しなければならない。ひとつの作品を分析的にみるとみえなかったものがみえるようになることを希求して読んでみよう。
しきりに波のくずれる音がする
コーヒーをかきまぜていると
夜の中心に堕ちてゆく陽があり
みえない闇へひとすじに走っている道がある
真昼の木洩日にめいていしていた
少年の放心の底へ行きつくには
このひとすじの道を一目散に駆けていけばいいのだ
冒頭。場所は那覇の地下喫茶。そこで詩が書かれる。喫茶店が詩人の仕事場だ。喫茶店で詩を書く詩人に山之口貘がいた。貧困と詩を切断しながら貧困を詩に取り込んだ詩人だ。貘を貧乏詩人とか生活詩人とか精神貴族なんていうひとが多いが、こういうパラダイムは手垢がつきすぎて鈍感になるから、現時点から新たな読みをする必要があると私は思っている。だがここでは触れない。
清田が家で書かないのは、理由がある。
「せまい間借りで幼い娘の寝息をききながら詩を書くということは、何か犯罪的な意識をともなわざるを得ない。」(「わが詩法」、「南北5号」、1976・8)
と書いていて、それから書く場所をさがして「古びた喫茶店」「地下喫茶」で書くようになったと告白しているからだ。これは私もよくわかる。生活する部屋で詩を書く気分が出ないと、車で海辺にいって波の音と風に吹かれながら書いたこともある。なんでこんな道楽をしているんだろうと思った。狭いアパートで暮らしていたし、3名の子供を抱えて生活に四苦八苦しているのに、生活と関係のない文学にうつつをぬかす自分の行為に、吐き気したことがある。そのため、文学をなかば捨てるように、狭い部屋を占拠している蔵書を古本屋のロマン書房に五千冊ほど売り飛ばし、しばらく書くことから離れたことがある。文学より生活を優先するために。なんとも不器用な錯誤を実行したものだと思っているが、悔いはない。文学を一度は捨ててみる。そういう経験が文学するものには必要だ。私には文学(詩)をするものはコウフクであってはならないという偏見があるようだ。
「しきりに波のくずれる音がする」。これは記憶の聴覚から生まれるインスピレーションだ。次は近代の飲み物であるコーヒーをかきまぜる。この行為はカフェでの習慣だ。だが、その行為は波のくずれを聴いているから習慣の行為ではない。詩人は波の音を聴く自覚的な幻覚におそわれている。コーヒーをかきまぜる行為にさえ、詩のエクリチュールに取り憑かれているのだ。憑依と求心としての記憶の回想化を頭脳に浮き立たせ、「夜の中心」というメタファがはじまり、そこに堕ちる、移動する。これは詩の生成の流れの姿である。どこへ堕ちるのか。少年期の、村の、道の、海の情景に、だ。そのとき現在の夜は「真昼の木洩れ日」に転換している。聴覚から幻覚に憑かれるように記憶の像があらわれ、次第に詩的記憶、想念の興奮の渦を創造しながら巻き込んでいく。つぎに出るのが「闇へひとすじに走っている真昼の道」だ。したがってその「道」は、ただの道ではない。作者の現在を貫くなつかしくも苦い像としての「ひとすじの道」だ。その道に「一目散に駆ける」という行為が衝動するのは忘却を破って駆ける出自の奪還だ。少年は彼であり今の彼自身ではない。出自を代弁する象徴としての少年である。
「波のくずれる音」は清田の精神生理と照応する。清田は海についてよく書いた詩人である。「沖縄・私領域からの衝迫」という連載エッセイがあり、「折口信夫にかかわりつつ」(以下「折口信夫―」)(新沖縄文学51号、1982年3月)の冒頭でも海について書いている。
「海を見ればなんであんなに心が静まるのか?今日の海は荒れているのに、その波のほてりのごとき腥い力に言葉を失っていた私の精神はつよく感応するのだ。私らが島に生まれ、海に囲まれて生きている限り、この関係は精神の生理の深いところで結ばれているはずだ。………略………海は荒れていても、あからさまに生の流動の無尽を見せてくれるから、私は安心してその流動に私の流れんとする暗い力をゆだねることができる。」
「海」についての感受性の表出は「海への思索」や「柳田国男にかかわりつつ」にもある。清田の詩には島での共同体への対峙からくるポリフォニックな言葉の産出があるが、ことばを韻律のごとく包容して覚醒させる「海」の感受性がよくでてくる。「絵の描けない少年」「南半球」「鎮魂の唄」「深夜の海に風がたち…」も海の感受性で書いた作品だ。「海」を取り入れた作品、詩句はほかにも随所にでてくる。海と向き合って自らの感受性やリズムを形成する感応的なものに私も同調する。その感応は海に近い地で生まれ育った私には別の形ででてくる。私の島の幼年期は海が遊ぶところであった。光景としての海ではない。海そのものを相手にその懐の中に入る、遊泳、浮き、潜水とか遊ぶ場所としての海であった。学校が休みになると毎日裸になって珊瑚礁の白い砂浜を仲間とともに駆けまわり、海に入って砂地を歩いたり泳いだり浮いたり潜って魚をさがして銛で刺したり、とにかく海が好きでそこで遊ぶのが日課だった。海が荒れていると、その荒れに心を当てながら心を鎮ませた。なぜあんな無辺大の大きな海水への畏怖感を感じずに無邪気に海に入ったのか。今思うと幼年のその遊びは「母なるもの」の羊水への無意識の回帰行動だったかもしれない。だが海が怖いことも知っている。あるとき仲間のひとりが溺れ死ぬ事故があった。初めて死者に遭遇した経験だった。悲しかった。それから羊水のように無意識に感じていた海が実は畏怖すべき深い生き物で人の命を奪うものであることを改めて知った。それから凪や荒れに敏感になる自分がいる。
あのカンタータとカノンのような海の揺れとさざ波は、感応的であり、情感的であり、島の人間の感情の照応や陰翳を表現しているようだ。沖縄三線音楽の弦の奏でるリズムは海の波を表現している。時にゆっくり、時に激しく奏でる、沖縄音楽の韻律は海の波の音を聴覚と音感にきわだたせた旋律とリズムであり、聴覚に植え付けた長い習性から生まれた自然のリズムだ。沖縄に生まれたものは誰でも海と波のさざめきを内面の音感に持っているはずだ。
陽は夏のなまぐさいけものの
飢えた腹のごとくなめらかにうるんで
怠惰な心をやさしくあやめている
突然むきになって母と諍い家をとび出すと
道は処刑場のごとく静まり
陽が身をのべて眠っている
作者の根にあるかつての過去が消滅しないで想起される情景にある。像はそこに存在する、あるいは、行為した世界を引きずり出した、その世界。あれは何だったのか、と回想する。幻覚に憑かれる島、村。南島の村、久米島、の太陽は明るい。まぶしすぎる。作者はこれを「なまぐさいけもの」としりぞける。ゆえに「獣」は「けもの」に解体される。「飢え」「なめらか」が逆説的に表明される。現在において村や島は、逆説でなければ語れない。平和だが「怠惰」として、平和だが、共同体の桎梏として、平和だが「処刑場」としての空間にある。太陽はまばゆく、「怠惰な心をやさしくあやめている」。これも逆説だ。「怠惰な心」とは虚無だ。ニヒリズムに類似した心だ。しかし少年のエスプリにニヒリズムがあるわけはないから、言葉を足せば太陽に打ちひしがれた村の空気であり閉じた世界への批判だ。自閉はエスプリに目覚め、突然むきになって「母」と諍い、荒れた感情を癒すために「家を飛び出す」。この光景は近代文学で頻出する、いわゆる自我の目覚め、発露の光景とみえる。「突然」はそうではなく次第に離反するエスプリの表情だろう。「母」は母胎であり、故郷であり、愛憎の自然であり、自立を促す存在だが、少年のエスプリにとって自然、夏、太陽、けもの、母、共同体は受容しながら依拠と同化を拒む対象だ。だから「道は処刑場」になるのだ。視覚を遠近する道が処刑場になるとは、なんという反土着、反風土、反共同、反母郷、反血族の場所なのか。この像の世界は想像ではない。リアルのあった世界、実際の出来ごとの世界、経験の世界だ。
それにしても異郷はまだ
少年の自閉の中で青桃の未熟さをたもち
波の押し返す放心の水際を
しきりに飛翔する白鳥が
徐々に島痛みを深めていた
島に在り 遠さを病むとは
また何と歓喜に近いことか!
今 陽の庭で腕を差しのべると
指の先からそのまま
異郷の想念がはじまる
何のさえぎるものもなく
異郷の夢の漂流物は空を移動する
「異郷」は少年にとって憧憬のようにまだあった。「異郷」を想う思念は近代の主題であり、罠であり、解放であり、希望であり、絶望であり、決別であった。少年の内部は「青桃」のようにまだ未知だ。ならば道は近代の未知だ。何もない島の村にいる自閉少年には躍動する海の波は癒しとなる。波がしぶきをあげ白くなると白鳥のようにみえる。その白鳥が飛翔する。白鳥は少年の魂の比喩だ。その魂の白鳥が「しきりに飛翔する」。だから魂の飛翔を「異郷の想念」にたきつけるようにしなければならない。ここに少年の精神形成の夢の反語が果たされ、ついには、それは「島痛み」として感受される。
離島の島の少年が「島痛み」をもつのは生を自覚し希求するときに出会う運命である。いや必然である。そして苦い。欠乏感、飢餓からの脱出、海の彼方への出航にいかにあこがれたか。島に生まれて島に生きた当事者でなければわからない。「島に在り 遠さを病むとは/また何と歓喜に近いことか!」。これは「ここではない世界」の発見の歓喜、島の少年が通過する彼方への放心の快楽、スキゾ的な感性、解放観念の覚醒の誕生だ。島での自然や伝統と背離する快楽はこの先アイデンティティの放棄となる運命になる。島の現実に覚醒すると未成の絶望を謳うしかない。これは精神、意識の解放を謳った言葉となる。「遠さを病む」ことが救いであり解放であったのは近代の自我文学の始まりに近い。「遠さを病む」とは「ここ」がもはや「ココ」ではないのだ。これは近代の宿命の情感であり、島のポエジー、詩の精神の発生であるともいえる。「遠さ」とはなにか。「異郷」か。そうだったかもしれないし、そうではないかもしれない。異郷=都市=近代、とみるのはまだ早計である。だが少年のころの「異郷」のイメージは残念だが、都市、近代であり、自我の生理からくるあこがれであった。しかし、これは当たっていて、真ではない。到達の遠近の視点がないからだ。移動する自由を確保したグローバル時代の現在では、だれでも移動心を実践できる。東峰夫の「オキナワの少年」のツネヨシ少年が売春屋を経営する親の家から決別するために小舟を盗んで島からの脱出(移動)を企図したのは理由がないわけではない。自閉した生理的な少年の精神解放の欲望を実践した行為だ。ツネヨシが目指したのは都市ではなく、「ここではない、どこか」だった。「こんなところは、もういやだ」と思うのは誰にもある経験であり、脱出を試みるのは生理の経験として誰にもあるはずだ。ツネヨシも島痛みを強烈にもった少年であった。「異郷の想念」「異郷の夢」は「何のさえぎるものもなく/異郷の夢の漂流物は空を移動する」。これは自由への、少年期にある幼い夢想の表現だ。そう、移動だ。移動には強いられた時と憧憬としての移動がある。ここで少年は曖昧な秩序化されたストイシズムを切り捨てる青い力動をもたねばならないし、アドレッセンスの空虚と不安を打ち砕かなければならない。
しきりに太鼓のはじける音がする
コーヒーをかきまぜていると
失語がやすらう傷口が癒える
今日の愉楽は愉楽のまま
少年の陽の庭での
眼にしみる群落のうながす
欲情の破裂をしなやかに躯幹にとじこめて
ひとすじにのびる道を一目散に駆けてくる奴がいる
夜はテーブル珊瑚の淵で赤ダイを釣った少年が
芝生の上で死んだように眠っている
微熱にうるむ肢体を置いたまま
起き上がると すねを洗っていた潮の感触が
真昼の庭で出世以前への回帰をうながした
これは聴覚だ。幻覚だ。ここは(地下)カフェだ。この「太鼓」の音は、村の祭りの音か、エイサーの踊りの音か。太鼓の音は波から転身して、いまや胸を打つ音だ。胸をうたれれば、「失語」ははじけやすらう。「失語」とか「発語」とか、ことばの敏感な感応を体験しているから、カフェの詩人はいま自由な瞬間にいる。なんという衝動か。少年は「失語」に自閉した。癒し、行為、想念、皮膚感覚、が新鮮なまま詩的感覚をたたく。太鼓、コーヒー、失語、群落から「愉楽」「欲望」を想い、少年のイメージを生きる回想を駆ける。赤ダイを釣った少年は自然とともにある。作者なのか。わからない。だがその少年は「眠っている」のだ。「「潮の感触」は自然の感触である。その感覚は「出世以前への回帰」を導き出す。「回帰」だって? 回帰というのは最後の方法ではないか。
………その昔 珊瑚礁を踏んで
向うの島の母へ会いにいったまま渡れずに
夜になって折り返してきた高貴な若者がいた
だがぼくはどこへ帰ればいいのだ
今 異郷に在って帰るところのないぼくは
ときに憑かれるように
北の山村へ車を駆って行くのだ
そこのきりぎしに立って
潮の回帰してゆく
遠い原境を想っている
「………」は折口信夫に関するものなのか、島の伝説なのか定かでない。だが、こんな高貴な若者の「母乞い」はエピファニーにはならない。エピファニーのように啓示を用いたかったろうが、それは「母乞い」に失敗した物語から現在を顕示する必要があったからと思われる。だから作者は現在に戻って「どこへ帰ればいいのだ」というスタンザをつぶやく。これは回帰するトポスが不在であることの表出とみていい。ここで「異郷」とは久米島から離れた沖縄本島の那覇になっていることがわかる。そうか。那覇が「異郷」か。そう、琉球弧にありながら本島以外の島のものにとっては、沖縄本島は「異郷」である。中心である那覇や首里はさらに「異郷」である。琉球弧、ウチナーのなかの「異郷」である。離島と本島に距離があるのは海が隔てる島々の歴史・文化のソウル・トーンがちがうからだ。ソウル・トーンは島の匂いや感触の違いを感受させる。島々の差異は琉球、沖縄、南島という琉球弧語で包括する安易なハイイメージでは語れない。ハイイメージを裂いて中に入らないと、島の距離感や心性のソウル・トーンはわからない。海の彼方には他者を意識させる差異の存在がある。ぼくらはいつもそれを実感してきた。だがそれもポストモダン的にみる必要はない。生の在所を流浪して住みついた場所が那覇であっただけの話だ。那覇にいて「帰るところのないぼく」が肝心だ。つまり詩人は「出自を現在に現出」してもその出自の家や村=というトポスを「帰るところ」ではないとする。だから島には帰らない。出自の久米島は帰るべき場所ではない。本当の詩人にとって「帰る場所」なんてどこにもありやしないというのが真実だ。だから私は清田政信を「本当の詩人」と評価する。この詩が求心的になる頂点の詩句は「潮の回帰してゆく/遠い原境を想っている」とポリフォニーからモノフォニーに収めたところだ。求心の果てに取り出した、この「遠い原境」とはなんだろう。清田は、それになにを見ているのだろうか。ここで次の文章をみる。
「詩の原境とは個人史として言葉もなく生きられる感受性の、遠心と求心への衝迫を二つながら現在の言葉の水準に回復し自覚する謂にほかならない。」(原境への意志、南北3号、1975・11)
こういう言い方を、その詩句に適用してみよう。原境とはあるものではなく、精神でつくるものであり、遠心と求心の両義的な視線からみた不在の原境であるから「不可視の、もうひとつの世界」としての原境へと詩を震わせ、未成のポエジーの闘いを決起することだ。とすれば「潮の回帰してゆく/遠い原境を想っている」は「魂の回帰してゆく/遠い原境を想っている」といいかえてもいい。それがなぜ「北」の「きりぎし」なのか。
清田はかつて「光はいつでも北に湧いた」(辺境、光と風の対話)と書いた。また「身のふり方を案じてつぶやくひとは/みなみへ去るがいい」とも書いた。この北と南へのまなざしは、北が日本で南が南島であることを暗示しているとすれば、ぼくらは北を求望してきたというわけだが、ほんとうに北は光であったのか。北は近代だった。その近代は北からやってきた。「みなみ」は幾人もの北の旅人のおかげで救済されたことがあるのは事実だ。だが、この「みなみ」=沖縄の近代は復帰後、北の本土からのすさまじい資本の投入で、すさまじく変貌、変質してきた。明治から続いた近代の強烈な浸透、本土中央の文化が浸透して「沖縄的なもの」が戦前、戦後復帰前の風俗から衰退するようにみえたが、政治の流動、復帰の決定、沖縄海洋博を契機に本土大企業の電通の戦略で「沖縄的なもの」が全国に宣伝された。が、せいぜい観光程度にしかすぎない。そこで電通はじめ本土の資本、マスメディアはさらなるモメンタムを投入、宣伝し「沖縄ブランド」形成に成功したら、沖縄資本も戦略的に利用し、「沖縄」「おきなわ」「オキナワ」「琉球」「琉球王国」「琉球王朝」「ニライカナイ」「シーサー」「おもろ」…と様々な沖縄的表象を取り出して売りにした。一方、本土側の言論界に基地問題等の沖縄問題を重視する傾向ができ、沖縄言論の欲望の囲い込みを推進し、沖縄の書き手がこれに呼応する言論構造ができあがったし、日本(ヤマト)に相対するかのように琉球回帰願望を持つ者たちが現出し、「沖縄的なもの」の復活を唱え、それは現在、しまくとぅば復興、組踊、琉球舞踊、古典音楽、三線などの伝統芸能や民芸、祭祀、御嶽等の独自文化性の賛美、奨励、首里城再建の興奮という形であらわれている。首里城を「沖縄の象徴」とする汎首里城思想への私の異和感は続くが、こういう傾向から思うことは、これらの文化意識、文化運動は、戦前の日本伝統主義、日本(日本的なるものへの)回帰を標榜した「日本浪漫派」に近いのではないかということである。今の沖縄の文化人、知識人、運動家の大半は「日本浪漫派」の沖縄版「琉球浪漫派」のような意識を形成しているのではないか。「琉球浪漫派」―つまり、近代以前の琉球や沖縄民族文化への回帰、琉球ナショナリズム、伝統を重視する意識の傾向だ。それは昔からあったが、沖縄戦から戦後にかけて経済復興とともに精神復興の形をとってあらわれ、回帰感情から生まれる沖縄アイデンティティと一体化した文化や思想の現出として盛んに露呈している。私はこれを否定はしない。アイデンティティは〈私〉の存在を〈他者〉の存在で自覚するものだから、その相対性をみとめながらも距離をおきつつ、沖縄に生まれた宿命からの自由の形成、その表現、思考の自由な活路を自らに課してやっていくつもりだし、古層を語る書物に近づき引用的に加担するときもある。しかし、流れが(国家)権力化する文化装置に傾くなら反意をもつことを厭わぬつもりだ。「矛盾したものが同居しているのが近代だ」といったのはたしかポール・ヴァレリーだった。「矛盾同居」を今流のいいかたでダイバーシティといってもいい。現代は観念のチャンプリズムにある。
ところで「潮の発作」には「釈迢空に」という献辞がついているのだが、なぜ「釈迢空に」だろう。釈迢空は折口信夫である。なぜ折口信夫ではなく「釈迢空」なのか。釈迢空は折口信夫が歌人の号名として使っているから、清田は、意識的に学者としての折口信夫ではなく、詩人、歌人としての釈迢空をもってきたと思われる。
洋なかの伊平屋の島に
いささかの知り人ありて、
渡り来ぬ。我ただ一人
もの言へど 言もかよわずー
もの言はず居るが さびしさ。
かそかなる家の客座に
うやうやし 我ひとり居る。
賑わえる那覇の湊に、
思ふ子を人にあづけて、
我ひとり 海を越え来ぬ。
そこ故に 時に思ひ出、
あやぶさに 堪えざらむとす。
(「伊平屋の村」)
清田は「折口信夫―」で折口が沖縄の伊平屋島を訪れた時のことを書いた詩を引用して、折口信夫を〈旅人〉と視座し少年の視線で書いている。そこで自身の少年時の自分をからませている。実は折口のこの詩の最後に次の反歌がある。
洋中の島の少年のさびしさを 人に語らば、
さびしからむか
折口信夫は、この孤島に「ひとりの少年」が自分をみつめていたことを知っていた。それを「少年のさびしさ」と歌った。清田の視線は、その少年の視線と折口信夫に憑依している。そして「折口信夫―」で島と近代を関連つけて抒情的な心性で語っている。その抒情は「寂寥」である。寂寥、さびしさ、幽か、静寂………は折口信夫が得意とする歌境の感情である。谷川健一は「折口の民俗学は対立、葛藤、郷愁、疎外をモチーフとするいわば不幸な民俗学」(折口信夫再考)と評したし、古くは杉浦明平が「折口信夫=釈超空」で「ペシミストたるはいうまでもなく、したがって、かれの調べは暗く厭世的で閉じこもって」いるとまでいった。たしかに明るくはない。自殺未遂をしたり、コカインを用いて古代の感覚を呼ぼうとしたり、自身が死者に憑依した小説(死者の書)を書いたり、どこか陰鬱で危ないところがあった。またゲイでもあった。だが古文献を読んで誰も気づかなかった古代の感性をつかむ直観力というものがあった。それが折口信夫の独自性や魅力として評価されたりしている。折口信夫=折口学については古代研究、呪詞、常世、マレビト、など断片的な知識しかもたないのでここで語ることはしない。
近代から古代の感覚へ降りる方法をとった、そんな折口信夫に対する清田の共感は彼の論理からみると少し情緒的であるように思う。
「この少年と旅人の関係は近代の観念から無縁な分だけ、近代の終焉へ向かってあるき出そうとする知の受難と浸透しあっている。近代は古代的な感性から切れることによって、人間が誰とも寂寥を分かち合えない存在であることを証明し、もはや寂寥をも明晰にきわめることによってすべての悲劇性からみはなされている。」
「折口信夫の声を低くした歌い口に私は二十年間の浪費のあとやっと親和をもつようになった。」
「過剰であることはそれだけでは何ものでもない。そこには遠近をひらく精神の力がない。彼方へ、未知へ存在を変貌させるきっかけがない。折口信夫は彼方へ憑かれた精神であり、人を彼方へさそうものは簡単なおどろきであり、宇宙へつなぐ魂の原型だということを知悉していた詩人だ。」
「潮の発作」からこの「折口信夫にかかわりつつ」までの間の距離に注目したい。「潮の発作」では釈迢空を意識して出自と少年の回想から「原境への回帰」というモノフォニーを打ち出したが、この論では別の注目すべきことを言っている。近代は「平面」であり「過剰」であり「浪費」であり、「折口信夫の声を低くした歌い口」に「やっと自分は親和をもつようになった」という言い方である。過剰、とは何をいっているのか。観念(知)の過剰を言っていると思うが、私は、それより過剰と切り捨てがからむ複雑系社会であり、ヴァレリーのいう「矛盾同居」の認識が近代(現代)に生きる我々を〈気づきの生〉に向かわせていると思う。資本主義が膨張した過剰は欠乏と並立しながらも、社会的ホメオスタシスを保っている。グローバル化した格差社会の顕現、世界に不満や混乱が渦巻いても、なお崩壊しないでいるのはその例だ。
支配的言説と本質を示唆する書物、語法を相対化しなければ〈バリアント化する現代〉という時代を読むことはできない。それを過剰言説に巻き込まれているといってもいい。私自身闇の中の明晰さを求めて現代の様々な心的現象の表現言語、狂気の問題など色々と思索を試行しているつもりだ。
ここで大岡信の「あてどない夢の過剰が、ひとつの愛から夢をうばった」という有名な詩句を思い出す。清田が折口信夫の「単純さ」や「簡単なおどろき」への感受性の志向をだしているのはなぜなのか。発語、失語、内域、原域、幻域といった不可視の求心するものをずっと主張した清田が時代の変貌と変質を感受していちはやく大岡の「あたしも何とか身のふり方を決めなくちゃあ」というパラグラフを「辺境」という作品に引用したのは、こういうことを言うためであったのだろうか。
『あんやんばまん 3号』(清田政信研究会、2021年10月発行) より転載















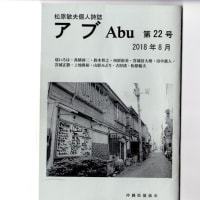
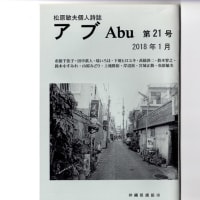


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます