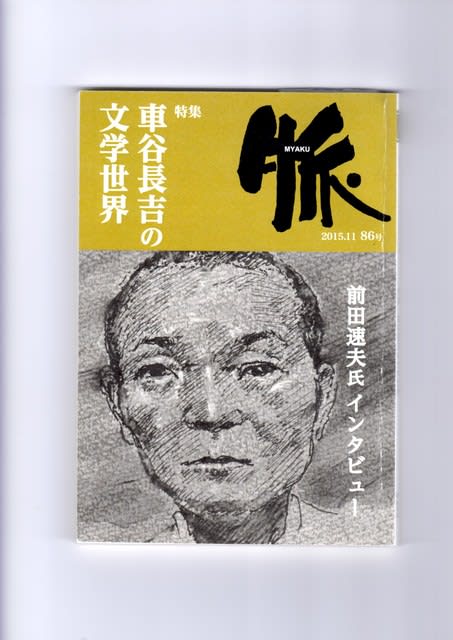
車谷長吉という作家を知ったのは、吉本隆明の『現在はどこにあるか』のなかの「私小説は悪に耐えるか」という文章でだった。私は近代文学、戦後文学、外国文学など純文学(こういう言い方は嫌いだが)の関心のある人以外はあまり読まない。一時期、推理小説に凝っているときがあったが今は大衆小説はほとんど読まない。吉本隆明の文章で、こういう作家がいるということを知って、関心をもった。詩人の高橋順子と結婚した作家であることも知って野次馬的になった。といっても『盬壺の匙』から『赤目四十八瀧心中未遂』ぐらいまでを読んで、そこで私の車谷長吉は終わっていた。
『脈』編集の比嘉加津夫さんから車谷長吉について何か書かないかと誘われなければ再読することはなかっただろう。今回、小説、エッセイ、随筆などにできるだけ目を通し、改めて読んだが、見方がかわっていくのを感じた。初期のころの車谷長吉にはなにか文士という切迫した凄みのようなものを感じたが、いろんな賞を受賞して文壇の住人=作家になったころというか、結婚して〈安定的生活の中の浮遊する自分〉を題材にしたころから、どうもこの作家の書くものは緩慢になってしまっているなという印象をもった。最後の私小説集である『飆風』まではいいが、聞き書き小説である『灘の男』あたりを読んだらルポ的な文章でつまらなかった。
車谷長吉の書く小説は出自とその血族、親族の生と死、村の人間、都会の落ちこぼれのような自意識、社会の底辺をさまよった経験や生活を語っているあたりがよかった。小説的な語りの印象というか読後に印象に残る文章が随所にあった。経歴は車谷長吉文学の武器であるが、その後あまりにそれに依りすぎて単純再生産の商品化した匂いがあって、そこで停滞しているなと感じてしまった。このことは小説作品以外に随筆(エッセイ)的な文章が多い作家であることでもわかる。
私は、『盬壺の匙』に書いた「あとがき」にある次の文章で車谷長吉という作家の像を形成していた。
「詩や小説を書くことは救済の装置であると同時に、一つの悪である。ことにも私小説をひさぐことは、いわば女が春をひさぐに似たことであって、私はこの二十年余の間、ここに録した文章を書きながら、心にあるむごさを感じ続けて来た。併しにも拘わらず書きつづけて来たのは、書くことが私にはただ一つの救いであったからである。凡て生前の遺稿として書いた。書くことはまた一つの狂気である。この二十数年の間に世の中に行なわれる言説は大きな変容を遂げ、その過程において私小説は毒虫のごとく忌まれ、さげすみを受けてきた。そのような言説をなす人には、それはそれなりの思い上がった理屈があるのであるが、私はそのような言説に触れるたびに、ざまァ見やがれ、と思ってきた。」(「盬壺の匙」あとがき)
この文章を読んで、そうだ、そうだ、文学する者は、こういう文学精神がなければならぬと拍手したのを思い出している。ここに車谷長吉という作家の存在理由があると思ったのだ。これは詩的精神に似ているな、外せないなと思った。のちに語った次のような文章とあわせて読むと立体的にわかってくる。
「私は二十五歳の秋、会社員を辞した。その時点での第一志望は、非僧非俗の世捨人として生きていくことだった。修行僧になれば、托鉢なり何なりして飯が喰うて行けるのであるが、私の場合はあくまで非僧非俗が願いだったから、下宿に閉じ籠もって小説原稿を書く以外に途がなく、併しそれも数年で下宿代が払えない身となり、つまり生活が破綻して、以後は関西へ帰って、旅館の下足番、料理場の下働きとして九年を過ごした。丸坊主、下駄履き、風呂敷荷物一つ、無一物で、タコ部屋からタコ部屋を転々とする、漂流の九年間だった。」(「もう人間ではいたくないな」―『阿呆者』所収)
文学を書くことは救済の装置である、自分は、生き方として「非僧非俗」の生き方を願った、喰うために作家になる以外道はなかった、しかし「書いたもの」は「心にむごさ」を感じるようなものであった、それは救いであったが、狂気でもあった、そんなふうにせっぱづまった気持ちで書いているのに、世の主流の小説観念は私小説を嫌っていた、だが俺はおめえらのいうとおりにはしないぞ、ざまあみやがれ、だ。というのが車谷長吉の立ち位置であった。書くことと生きることとが一致している見事な主張だ。ブラボー、いいぞ、長吉!
車谷長吉が文学活動を開始したころの状況について私流の身勝手知識で小説の雰囲気を思い出してみる。昭和51(1976)年に村上龍の「限りなく透明に近いブルー」が芥川賞を受賞し、爆発的に売れ、1977年、三田誠広「僕って何」が芥川賞、昭和56(1981)年には田中康夫の「なんとなく、クリスタル」が文芸賞からこれまた爆発的ヒットし、昭和62年(1987)年に村上春樹の「ノルウエイの森」が発表されて、これも社会現象までなった。こういう代表的な作品の背景をみればわかるとおり、都会の青春小説が隆盛している。この時期は高度経済成長、1億総中流、消費社会、といった社会の安定化に市民の個人化が進み、好みの生活で生きるような時代であった。その流れのなかで日本の文学は昭和文学の終焉時期を迎え平成文学時代に突入したとみることができる。
そんな時代にさきにあげた創作(小説)精神というか、文学精神をもっていた作家がいたということに私は、日本の現代文学は捨てたもんじゃないなという感想をもっていた。この「あとがき」に書いている大意は、私の文学についての考え方にも通じるものがあった。「文学を書くことは救済である」「書くことは狂気である」という言い方は、平成時代の今日ではおおげさに聞こえるかもしれないし、あるいは、アマチュア的な思い込みのように聞こえるかもしれないが、文学するものの魂を充分に触発して逆に「ほっと」させたのだ。
村上龍や村上春樹、田中康夫らの書いたものはさっきもいったように都市型文学である。都市のなかの中流の市民生活で浮遊する都市型人間の物語を都会風俗豊かに空間化することに終始している。そこに時代的感性を取り込むのがうまい。そのために時流の若者の読者層がいる。そして彼らは最初からプロの作家然としていた。
これに比べて、車谷長吉の読者層は誰であろう。おそらく、若者ではないだろう。では誰か。中年の会社員か。会社員なら司馬遼太郎やらではないか。こういう問いがでるほど、車谷長吉は時代にのった作家ではなかった。車谷長吉の小説世界は端的にいって生活者の素材や風景が異様に重たく暗くでている。こういう作品は時代の感覚や風俗好みの生活感のない都市型若者には受けない。つまり、マイナー作家に甘んじるしかない。
車谷長吉の経歴をみてみる。高利貸しの祖母、その娘が母となって、父は吃りで発狂、叔父は自殺、村で初めて東京の大学に進学したいわば秀才、慶応大学卒、東京の中小広告会社就職、右翼が経営する新左翼系雑誌の編輯記者、女性へのストーカー、坊主頭に頭陀袋、旅館の下足番、タコ部屋を渡り住み、料理屋の下働き、3名の人妻との姦通、三島由紀夫賞、直木賞、元ミス駒場の美人詩人と結婚、都下に一軒家を持つ…………こういう個人史を羅列するとある種の不幸、底辺、やばい生活、上向きのイメージができあがる。
作家歴を重ねると、昭和47(1972)年に「なんまんだあ絵」(新潮新人賞候補)で文壇的出発し、昭和56(1981)年に「萬蔵の場合」(芥川賞候補)、昭和60(1985)年に「吃りの父が歌った軍歌」、平成4(1992)年に『盬壺の匙』(三島由紀夫賞)、を発表、平成7年(1995)の「漂流物」は芥川賞候補になるがまた落選する、しかし平林たい子文学賞を受賞。平成10(1999)年に『赤目四十八瀧心中未遂』でついに直木賞をとって名実ともに作家となる。
ところで車谷長吉はいわゆる私小説作家ではない。実生活だけを記述する私小説家ではない。彼はこういっている。
「そもそも、私小説を書くことは罪深い振る舞いである。悪である。業である。私はそれを覚悟した上でなしているのだが、併し私のように反時代的な毒虫のごとき私小説を書いていると、まず一家眷属、すなわち血族の者たちに忌み嫌われている。新潮平成六年八月号に「抜髪」を発表し、それが週刊新潮で大きく喧伝された時は、田舎のお袋は同じ村内の親戚の者(母の弟)に呶鳴り込まれ、押し入れの中に三日間隠れていた。以後、お袋は自分の里へ出入り禁止の処分である。私は腸が引き裂かれるような思いがするのである。併しそれでも書かないではいられないのが小説である。難儀なことである。」(文士の業)
「二十五歳で文壇に出て以来、私の書くものの四割ぐらいは私小説だった。いまは六十一歳である。当時は、私小説を撲滅しなければ、日本の小説はよくならない、という議論が中心で、極端に言えばもう私小説は瀕死の状態だと言われていた。それが文壇の時流だった。何でも人の言うことには疑問を持ち、反時代的に生きたい私は、私小説で名をあげようと決心していた。そして最初に書いたのが「なんまんだあ絵」だった。これは田舎の祖母の死について書いた小説だった。小説であるから、内容は虚実皮膜の間にあるものだった。これがその後の私の私小説の方法となった。」(はじめての聞き書き小説―『阿呆者』収録)
「虚実皮膜の間」という言葉がでてきたが、これは車谷長吉の作品を理解するのに大事なキーワードである。この言葉は、「読むことと書くこと」という講演でも車谷自身が小説の書き方としてネタばらしている。
小説は事実だけをいうものではない、「私たちは郊外のレストランへ行って、牛肉のステーキを喰った。」という文章はふつうの日常、作文であり、「私たちは郊外のレストランへ行って、虎の肉を喰った。」と書くことによって文学になる、日常のありふれたものを「非日常」「反世間の常識」とすることが文学である、と。こういう言い方は実に詩の書き方にも通用する。現実を比喩やイメージで転換する方法のことなのである。
「近松門左衛門は∧文学における真は虚実皮膜の間にある∨と言うた。この「虚実」とは、事実そのままかそうでないか、ということだけではない。そもそも文学においては、「虚」ということが二重構造になっていることが、まぎらわしいのですが、一つは事実であるかないか、事実でないというのは「嘘」であるから、それ自体一つの「虚」であるが、さらにその奥に、「虎の肉を喰った。」というような非日常性、非現実性という「虚」が必要なのです。」(読むことと書くこと、講演、平成12年3月、三田文学平成13年冬季号、『銭金について』収録)
こういう言い方は、平成13年11月、藤村記念館での講演「島崎藤村の憂鬱」にもある。
車谷長吉はここで自分にとって私小説というのは虚実の物語であるということを白状している。とするなら、のちに書いた『贋世捨人』なども自伝的小説だが、虚実ごとだと思ったら、そう読めばいい、ということになる。自分の体験や環境をモデルにして心理と関係とを嘘をまじえて自在に書いていく。私は車谷長吉がいう「虚実皮膜」の方法を知って私(わたくし)小説の読み方を教えてもらった。読者は作家が書くものを実際にあったことを書いた小説だという思い込みで、読んではいけない、ということである。
私小説を読むとき、読者は作家の暮らしの実際を知らないから、書くものをまるで事実であるかのように読んでいる。車谷長吉の方法は実際のモデルがあって実際の出来事があって、それを実とすれば、ちがうこと(ひと)=虚を入れ込んで物語をふくらませていると告白しているのである。
私もだまされるところだった。吉本隆明が書いている「私小説は悪に耐えるか」を読んだあと、作品をすっかり信じ切ってしまったのが私自身のお粗末だった。
吉本隆明が書いたそれは平成6年12月であるから、そのころと以後の作品をくらべてみると今はもう車谷長吉が「私小説作家ではない」ということは明白な事実である。平成10年に出した『赤目四十八瀧心中未遂』は架空の人物が多く入っていることを車谷長吉自身が後に語っている。(この作品を書くにあたって3名の人妻との姦通体験が「藝のこやし」になったと「現代に愛は成立するか」で書いている。)
若い頃、文学仲間のある友人が、ある東京の有名な女流詩人が大酒のみで男どもと勝負するように煙草すぱすぱ、飲み屋で大酒飲んでよく悪態をついて男に暴力をふるったり、通りの穴におちて大けがをした、あの女流詩人はそういう女らしいよ、と話を聞かされていたが、実際は、そういう話も尾ひれがついて大げさに伝説的に語られるところがあって流布したものだった。ひとの話はうわさが半分は入っておもしろおかしくいわれることが通説なのに、まじめな私はすっかり信じ切ってしまうところがあって、「らしいよ」なのに「そうだ」になってしまう。虚像を信じ込んでしまうところがダメなところで、大人になっていなかった。などと反省する。
私小説が「罪ごと」や「悪ごと」を描くものであるから忌み嫌われるというのは、あきらかにしてはいけない実生活を書くからである。つまり「恥」として世間に隠しておきたい世界をあばくからである。
ここで思い出すのは、島尾敏雄の「病妻もの」である。『死の棘』は夫婦の家庭生活の実際のすさまじい情景を書いていて、「むごさ」がありながら、「祈り」の姿がある。しかし車谷長吉にはその「祈り」がない。車谷の人間への見方、感受性が、人間の救いがたいものをみているからである。車谷長吉の心の眼は俗生活から離れたところにある。しかし島尾敏雄は俗生活のなかで病気の妻と真摯に対峙していた。そこは車谷長吉と島尾敏雄のちがいである。
また、似ているような作家に、漫画家、つげ義春がいる。つげは「自閉的」「人間の弱さ」「貧しさ」「夢」というものを題材にしている。私はつげ義春が好きで夢中になって読んでいた時期がある。現実の日常風景に夢的な発想を持ち込んで描いた漫画は実に面白かったし、つげの方法は沖縄の風土にもってきたらすごく面白いだろうな、いつか試してみたいな思ったりしている。つげと比べると車谷長吉の世界はどうだろう。現実に対して仏教的観念を対置しすぎではないだろうか。
現在の時点で私小説をみると『苦役列車』で芥川賞をとった西村賢太はどうだ。車谷長吉にも不幸はあるが、車谷は日本の地方(兵庫県飾磨)の旧地主階級層で戦後解体された中流農家であったようである。西村賢太は父の犯罪ごとで社会から疎外された貧困家庭で生まれて、それを全身で受けて社会にむかって恥じることなく堂々として生きている。救いのないような生活をしているのは、西村賢太のほうが上だろう。超越しているといってもいい。繊細さは車谷長吉、リアルの骨太さは西村賢太といおうか。
それともうひとり忘れてはならない作家がいる。中上健次である。中上は1975年(昭和50年)に、『岬』で芥川賞を受賞している。車谷長吉よりひとつ下。1946年生まれ。紀州の路地の作家、「土俗的な作風」といわれる。私は中上健次の書くものには、個人的に強い関心を持っている。この作家は文学空間が大きく底の深いものをもっているなと思わせるのだ。それが何であるかはいずれ取り組みたいと思っている。
ところで、車谷長吉は高校生のころ夏目漱石を読んで文士になりたいと思い、社会に出てからは「世捨人」のように生きたいと思って作家になったといっている。それは西行の影響だと何度もいっている。ここは車谷文学読解の重要なところである。なぜなら車谷長吉は、いわば「世捨人になりたい」にはじまって「世捨人になれなかった」で終わっている作家だからだ。つまり西行的な生き方への憧憬と挫折があるのである。
「私が小説原稿を書きはじめたのは、二十五歳の時だった。三島由紀夫の自刃に触発されたことも深かったが、創元文庫の尾山篤二朗校注「西行法師全歌集」を読んで「世捨て」という生き方に強く心を奪われたのである。つまり発心したのだった。」(金と文学)
「私は二十五歳の時、創元文庫「西行法師全歌集」を読んで、自分も世捨人になりたいと思うた。ただその時は、西行が紀州に広大な荘園を有した金持ちであることは知らなかったので、誰でも世捨人になれるもんだと思うていた。ところが銭がなければ、世捨人にはなれないのである。西行はすべてを捨てたと言われているけれども、広大な荘園だけは捨てなかった。当時においても、銭が命の世の中であったから。」(西行―『阿呆者』所収)
「西行の生きた時代においては、荘園に縛りつけられている百姓などは、人間の内には数えられていなかった。……略…………世捨てというのは、単に京都の貴族社会を捨てるというだけのことであって、荘園の百姓をも含めた世の中全体を捨てるという意味ではなかった。当時は田舎の無学文盲な百姓などは人間の内には数えられていなかったので、都では貴族を捨てて世捨人になることは大変なことだと思われていたのである。」(同)
「西行はうちのお袋が言うたように、荘園の百姓に働かせておいて、その上がりで自分は好き勝手に行動し、無一文が一番ええ、というような歌を詠んだ男である。下司などは、人間の内には算えていなかったのだろう。また長明も兼行も貧乏が好きで、そういう窮乏生活を経験した人だが、併しこの人たちも下級貴族であって、してみれば、下級とはいえ、貴族である以上、なにがしかの社領からの上がりはあったのだ。だから飢え死ぬところまではいかなかった。芭蕉は全国各地の弟子に連句。発句の教授をすることで、謝礼を受け取っていた。
こう見てくると、これらの人たちも、その言葉は兎も角、生活面ではみな贋世捨人だったのではないか。一休が女にうつつを抜かしたように。」 (「贋世捨人」)
車谷長吉には「母」(祖母を含めて)の影響が強い。(同じ重さで弟の存在がある。「吃りの父が歌った軍歌」は弟について書いたところが重要なポイントである。)車谷長吉は深層心理的には「母なるもの」への畏怖と従属心があるように思う。西行に対して、現実の側から批判した母がいる。そう諭した母は息子の「西行熱」をさまそうとして立派である。リアリスト、生活者の視点で文学を見定めた評価は世の文学史家や評論家を一蹴して立派である。
車谷長吉が西行を読んでこんな生き方もあるのかと感銘して、自分も「世捨人」になりたいと願う。しかし、長吉よ、それは、観念的で甘いんじゃないの、というのが生活者の母のやさしい警告である。母のその論理は実生活を知悉したものの考えであり、生活から発した論理は誰も否定できないし反抗もできない。そのせいか、のちに車谷自身も覚めて西行の世捨てを辛辣にいっている。車谷長吉にとって作家業は、実生活社会で世捨人に近い生活ができる最適な職業でもあった。だから「贋世捨人」=作家になることで自己肯定して生きる道を選んだのである。私は、これほど作家になることを説明した作家をほかに知らない。
西行については小林秀雄の「西行」や吉本隆明の「西行論」があるが、これには西行が世捨人であったことは重視していない。歌を書いたことが「西行」の西行たるゆえんであるという感じである。西行は、世捨人ではなく「出家遁世」なのである。小林秀雄の「西行」のなかの一節。
「西行は何故出家したか、幸いその原因については、大いに研究の余地あるらしく、西行研究家達は多忙なのであるが、僕には興味のない事だ。およそ詩人を解するには、その努めて現そうとしたところを極めるがよろしく、努めて忘れようとし隠そうとしたところを詮索したとて、何が得られるものではない。」
ああ、小林秀雄という人はこういう人なんだな。人の境涯なんかには興味がない。人がどんな生活、境遇にあろうとも俺には関心がねえ、人間の価値はその人が作り出したものにある、かれが何を考えているかにある、ということなのだろう。「努めて忘れようとし隠そうとしたところ」を暴くのは意味がないという感じである。小林秀雄が断定的にみているのは、「西行は生得の歌人であった」というこの一点である。こういういいかたは、中原中也に対しての言い方でもあった。詩人や歌人は詩歌で語るからこそ存在する。そして「生得の」詩人こそが語るに値する。これが小林の方法である。小林の見方は誤っていないが、どうも天性重視でつまらない。あと一声が足りないのである。才能があろうがなかろうが、人は、自分の在り方として文学を選ぶ場合もあるのだ。そこは認めなければならない。小林秀雄の近代批評とは天才の素質をもった文学者や芸術家の成果と苦悩を煮詰めたことではないか。「努めて忘れようとし隠そうとしたところ」は歌で読め。作品で読め。言葉をまわしこめ。それはわかるが。………車谷長吉は小林秀雄の「西行」も読んでいたはずだが、その文学芸術主義的な西行観になんとも思わなかったのか。
小林秀雄は車谷長吉に興味を持っていたらしい。おそらく車谷長吉の小説をほめた白州正子(小林秀雄の遠縁にあたる)の影響であろう。こういう逸話がある。自伝的な小説『贋世捨人』のなかで、車谷長吉が芥川賞候補にあがったが落選した選考会の日に小林秀雄から電話が掛かってきて、「僕はね、新橋の吉野屋で呑みながら、文藝春秋からきみの朗報が入るのを待っていたんだよ。馬鹿ッ。」と言ったという。小林秀雄がほんとにそういったか。それは確認できない。だがそういう人だろうな、という感じはなんとなくある。小林秀雄という批評家は自分がそう思っている確信がはずれたとき、すごく機嫌が悪くなる人じゃないか。もちろん私は実際あっていないから知らない。しかし、彼の講演録や批評文を聞いたり読んだりすると自信たっぷりに自分を保つその姿勢がある人という印象があるから、そう感じるのである。
西行が世を捨てたのは真実か。たしかに西行にとっての「世」は武家や貴族階級の社会であって、それを捨てただけの話ではないか。かれがどんな歌を歌ったとしても、その背後を考えると庶民(農民)とはやはりちがうなと冷たく覚めてしまう。ほんとうに世を捨てたのではない。出家しただけである。つまり、地位も名誉もいりませんと言っただけのはなしである。かれのそのあとの歌は、その弁明の歌であるのではないか。西行にとって「世」というのは「世間」のことではないことはあきらかである。車谷長吉もそこに気づいたのである。
小林秀雄は西行の歌は叙情詩でも叙事詩でもなく思想詩である、とその「西行」のなかでいっているが、世に出ることのない民衆にはまったく無縁の話である。それを後世のエリート文学者や学者が、自分たちだけの〈世〉を作り、無常観、仏語的に美しく精神的に解釈して、すごい歌人だとはやしたてる。小林秀雄の「西行」は最たるものだ。私は小林秀雄の知性をたいそうなものと思うが、解釈の立ち位置を疑問に思う。その理由は前に書いた。かれの『近代絵画』や「ゴッホの手紙」はすごみのある文章であるし私も影響を受けた。かれの精神というものに対する畏怖のこころは学ぶものがある。小林秀雄は絵に対しても視る人よりも読む人だった。焼き物でも視るよりも読む人だった。それが小林秀雄的である。独特な見方はだから視ることを超えて読むところにあったのである、そこが小林秀雄のすごいところだと私は思っている。
車谷長吉は西行の影響を受けて世捨人になることを志したが、なりきれず、贋世捨人=作家となった。そのあと、かれは無常観と仏道を強烈に意識した。そしてつぎに関心を深めたのは、「つれづれ草」の吉田兼好である。兼行は世捨人というより、隠遁者であったから、そのスタイルが自分にあうと思ったのだろう。兼行について書いた文章が多くなっているのは、西行くずれの証拠である。
車谷長吉は文壇社会で辛酸なめながらも出世した成功人であった。二度も芥川賞の候補にあがりながら、かなわず『赤目四十八瀧心中未遂』でついに直木賞をとって、自他とも認める作家となった。つまり「喰っていけるようになった」。俗世間の利益追求の「うす汚い金」にまみれた世界で生きなくてすんだ。
小説づくりは巧い。母はおしゃべりな人だったというがその血を受け継ぐ車谷長吉も記憶の良さと語りのうまさがある作家でもある。深沢七郎の「楢山節考」に影響受けて書いたと思われる「なんまんだあ絵」や「漂流物」は登場人物が長々としゃべる話がでてくる。この「しゃべりもの」という手法は車谷長吉の特徴である。ドストエフスキーの小説にもそういう長々と「しゃべる」人物が出てくるが、読者を退屈させないのは相当工夫がいる。
『盬壺の匙』の冒頭の文章。
「今年の夏は、私は七年ぶりに狂人の父に逢いに行った。その時、母から『去年の夏、宏ちゃんの三十三回忌をした。』と聞いた。宏ちゃん、というのは私の母の次弟で、私には叔父にあたる人であるが、その人のことを、私は「宏之兄ちゃん。」と呼びながら育った。……略…………
宏之叔父は昭和三十二年五月二十二日の午前、古い納屋の梁に粗縄を掛けて自殺した。享年二十一。私が小学六年生の時のことだった。」
「狂人の父」という眼をひく言葉を最初にガツンと出している。ところが、この小説、内容の展開は、狂人の父に関するものではなく、自殺した叔父の「宏之」についてのことである。内容を読んでいくと父のことがあまり出ず不自然だなと思う。おそらく、作者は、書きあげてから後で、インパクトを、つまり「非日常」を与えるために、「狂人の父」を出したと推測する。こういう異常性を出すことで、作品に高揚感を与え、読者が飛びつく計算が入っている。言葉遣いにも独特さの工夫がある。たとえば「思った」を「思うた」、セックスを「まぐわい」、妻を「嫁はん」、トイレを「便所」、下着を「下穿き」、美人を「別嬪」など………。車谷長吉流というか、伝統的な日本語の言い方にこだわる姿勢というのがある。ここには近代嫌いの車谷長吉がいる。
『贋世捨人』は面白かった。車谷長吉の書くものには、実名で登場するひとたちが多い。高橋順子、小林秀雄もそうだが、辻邦生、川村二郎、竹内好、吉本隆明、大江健三郎、保坂和志、陳舜臣………………。
60年代から80年代にかけて出ていた「現代の眼」という雑誌を出していた現代評論社のオーナーが、実は右翼の人であったということが書かれているのを知って、驚いてしまった。その筋の人は知っていただろうが、わたしははじめて知って驚いたのである。この雑誌はいわゆる新左翼系、反体制、反権力を標榜した言論誌で書き手も当時のそうそうたる人たちが書いていた。私もときどき購入して読んでいた。その「現代の眼」編集部に車谷長吉は勤めていたというのである。その社内の人間模様もリアルで面白かった。
車谷長吉はやはり「捨て身の作家」であった。「人の顰蹙を買う作家になった」(「まさか」)と自らを語っているが、『贋世捨人』の最後にある次の文章。
「この死を機に、愚図の私はようやく、ふたたび東京へ出て行く決心を固めた。非僧非俗の贋世捨人として生きていく道は、どうあっても文士になるほかに方法がないと思うた。私の目の前には陳舜臣氏の虚ろな口が大きく開いていた。あの虚ろな口が、つまり小説家だった。私はあの口へ入っていくのだ。
私の手許には、二萬四千円しか現金がなかった。それが私の全財産だった。八月四日、その金を握って、私は東京へ仕事を捜しに行くべく、姫路駅から普通電車に乗った。弟にもらった萬年筆一本と、粟田口近江守忠綱の匕首をふところに服んで。いよいよとなったら、匕首で首の頸動脈を切って、自決する覚悟だった。
電車の窓に、猛夏の播州平野が遠ざかって行った。」
ここには、まさしく「捨て身」になって作家(文士)になる道に生きようとする作者の決意が描かれている。「この死」とはこの年、車谷長吉と同じ38歳で心筋梗塞で死んだ従兄の死のことで、「陳舜臣氏の虚ろな口」とは陳舜臣が料理屋で小説家は奥歯に力をこめて書く仕事だから奥歯が殆どなくなって虚ろな口になったと言っているのを聞いた経験を言っている。「匕首」をしのばせて作家になれなかったら、それで自決するんだという、なんともカッコつけたなと思わせる。(嫁はんに捨てられたら自殺するつもりでいると、どこかで書いてもいる。)車谷長吉は自らの全身の生き方を「捨て身」のところまで追い込んでいった作家であったのだ。ほかの平均的な作家志望者なら「ダメだったら、ほかの仕事みつけてはたらくさ」ぐらいの適当な気概が関の山だろう。
こういう逸話を書いている。芥川賞候補になった選考会で落選して、落胆に逆憤して、九人の選考委員を呪い殺してやるつもりで金物屋で五寸釘を九本求めた。そして―
「天祖神社は鬱蒼とした樫や公孫樹の奥に鎮まっていた。あたりは深い闇である。私は公孫樹の巨木に人形を当てると、その心臓に五寸釘を突き立て、金槌で打ち込んだ。金槌が釘の頭を打つ音が、深夜の森に木霊した。一枚終わると、また次ぎと、『死ねッ。』と心に念じながら、打ち込んでいった。打ち終わると、全身にじっとり冷たい汗をかいていた。全身に憎悪の血が逆流した。」(「変」―『金輪際』所収)
こういう描写は「虚」であったとしても、怨念まみれた鬼気があってすごいな、と思う。こういう感情は「捨て身」でなければ出てこないだろう。ところが、作家登竜門の直木賞をもらって文壇人生活が板についた後に書いた「文士の生き方」では「文士はあんまりいいものではないな」という不満をこぼしている。実際そうかもしれない。しかし、なんと贅沢なことか。
車谷長吉は無名時代、辛酸なめたかもしれないが、ある面で恵まれていたなあという感じを与える。大手出版社の新潮社や文藝春秋社の雑誌編集者が関西まで訪ねてきて、作品を書くようにすすめるところがある。そのあとも何度も書け書けと尻を叩かれる。書いても書いても直し直しが入っていやになるところがあるが、しかし、無名の書き手からみると、そういうふうに有名文芸雑誌の編集者が目をつけてくれるのは、うらやましいんじゃないか。沖縄には東京に住まずに地元で書く器用なプロ作家がいるが、ほかにもプロの作家を目指している無名のひとは多い。だが大手の雑誌の編集者から書くように奨められるひとは、ひとりをのぞいてほとんどいないんじゃないだろうか。中央文壇に取り上げられず孤独な境遇でしこしこと作品を書き、ローカル文壇や同人誌やらに発表しているのが現状である。
(「脈」86号―特集 車谷長吉の文学世界 2015.11 に書いたもの再掲載)















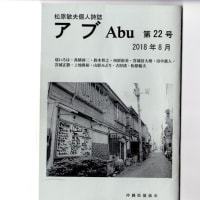
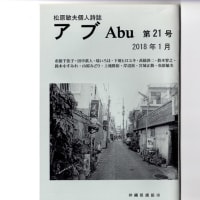



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます