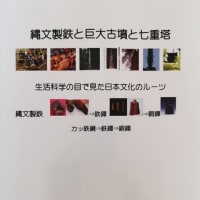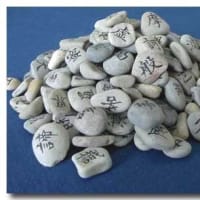奈良の都は「緑色の瓦寺院が美しい紀元前1000年頃の古代都市」だった
・天平の甍・「青に良し奈良の都は咲く花の匂うがごとく今盛りなり」
生活科学の目で見た超古代史・2017・12・5・百瀬高子瓦・
「天平の甍」は有名な井上康の歴史小説タイトルだが時は奈良時代・鑑真和尚が唐から13年?掛けて日本に仏教を広めるために渡来し唐招提寺建立した話だが唐招提寺で緑釉薬の瓦が出土している上に単なる緑色瓦ではなく二色の奈良三彩とか奈良二彩とかいう手の込んだ波状紋緑釉瓦が出土している。
・其処でネットで緑釉陶器や緑釉瓦を調べたら京都西大寺とか仁和寺とか動画のように彼方此方から緑釉瓦が出土している。緑色の釉薬は鉛で彩色する。鉛は低温溶解鉱物で400℃程度で溶解するという。400℃程度は焚火の発火点が350℃位と記憶するから焚火程度の温度で緑色の土器は焼成できる。この事実は緑釉陶器・瓦は縄文時代の産物と言えるのではないか。縄文土器は焚火の7ー800℃程度で焼成したと言えるので、焚火程度の温度で焼ける緑釉陶器は鉛含有率の高い地域の土で作れば土器は縄文時代に当然焼かれていた事が考えられる。
・そしてその地域が諏訪の縄文繁栄地域の諏訪・岡谷地域の丘を一つ越えた隣の塩尻・松本地域の土壌は鉛含有率が高く、今でも松本の土では土器が焼けないと言われている。形成した土器を焼き始めると溶けて、土器の形にならないと聞いた。鉛含有率が高いからこその自然現象だ。そして多くの緑釉陶器が出土している。そして諏訪地域ではなかった銅鏡の八陵鏡や後には銅鐸なども出土している。
・以上の事から鉛を釉薬にした土器が作られるようになっているが、その時代が、松本市東山沿いの縄文中期後半の土器が出土している地域の遺跡だという事。故に鉛の緑色の美しい土器は縄文中期後半から後期始めには作られ始めたと推定できる。
・さて天平の甍だが、奈良とか京都などでこの緑釉瓦が多く出土しているのは寺院だけでなく都城と言える建造物からも出土しているので、緑色瓦の文化時代の存在が推定できる。奈良・京都では紀元前1000年(今から3000年前)頃の当時珍しい寺院など屋根に美しい緑色の瓦が並び、都を彩っていた事が考えられる。
・鉛釉は低温溶解だから土器は水の浸透は防止できるが土師器より弱い土器と言える。同じ時代より以前から炭による黒色土器が存在し、共伴出土から見ると赤彩土器は少し以前に主力のあった土器のようだ。黒色土器は見た目が悪い。しかし黒色土器の瓦も赤彩土器の瓦も存在する。勢力の違いだろうか。各色の瓦は近似時代の文化だったことが考えられる。
・ただ緑色の釉薬は高温で銅の場合もある。銅を熔解できるのは900℃位の高温が必要だから、銅鏡時代になれば銅釉の青い瓦は焼かれたかもしれないから、須恵器や銅の時代になると鉛釉の瓦は焼かれなかったのではないかと推定できる。だから奈良三彩とか緑釉瓦の時代は長くは続かなかったと推定できる。
・仏教伝来が奈良時代だと言う常識だが、今まで書いたり動画にしてきたように原始仏教は縄文後期には松本や塩尻で生まれていた。瓦塔の出土や古代瓦や伝承等で、また日本最古の信仰対象の善光寺出土瓦にも緑釉瓦、赤い瓦等が存在している。以上から現実に「青に良し奈良の都は咲く花の匂うがごとく今盛りなり」の時代は紀元前1000年頃(今から3000年前頃)の時代だったと言える。
「天平の甍」のタイトルで青い瓦の古代都市の動画を配信しました。60番目位にあるので見て下さい。