島根郷土芸能舞台(島根・神話博しまね しまね魅力発信ステージ)
古代出雲歴史博物館のサイトによれば、島根県には神楽を伝える団体が250もあるのだとか。
となると、神話博期間中、連日神楽のステージがあっても出演者は日替わりで、同じ団体が何日もつとめるということはなさそうだ。
今日は「万九千社立虫神社」の担当だった。
(司会者はたしか「まんくせんしゃたちむしじんじゃ」と呼んでいた。)
〈大出雲展〉で売店の脇でひっそり上映されていたヴィデオによれば、神在月に全国の神様が集合し、ここから旅立たれるという小さいけれども、古く重要な神社だ。
島根の神楽にはいろいろ系統があり、〈出雲神楽〉は神話をモチーフに、能狂言の手法を採り入れた荘厳な舞が特徴だとか。万九千社はこの系統だ。
「四方剣」とは、神事色のつよい七座の舞のうちの一つで、4人の舞い手が前段では御幣と鈴を、後段では剣を持って舞い、その場のすべてを祓い浄め邪悪なものを断ち切る意味をもつそうだ。舞い手は皆、直面。
まずは、小さなシンバルのような鉦2,横笛4、大小太鼓1名の楽人が登場して後ろに並び、その前で4名が舞う。



午後の回は「荒神(国譲り)」だった。
お話は、出雲に〈経津主神(ふつぬしのかみ)〉と〈武甕槌神(たけみかずちのかみ)〉が現れるところから。

ワキ方の名乗りや着きゼリフのようなものがあって、ふたりがひとしきり舞ったあとに〈大国主命(おおくにぬしのみこと)〉と息子の〈事代主神(ことしろぬしのかみ)〉がやってくる。
このふたりの姿形は、大黒様と恵比寿さまそのもの。

国を天つ神に譲れと迫られ、大国主は自分はよいが念のため息子たちの意見も聞いてくれと答える。
その場にいた事代主神はあっさり承諾するも、あとからやってきた次男〈建御名方神(たけみなかたのかみ)〉は承知せず、使いの神々と力比べをすることになる。これに負けて国を譲ることに。

というお話。このあと天から下ってくるのが邇邇芸命(ににぎのみこと)だから、要するに、天皇家の正統性を言いたいがために作られた神話なのだなと納得。
たしかにお能にも似ているけれども、もっと素朴で、どちらかというと狂言、歌舞伎テイストが感じられる。
こちらから見る限り、謡はほとんど太鼓方が謡っているようだった。
とても通る張りのある声だ。
パンフレットによれば、〈出雲神楽〉に比べて、〈石見(いわみ)神楽〉はもっと派手な演出が多いらしい。
代表的なのが「八岐大蛇」で大蛇の作り物が大活躍する。このステージでも連日さまざまな団体が「八岐大蛇」を上演する。
また、〈隠岐神楽〉は大漁祈願など祈祷色が強く、より素朴で古風なのだそうだ。
ここに会期中ずーっと座っていたら、ずいぶんしまねの神楽に詳しくなるだろうなぁ。
知らなかったのだが、この前日に京都春秋座で石見神楽、隠岐神楽の公演があり、無料で観劇できたらしい。
ともあれ、今日一日で、出雲神話の大筋がだいぶイメージできるようになった。
もう少し古代の神々の名が覚えやすいものだとよいのだけれども(_ _;)
*
ところで11/8に〈出雲篝能〉というものが催され、新作能「出雲」を桜間右陣が、狂言「樋の酒」を野村萬斎が演じるそうだ。
しかもオープニングには、三斎流家元による神前点前というものがあるのだとか。
会場は出雲大社。
魅力的だなぁ。。。

古代出雲歴史博物館のサイトによれば、島根県には神楽を伝える団体が250もあるのだとか。
となると、神話博期間中、連日神楽のステージがあっても出演者は日替わりで、同じ団体が何日もつとめるということはなさそうだ。
今日は「万九千社立虫神社」の担当だった。
(司会者はたしか「まんくせんしゃたちむしじんじゃ」と呼んでいた。)
〈大出雲展〉で売店の脇でひっそり上映されていたヴィデオによれば、神在月に全国の神様が集合し、ここから旅立たれるという小さいけれども、古く重要な神社だ。
島根の神楽にはいろいろ系統があり、〈出雲神楽〉は神話をモチーフに、能狂言の手法を採り入れた荘厳な舞が特徴だとか。万九千社はこの系統だ。
「四方剣」とは、神事色のつよい七座の舞のうちの一つで、4人の舞い手が前段では御幣と鈴を、後段では剣を持って舞い、その場のすべてを祓い浄め邪悪なものを断ち切る意味をもつそうだ。舞い手は皆、直面。
まずは、小さなシンバルのような鉦2,横笛4、大小太鼓1名の楽人が登場して後ろに並び、その前で4名が舞う。



午後の回は「荒神(国譲り)」だった。
お話は、出雲に〈経津主神(ふつぬしのかみ)〉と〈武甕槌神(たけみかずちのかみ)〉が現れるところから。

ワキ方の名乗りや着きゼリフのようなものがあって、ふたりがひとしきり舞ったあとに〈大国主命(おおくにぬしのみこと)〉と息子の〈事代主神(ことしろぬしのかみ)〉がやってくる。
このふたりの姿形は、大黒様と恵比寿さまそのもの。

国を天つ神に譲れと迫られ、大国主は自分はよいが念のため息子たちの意見も聞いてくれと答える。
その場にいた事代主神はあっさり承諾するも、あとからやってきた次男〈建御名方神(たけみなかたのかみ)〉は承知せず、使いの神々と力比べをすることになる。これに負けて国を譲ることに。

というお話。このあと天から下ってくるのが邇邇芸命(ににぎのみこと)だから、要するに、天皇家の正統性を言いたいがために作られた神話なのだなと納得。
たしかにお能にも似ているけれども、もっと素朴で、どちらかというと狂言、歌舞伎テイストが感じられる。
こちらから見る限り、謡はほとんど太鼓方が謡っているようだった。
とても通る張りのある声だ。
パンフレットによれば、〈出雲神楽〉に比べて、〈石見(いわみ)神楽〉はもっと派手な演出が多いらしい。
代表的なのが「八岐大蛇」で大蛇の作り物が大活躍する。このステージでも連日さまざまな団体が「八岐大蛇」を上演する。
また、〈隠岐神楽〉は大漁祈願など祈祷色が強く、より素朴で古風なのだそうだ。
ここに会期中ずーっと座っていたら、ずいぶんしまねの神楽に詳しくなるだろうなぁ。
知らなかったのだが、この前日に京都春秋座で石見神楽、隠岐神楽の公演があり、無料で観劇できたらしい。
ともあれ、今日一日で、出雲神話の大筋がだいぶイメージできるようになった。
もう少し古代の神々の名が覚えやすいものだとよいのだけれども(_ _;)
*
ところで11/8に〈出雲篝能〉というものが催され、新作能「出雲」を桜間右陣が、狂言「樋の酒」を野村萬斎が演じるそうだ。
しかもオープニングには、三斎流家元による神前点前というものがあるのだとか。
会場は出雲大社。
魅力的だなぁ。。。











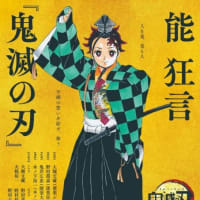









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます