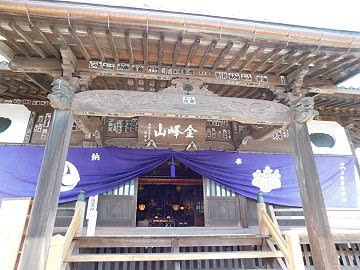【関野宿辺りの甲州街道1】

ウルトラ●ンの罠に落ちた我々ですが、ルートミスにもめげず国道20号線を進みます。相模川を左手にした相州四ヶ宿(小原宿・与瀬宿・吉野宿・関野宿)は台地上にあるのですが、関野宿を出た辺りから徐々に下り坂となっていきます。
【関野宿辺りの甲州街道2・えのき坂】

えのき坂の標柱。一里塚に多く植えられたという榎が語源でしょうか?この辺り、こういった標柱や道標があちこちに立っています。しっかり確認しながら進めば、本来は道筋を間違えようがないのでしょうが…。
【関野宿辺りの甲州街道3】

道はループを描き、下り坂が続きます。
【関野宿辺りの甲州街道4】

相模川を左に見下ろしながら進みます。本来の甲州街道はこの辺りから、川に向かって降りていくルートだったようですが、ガイドブックなどによると、道筋は正確には確認できていないそうです。
かつて獅子岩、衣滝と呼ばれた名勝が存在したのもこの辺り。「新編相模国風土記稿」によると、獅子岩は「高さ8尺(約2.4メートル)周囲1丈3尺(約3.9メートル)、甲州街道の傍らにあり」とのこと。その名の通り獅子の形のような岩だったのでしょうか?衣滝は「獅子岩の傍らにあり、瀑勢1丈2.3尺(約3.9メートル)、幅5.6尺(約1.5メートル)、その形象殆ど衣を翻すが如し」だったそうです。
獅子岩と衣滝、今も残っているのか、はたまた国道から見えるのかどうか?はわかりません。
【関野宿付近の甲州街道5】

名倉入口の信号で国道と分かれ、左手の小道を相模川に向かって下っていきます。
【関野宿付近の甲州街道6】

道端のヒガンバナがまた見事に咲いていました。昔の旅人は、四季折々の景色をこうやって楽しむ余裕はあったのでしょうか?
【境沢橋】

名倉入口の信号から歩いて5分程度、やって来ました、神奈川県と山梨県の県境を流れる境川に架かる境沢橋です。昔は相模と甲斐の国境。ガイドブックなどによると、江戸時代には、ここから40メートルほど下流に、境川を越える長さが6間(約9メートル)、幅6尺(1.8メートル)の土橋が架かっていたそうで、茶屋が3軒ほどあったとか。江戸時代と場所こそ若干違うとはいえ、ま、それでも無事に国境を越えて、いよいよ甲斐の国、山梨県へと入ります。
【境川】

境沢橋から見た境川下流方面。相模と甲斐の国境を流れていたから境川。あと少しで相模川に流れ込みます。
【山梨県に入った甲州街道】

今までは高台からひたすら下って境沢橋へ到達しました。で、下りがあるということは上りもあるわけで。目指す上野原は、文字通り崖の上にある原(というのが地名の起源とのこと)。ヘアピンカーブをうねうねと上り、今来た道を見下ろしながら歩きます。真夏の日差しのもとだと、結構つらいかもしれませんね。秋でよかった~。
【諏訪番所(諏訪関)跡】

境沢橋から歩くこと約20分、坂道の途中にあるのがこの諏訪番所跡。そもそもは武田家が設置した甲斐二十四関のひとつで、江戸時代には、ここで通行の取り締まりと物資の出入りの調べを行っていたそうです。ただし解説板によると、通行手形は男は不要、女性は江戸方面へ行く者のみ改められたとか。結構、ゆるい番所だったのかな?ここに10名の役人(番所定番9名、獄舎取締1名)が詰めていました。
これまた案内板の解説によると、明治になって番所の役宅は、あの政財界の大物・渋沢栄一の別荘として移築されたとのこと。よっぽど素晴らしい建物だったのか、趣ある家屋だったのか…?
【諏訪番所前の甲州街道1・関野宿方面】

番所前で今来た道を振り返るとこんな感じ。随分と上ってきました。江戸時代の旅人も、坂道に息を切らせながらここへたどり着き、荒い息遣いのままお役人の改めを受けたのかもしれませんね。
【諏訪番所前の甲州街道2・上野原宿方面】

番所役人の改めも無事終わり、さて、上野原を目指そう!という旅人の前には、まだまだ続く上り坂が…。
そんなわけで、我々もまだ上り坂を進むわけですが、この先、上野原宿に入るまでには、もう少し歩かなければならないようです。