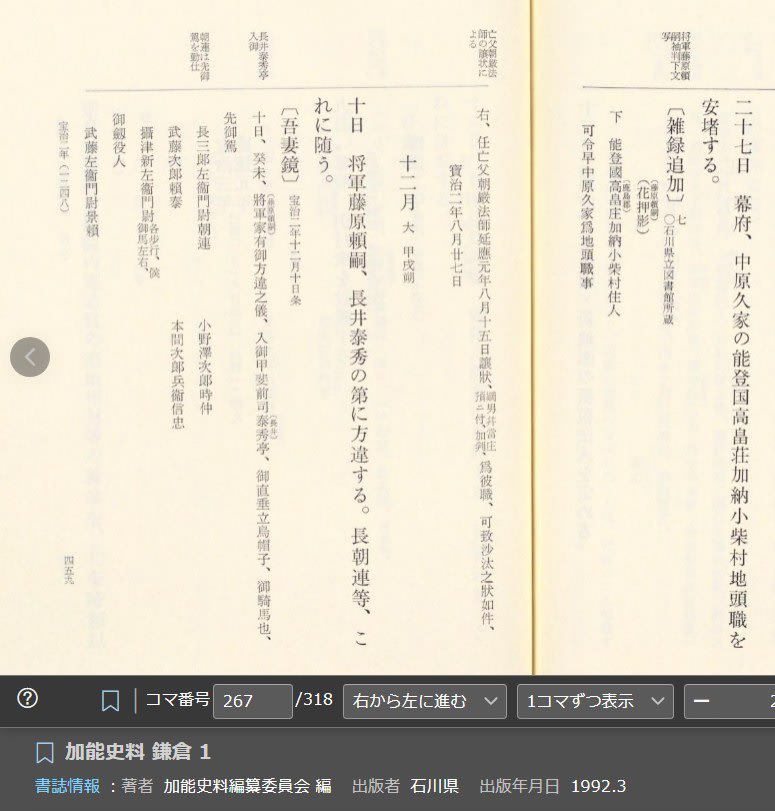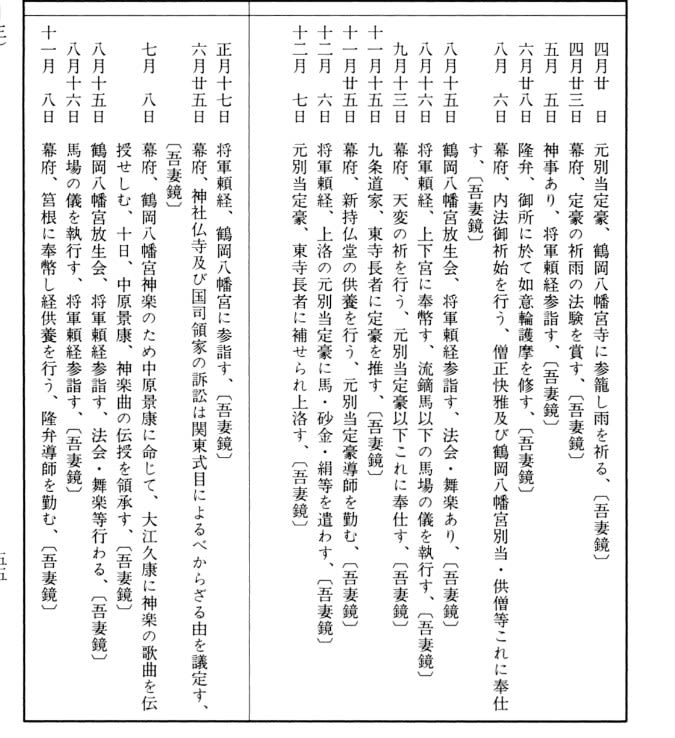下 河守御荘観音
四至
東限 前岬水落
西限 中尾西隠迫北
南限 私市庄境長尾
北限 赤坂尾上り貞久重色境なる槻
この外中楽通梧(あおぎり)椆(しげる)迎土坪在之・・・「土」の文字は〇
右件 山林者為観音寺御本尊の敷地幷坊敷寺之寄進〇然者奉存天●(切れている)
〇久兼者御領主等の子孫繁富故〇
領内の沙汰人等亙(わたる)存代旨仍寄進〇件(必件?)以下
延應元年己亥 十一月六日 地頭沙弥蓮忍
******
以上、わからない文字が〇 欠字●
やはり、久兼とは、人物名かと思う。
領主の「主」があっているか?
沙汰人:荘園においては下司・公文などの在地の荘官、あるいは在地の有力者で荘官の職務を代行する者を指す場合があり、「沙汰人職」と呼ばれる独自の所職が成立した例(若狭国太良荘)もあった。 (wikipedia)
そこで、久兼と地頭沙弥蓮忍とは「領主と地頭」という関係でありながら、地頭が寄進の文書を書いているのは、何故だろうか。依頼された?もしくは血縁関係があって相伝し、寄進した?
久兼の前の一文字が「地」に読めたが、実は「〇」こそが、名字なのではないだろうか?「紀」か?
「江」ではないようだが。
紀久兼、確かに鎌倉初期あたりにまだ存命であると思う。
本の内容は見えなかったが、【藤原隆親母・藤原雅長】と共に文書がある。
年代も鎌倉前期のようである。河守御荘は四条家と関係があったので、これは「紀久兼」有力かもしれない。
藤原維俊・紀久兼・中原為弘・紀成兼ともあるが、これは年代が1156年周辺と思われる。