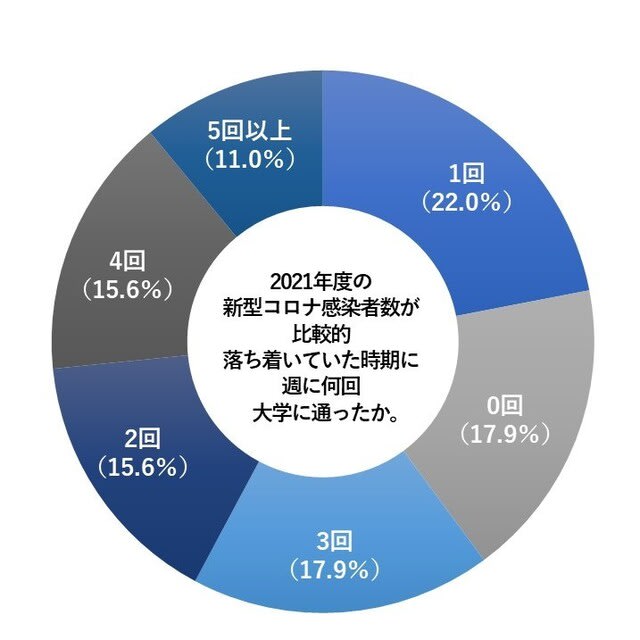ニュースネットは2022年3月1日~3月8日の間、神戸大の大学生・大学院生を対象にTwitterとGoogleフォームを用いて、オンライン授業に関するアンケートを実施し、Googleフォームでは173人から回答を得た。この記事では、「コロナ禍での教育と学生生活①」に引き続き、その結果をもとにコロナ禍での授業や学生生活に対する学生の満足度や意見を紹介する。<佐藤ちひろ、笠本菜々美、島袋舜也>
▼「コロナ禍での教育と学生生活① オンライン授業を問う」のページはこちら
1・2年生の8割が交友関係に問題
オンライン授業で困ったことに関しては、「交友関係」が132件で最も多く、次に「生活習慣」、「勉強方法」が続いた。困ったこととして「交友関係」を挙げた学生は、1年生の80%、2年生の77%、3年生の63%となっていた。

交友関係に関しては、「友達ができないことは私のこの一年の最大の問題でした(法・1)」、「1人でパソコンに向かい続けるのが流石に苦痛になってきた(法・2)」、「同じ授業を受けたあと、オンラインはそのまま解散するだけだが、対面なら雑談とか疑問の共有とかで仲良くなれたのかなとか思った(文・3)」、「交友関係が狭まり気分が落ち込む(理・1)」、「友達がとても少なく、悲しかった(国人・1)」、「友人がたくさんはできないまま3回生となり、今から多くの友人をつくるのは厳しそうであること(済・2)」、「友達0人だし、演習問題なさすぎ(工・2)」、「人と会わないから孤独感が増す(済・2)」、「オンライン授業では新しく友人を作ることができず、わからないことがあった際に誰に相談すればいいかわからなかった(文・1)」などの意見があった。
1年生に限らず、2年生でも交友関係における課題を挙げる学生が多かった。
下宿生の約半数 オンライン授業で生活習慣が悪化
次に多かった「生活習慣」を選択した学生を自宅生、下宿生別で見てみると、自宅生の39%、下宿生の45%が選択していた。自由記述欄には、「生活リズムが悪化する。規則正しいスケジュールが崩れる。自らを律さないと学修時間が減少する(法・1)」、「オンデマンド授業をまとめて見ようとすると平気で徹夜してしまう。一人暮らしだと生活習慣が容易く崩壊してしまう(法・1)」、「知り合いがいないため、勉強法など相談できない。また、ずっと人とも話さずに1人で家にいるため生活リズムが狂ってしまい、気が滅入ってくる(法・1)」などの意見があった。
交友関係の希薄化が学習にも影響
勉強方法に関しては、「どうやって勉強すればいいかわからない、何をどのくらい勉強すればいいかもわからない、友達できない、パソコンの調子悪かったりネット混んでたら詰む(法・1)」、「テスト勉強の仕方なども全く分からず不安だった。友達も作りにくかった(法・1)」、「大学の友達がいないから、課題の相談などできない(法・1)」といった意見があった。
また、「オンライン授業で一週間が埋め尽くされると本当に外に出なくなるので気分もふさぎ込んだ(文・1)」、「質問や要望を言うところがあちこち分散している為連絡しづらい。オンラインでは学習の広がりもなくなかなか興味を持ち深める事が難しいと感じた。長引くオンライン授業は授業について行くのも大変、また自己のメンタルを保ち生活するという基本的な気力を守ることも本当に大変だった。本当に辛いです。もう動画はうんざりです。有効とか言われてる人たちに、やってみてほしい(済・2)」、「部屋にずっと籠もる生活は心身にダメージがあった(国人・1)」、「画面を見続けることにより心身に疲れが溜まること(国人・3)」など精神面への影響が多く述べられていた。
オンライン授業により同学年や、同じ授業を履修している学生間の交流がほとんど存在しないことが学生の精神面に影響を与え、それがさらに学習にも影響を及ぼしているということが見受けられる。
今まで以上に自分次第・自己責任な学生生活
他にも、「自制はできたかもしれないが、授業に緊張感がない分、だらけてしまって勉強に集中できなかった(法・1)」、「同じ講義を取っている人が目に見えないので、1人で勉強している感が強く、意欲を継続するのが難しかった(法・2)」、「モチベーションや集中力が保てない。友達になかなか会えず孤独感を覚えた(法・2)」のようにモチベーションを保つことの難しさに触れる意見が多くみられた。
また、「対面の方がディスカッションは深まるし行いやすい。友達が集中して聞いているので私も集中できる(国人・2)」、「一回生の頃は交友関係が全く発展せず非常に苦しかった。また、授業内容で分からないことなどを教授に質問できなかったり、文面だけでの質問しか対応していなかったため十分に理解を深めることができなかった(工・2)」、「やりたいことと、授業の比率が難しく、勉強がおろそかになってしまう(海・2)」など、オンライン授業での課題を口にする学生もいた。
オンライン授業によって学習の自由度が増したことに伴い、今まで以上に自分次第・自己責任の面が大きくなったようだ。
最後に、「大学に対して意見・要望があれば、自由にお書きください」という欄を設け、学生からの意見を集めた。
「対面かオンラインか選択させてほしい」 ハイブリッド授業希望の声多数
授業に関して、「対面授業を受けたいのが一番の要望だが、オンライン形式にもメリットは多いので可能な限りハイブリッド式にしてほしい(法・1)」や「せめてハイブリッド授業を増やして欲しいです。このままでは何も得られないまま終わってしまいそうです(法・1)」のようにハイブリッド方式の授業を望む意見が最も多く、次に「お願いですから対面増やしてください(法・1)」や「対面授業をして欲しい。人間関係がどんどん希薄になっていくと精神的にも辛い(法・1)」、「首都圏の大学のほうが対面が多いというのは理解に苦しむ(国人・1)」など対面授業を望む声が多かった。
一方で、「オンライン授業を継続してほしい。好きなタイミングで授業を再度見直せるため、対面の時よりも明らかに授業の内容の理解度が高まったと感じているため(営・3)」といったオンライン授業の継続を求める意見も一定数みられた。
課外活動にも多くの課題
「もう何も思わない。サークル活動を許してくれさえすればそれ以外は望まない。自分でなんとかする(文・3)」や「課外活動の制限を緩くして欲しい。他大生との練習を許可して欲しい。同じ部活に所属しているのに、通う大学がちがうという理由で全体で活動できない。これが来年も続くようなら部の活動水準の維持や存続に関わると思う(農・2)」「学内の施設を課外活動用にもっと解放してほしい(国人・3)」「サークルのためだけにオンラインしかなくても隙間時間で登校したりするのが労だった。サークルなんて学生の本分じゃないしやめちゃえばいいだけなのかもしれないが、もう少し放課後に参加しやすい環境を用意してくれてもよいのではと思ってしまった(文・3)」「部室まで学内WiFiが飛んでいないため部活との兼ね合いが上手くいかない(国人・1)」と課外活動に言及する意見もみられた。
長引くコロナ禍 学生の様々な声
他にも、「一方的に撮り溜め・使い回しの講義動画をアップしたり、大量に課題を出したりするのはやめてほしい(法・1)」、「実験を含む授業に関しては対面で実施して欲しい(理・2)」、「演習問題もっとやって欲しい(工・2)」、「ゼミは必ず対面で開講してほしい(営・2)」、「せめて専門科目は対面授業にして欲しい(法・1)」、「同じ学部や授業で感染者が出てもそのまま授業を行うのは対策を行っていても休講や連絡をして欲しい(理・2)」、「2020年度入学生には、特にお願いしたいです。学生間の交流を支援してほしい。やれなかった事を遡って、順序立ててやってほしい。なかった事にしてほしくないです(済・2)」、「文化祭などイベントを対面で行って欲しい(農・1)」、「大学が主催する学生間交流イベントを開催して欲しいです(海・1)」という意見が集まった。
アンケートの結果を見ると、オンライン授業、対面授業それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらを望むかは各学生によって大きく異なること、そして約8割の学生が交友関係における問題を抱えているものの、大学にコロナ禍以前のように毎日通いたいかというと、全員がそれを望んでいるわけではないということが明らかになった。
本記事「コロナ禍の教育と学生生活②」では、オンライン授業に対する学生の声を紹介した。
続く「コロナ禍の教育と学生生活③」では、国際教養教育院長の大月一弘教授と法学部長の高橋裕教授への取材をもとに、大学側の姿勢に迫る。
▼ニュースネットは本記事に関するご意見・ご感想を募集しています。ご意見及びご感想は以下のフォームからお願いします。
https://forms.gle/hdZS7m3xGcxCTXXe8
了