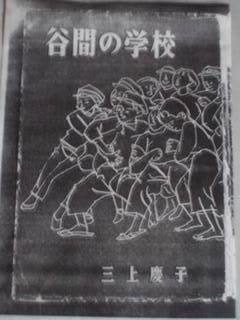(学校のトイレ)・・・いまとむかしのことです。先日、(これまた、テレビからのことですが)学校のトイレは和式が多くて⇒子どもが入れない、というのがあっていました。
いまの家庭のトイレはほとんどといっていいくらい洋式化されているようです。地震によって学校が避難所になった時に、このことが話題になりました。山江でも運動会などのときにお年寄りの方から要求がありました。確かに膝が痛い人には無理なる姿勢です。そこで、一度にとはいかないので徐々に洋式化にしていくということで進んでいるはずです。
テレビのコメンテーターの人たちも世の流れと理解してのトークでした。和式から洋式への改築の問題は(お金)です。そうしたいのはヤマヤマでも、先立つものがなければです。洋式だとスペースも必要です。5つあったものが4つに減るだろうと思います。
むかーしの話です。私が小学校低学年の頃です。東間小です。6年生の人が肥え樽を2人で担いで運動場南側の畑に運んでいました。運動場を突っ切ってです。自分たちも6年生になったらしなければならないこと、臭いだろうなと思って見ていました。むろんその頃はポットン便所です。しかし、私が6年生になる前に、汲み取りに変わって肥え樽を担ぐことはありませんでした。昭和30年代中ごろのことです。
いまだとペアレントさん方の猛反対にあいそうなことですが、むかしは当たり前のことのように行われていて、そのうちに自分たちがという、気持ちが宿っていたのかもしれません。
洋式化になると、いわゆる便所座りができなくなります。足腰が弱くなるという指摘もありました。これまた難しいことですね。
今日の天気( )
)
いまの家庭のトイレはほとんどといっていいくらい洋式化されているようです。地震によって学校が避難所になった時に、このことが話題になりました。山江でも運動会などのときにお年寄りの方から要求がありました。確かに膝が痛い人には無理なる姿勢です。そこで、一度にとはいかないので徐々に洋式化にしていくということで進んでいるはずです。
テレビのコメンテーターの人たちも世の流れと理解してのトークでした。和式から洋式への改築の問題は(お金)です。そうしたいのはヤマヤマでも、先立つものがなければです。洋式だとスペースも必要です。5つあったものが4つに減るだろうと思います。
むかーしの話です。私が小学校低学年の頃です。東間小です。6年生の人が肥え樽を2人で担いで運動場南側の畑に運んでいました。運動場を突っ切ってです。自分たちも6年生になったらしなければならないこと、臭いだろうなと思って見ていました。むろんその頃はポットン便所です。しかし、私が6年生になる前に、汲み取りに変わって肥え樽を担ぐことはありませんでした。昭和30年代中ごろのことです。
いまだとペアレントさん方の猛反対にあいそうなことですが、むかしは当たり前のことのように行われていて、そのうちに自分たちがという、気持ちが宿っていたのかもしれません。
洋式化になると、いわゆる便所座りができなくなります。足腰が弱くなるという指摘もありました。これまた難しいことですね。
今日の天気(
 )
)











 )
)


 )
)

 )
)