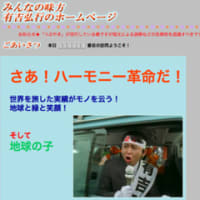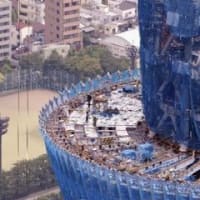スカンジナビア地方に広く生息するレミング(タビネズミ)は、3~5年周期で個体数が自然に急増する傾向を持つ。急増するとエサを求めて集団移住を始めることでもよく知られる齧歯(げっし)類だ。
ときには新天地を求めて海や川に飛び込むこともあるので、集団自殺をするという、まことしやかな伝説まで生まれている。
レミングは、かなり長い間「集団自殺をする」と考えられていた。スカンジナビアでは「集団で海に飛び込む」という伝説が古くから知られている。「集団自殺をする」とする説は近年まで信じられており、現在でも誤解している人々は多い。実際には、集団移住を行っている際に一部の個体が海に落ちて溺れ死ぬことはあるが、これは自殺ではなく事故であり、すべての個体が海で溺れ死ぬことはない。また、レミングは泳ぎがうまく、集団移住の際に川を渡ることは良くあるっという。
この様な誤解が生まれた原因としては、周期的に大増殖と激減を繰り返しており、集団移住の後、激減することから誤解された。集団で川を渡ったり、崖から海に落ちる個体があることから誤解された。
この誤解が広まった一因として、1958年のウォルト・ディズニーによるドキュメンタリー『White Wilderness』(日本語題:『白い荒野』)が上げられる。このドキュメンタリーでは、レミングが崖から落ちるシーンや、溺れ死んだ大量のレミングのシーンがあるが、現在では捏造であることがわかっている。
レミングの増加ぶりはすさまじく、以前のノルウェーでは道で死んでいるレミングを片付けるために、除雪車が出動せざるを得ないほどだった。ところが近年、この現象がほとんど起こらなくなったことがスカンジナビア各地で報告されている。
ノルウェーにあるオスロ大学のキレー・カウスルド教授らは、1970年からノルウェー南部におけるレミングの周期的な急増現象を分析してきた。この地域では1994年以降、爆発的な増加が起きていないことが分かっている。そこで、同地域の気候データと照らし合わせたところ、気温の上昇が関係している可能性が浮かび上がった。10年以上もレミングが急増していないのは地球温暖化のせいかもしれないという。今回の研究結果は、今週「Nature」誌に掲載される。
レミングは冬になると雪の下に掘ったトンネルの中で暮らす。地表近くには地熱で暖められて雪が解けている場所があり、そこからコケなどの食料を調達することができる。
しかし、近年の温暖化はこうした雪原の構造を変えてしまった。同地域は冬になると氷点下が続くような気候だったが、最近では冬の間に何度も0度を上回る。そのたびに雪解けと再凍結が繰り返されるので、雪の下のトンネルにも水があふれ、その水がまた凍って地表に氷の層ができる。この状況がレミングに壊滅的な打撃を与えているのだ。巣穴が水浸しになって多くのレミングが溺死している。生き残ってもエサは氷の下なので、食べることができずに餓死するケースが多いという。
研究チームは気候の変動でレミングが全滅することはないだろうと考えているが、生態系に与える影響は甚大なものがあるという。カウスルド教授は、「捕食者と被食者、植物の関係性が変われば、生態系全体が変化してしまう」と懸念している。
(ナショナルジオグラフィック)
ときには新天地を求めて海や川に飛び込むこともあるので、集団自殺をするという、まことしやかな伝説まで生まれている。
レミングは、かなり長い間「集団自殺をする」と考えられていた。スカンジナビアでは「集団で海に飛び込む」という伝説が古くから知られている。「集団自殺をする」とする説は近年まで信じられており、現在でも誤解している人々は多い。実際には、集団移住を行っている際に一部の個体が海に落ちて溺れ死ぬことはあるが、これは自殺ではなく事故であり、すべての個体が海で溺れ死ぬことはない。また、レミングは泳ぎがうまく、集団移住の際に川を渡ることは良くあるっという。
この様な誤解が生まれた原因としては、周期的に大増殖と激減を繰り返しており、集団移住の後、激減することから誤解された。集団で川を渡ったり、崖から海に落ちる個体があることから誤解された。
この誤解が広まった一因として、1958年のウォルト・ディズニーによるドキュメンタリー『White Wilderness』(日本語題:『白い荒野』)が上げられる。このドキュメンタリーでは、レミングが崖から落ちるシーンや、溺れ死んだ大量のレミングのシーンがあるが、現在では捏造であることがわかっている。
レミングの増加ぶりはすさまじく、以前のノルウェーでは道で死んでいるレミングを片付けるために、除雪車が出動せざるを得ないほどだった。ところが近年、この現象がほとんど起こらなくなったことがスカンジナビア各地で報告されている。
ノルウェーにあるオスロ大学のキレー・カウスルド教授らは、1970年からノルウェー南部におけるレミングの周期的な急増現象を分析してきた。この地域では1994年以降、爆発的な増加が起きていないことが分かっている。そこで、同地域の気候データと照らし合わせたところ、気温の上昇が関係している可能性が浮かび上がった。10年以上もレミングが急増していないのは地球温暖化のせいかもしれないという。今回の研究結果は、今週「Nature」誌に掲載される。
レミングは冬になると雪の下に掘ったトンネルの中で暮らす。地表近くには地熱で暖められて雪が解けている場所があり、そこからコケなどの食料を調達することができる。
しかし、近年の温暖化はこうした雪原の構造を変えてしまった。同地域は冬になると氷点下が続くような気候だったが、最近では冬の間に何度も0度を上回る。そのたびに雪解けと再凍結が繰り返されるので、雪の下のトンネルにも水があふれ、その水がまた凍って地表に氷の層ができる。この状況がレミングに壊滅的な打撃を与えているのだ。巣穴が水浸しになって多くのレミングが溺死している。生き残ってもエサは氷の下なので、食べることができずに餓死するケースが多いという。
研究チームは気候の変動でレミングが全滅することはないだろうと考えているが、生態系に与える影響は甚大なものがあるという。カウスルド教授は、「捕食者と被食者、植物の関係性が変われば、生態系全体が変化してしまう」と懸念している。
(ナショナルジオグラフィック)