地図オタが高じて、何年か前に『地理情報データハンドブック』という本を買った
これは、財団法人 日本地図センター発行のA4サイズのソフトカバー本である。
国土地理院の地図データをまとめた本で、それはそれは楽しい内容である
標高2500メートル以上の山岳・主な河川や湖沼・沿岸名称・国道リストなど、
どこを読んでも飽きることがない
さらに、「地形図で見る主な地理項目」と題して、地形や人文地理項目を読み取るにはどの地形図が良いか、
といったリストまである。
余談ではあるが、「第4次噴火予知計画対象火山」には、昨年から今年にかけて噴火した
御嶽山や口永良部島も載っているが、箱根山は載っていない。
さて、この本の109ページには「都道府県の平均標高と最高地点の標高」という項目がある。
日本の平均標高は、382メートルである。
平均標高がいちばん低いのは、標高45メートルの千葉県である。
県の最高峰が標高408メートルの愛宕岳で、県境がすべて河川なのだから、当然と言えるだろう。
(しかし、何年か前に家族で千葉県を訪れたとき、房総半島を横断したのだが、
結構な山道を車で走破したような気がする)
平均標高が100メートルを下回るのは、千葉県の他には標高82メートルの沖縄県である。
低い方から3番目は、茨城県である(標高100メートル)。
さて、高い方であるが、平均標高が1,000メートルを超えるのは、予想通り長野県である。
その数値は、1,132メートル。
確かに、地図帳を見ても、長野県は標高が高いことを示す茶色系統で塗られている。
それに次ぐのが、富士山を擁する山梨県である(標高995メートル)。
上位5県を整理すると
 長野県 1,132m
長野県 1,132m
 山梨県 995m
山梨県 995m
 ○○県 764m
○○県 764m
 岐阜県 721m
岐阜県 721m
 富山県 665m
富山県 665m
5位の富山以外は、内陸県ばかりである。
これは、海に面していると、どうしてもその部分の標高が低くなるからであると思われる。
日本の内陸県は8つある。
栃木・群馬・埼玉・長野・山梨・岐阜・滋賀・奈良である。
栃木県の平均標高は461メートル。
埼玉県は、関東平野にほぼ覆われているので248メートル。
滋賀県は327メートル。
奈良県は570メートル。
西日本は、2,000メートルを超える山がないので、思いの外標高が高くない。
ということで、伏せ字になっている第3位の県は…
そう、群馬県である
住んでいる自分でも「山ばっかりだなあ」と思っていたが、
こうして数値に出ると改めて山岳県であると実感する。
(というか、なぜ飛騨のある岐阜や立山のある富山よりも高いのか、納得がいかなかった)
ぐんうま県は、夏になるとよく名前の出る館林あたりは標高がそう高くないのだが、
(地図で見ると、平野部を示すカエル色に塗られている)
県の西部と北部がことごとく山地なのである
県の形は、かの上毛かるたで「鶴舞う形の群馬県」と言われているが、
首部分以外が見事な茶色に塗られていることになる。
こんなことを書いているが、ぐんうまが山岳県であることを密かに誇りに思っている
なお、このデータハンドブックには外国のデータも少しだけ載っており、
墺国は、面積84千㎢(約84,000㎢)、人口811万人
首都である維納の位置は、北緯48°13′、東経16°22′である。
日本の最北端(北緯45°33′)よりも北にある。
なるほど、夏場は夜明けが早くて日の入りが遅いわけだ。

これは、財団法人 日本地図センター発行のA4サイズのソフトカバー本である。
国土地理院の地図データをまとめた本で、それはそれは楽しい内容である

標高2500メートル以上の山岳・主な河川や湖沼・沿岸名称・国道リストなど、
どこを読んでも飽きることがない

さらに、「地形図で見る主な地理項目」と題して、地形や人文地理項目を読み取るにはどの地形図が良いか、
といったリストまである。
余談ではあるが、「第4次噴火予知計画対象火山」には、昨年から今年にかけて噴火した
御嶽山や口永良部島も載っているが、箱根山は載っていない。
さて、この本の109ページには「都道府県の平均標高と最高地点の標高」という項目がある。
日本の平均標高は、382メートルである。
平均標高がいちばん低いのは、標高45メートルの千葉県である。
県の最高峰が標高408メートルの愛宕岳で、県境がすべて河川なのだから、当然と言えるだろう。
(しかし、何年か前に家族で千葉県を訪れたとき、房総半島を横断したのだが、
結構な山道を車で走破したような気がする)
平均標高が100メートルを下回るのは、千葉県の他には標高82メートルの沖縄県である。
低い方から3番目は、茨城県である(標高100メートル)。
さて、高い方であるが、平均標高が1,000メートルを超えるのは、予想通り長野県である。
その数値は、1,132メートル。
確かに、地図帳を見ても、長野県は標高が高いことを示す茶色系統で塗られている。
それに次ぐのが、富士山を擁する山梨県である(標高995メートル)。
上位5県を整理すると
 長野県 1,132m
長野県 1,132m 山梨県 995m
山梨県 995m ○○県 764m
○○県 764m 岐阜県 721m
岐阜県 721m 富山県 665m
富山県 665m5位の富山以外は、内陸県ばかりである。
これは、海に面していると、どうしてもその部分の標高が低くなるからであると思われる。
日本の内陸県は8つある。
栃木・群馬・埼玉・長野・山梨・岐阜・滋賀・奈良である。
栃木県の平均標高は461メートル。
埼玉県は、関東平野にほぼ覆われているので248メートル。
滋賀県は327メートル。
奈良県は570メートル。
西日本は、2,000メートルを超える山がないので、思いの外標高が高くない。
ということで、伏せ字になっている第3位の県は…
そう、群馬県である

住んでいる自分でも「山ばっかりだなあ」と思っていたが、
こうして数値に出ると改めて山岳県であると実感する。
(というか、なぜ飛騨のある岐阜や立山のある富山よりも高いのか、納得がいかなかった)
ぐんうま県は、夏になるとよく名前の出る館林あたりは標高がそう高くないのだが、
(地図で見ると、平野部を示すカエル色に塗られている)
県の西部と北部がことごとく山地なのである

県の形は、かの上毛かるたで「鶴舞う形の群馬県」と言われているが、
首部分以外が見事な茶色に塗られていることになる。
こんなことを書いているが、ぐんうまが山岳県であることを密かに誇りに思っている

なお、このデータハンドブックには外国のデータも少しだけ載っており、
墺国は、面積84千㎢(約84,000㎢)、人口811万人
首都である維納の位置は、北緯48°13′、東経16°22′である。
日本の最北端(北緯45°33′)よりも北にある。
なるほど、夏場は夜明けが早くて日の入りが遅いわけだ。










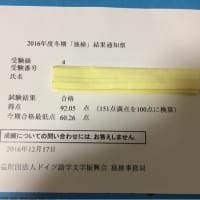







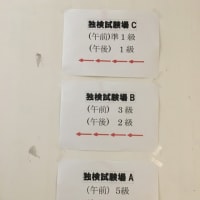

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます