 大学時代落語研究会に所属し、練習・練習・練習。一週間、6回ちょうどお昼の12時から一時までが練習時間。当時の演技部長が大体、その週のだれが、上がるか指図します。
大学時代落語研究会に所属し、練習・練習・練習。一週間、6回ちょうどお昼の12時から一時までが練習時間。当時の演技部長が大体、その週のだれが、上がるか指図します。例えば、私の出番が木曜日だとすると、前日までに、何を演じるか、何分ぐらいかを報告します。大体一日五・六人ぐらい。一年生だと、小噺だと、一年生と二年の誰と誰。
次の日は、と言うように月曜日に一週間の予定を発表。それに併せて、練習。
もちろん、うまい人とヘタは、いってこいほどの技量の差があります。そりゃ、もう持って生まれた演技力。うまい人の落語には、「ちから」が抜けている。けっして、大げさにせず、自然と笑いが起こる。ヘタは、妙に笑いを取ろうとするから、「ちから」が入っていて、・・・。墓穴を掘る。大体私は、後者。
一番うまいのは、「標」。標と書いて、「しめぎ」と読みます。こいつは、うまい。プロになれるレベル。ただ、余り一生懸命は、やりたい思わないのだと思う。やれば、そこそこの落語家になっていたことだろう。私たちの部員数は、時代によって異なるが、大体、四十~五十人ぐらい。四年生になると、そんなに部活に出てこない。もちろん、出てきてももちろんOK。一年生は、募集して、大体十四人。そのうち何人かは、止めることもある。私の同級生も、こりゃ、俺に向いていないと辞めていきました。 辞めるのは一年生の内が一番。だいたい、そうなっているようです。一年耐えた奴は、雰囲気に慣れ、生活を楽しんでいるようです。先輩・後輩の区別は、とても厳しい。普段、先輩にためぐち何かしたら、もう、殴られます。基本的には、殴る様な人は、極く少数。私は、一度も殴ったことはありません。もちろん、その立場でやっいることが多い。これも一つの役割分担。
一年に二回公演会。六月と十一月。演じては、十人ずつぐらい。六時開演。九時閉園。
3時間で十人。一人約10分~20分。三年生を後半にして、大体演技部長と部長が一年間の演じ手を決めていきます。私は。二年生の時、「孝行糖」という与太郎者をやりました。
そして、三年の秋に「火焔太鼓」。大体、みんな四つか五つぐらい自分の好きなネタを持って居る。その中から、周りとダブらないように、配慮して決めます。
もう打ち上げは、大変。みんな演じ手に酒をつぎ・・・・。その日は、感動に次ぐ感動。
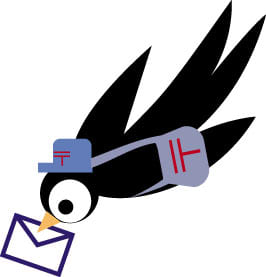
こう言うのは、やった人でないとわかりません。もう、そりゃいつも大変。一度は、救急車呼んだことがあります。栗村という日本放送でアナウンサーやっている奴。たしか、私の二年下でした。いろんな奴が、それぞれの個性をぶつけ、「落語」に息吹をふきこむ。
簡単なようで難しい。けど、面白かった・・・。若いからできたようなもの。発表会を終えると、もうその人の芸、といえるしろものではないが、人間的な幅が生まれます。本人にも、自信のようなものを感じながら、舞台に立てるようになる。いろいろ慰問や呼ばれての企画でやることがあっても、一度「大舞台」を経験すると、・・・こなせるようになる者だ。ただ、すべてのことには、上には、上。当たり前の話。
落語に出会い、変わったことは、『ドモリ』が大学一年の夏で、ほとんどわからないレベルに・・・。卒業時期は、気づかれないレベルへ。もちろん、あわてて話そうとすると・・・、たまに戻りますが・・。後は、その個性的な生き方。実に個性的。大学八年生も居ましたから・・。福田は。六年生まで。一人一人の人間性がよくわかりました。まさに、
裸のつきあい。友達と呼べる親友がたくさん出来ました。ま、人間を見る上でこんなに面白い連中もありません。後日その個性については、触れます。ま、楽しければ、何でもし、怖い者しらずの所がありました。正に、青春。今も楽しいがあの頃は、格別。若さ。馬鹿さがあったから。
再見。










 それで、何故引きこもっていますか。
それで、何故引きこもっていますか。