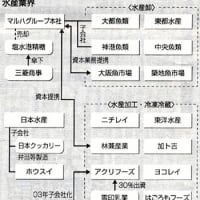福岡市の人工島事業の収支試算が1999年の事業点検で黒字に書き直された問題で、第3セクター「博多港開発」の元社長、志岐真一被告(67)が21日、福岡地裁の公判で「社長になり、約40億円の黒字試算の計画を引き継いだが、土地売却単価が高過ぎて非常に甘いと感じた。市はその後、融資を渋る銀行団に、将来の損失を補償する旨の文書を出した」と証言した。
市は黒字試算を根拠に事業継続を決めたが、水面下で博多港開発の債務を肩代わりする“念書”を出していたとなれば、事業点検の信頼性が根幹から崩れることになる。
この日は、博多港開発のケヤキ・庭石購入事件で、商法違反(特別背任)に問われた志岐被告の被告人質問が行われた。
弁護人が99年6月の社長就任の経緯について質問したところ、志岐被告は「山崎広太郎市長から『助役をやめてくれれば社長に推薦する』と言われ、従った。就任時、すでに事業継続は決まっていた」と述べた。
事業点検で出された黒字計画については「2002年に土地売却を始めることになっていたが、埋め立て免許が交付された5年前の計画から何も進んでいなかった」と指摘。「道路など具体的な基盤整備が全く決まっていないのに、土地売却単価も当時の相場の1.2倍で設定されており、見直しが必要だった」と説明した。
一方、事業点検直後、融資銀行団のうち、当時の日本興業銀行が融資の中止を申し入れるなど、銀行団との調整が難航していたことを認めたうえで、「市の第3セクターに対する債務保証は法的に禁じられているが、市が銀行団に損失を補償する文書を差し入れた」とした。現在、事業を統括している市港湾局事業管理課は「損失を補償する内容の文書が存在するかどうかは確認中だが、市は株式会社に対して損失補償を行わないという明確な方針があり、文書を出したとは考えにくい」と話している。
人工島事業を巡っては、01年秋、十数行の銀行団のうち鹿児島銀行などの融資停止が発覚。博多港開発からの返済が滞ることを懸念した銀行団の要請で、市は02年、緊急融資制度(上限200億円)を創設するなどし、融資継続を取り付けた。市は89年の計画案発表以来、「税金を使わない独立採算事業」と言い続けてきたが、市民からは「崩壊した事業への実質的な債務保証」との批判が出ていた。
三橋良士明(よしあき)・静岡大教授(行政法)の話「自治体の第3セクターへの債務保証は法的にできないとの見解もあり、この文書は俗に言う『隠れ債務保証』と言える。税金を納める市民に説明もないまま損失補償のリスクを引き受ける文書を交わしたとなれば、大問題だ。自治体の透明性、情報公開が求められる時代に逆行している」
読売新聞 2005年7月22日
Link
市は黒字試算を根拠に事業継続を決めたが、水面下で博多港開発の債務を肩代わりする“念書”を出していたとなれば、事業点検の信頼性が根幹から崩れることになる。
この日は、博多港開発のケヤキ・庭石購入事件で、商法違反(特別背任)に問われた志岐被告の被告人質問が行われた。
弁護人が99年6月の社長就任の経緯について質問したところ、志岐被告は「山崎広太郎市長から『助役をやめてくれれば社長に推薦する』と言われ、従った。就任時、すでに事業継続は決まっていた」と述べた。
事業点検で出された黒字計画については「2002年に土地売却を始めることになっていたが、埋め立て免許が交付された5年前の計画から何も進んでいなかった」と指摘。「道路など具体的な基盤整備が全く決まっていないのに、土地売却単価も当時の相場の1.2倍で設定されており、見直しが必要だった」と説明した。
一方、事業点検直後、融資銀行団のうち、当時の日本興業銀行が融資の中止を申し入れるなど、銀行団との調整が難航していたことを認めたうえで、「市の第3セクターに対する債務保証は法的に禁じられているが、市が銀行団に損失を補償する文書を差し入れた」とした。現在、事業を統括している市港湾局事業管理課は「損失を補償する内容の文書が存在するかどうかは確認中だが、市は株式会社に対して損失補償を行わないという明確な方針があり、文書を出したとは考えにくい」と話している。
人工島事業を巡っては、01年秋、十数行の銀行団のうち鹿児島銀行などの融資停止が発覚。博多港開発からの返済が滞ることを懸念した銀行団の要請で、市は02年、緊急融資制度(上限200億円)を創設するなどし、融資継続を取り付けた。市は89年の計画案発表以来、「税金を使わない独立採算事業」と言い続けてきたが、市民からは「崩壊した事業への実質的な債務保証」との批判が出ていた。
三橋良士明(よしあき)・静岡大教授(行政法)の話「自治体の第3セクターへの債務保証は法的にできないとの見解もあり、この文書は俗に言う『隠れ債務保証』と言える。税金を納める市民に説明もないまま損失補償のリスクを引き受ける文書を交わしたとなれば、大問題だ。自治体の透明性、情報公開が求められる時代に逆行している」
読売新聞 2005年7月22日
Link