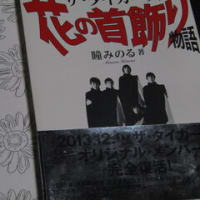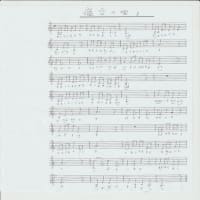夏目漱石を読むという虚栄
4000 『吾輩は猫である』から『三四郎』の前まで
4100 笑えない『吾輩は猫である』
4140 「吾輩は死ぬ」
4141 「有名」
ワガハイは、幼いころに泣き真似を覚え、語り手に成り上がっても泣き真似を続ける。
<吾輩は死ぬ。死んでこの太平を得る。太平は死ななければ得られぬ。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。難有い難有い。
(夏目漱石『吾輩は猫である』十一)>
この場面の聞き手は誰だろう。「太平を得る」は意味不明。
<おれはそれぎり永久に、中有(ちゅうう)の闇へ沈んでしまった。
(芥川龍之介『藪の中』「巫女(みこ)の口を借りたる死霊(しりょう)の物語」)>
語り手の「おれ」は「死霊」だから、この文は合理的だ。『サンセット大通り』(ワイルダー監督)参照。
語り手のワガハイに対応する聞き手の正体は不明だ。
<吾輩は新年来多少有名になったので、猫ながらちょっと鼻が高く感ぜらるるのは難有(ありがた)い。
(夏目漱石『吾輩は猫である』二)>
ワガハイの手記を読んだ人たちが作中に実在するらしい。では、その人たちは、〈猫は字を書ける〉と信じているのだろうか。そうではなかろう。だから、この作品は不合理だ。不合理ではないとすると、苦沙弥がワガハイに成りすまして書いたものを発表したことになる。そして、その事実に、語り手のワガハイがまったく触れていないことになる。
<そこで一瞥してみますというと、このまったく独特で風変りな筆跡にこころ惹かれましてね、すこし読んでみたんですが、そのうちなぜか自分じしんにもわからぬままに、こいつはもしかするとムルの仕業かもしれんという異様な考えが頭にうかんできたのです。理性、というか、そう、われわれだれひとりとして逃れることのできないある種の生活経験、そしてこれがまた結局のところ理性にほかならないのですが、要するにその理性なるものが、そんな考えは不合理だ、だって猫にはものが書けないのだし、まして詩などをつくることはできないのだから、とわたしに言うのですが、それでもわたしはその考えをどうしても棄てることができなかったのです。
(E・T・A・ホフマン『牡猫ムルの人生観』第一巻)>
「わたし」は人間で、ムルの書いた「詩」を読んで戸惑っている。一方、ワガハイの呟きが『吾輩は猫である』という作品の内部の世界において、どのような性質の「もの」なのか、読者にはまったく想像できない。作者は「理性」を無視している。だから、笑えない。
4000 『吾輩は猫である』から『三四郎』の前まで
4100 笑えない『吾輩は猫である』
4140 「吾輩は死ぬ」
4142 「理性」がない
Nの小説の聞き手は正体不明だ。
<最後の審判のらっぱがなんどき鳴ってもいい。私はこの書物を手にして、至高の審判者のまえにすすみでよう。私は声を高くしていおう。これが私のやったことです。考えたことです。かつてあった日の姿です。善も悪も同じようにすなおに語りました。わるいからといって何一つかくさず、よいからといって何一つつけ加えませんでした。たまに何か勝手な文飾をほどこしたとすれば、それは記憶の喪失でできたすきまをみたすためにすぎなかったのです。真実だったとさとってこれを真実としたことはありますが、いつわりだとさとってこれを真実としたことは決してありません。私は自分のかつてあった姿をそのまま示しました。さげすむべき、いやしい人間であったときは、そのように。善良で、寛大で、けだかい人間であったときは、またそのように。永遠の存在である神よ、私はあなた自身が見られたままに、私の内面をさらけだしたのです。私のまわりに無数の同じ人間の仲間をよせあつめ、彼らに私の告白をきかせ、私の卑劣さに声をあげ、私のあさましさに顔を赤らめさせてください。そしてこんどは、彼らの一人一人に、あなたの玉座のもとに、私と同じ誠実さでその心をうちあけさせてください。そして、ただの一人でも、あなたにむかって、「私はこの男よりすぐれています」といえるものがあったら、いわせてください。
(ジャン‐ジャック・ルソー『告白録』巻一)>
Pが「審判者」なら、彼は「遺書」を評価すべきだ。そのために、彼はP文書を再開する義務がある。ところが、作者はP文書の再開を避けた。なぜか。
<私は私の過去を善悪ともに他(ひと)の参考に供する積りです。然し妻だけはたった一人の例外だと承知して下さい。私は妻には何にも知らせたくないのです。妻が己れの過去に対してもつ記憶を、なるべく純白に保存して置(ママ)いて遣(ママ)りたいのが私の唯一(ゆいいつ)の希望なのですから、私が死んだ後(あと)でも、妻が生きている以上は、あなた限りに打ち明けられた私の秘密として、凡てを腹の中にしまって置(ママ)いて下さい」
(夏目漱石『こころ』「下 先生と遺書」五十六)>
「過去」が〈前歴〉という意味なら、それは「ふつう、人に知られたくない事柄について用いる」(『類語例解辞典』303‐01)から、「善」という言葉にそぐわない。だから、「過去」は意味不明。「他(ひと)」つまりRは、Qと重なる。Sは「遺書」をPに送って死ぬ「積り」だから、「他(ひと)」に発信する余裕はない。「積り」になれるわけがない。「参考」にするかどうかは、「他(た)」の決めること。僭越。「供する積り」は〈あなたを介して「供する積り」〉の略か。
「純白に保存して」は意味不明。だから、「希望」は不可解。この文の趣旨は、「妻の記憶に暗黒な一点を印(いん)するに忍びなかったから」(下五十二)などと同じらしいが、「暗黒な一点」の具体例は不明。P文書の語りの時点では、静は生存している。語りの場は「秘密」だ。
4000 『吾輩は猫である』から『三四郎』の前まで
4100 笑えない『吾輩は猫である』
4140 「吾輩は死ぬ」
4143 口封じ
『吾輩は猫である』には一貫性がないように思える。
<猫の視点から人間世界を見るという奇抜な着想による作品。語り手の飼い主である苦沙弥(くしゃみ)先生の書斎に集まる美学者の迷亭、物理学者の寒月ら、また俗物の実業家夫人など、戯画化された登場人物の様子と、その取りとめもない談論を描く。文明批評を軽やかな文体にのせた、知的ユーモアにあふれる風刺小説。
(『日本歴史大事典』「吾輩は猫である」佐藤泉)>
「人間世界」は意味不明。「人間」以外の猫のことも、多く話題になっている。しかも、両者は影響し合っている。ワガハイの猫としての成長と苦沙弥の絶望の深化が並行しているのだ。ワガハイの死は事故だが、作者は「先生」どもが精神的な袋小路に入ったからワガハイを殺したのだろう。ただし、企画倒れだから、わかりにくい。「奇抜」ではない。『牡猫ムルの人生観』のパクリだ。他にも多くの書物から陰に陽に引用されている。それらをことごとく点検することは、私などには不可能だ。つまり、独創性を計量することは、私にはできない。誰にできたのか。
「語り手の飼い主」は不適切。〈語られるワガハイの「飼い主」〉だ。ただし、彼は「飼い主」らしいことをしていない。ムルの「師匠」とは大違いだ。「とりとめもない談論」と思うのなら、小説を読む能力がかなり不足している。本筋はあるのだ。ただし、それは隠蔽されている。
「文明批評」は誤読。あるいは、「文明」も「批評」も意味不明。「批評」になっていない。どんなに甘く読んでやっても、「書斎」派の与太話だ。隠蔽された物語の存在に気づかないから、「とりとめもない談論」と誤読してしまうわけだ。「軽やかな文体」ではない。むしろ、重苦しい。劇団ひとりの台詞さえ、佐藤は「軽やかな文体」と評するのかもしれない。「知的ユーモア」ではなく、書生気分の抜けない「先生」どものみっともない雑言だ。「風刺小説」に偽装された不安と怨恨の露呈。
<風刺であるためには、対象に対して距離をとり、憤りを抑制して表現する必要がある。この独特な態度こそが風刺の本質であり、その表現は対象の誇張的変形を伴い、機知を示すことが多い。
(『日本大百科事典(ニッポニカ)』「風刺」佐々木健一)>
「モリエールの『人間嫌い』のアルセストやスウィフトのガリバーのように、最後には社会から疎外されるという形で否定される風刺の主体もある」(『ニッポニカ』「風刺」)ということだが、ワガハイは「疎外される」のではない。「先生」どもの代わりに死ぬのだ。
『こころ』も同様だ。Sは誰かに「疎外される」のではない。疎外されているような妄想を抱いて自殺を夢見ている。だが、真相は逆で、Sは実際に疎外されているはずだ。彼は口封じのために、作者に殺された。ただし、読者にはどうとも決めかねる。
(4140終)