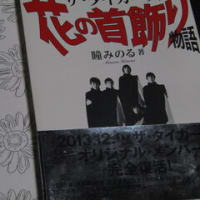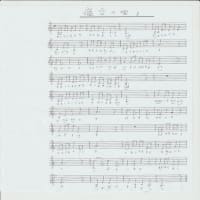書評
『シン読解力 学力と人生を決めるもうひとつの読み方』(東洋経済新報社)
著者 新井紀子
11 AIを使いこなせる人材になる
「AIを使いこなせる人材になる」その前に、AIからであれ、何からであれ、誰からであれ、入手した情報を過信しない人間になることが先だ。そのためには直感を磨かねばならない。勿論、直感を疑う必要はある。しかし、直感や印象や感覚などが働かない「人材」なんか、ロボットと変わりがない。
*
チャットGPTなどの生成AIの出力にはウソ(ハルシネーション)が含まれます。
(p73)
*
やっと「ウソ」の意味が記される。だが、「ハルシネーション」の訳語が示されていない。辞書を見ても、私は迷う。
*
1幻覚.→ILLUSION 類語
2(幻覚によって見える)幻影,幻.
3誤った考え[信仰,信念,印象],思い違い,錯覚,妄想,迷い
(『ランダムハウス英和大辞典』「hallucination」)
*
インスピレーションと、どう違うのだろう。
*
チャットGPTを使いこなすために必要になるスキルとはなにか?
それが、これから本書でお話しする「シン読解力」です。
(p74~75)
*
「チャットGPTを使いこなすために」限らず、また、「シン」がどうであれ、まともな読解力は、日常生活で必要だ。
*
チャットGPTとタッグを組んで生産性を上げるには、少なくともチャットGPTと遜色のない読み書きスキルが必要です。
(p75)
*
また、意味不明だ。「チャットGPTとタッグを組んで」って、擬人化だね。実際にはどういう作業だろう。「少なくとも」とあるが、多い少ないの話ではなかろう。「チャットGPTと遜色のない」は〈「チャットGPTと」比べて「遜色のない」〉と補ってもいいかな。読解力の話が「読み書き」になったよ。なお、本書では、作文力の話は出てこない。
*
私たちはチャットGPTの出力を、まず読んで理解できなければなりません。「なんかいい感じに書いてあるからOK」ではダメです。さらに出力を読んで、理解するだけでも不十分です。
なにしろ、相手は呼吸をするようにウソをつきますから、ファクトチェックをする必要があります。
(p75)
*
「出力」は専門用語で、〈出力された情報〉のことらしい。
新井の作文も「なんかいい感じに書いてある」が、読者は眉に唾を付けよう。
「さらに」で話が飛躍する。本書の主題は「理解するだけ」のはずだ。
「ファクトチェック」なんか、二の次、三の次だよ。本気で言うのなら、宗教やイデオロギーなどの「ファクトチェック」を済ませてからにしてくれ。
わかったつもりになることは、「相手」が誰であれ、何であれ、不可避だ。警戒すべきなのは、わかったふりだ。「必要」なのは、この違いを自覚することだ。
曖昧と難解は違う。
例えば、「ウソ」の意味は曖昧だから、ファクトチェックはできない。一方、「ハルシネーション」が専門用語なら、素人には難解なだけで、ファクトチェックはできる。曖昧と難解の区別ができないのなら、何を読んでも理解できない。
(11終)