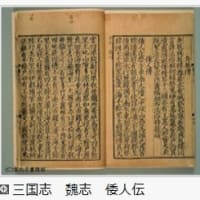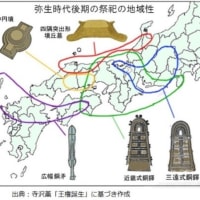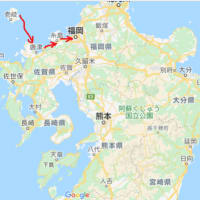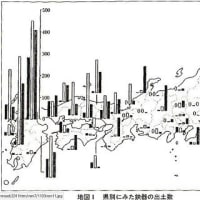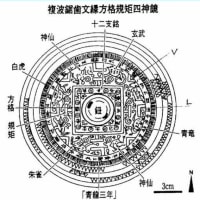続いて、遺跡から考えてみます。
サンプルは、吉野ヶ里遺跡です。
ピーク時(卑弥呼の時代)
・環濠が二重になり環濠内に1200人
・農耕など食料を作る為の集落とあわせて5400人
環濠内では
・王族
・織物や鋳造な特殊な産業
・環濠を守る戦闘員
・祈祷師
・食料保管、分配の為倉庫があります。
都 となる部分です。
環濠の外は
・農耕や狩猟など食料を生産する人
面積的には、環濠内より何倍も広いです。

こんな感じの集落が環濠の周囲にいくつもあったのでしょう。
簡単に
吉野ヶ里が5000人
弥生時代に人口が300万人なら
吉野ヶ里規模の集落が各地に600程あった。
吉野ヶ里の半分ほど規模なら1000程
倭国は100国から30国なった
ならば、吉野ヶ里規模が20個ほど集まって1国?
まあ、想像は出来ます。
食料を準備する人口 4
食料を管理、祈祷を行う人 1
の割合ではないでしょうか。
農耕を行う集落は
数ヘクタール程の農地に
10~15戸程に人々
一戸 10数人なら
一集落が200人程
4000人は
20程の小さな集落が
環濠の周囲にあって
環濠内で生活する人口を支えていたのでしょうか。
つまり、吉野ヶ里(河川が一つ)は
200~400戸+環濠内の戸数
弥生時代の最大と思われている吉野ヶ里遺跡
対馬国千余戸にも及ばない規模です。
人口5400人は、全くの小国と云う事です。
唐津湾の末廬国 5倍以上
博多湾の奴国 25倍以上
邪馬台国7万戸は比較になりません。
吉野ヶ里規模の集落が100以上あって邪馬台国
人口は農地面積の比例するでしょう。
吉野ヶ里の5倍ほど=唐津湾(末廬国)
唐津湾の5倍ほど =博多湾+多数の河川沿い内陸まで(奴国)
考えられない事もないで鵜す。
では、邪馬台国7万戸
奴国(博多湾)の3倍以上
・有明海の場合
長崎、佐賀、福岡、熊本を広い範囲です。
※吉野ヶ里は、邪馬台国の一つだったかもしれません。
或いはその他21国の
呼邑国(おぎこく)=小城
華奴蘇奴国(かなさきなこく)=神崎
の可能性もあります。
邪馬台国 近畿説(奈良盆地)の場合
7万とは奈良盆地だけでは狭すぎます。
邪馬台国は
大阪湾~奈良まで広い地域を指しているでしょう。
近畿全体が邪馬台国7万戸(35万人)かもしれません。
卑弥呼の宮殿が吉野ヶ里遺跡より
何十倍も大きい必要はないです。
婢千人と共に生活しています。
規模的には、吉野ヶ里の環濠です。
但し、吉野ヶ里の環濠は二重構造で
守衛の武人がいたはずですの
卑弥呼と共に生活していた婢千人は
吉野ヶ里内環濠ほど地域で生活していたかもしれません。
周囲に男性の守衛が生活していたとすれば
卑弥呼の宮殿が吉野ヶ里の2倍程の環濠集落だったのではないでしょうか。
しかし、近畿説に 弥生時代の300万人を考えると
・九州には 奴国他 3万戸(15万人程)
※九州に吉野ヶ里規模の集落が30
少し少ないような気がします。
・近畿には 邪馬台国7万戸(40万人程)+狗奴国
・山陰には 投馬国 5万戸(30万人程)
瀬戸内海や四国を鑑みても
西日本に300万人の三分の一
100万人では少ないように思います。
弥生時代初期~中期 人口は九州と山陰に
弥生時代末期であれば人口は西日本に集中
です。
7万戸の 邪馬台国 と
隣接する国 狗奴国(対等に戦える)
この二つが共存する土地があったのでしょうか。
邪馬台国7万戸も大げさな数値とも云われています。
サンプルは、吉野ヶ里遺跡です。
ピーク時(卑弥呼の時代)
・環濠が二重になり環濠内に1200人
・農耕など食料を作る為の集落とあわせて5400人
環濠内では
・王族
・織物や鋳造な特殊な産業
・環濠を守る戦闘員
・祈祷師
・食料保管、分配の為倉庫があります。
都 となる部分です。
環濠の外は
・農耕や狩猟など食料を生産する人
面積的には、環濠内より何倍も広いです。

こんな感じの集落が環濠の周囲にいくつもあったのでしょう。
簡単に
吉野ヶ里が5000人
弥生時代に人口が300万人なら
吉野ヶ里規模の集落が各地に600程あった。
吉野ヶ里の半分ほど規模なら1000程
倭国は100国から30国なった
ならば、吉野ヶ里規模が20個ほど集まって1国?
まあ、想像は出来ます。
食料を準備する人口 4
食料を管理、祈祷を行う人 1
の割合ではないでしょうか。
農耕を行う集落は
数ヘクタール程の農地に
10~15戸程に人々
一戸 10数人なら
一集落が200人程
4000人は
20程の小さな集落が
環濠の周囲にあって
環濠内で生活する人口を支えていたのでしょうか。
つまり、吉野ヶ里(河川が一つ)は
200~400戸+環濠内の戸数
弥生時代の最大と思われている吉野ヶ里遺跡
対馬国千余戸にも及ばない規模です。
人口5400人は、全くの小国と云う事です。
唐津湾の末廬国 5倍以上
博多湾の奴国 25倍以上
邪馬台国7万戸は比較になりません。
吉野ヶ里規模の集落が100以上あって邪馬台国
人口は農地面積の比例するでしょう。
吉野ヶ里の5倍ほど=唐津湾(末廬国)
唐津湾の5倍ほど =博多湾+多数の河川沿い内陸まで(奴国)
考えられない事もないで鵜す。
では、邪馬台国7万戸
奴国(博多湾)の3倍以上
・有明海の場合
長崎、佐賀、福岡、熊本を広い範囲です。
※吉野ヶ里は、邪馬台国の一つだったかもしれません。
或いはその他21国の
呼邑国(おぎこく)=小城
華奴蘇奴国(かなさきなこく)=神崎
の可能性もあります。
邪馬台国 近畿説(奈良盆地)の場合
7万とは奈良盆地だけでは狭すぎます。
邪馬台国は
大阪湾~奈良まで広い地域を指しているでしょう。
近畿全体が邪馬台国7万戸(35万人)かもしれません。
卑弥呼の宮殿が吉野ヶ里遺跡より
何十倍も大きい必要はないです。
婢千人と共に生活しています。
規模的には、吉野ヶ里の環濠です。
但し、吉野ヶ里の環濠は二重構造で
守衛の武人がいたはずですの
卑弥呼と共に生活していた婢千人は
吉野ヶ里内環濠ほど地域で生活していたかもしれません。
周囲に男性の守衛が生活していたとすれば
卑弥呼の宮殿が吉野ヶ里の2倍程の環濠集落だったのではないでしょうか。
しかし、近畿説に 弥生時代の300万人を考えると
・九州には 奴国他 3万戸(15万人程)
※九州に吉野ヶ里規模の集落が30
少し少ないような気がします。
・近畿には 邪馬台国7万戸(40万人程)+狗奴国
・山陰には 投馬国 5万戸(30万人程)
瀬戸内海や四国を鑑みても
西日本に300万人の三分の一
100万人では少ないように思います。
弥生時代初期~中期 人口は九州と山陰に
弥生時代末期であれば人口は西日本に集中
です。
7万戸の 邪馬台国 と
隣接する国 狗奴国(対等に戦える)
この二つが共存する土地があったのでしょうか。
邪馬台国7万戸も大げさな数値とも云われています。